

さて、ゆるりとはじめましょう。
星を見ることとかたとえば、世界を楽しむのはそんなに難しいことじゃない。想像力と好奇心、そしてほんのちょっぴりの知識。意味もなくどきどきしながら、ぐるぐる回る星や、深い海の底のことを考える。あるいは、すごく遠いところや、すごく小さいもののことを。そう、世界はもっと美しかったり、不思議だったり、かっこよかったりするはずなんだ。
「世界は寄りかかることなく、僕らのそばに立っている木だ」と表現した作家がいた。世界はどこまでも無関心だけれど、僕らはそのそばにいて、なんとなく安心している。僕らは、そのありようを見つめながら、なんとなく喜んでいる。
たとえば、人は、たまには立ち止まって、星のことを考えたりするべきなんじゃないだろうか。それで、お腹がいっぱいになったり、お金が儲かったり、まして世界が平和になったりはしないんだけど、それでも、自分の一部を星の世界に置いておくのは、そんなに悪いことじゃないはずだ。
いや、別に、風や海だっていいんだけどね
続 落書き宣言よく見てみよう。世界には涙を流す被害者と、当惑する第3者しかいない。そう、君の目に悪が映るとしたら、それは君自身もまた悪であるかもしれないということだ。人は怒りと悲しみの中でこのことをあまりにたやすく忘れる。
考えるべきなのは、何が正しく何が間違っているかではなく、それが誰にとって正しく、誰にとって間違っているかの方だ。
真実は無数にある。おそらく人の数だけある。僕らはあらん限りの想像力を尽くして自分だけの真実を選び取る。そう、君の目の前にあるのがまぎれもなく真実だ。たった一つ、君だけの真実。だけどその真実は、君の目の前にいるあの人の真実とは決して一致しない。それはむしろ喜ぶべきことであって、悲しむべきことじゃないはずだ。
ここで語られていることは、誰かさんが言ったように便所の落書き以上のものじゃないだろう。でも、少なくとも僕は心からこの落書きを信じているし、同じように、あなたの言葉があなたにとって紛れも無く真実であることを、僕は信じたいと思う。たとえそれが、僕の真実と相容れないものだとしても。
とりあえず所信表明ということで、昔の日記から再掲載。
. Date: 20030429 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Severe acute respiratory syndrome (SARS)重症急性呼吸器症候群
つーか、厚生労働省のコンテンツはゴミだな。
・一般向けコンテンツが一つも無い。
・一般的に流通している『SARS』という単語が使われてない。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0318-1.html
WHO
http://www.who.or.jp/sars/index.html
CDC
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/index.htm
What Everyone Should Know About SARS by CDC
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/basics.htm
[book]買った本鈴木真二『飛行機物語』中公新書
本村凌二『馬の世界史』講談社現代新書
井田茂『異形の惑星』NHKBooks
. Date: 20030430 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新ソユーズカプセル国際宇宙ステーションに到着
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030330125105
久々の、つっこみねた。ちょっと細かいかなあ。
他人の書いたもののあげあしを取って喜ぶ趣味はあまりないんだけど(楽しいんだけどね)、個人サイトやフィクションならともかく、「権威あるマスコミサイトの記事」としては、どーかと思うなあ。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030501 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]エイミー・トムソン『ヴァーチャル・ガール』ハヤカワ文庫(amazon)AIの研究が禁止されている近未来。科学者アーノルドによって造られた、自我を持つ美少女アンドロイドマギーが、人々との交流を通じて成長していく。というお話。
浅い。とにかく浅い。
物語の構造的には、おおむね「喪失物語」なんだけど。読者は喪失の理由も、喪失したものもぜんぶあらかじめ知っている。知らないのは主人公だけ。喪失に関わる謎解きの要素は一切ない。じゃあ、回復のために何らかの「闘争」があるかというと、これもない。他人からぽんと蓋を開けられるだけ。こんなの「喪失物語」じゃないよ。ただ、ストーリーが停滞しただけやんか。ちょっと工夫するだけで面白くなりそうな設定や、伏線になりそうな描写が山のようにあるのに、全部ボロボロ捨てるんだもんなあ。
主人公のアーノルドのキャラクターもシーンの都合のいいようにころころころころ変わるせいで、感情移入も出来なければ、反発も出来ない。アーノルドの行動原理は、最後までよく分からない。『美少女萌え』『親父なんか嫌いだ』『ただのメカオタク』・・・。サブキャラクターも、出てくる人出てくる人、みんな凄く浅ーいところで喜んだり悲しんだりしている。肝心のAI禁止法も「捕まったら分解されてしまう」というマギーの台詞の上にしか出てこない。誰も捕まらないし、アンドロイドだからといって、排斥されるシーンもほとんどない(実質的には、ワンシーンだけだよね)。
主人公が作った美少女アンドロイド、マギーのキャラクターが読者に媚びまくった設定になっているせいで、受けがいいのかもしれないけれど、なんでこんなものがキャンベル賞を取るんだ?浅い。浅いぞ。ぐおー。
とはいえ、最後まで読んでしまったのは、端々の描写がそれなりに面白いから。アンドロイドからみた世界、というのがそれなりに描かれている。フレーム問題とか、メモリに蓄えられた記憶とか、電源が足りない!とか、セックスとか。でも、そういうものが、ちっとも、ストーリーやキャラクターに深みを与えてない。そういう風に見えました、そういう風に感じました、ってだけなんだもの。浅い、浅いぞ。ぐあー。
えーと、色々貶しましたが、「美少女アンドロイド」と書いてあればとりあえずいい、という人にはお勧めです。今アニメ化すれば、きっと、マギーに萌え狂う人々が続出するでしょう。私は・・・見ないだろうなあ、やっぱり。
. Date: 20030509 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary ジャックナイフのコツひさしぶりに、自転車の話をしましょう。もうお忘れ/ご存じないかもしれませんが、私はMTB乗りです(へっぽこですが)。ずいぶん前に、JunkyardReviewで空を飛ぶための道具だとか重力とダンスだとか書いた覚えがありますが、今日はそういうお話です。
さて、自転車のあまり役に立たない技術の一つに『ジャックナイフ』という技があります。
ブレーキをロックさせて、後輪をひょいっと上げてみせる、というかっこ良いんだか良くないんだかよく分からない技です。自転車のブレーキをロックして前転したことがある人はここを見ている人でも1人や2人じゃないと思いますが、あれを前転寸前で止める感じ、といえば分かるでしょうか。
具体的な方法は、ネット上にけっこう沢山転がっています。ただ、なぜか、世間のHowToページには動きの説明はあっても、乗ってるときの感覚を説明したものはあまりありません。せっかくですから、そちらを中心に書きましょう。
絵を見ながらのほうが分かりやすいので、以下のページを参照してください。 具体的な方法も、分かりやすく説明されているのでおすすめです。 http://www.katch.ne.jp/~isog/tech12.htm http://www.ne.jp/asahi/mtb/trial/motomu/jackknife.html http://member.nifty.ne.jp/AEMM/HOW-1.html
色々なHowToページで、フロントを押し込む、足をしゃくると、書いてありますが、あくまでこの動きの中心点は前輪の接地点です。こう書くと当たり前ですが、乗っているとたいがい忘れます。どんな方法にせよ、「ハンドル越しに見えるあの一点を中心に世界が回転している」という身体感覚を掴むのが一番の早道かと思います。なんだか禅みたいですが、本当です。
さて、始めましょう。ゆっくり、歩くぐらいのスピードでアプローチします。ふらついたりせずに、安定した姿勢が保てる最低のスピードで充分です。普通の走行スピードでやったらまず間違いなく前転します。
前加重ぎみ(最初はハンドル7、ペダル3ぐらいがやりやすいと思います)で両方のブレーキをロック(ガキン、ではなく、きゅうっ、という感じです)。ここで慣性に逆らわずにペダルに残っていた加重をすっとハンドルに移しながら、加重の抜けた足をたたんでやると、ふわっと後輪がついて来ます。同時にその位置に体を残すように、遠ざかっていくハンドルを送り出してやります。感覚的には前輪の接地点を軸に回転するMTBの動きを邪魔しないように、腕を伸ばしながら足をたたむ、という感じです。
オーバースピードになっていなければ、重心は常に前輪の接地点の手前にありますから、前転はしません。逆にいえば、あの点を超えないように上に逃げるという感じが近いかもしれません。「あ、早い」と思ったら、フロントブレーキを解除すれば後輪は落ちます。
アプローチの時の前加重は慣れれば5:5でも、1:9でも同じです。ようするに慣性の法則に逆らわないスピードで後輪の加重が抜ければ後輪は上がります。ジャックナイフの高さを決めるのは、このときの荷重移動のタイミングとスムーズさです。アプローチのスピードは高さとあまり関係ありません。
さて、一瞬の無重力の後に、後輪が落ち始めます。今度は逆に、たたんでいた足を伸ばしながら、ハンドルを手前に戻します。つまり、さっきと全く逆の動作です。体の重心の位置は変化しません。上手くいけば、後輪はほとんど音を立てずに、すとん、と接地します。あとは、落ち着いてブレーキを開放し、足をつかずに走行状態に戻ります。後輪を落とした反動でそのまま後ろに下がるという動きにつなげることもできます(ペダルが空転しないので、意外と難しいです)
この一連の動きを外から見ていると、前輪の接地点からの垂直軸と、体の重心から接地点へ引いた線の角度は常に一定です。この角度が垂直に近づけば近づくほど、高度も滞空時間も長くなります(当然、前転のリスクも高くなります)。
感覚的には、後輪が上がり始めてから接地するまで、自分と前輪の接地点との位置関係はほとんど変化しません。MTBも自分の体もかなりダイナミックに動いているのに、その動きは全て相殺されてしまいます。世界が激しく動いているのに、その動きの中心と自分の意識だけが一定の距離を保ったまま静止している。この感覚は、ジャックナイフに横回転を加えるジャックナイフターンをやっているときはさらに顕著です。
では、皆様。くれぐれもお怪我のなきよう。
ある掲示板へのコメントとして書き始め、興に乗って書くうちに長くなりすぎたのでJunkyardReviewに掲載しようと思ったが、あまりに偏っているので、こちらで公開。
ひさしぶりに、自転車の話をしよう。
動いているものを見るためには、精神は静止している必要がある。狂ったみたいなスピードで山を下っているときも、街中で人の流れをすり抜けながら走っているときも、精神状態は限りなく静止に近い。
加速する程に、精神の分解能が上がっていく。指先でなぞるように、路面の細かい変化を全身で感じ取る。激しい振動と姿勢変化の中で、精神はまるで空中をすべるように滑らかに移動する。
世界が自分の周りで刻一刻と自分との相対位置を変える。一定の距離を保ちながらその動きに追従する。流れに逆らわないように、世界の動きに自分の動きを重ねていく。まるで、重力とダンスを踊るように。
そう、自転車は空を飛ぶための道具なんだ。
(2001.11.14 JunkyardReview)
. Date: 20030511 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary junkyard review更新衛星軌道上で始めてレンダリングされた3DCG作品のお話
大好きな http://www.oyonale.com/で、たまたま見つけた。
"Rendering images on the International Space Station"
はぁ?って感じで読んでみたらビックリ。ほんとにISSでレンダリングしてるし・・・。
それにしても、いい絵だ。
. Date: 20030512 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingを、これはいいなあ。放流されたら見に行こうっと。
だけど、問題は本当に隔離されるのかってとこですねえ。里親を募集しているみたいだけれど、増やして帰さないやつとか、普通のめだかと入れ替えるやつがいないとは限らないだろうしねえ。飼えなくなった生き物は、たとえめだかであっても、殺すしかない。その倫理観をどうやって子どもに教えればいいのか、難しいなあ。
健康増進法の施行で、駅の前で立ちタバコしている人が明らかに増えた気がする。非喫煙者だが、嫌煙というほどでもない私でも、あれはどうかと思うなあ。あれなら喫煙所をちゃんと設けてくれる方がいいよ。
アメリカ合衆国建国時の著作権保護期間である「制作後14年間」に戻そうキャンペーン。申請による延長が可能で、最大28年間。うん、それぐらいがちょうどいいね。
Deep Impact: Send Your Name to a Comet!
「彗星に自分の名前を送ろうキャンペーン」byNASA。
名前を登録すると、2004年12月に打ち上げられるDeepInpactに積み込まれるCD-ROMに名前が掲載される。今年一杯申し込み受付中。んー、CD-ROMか、微妙だなあ。
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030412143159
もはや恒例のColombia Lostアップデート。もうこの手の情報を発信してる個人サイトはここだけなんじゃないだろうか・・・。もう3ヶ月になるのか。早いねえ。
ずいぶん事故のプロセスがはっきりしてきた。そろそろ、まとめページも準備したいなあ。
. Date: 20030513 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]神林長平『小指の先の天使』早川書房(amazon)時間をかなりあけてかかれた連作短編という形式だからだろうか、神林長平の「世界観ぐるぐる感」がずいぶん薄れていて、実にさらっと読める。『猶予の月』みたいなのが好きな向きには、物足りないかもしれない。でも、神林長平の書くあの乾いた「郷愁」とか「せつなさ」が好きだという人にはとてもお勧め。作品で言えば『魂の駆動体』とか『あなたの魂に安らぎあれ』とかかな。個人的には『あな魂』は神林ベスト作品なので、実はこれはものすごく褒めていたりする。
. Date: 20030514 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary リサーチャーという仕事実は、情報の受け取り方の中には、「能動的な受信」というマインドセットがあって、文章書いて食べてる人やリサーチャーと呼ばれる人の多くはみんなこの技術を使っている(と思う)。これは、「必要のない情報を切り捨てること」と「残った情報から新しい事実を組み上げること」のふたつからなっていて、かならず何らかのアウトプットが前提となっている。
そう、まず何よりも先にアウトプットのイメージがある。よくある勘違いに「情報を集めてから、それに従って結論を導き出す」というのがあるけれど、これはものすごく効率が悪い。下手をするといつまでたっても終わらない。結論は先にある。これを、仮説と言い換えれば、サイエンスリサーチだって同じことだ。「事実を組み合わせれば、どんな結論にも到達することができる」これはリサーチャーの信念であり、戒めとして覚えておいた方がいい。そして、どんな結論を選ぶのかは、それぞれリサーチャーのセンスと良心が決める。当然、クライアントの意向が最優先されることは言うまでもない。
あるアウトプットを出すために必要な情報だけをスクリーニングし、再編成することで新しい事実をつくる。これが、情報が生み出される時の基本的な構造だ。人間には認知限界があって、あるアウトプットを出すためには、どこかでインプットを制限してやらないといけない。平たく言えば、見切りをつける能力のことだ。そのインプットの制限さえできてしまえば、アウトプットをつくるのは難しくない。
普段リサーチャーの仕事をしていて、自分が一番時間をかけるのは、じつはこのスクリーニングのためのフィルターを作ることだ。どのくらいの範囲まで押さえれば、嘘をつかずに済んで、お客さんに満足してもらえる網羅性とオピニオンが組み上げられるか。それが分かれば、レポートは書ける。作るレポートが5ページなのか50ページなのかで、その深さと広さが変わるだけだ。
そして、このフィルターを作る作業こそが、レポートのシナリオを作ることに他ならない。そのレポートが誰に読まれ、なにに使われるかを頭に置きながら、スクリーニングする情報の深さと広さを決める。どういう流れで、何と何を述べれば足りるのかを見極める。最初は大雑把でかまわない。そのシナリオに従って情報をマッピングしていけばおのずと細部は見えてくる。
さて、問題は個々の情報に対してどうアプローチすればいいかという点だけれど、これにも実はちょっとしたコツがある。よほど鈍感な人間じゃない限り、こういうリサーチを一度でもやれば、情報というものが相対的なものでしかなくて、絶対的な真実なんてものが存在しないことに気付くはずだ。あらゆる情報は歪んでいて、歪んでいるからこそ情報として価値がある。逆にいえば、その歪みを読み取るために、情報を集めているといったほうがいいかもしれない。
リサーチャーにとっては、ある情報がある立場の人間からどう見えているかの方が、表面的な情報よりも重要性が高い。それが分かれば、自分の立ち位置を決めることができるし、その周りに拾い上げた情報をちゃんとマッピングしてあげることができる。注目すべきなのは、事実ではなく視点のほうだ。
そして決して忘れてはいけないのは、リサーチをやっている君自身もある歪んだ視点に立っているということだ。君はニュートラルな存在ではない。自分自身がどう歪んでいるかを認識するのは簡単なことではないけれど、そのことを自覚してさえいれば、シナリオを修正することは難しくない。
君は全てを知ることは出来ない。でも、それは、目の前の情報を作った誰かも同じことだ。嘘をついてはいけないけれど、真実を明らかにしようなんて思わない方がいい。それは君が決めることじゃない。実は、お客さんが欲しがっているのは、真実ではなく、その真実を見るための視点のほうだ。信じるに足るだけの情報と、それを読み解くための視点をちゃんと手渡せば、真実はお客さんが作ってくれる。リサーチャーというのはそういう仕事だ。
上の文章は、ずいぶん昔に、リサーチャーのクリエイティビティという議論をしたときに勢いで書いて、ハードディスクの肥やしになっていたもの。Blogの話を読みながら、何となく思い出した。ものすごく読みにくいけれど、覚え書きなので悪しからず。
Underconstruction by Taiyo@hatena
http://d.hatena.ne.jp/t_trace/20030513#1052827126
私が“米国式日記サイト”blogに注目する理由
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20030511/1/
どう読んでも、単に「日々のよしなし事日記」と「ニュース紹介日記」を分ける言葉ができた、というだけに見えるのは気のせいかなあ。まあ、世の常として新しい言葉ができれば、新しいビジネスが生まれるのはいつものことですけどね。
上に関連して言えば、Blog/Web日記は「能動的受信」のためのメディアだ、というのが個人的な感想。自分の立ち位置を確認するのに、こんなにふさわしいメディアはないと思う。アウトプットを続けることで、インプットがどんどん研ぎ澄まされていく。Blogが既存のマスメディアを脅かしているとすれば、それは情報ソースとしてのBlogではなく、情報を相対化しようとするBloggerのマインドセットの方なんじゃないかなあ。
. Date: 20030515 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingCracking idea gets to the core (nature)
TNT火薬数メガトンに相当する核爆弾で地面に割れ目を作って、そこに大量の融けた鉄を流し込む。鉄は自重でどんどん沈んでいって、一週間ぐらいで地球のコアに達する。この鉄の塊の中にグレープフルーツ大のプローブを入れておけばマントル層とコア層の調査ができるぞ!というお話。プローブからのデータは極微弱な地震波を発生させて、重力波検出施設LIGO(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)で拾う。
でも、プランを作った本人も「実現したらビックリだね」とか言ってるらしい。
A Modest Proposal by David J. Stevenson
→JunkyardReview掲載予定
Scientists: Only 10 Percent of Big Ocean Fish Left (Reuters)
マグロやカジキなどの外洋性大型魚が激減しているという話。
ちなみに、日本のマグロ消費量は世界の6割を占める。クジラの次はマグロかな。
Space Station Science Picture of the Day: Star Trails (Science@NASA)
ISSは、地球に対して水平飛行をするように軌道上を周回している。そのため恒星に対しては、地球を一周するごとに反転するような動きとなり、たった30秒の露光で星が円を描いて光跡を残す。また、当然ながらこの「ISSの天の北極」は地球から見る北極星とは違っており、この写真では鶴座を向いている。
Brighter Neptune suggests a planetary change of seasons (EurekAlert!)
6年に渡るハッブル宇宙望遠鏡による観測で、海王星が徐々に増光していることがわかった。これは海王星の雲の幅が増えていることが原因で、海王星にも四季があることを示唆している。
http://a.hatena.ne.jp/isana/
ほったらかしにしてあったアンテナにサイトを追加し、カテゴリ分けをする。
これで多少使えるリストになったかな。
. Date: 20030516 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping超指向性音響システム「ここだけ」を製品化,発売 (三菱電機エンジニアリングプレスリリース)
超音波のひずみが、ちょうど可聴域になるように調整された音響システム。超音波の直進性のために、ごく限られた範囲の外では音が聞こえない(たぶん反射があるから全く聞こえないわけじゃないはずだけどね)。
この技術、海の向こうではずいぶん前からAudio SpotlightとHyper Sonic Soundが競争している。国産は初かな。
Jeff Hawkinsインタビュー(ZDNN)
Handspringの創設者。Palm作った人。
「デスクトップ/ノートPCは携帯電話/PDA統合型デバイスのアクセサリになろうとしている」そうな。そうか?確かに、日本の中高生みたいに「モバイル」が主目的ならそうなんだろうけど。素直に考えると、やっぱりこの二つには主従関係なんてないんじゃないかなあ。ちょっと色眼鏡かかってませんか、Mr.ホーキンス?
ミンスキー氏、最近の人工知能研究を批判 (HotWired)
んー、「最近の若者は夢がないぞ」という爺さんには、最近の若者の夢が見えていない、という好例ですな。「心の社会」(amazon)は面白かったんだけどねえ。かっこ悪いなあ。
『我輩はサルである』は可能か? (Hotwired)
「タイプライターと無限の時間を与えれば、サルでもシェイクスピアの作品を作り出すことができる」という有名なテーゼの実践。ちゃんと皮装本も買える。
http://www.vivaria.net/experiments/notes/publication/
PDF版なら無料でダウンロードできる。おすすめ。
個人的には自己意識や知能というのは、感情移入の能力と同じものだと思っているので、サルが打ち出したシェイクスピアも、中国語の部屋も、チューリングテストも全部知能が存在することの証明になると思っている。あたかも知能を持っているかのように見えるものには、知能がある。明快でしょ。
HalfLifeというPCゲームの続編のデモムービー。リアルタイムでこれだけの物理シミュレーションが動くんですか?マジですか。最近はみんなこうなんですか?ゲームの趣味はほとんどないけれど、これは触ってみたいなあ。
Wired to the Brain of a Rat, a Robot Takes On the World (NewYorkTimes)※要登録無料
ネズミの脳細胞を利用したロボットをジョージア工科大で作っているというお話。
Nedelin Disaster
1960年11月24日に旧ソ連バイコヌールで起きたICBMの事故。
http://www.russianspaceweb.com/r16_disaster.html
http://www.astronautix.com/articles/therophe.htm
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030416031918
下で予告した、地球の内部構造を探査する方法の話。
ちょっとまとまりが悪いなあ。あとでちょこっと直すかも。
. Date: 20030519 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Dailiy ClippingPostPet&AirBordの八谷和彦氏がメーヴェを作っているというお話。上記サイト1/2のラジコン模型の飛行動画が見られる。おー、それっぽいですねえ。でも、このままの形で、「あの飛行姿勢」をパイロットに取らせたら、ピッチもロールもものすごく不安定なはず(たぶんまともに操縦できない)。
まあ、八谷氏も「あの形」にはこだわらないって言っているみたいだし、最終的にはもう少し現実的な姿に落ちつくんじゃないだろうか。でも、「パーソナルジェットグライダー」というコンセプトにはものすごく期待。
サーバクライアント方式ではなくライブラリ方式のかな漢字変換システム。Linux、BSD、Solaris。emacsからも利用可。
PoBOXの後継。単文節変換、辞書への品詞・頻度情報の付加、ひらがなによる入力など。
なんでや、なんでワシのPCはドック入りしとるんや?うう。
不正なベクトルが入力されたために、セーフモード<%= fn 'トラブルの際に、最低限必要な機器のみを動作させ、地上からの指示を待つモード' %>へ移行したとのこと。搭載機器の調整に支障が出る可能性があり、ミッションコントロールではリカバリープログラムを作成中。
もう絶版になったと思いこんでいたが、都内某巨大書店の棚で偶然出会い、あっという間に読了。理論物理学者にしては珍しいタイプのエッセイを書く人だなあ。いろんなタイプの文章が入っているので一概には言えないけれど、あえて言うなら、科学を誰にでも分かりやすくではなく、科学の美しさや奇妙さをさらっと切り取って見せるというタイプのエッセイ。
Junkyard Reviewで目指しているものに、とても近く、それゆえに遠い。
前からなんとなく不安な挙動を示していた液晶のバックライトが、とうとう点かなくなってしまった。仕方なく修理に出す。あー、副脳がないのはものすごく不安。まあ、これを機に山のようにたまった積読を消化することにしようかな。
. Date: 20030520 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Dailiy Clipping軌道決定次世代型無人宇宙実験システム(USERS) (USEF)
昨年9月10日、H-IIAF3によって打ち上げられたUSERSの帰還・回収を5月26日(予備日:5月27日?6月5日)に実施。
Countdown to Mars begins (BBC)
Mars Expressが6月2日にカザフスタンから打ち上げ。
It's a knockout : First rat to have key genes altered. (Nature)
初のノックアウトラット。これまで、ノックアウト「マウス」はいたけれど、「ラット」は初めて。マウスは小さすぎて生体学的な実験にはあまり向かず、主に遺伝学系の実験に使われている。ラットはマウスの10倍ぐらいある上に物覚えが良いので、薬学や医学、心理学などの分野で利用されている。ラットのノックアウトができたのは革命的。
. Date: 20030521 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新下で予告した、『ひまわり』のお話。
余禄の軌道制御の話は、いつかネタにしようと思ってストックしてあったものを蔵出し。
Shuttle関連で使おうと思ってたんだけど、まあいいか。
延命のひまわり5号、22日に米気象衛星にバトンタッチ (asahi.com)
今日でひまわりからの映像は最後。
今運用されているひまわり5号は、とうの昔に耐用年数が切れていて、あっちこっちにがたがきている。本当なら次世代機が打ち上げられるはずだったけど、2年前のH-IIAの事故で失われてしまったために、代替ができず、騙し騙し運用していた。流石にもうや倍ってことで、アメリカから「GOSE-9」という衛星をレンタルして、使う事になった。実は、このGOSE-9も耐用年数が切れているんだけどまだ元気だからいいや、ってことらしい。夏には後継のMTSATが打ち上げられるはずだったんだけど、製造会社のミスが重なって、来年1月までずれ込んでいる。運用開始は3月頃かな。
→Junkyard Review 掲載予定
ま、まじポンですか。この間、TEFALの鍋とフライパンセット買ってホクホクだったのに・・・。
あまりに不安だったので、ちょっと調べてみた。フライパンをごく普通に使っている場合には、180度ぐらいまでしか温度は上がらない。ただ、空焼きするとアルミ鍋は300度近くまで上がるため、有毒ガスが発生する可能性がある。だから、フッ素加工のフライパンは絶対に空焼きしてはいけない。そーいえば、説明書にもそう書いてあったよ。
http://www.fluon.jp/b/b_4/b_4_1.html
http://www.jfia.gr.jp/fusso/toriatuk.htm
http://www.nakao-alumi.com/kappa/faq.htm
→Junkyard Review そのうち掲載予定?
コンピューターの原理の概説書としても、脳科学の概説書としても中途半端。おまけに両者がほとんどリンクしていない。コンピューターの歴史と概念をざーっと説明する。最新の脳科学を専門用語垂れ流しでざーっと解説する、以上。両方の内容がぶちまけてあるだけで、ぜんぜんまとめようとしないので、まったく印象が残らない。科学啓蒙書としては最低レベル。
同じ作者(茂木氏)なら、 『心を生み出す脳のシステム』NHKBook(amazon) のほうが一千倍まし。
. Date: 20030522 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingSwitch-A-View (Xerox)
当てる光の波長によって、隠れた画像が現れる印刷。Xeroxの底無し技術力がまた一つ。
How does Dyson make water go uphill? (BBC)
James DysonがChelsea Flower Show に出展した、"Wrong Garden"という作品の紹介。まるで、坂を水が昇っていくように見えるそうな。うぉー、見たい。上記リンクでは、その理屈を紹介している。ちなみに、このダイソン氏は、あのダイソンクリーナーの開発者。
第7次クルー科学主任ドン・ペティの滞在記。montreal lifeのkay-jさんの労作。ものすごく面白い、おすすめ。
つづいて、ISS第7次滞在クルーのエド・ルーの手紙も翻訳されている。
. Date: 20030523 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingSARSは宇宙から来た=英国・インドの学者3人が有名医学誌に新説発表
相変わらず、そんな事いってんのかこのおっさん。このニュースに出てくるチャンドラ・ウィクラマシン教授はパンスペルミア説(胚種広布説)の有名人。この人、ことあるごとに「エイズは宇宙からー」「インフルエンザは宇宙からー」と叫んでいる。おなじくパンスペルミア説と定常宇宙論で有名な故フレッド・ホイル先生の弟子にあたる。トンデモ加減はちゃんと受け継がれてますねえ。
おいおい、大丈夫か?画像の配信がされなかったり、遅れたりしたそうな。アメリカ側の言い分だと「なおった」らしい。というか、搭載機材のコンディションも聞かずにレンタルするなよー。
宇宙航空研究開発機構 | JAXA(NASDA)
2003年10月1日に宇宙開発関連3団体が統合されて誕生する新団体の、ロゴと略称が決定。Japan Aerospace Exploration Agencyで「JAXA=ジャクサ」。んー、「じゃくさ」ちょっと読みにくいなあ。
あーそうか、日本航空技術協会(Japan Aeronautical Engineers'Association)と被ってるんだ。
http://www.jaea.or.jp/
. Date: 20030526 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新数日前に予告していた、テフロン加工のお話。また、まとまりのない文章になってしまった・・・。うーむ。
ちなみに、T-FALのフライパン&鍋セットは凄くいいぞ。
[clip] Daily ClippingShuttle Investigation Chief Calls Rescue Try 'Conceivable' (NewYorkTimes)※要登録無料
コロンビアの右翼の破損が軌道上で判明していたら、アトランティスを緊急で打ち上げて乗務員を救い出すことができたかも知れないというお話。プリフライトチェックをせずに、突貫作業で打上げ準備をすれば間に合ったかもしれないということのようだけれど、そーいう問題じゃないだろう。
可能性としてはあったかもしれないけれど、ものすごく偶然に左右される話だよね。チェックで不具合が見つかるのはいつものことだし、チェックをせずに打ち上げて事故になったりしたら目も当てられない。問題は、助けられたかどうかじゃなく、助けられる体制が作られていなかったことでしょう。シャトル計画が予想以上にメンテナンスコストがかかって、年間の打上げ数が予定よりもかなり縮小されたことで、すでに、軌道上で予備のシャトルがレスキューを行う道は閉ざされていたんだ。それをさておいて、助けられたかもしれないと騒ぐのはあまりに浅はかというものじゃないか?
地球の兄弟いっぱい? 惑星の半分以上「岩石型」と試算 (ASAHI.COM)
惑星形成理論の井田教授が、惑星系のうち岩石を主成分とする惑星のしめる割合はこれまで思われていたよりも多く、半分以上になるのかもしれないという発表を26日からの会合で行うとのこと。うぉおおおおお、期待。
Astronomy Picture of the Day 2003.05.26
初めて地球以外の惑星軌道上から撮影された地球の画像。
そうだ、僕たちはこの光景を見るためにあそこに行くんだ。僕たちは特別な存在ではない、ただそのことをを知るために、莫大なコストを掛け、命を賭してまでロケットを飛ばし、僕たちはあそこを目指す。なんたる無駄遣い。なんて素晴らしい無駄使いなんだろう。
延長保障に入っていて、本当によかった・・・。
. Date: 20030529 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingES細胞:国産初の作製に成功 京大再生研 (Mainichi INTERACTIVE)
えー、あちこちの新聞で話題になってましたが、なぜかこのES細胞がクローンの倫理を巡って喧喧諤諤の議論の対象になっている(いた)ことに触れた記事はあまりない。今のところ日本ではES細胞の基礎研究はOKだが、個体発生などへの応用は禁止されているが、ヒトの胚の商用化につながるとか、クローン人間の研究とすれすれなどの理由から反対する声もある。
参考)ASAHI.COM記事
参考URL)
京都大学再生医科学研究所 ヒトES細胞プロジェクト
http://www.grs.nig.ac.jp/escell/human/index.html
同、参考資料のページ
http://www.grs.nig.ac.jp/escell/human/04_03_01.html
宇宙科学研究所、「はやぶさ」のイオンエンジン着火試験を開始(PDF)
いぇー!順次テストをして、出発は6月中旬とのこと
成層圏IT基地はいよいよIP通信実験へ (InternetWatch)
通信総合研究所がNASAに『Path Finder Plus』を借りてやってるやつ。
FLASH FILM FESTIVAL Finalists/Winners (Flashforward2003)
Sci/Tech Web Awards 2003 (Scientific American)
. Date: 20030530 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [usability] 文章を書くための技術Undercoustructionの太洋さんと、OneNightStand"Studio-S"のいのしょさんと都内某所で会食(こう書くとオフ会みたいだな)。ずいぶんこの話題で盛り上がる。
文章を書くというのは純粋に「技術」であって、それを芸術にするかどうかはまた別の問題だ。日本の国語教育はひたすら「文学を読むこと」に傾倒してきたし、わずかながら行われている作文教育も「文学者を育てる」ことを最終目標としているようにみえる。
日本人は驚くほど、文章を書くことに対するトレーニングを受けていない。大学に入って英語で論文書くためのトレーニングを受けさせられて、目からうろこが落ちた。ほとんど公式に当てはめるように、定められたフレームにそって文章を書くと、それなりのものが出来上がる。
例えばこういう感じ。
「私がこれから主張するのはXがYだということである」
「理由1」「理由2」「理由3」
「つまり、わたしのいいたいことはXがYだということなのだ」
こう書くと、「こんなものは文章じゃない」といってバカにする人がいるけれど、一度やってみるといい。実は、この中に文章を書くためにやらなきゃいけないことがぎっちり詰まっている。このフレームが要求しているものをちゃんとこなせるなら、かなりの文章力だと思っていい。コンセプトと目的の言語化。目的を実現するための手段とプロセスの明確化。その手段同士のフォーカスとスコープの一致・・・こういうことが適切に行われていないと、このフレームで文章は書けない。
これはなにも論文を書くためのフレームじゃない。伝えたいことを構造化して要素に分解し、再配置するというのは、自分の考えを形にして人に伝えるための基本的な技術だ。小説だって、エッセイだって、そのプロセスを経て書かれている(無意識にやっている人もいるし、意識的にやっている人もいる)。文章力というのは「表現力」の問題ではなく「論理的思考能力」の問題なんだ。
日本の「国語」の授業には、この「文章を書くための思考能力」を磨くことがすっぽり抜け落ちている。これは、かなり憂慮すべきことじゃないだろうか。
これはH-IIF3で打ち上げられたUSERSの再突入カプセル。どうやら無事に回収されたみたい。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030602 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 葛西臨海水族園久しぶりに行ったが、なぜか棘皮動物の楽園と化していた。どの水槽にもこれでもかとナマコやヒトデが転がっているし、「エキノデルマータ」(棘皮動物)マークがわざわざついていたりする。どうしたんだ葛西、ナマコやヒトデはメジャー受けするとは思えないぞ。もう少しキャッチ-なほうがいいのでは・・・。
バーニャカウダというのは、にんにくとアンチョビとオリーブオイルで作ったソース。あっためて野菜なんかをつけて食べるものとして、イタリア料理の本なんかにレシピが出ている。が、フランスパンにつけて食べるとすごく美味しい。あまりに美味しかったので、メモ代わりに書いておく。臭さを取るために、事前ににんにくを牛乳で煮るのがコツ。
材料
・にんにく:1?半個(粒ではない)
・アンチョビ:にんにくと同じぐらい
・EXバージンオリーブオイル:上記二つを足した量の倍ぐらい
・牛乳:適量(後述)
「まず、にんにくの下ごしらえ」
1)にんにくを剥いて、半分に割って芯を取る。
2)小鍋ににんにくを投げこみ、牛乳1、水1の割合でひたひたになるぐらいに
して、火にかける(中火ぐらい)。
3)沸騰したら、ふきこぼれないように弱火にして5?6分煮る
4)汁を捨てる。
5)2?4を全部で3回繰り返す
「次に裏ごし」
6)にんにくを裏ごし
7)アンチョビも、包丁で叩いて細切れにする(裏ごしすればなおよし)
めんどくさければ、「アンチョビペースト」を買うとよい
「混ぜて、あっためる」
8)出来上がったにんにくとアンチョビのペーストに、
オリーブオイルを加えて、弱火で暖める(3分ぐらい)
出来上がり!
バーニャカウダは「温かいお風呂」という意味で、温かいうちに食卓に出して野菜などをつけて食べる。雰囲気としては、フォンデュみたいな感じ。パブリカとか、塩茹でしたブロッコリーとか、ジャガイモとか、きゅうりとか、にんじんとか何でもいいみたい。
お勧めはなんと言っても、フランスパン。美味すぎ。赤ワインがうまうま。
パンにつけるなら冷えてても大丈夫。ちゃんと密閉しておけば1?2週間は持つそうな。
. Date: 20030603 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [usability] Contents Usablityこの間の『文章を書くための技術』という偉そうな文章が某所から参照されていたので、自分の興味が枯れないうちに続き(?)を書いておくことにする。実はあの文章の元は、新人教育用のメモとして書かれたものを思い出して引っ張り出してきたもの。元の文章は、紆余曲折を経て、下の絵になる。
http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/web_c-use01.png
これは、社内研修用に作った「企業Webサイト設計のための覚え書き」の一部。
「User-Centered Design」という考え方では、「ユーザーの経験をデザインする」ことを主眼においているけれど、「じゃあユーザーって誰よ?」とか、「具体的にどうすればいいの?」という疑問にはあまり応えてくれない。そこでひねり出したのが、上のチャート。
「真っ白なユーザー」はいない。ユーザーはサイトを訪れる時に、常識や慣習、既存の概念、予備知識などを携えてやって来る。そして、彼らはそのサイトに対して何らかの期待をもっているはずだ。「企業情報」かもしれないし「リクルート情報」かもしれない、もっと抽象的に「なんか面白いもんねーかな」かもしれない。Webサイトのそれぞれのページは、そういうユーザーの期待を引き受けつつ(時に裏切りながら)、次のページへその期待を引き継いでいかなければならない。
当然、ユーザーの期待はページを辿るごとに解消されたり、変化したり、強化されたりするはずだ。そのユーザーの期待の変化こそが、ユーザー経験そのものであり、「経験のデザイン」がフォーカスすべきポイントになる。そのコンテンツに相対した時、ユーザーが何に期待し、何をすでに持っているのか、それを検証しながら注意深くコンテンツを配置していく。それがWebサイト設計の中心課題となる。コンテンツにもユーザビリティがある。それは見た目ではなく、中身の問題だ。
これは、Webサイトの話だけれど、文章だって全く同じ(極論すれば、デザインや画だって同じだと思う)。「わかりやすい文章を」とか、「読み手のことを考えて」とか、「論旨をはっきりと」とか、言い方は千差万別だけれど、実はこれらは中心にある問いに全く答えていない。「分かりやすさ」や「読み手」や「論旨」は、時と場合によって全く違うし、文章を読んでいる最中にもどんどん変化していく、それにちゃんと追従しながら文章を書くのは、かなり難しい。
先日の文章の中で例として紹介した「フレーム」も、当然ながらこの「読者の期待への追従」を暗に要求している。読者の期待を無視して論理を展開させても、文章は説得力を持たない。そういう文章は、どんなに論理的整合性が取れていて主張が正しくても「的外れ感」残る。逆に、構造がなくても、ユーザーの期待に応えている文章は十分な説得力を持つはずだ。
文章を書くための技術としてあげた、「コンセプトと目的の言語化。目的を実現するための手段とプロセスの明確化。その手段同士のフォーカスとスコープの一致」というのは、実はこういうことだ。「論理的考能力」と一言で書いたけれど、その向かうべき先は、論理の構造ではなく、ユーザーの期待とコンテンツの整合性の方だ。あるトピックを表現するために、非論理的な表現が必要なこともある。問題は論理的か否かではなく、そのコンテンツが正しい方向を指差しているかどうかの方だ。
ひゃー、読み返すとまた偉そうだなあ。しかし、自分でこんなことを書きながら、一つ一つが刺さる刺さる。いたたたた。言うのは簡単なんだけど・・・がんばろうっと。
. Date: 20030604 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingLizards help adhesive design(Nature)
ヤモリの足をモデルに、とても粘着力の強いテープが作られたという話。
Junkyardで以前紹介したこれが、実用化されたってことかな。フォロー書こうかな
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030504174611
上のヤモリテープの記事。短めだけどフォロー記事だからいいかな。
Junkyard Reviewは火星ネタを準備中。
でも、底なしなので、どこをどう書こうか迷っている。探査機の話はみんな書いているしねえ。
. Date: 20030605 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [excel] Excelで遊ぶ最近、Excelにはまっている。特に「分布図」が楽しい。
下は、試みに作った「星図」、テスト版なので、まだ白鳥座しか入ってない。
赤経と赤緯のデータを、ちょこちょこ変換して、三角関数に放り込んだだけのもの。
http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starchart_test01.xls
※Exelのファイル直リンクなので注意。
もう少し工夫すれば、著作権を気にせずに使える星図が・・・うふふふふ。
※某所で紹介していただいたようなので、ご報告までに(06.19)
新しいバージョンがアップされています、カテゴリの[excel]から関連記事を辿ってください。
. Date: 20030606 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [usability] 文章を書くための技術(追記)こんなことを偉そうに書けるほど、私の文章が分かりやすいとは思えませんが・・・、まあ自戒も込めてということで。
わかりやすさは、ただの表現技術の問題ではないのだ。(山形浩生)
あー、全部ここに書いてあった。引っ込めようかな・・・。
なんだか、文章の型の話があちこちで引用されているみたいだけれど、いいたかったことは、「型に入れて書けばオッケー」という話じゃなくて、「型にはめるためには、実はかなり高度なことをやらなきゃいけない」という話のほうだ。その「高度なこと」っていうのが、「読んでいる人の期待に応えること」。二回目に書いたように、読んでいる人の期待に応えることができれば、型なんかにはまってなくても説得力をもたせることができる。逆にいえば、型にはめたって、その文章が読んでる人の期待に応えていなければ、ちっとも分かりやすくなんかならない。
これは、山形氏も述べていることだけれど、「型」は嵌めるためのものではなく、使うためのものだ。ユーザーの期待に応えるためのフレームとしては「型」も悪くないツールだと思う。でも型にはめれば分かりやすくなるかといえば、絶対にそうじゃない。「りんごは、赤くて丸いから、おいしい」、この文章には全く説得力が無い。だって、これっぽっちも理由になっていない。要するにこれは型に沿って書かれていない。
僕の思う「文章を書くための技術」というのは、「型にそって書くこと」よりも、むしろ「型に沿って書くために考えなければいけないこと」のほうだ。正しく使うなら、型は思考をドライブしてくれる。なぜなら、型が僕たちにある思考を要求するからだ。自分が一番伝えたいことは何か、誰に向かって伝えようとしているのか、そしてそれを伝えるためには何をしなくちゃいけないか。そういうことがちゃんと考えられていなければ、型に沿って文章を書くことはできない。
文章の型も武道や花道の型と全く同じ。型に沿って体を動かすと、自分の体のぶれや欠点があらわになるように、型に沿って考えると、自分の思考のぶれや曖昧さが見えてくる。そして、型の意味や型が要求しているものを理解せずに無自覚的に使っても全く意味が無いのも同じだと思う。「型破り」は型が表現していることをちゃんと組み入れた上で破るから意味がある(「守破離」やね)。
そして、僕は個人的に、その型が表現しているものの根幹にあるのは、「読み手の期待に応える」ことだと思っている。これは、面白いテーマを探そうとか、興味を引くような文言を使おうってことじゃない。前回書いたことだけれど、文章を読むときには、たいていの人が次にくる展開を「期待」しながら読み進めていく。たとえば、"しかし"、とかいてあれば、前の言葉を否定する内容が来るはずだ。読み手は、おおっ、と思いながら身を乗り出す。そこで「実はね・・・」と切り出す。あるいは、あるトピックを持ち出すならば、当然押さえておくべき事項がある。僕が「期待に応える」と書いたのは、こういう読み手とのリアルタイムのやりとりのことだ。
上の山形氏の文章に書かれている「話すように書く」という感覚は凄く近いような気がする。ただ、これはそんなに簡単なことじゃない。きっと、山形氏は普段から人にものを説明するのが仕事(彼は本業がコンサルタント)だから、ちゃんと一番相手の聞きたいことを話すというトレーニングを積んでいるんだろう。でも、これはずいぶん想像力がいるし、その想像力を維持するために、ある種のテンションと自制心がいる。
「分かりやすく」という言葉は、「何を」と「誰に」が無いと全く意味をなさない。でも、これをちゃんと意識するのは、結構大変だ。彼の言うように「これを伝えたい」という強烈な欲求と内容がないと、文章はどんどん散漫なものになっていく。実は、一番大変なのは、文章を書いている間、その「これを伝えたい」という想いを維持することなんじゃないだろうか。
ああああ、この話題で書くたびに、すどーんと落ち込むなあ。こんなこと書いているけれど、自分じゃ全然やれちゃいないし・・・。文章書くのって本当に難しいよ。
科学雑誌、読んでますか?(slashdot.jp)
日経サイエンスと、ポピュラーサイエンスは読んでるが・・・。前者は専門的すぎて「面白み」に欠ける(つーか高いよ)。後者はかなりテクノロジー寄りだけど、いまでてるなかではおすすめかなあ。
でも、一般向け科学雑誌として一番優れているのは『子供の科学』だと思うぞ。いや、冗談抜きで。
と、昼休みに今月号のポピュラーサイエンスを読んでいて気付く。
ぐらぁ、GUIの生みの親「アラン・キー」ってだれだぁぁぁ。きー。
いつも思うんだけど、この雑誌、訳がいまいちなんだよなあ・・・。
. Date: 20030609 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [excel] Excelで遊ぶ2先日からちまちま作っている「エクセルの分布図で星図」をバージョンアップ
http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starchart_test02.xls
今度は、赤道座標から地平座標に変換して、観測地と日時を入れるとちゃんと位置が出るようにしてみた。まだ、何となく三角関数の変換が怪しい気がするけど、ちゃんと24時間で北極星の周りを白鳥座が一周する。原点が天頂、上が北、下が南、右が東、左が西(のはず)。
あとは星座線か・・・力技で出す方法ならあるけど、何かいい手がないかなあ。
こと座を追加、アルゲニブ(秋の大四辺形の一部)を追加(チェック用)。
計算値を再チェック。時間の計算値を修正。
ついでに、X軸の左右を入れ替えて地表から見上げた状態に修正。
でも、やっぱり歪んでるねえ。
Girl With Dreams Names Mars Rovers 'Spirit' and 'Opportunity' (NASA)
今月、打ち上げ予定のアメリカの2つの火星ローバーが「スピリット(魂)」と「オポチュニティ(機会)」と名づけられた、というニュース。
「私は孤児院にいました。そこは暗くて、冷たくて、寂しい場所でした。夜、私はきらめくような空をみて、気分を紛らわせていました。私はそこを飛ぶことを夢見ていたんです。アメリカは、どんな夢でもかなえることができる場所です。その「魂(Spirit)」と「機会(Opportunity)に感謝をしたいと思います」(採用されたSofi Collinsのエッセイ)
. Date: 20030610 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping2chの同名スレのまとめサイト。私にとっては、むしろ萌え(燃え)サイト。
この目で見てみたい物件が目白押し。うわー、うわー、うわー。
著作権侵害の立証責任転換(真紀奈17歳)
今、作られようとしている新しい著作権法では、著作権違反で訴えられた側に、該当作品が複製や翻案ではないことを立証する責任があるらしい。えー、それは立証責任に関する原則に反してませんか?立証責任は訴えを肯定する側にかせられる責任じゃなかったっけ。
個人的にcopyrights resignedを標榜しているけれど、このルールで訴えられたらたまらんなあ。お願いじゃ済まなくなるねえ。
ここを読むと、立証責任がどちらにあるかは、ケースバイケースということらしい、ただ原則として「権利が侵害された」という場合には、侵害されたと訴えている側に立証責任があるとするのが通例みたい。上にも書かれているけれど、「不在の証明」は別名「悪魔の証明」とも呼ばれ非常に立証が難しいとされている。「私はパクってなんかいません」という証明がどれほど難しいか、想像するだにおそろしい。
. Date: 20030611 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingNASA's 'Spirit' Rises On Its Way To Mars(NASA)
無人火星探査車「MER:Mars Exploration Rover」を載せたデルタロケットは、日本時間の昨夜午前2時58分、無事に打ち上げられました。打ち上げられたのは、2台あるMERのうち「スピリット」の方。火星到着は7ヵ月後、年明けですね。もう一台の「オポチュニティ」は今月26日、午前1時38分(日本時間)に打ち上げの予定。
. Date: 20030612 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingJavaが入っていれば、動画カメラのコントロールもできる。あー見たいなあ。でも、この感じだと近くには寄れなさそう。うむむ、やっぱり行ってみよう。
. Date: 20030613 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 改正著作権法が成立がーん、通っちゃった・・・。
この間紹介した、「バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳」にまとめがあります。詳しくはそちらを。
ちなみに、ここの法律関係の説明は秀逸のわかりやすさです。お勧め。
関連して、最近始まったローレンス・レッシグのBlog翻訳から
著作権で縛ると、古い映画が腐る、というお話。
[clip] Daily ClippingThe Empire That Was Russia: The Prokudin-Gorskii Photographic Record Recreated
帝政ロシア時代のカラー写真。すげー。
何が凄いってこの時代、まだカラーフィルムは存在しない。というかフィルムもまだない。これは、3色のカラーフィルタで白黒撮影した3枚のガラス乾板を、対応するフィルタを通して一つのスクリーンに投影することでカラーの画像を得るという方法で撮影されたもの。上記のサイトに掲載されているのは、このガラス乾板をPC上で合成して復元したもの。
. Date: 20030616 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary IWC@ベルリンJapan threatens whaling walkout (BBC)
日本が「現在開催されているIWCのカンファレンスで進展がなければ、IWCを脱退することも辞さない」と言っているというニュース。なんで、日本語のソースが見つからないんだろう。
関連記事)Battle joined over world's whales(BBC)
日本はこの間、調査捕鯨のデータを示して、南氷洋でのクジラの頭数は増加しており(一部では増えすぎて漁場を荒らしているという話もある)、商業捕鯨を再開しても問題ないと主張してきたが、IWCではのらりくらりと具体的な議論が避けられてしまい、議論が全く進展しない。そういう状況に対して「いいかげんにしないと切れるぞ」と言っているわけですね。
参考)
極北同盟(ノルウェーとアイスランドの捕鯨協会によって組織された反反捕鯨団体)
水産資源の持続的利用を考えるページ(水産庁捕鯨班)
クジラ・ポータルサイト(ベルリン会議のレポートが掲載されている)
グリンピース・ジャパン:捕鯨関連ページ(捕鯨反対派からの意見)
日本にいると、捕鯨推進派の意見が大半で、賛成派の意見はあまり見えません(推進派の文脈の中で読むのが大半でしょう)。ぜひ、GPJのページも一読されることをお勧めします。ちなみにわたしはどちらかと言えば捕鯨推進派ですが、つい粗探しをしながら読んでしまう自分に愕然としました。落ち着いて、想像力をフル回転しながら読むと、どちらの立場から見ても、相手が欺瞞に満ちて見えるという構造が見えてくるはずです。青筋を立てて反論するまえに「私たちはこう見られているんだ」という事実を受け入れるのは、悪いことじゃないと思います。
全然関係ないですが、先日渋谷の某有名クジラ料理店の前を歩いていたら「勇魚コース」の文字が・・・。思わず、ふらふらと店に吸い込まれそうになりました(勇魚は本名なんです)。ご、5000円か、いつかは食べに行こう、そうしよう。とりあえず、今度ランチを食べに行こうかな。
そうそう、僕が捕鯨に賛成なのは、こういうものを食べられなくなるのはちょっと寂しいというごくパーソナルな理由です。だから、減っているんだから食べるなと言われれば、仕方ないかなあと思うし、いやいや増えているんだから食べてもいいよ、といわれれば、そうか良かったなあと思う。昔は積極的推進派だった時もありましたが、今はそういう感じです。
. Date: 20030617 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping空中写真閲覧サービス(試験公開) (国土地理院)
東京・大阪・名古屋の1940年代?50年代、1990年?2000年の航空写真が閲覧できる。結構楽しい。でも、ちょっとサーバが重いなあ。こういう場合は、ガンガン負荷をかけてテストに貢献する方がいいのか、そおっとさわる方がいいのかどっちなんだろう。
Greater protection for whales agreed(BBC)
IWCの1日目に、「鯨類保存委員会」の設立が圧倒的多数で採択されたとのこと
日本語記事)ASAHI.COM
BBCの記事の中で、メキシコの委員も述べているように、IWCはInternational Whaling Commissionの略(国際捕鯨委員会)で、本来鯨類資源の持続的な利用について協議する国際委員会のはず、その場所で「鯨類保護」の委員会の設立が採択されるのは確かにちょっとおかしいような気がするねえ。
あなたの人生は誰のもの?(NikkeiBP)
昨年,住民票コードが印刷されたハガキを受け取ったとき,特になんとも思わなかった方も多いと思う。しかし,私は「ああ,これでおしまいだ」と思った。
私にとって,この11ケタのコードはデータベースのプライマリ・キーに見えた。これまでバラバラに収集されてきた,そしてこれからも収集されていく個人情報あるいは顧客情報が,このコードによって関連付けられ,統合されていく姿が脳裏に浮かんだ。
なんて、幸せな人なんだろう。個人情報が分散していたから「プライバシー」とやらが保護されていたとでも思っているんだろうか。問題なのは、データが一元化されることではなく、情報が分散していれば個人情報は把握できないはずだ、なんていうナイーブな神経の方じゃないか。
なんだか腹が立ってきたので→Junkyard Reviewに掲載予定→中止
. Date: 20030618 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily Clippingゲームボーイカメラで撮った写真。モスクワの写真がすばらしい。写真は画質や解像度「だけ」じゃないのだよ。
from Doodle
Junkyard Reviewに掲載しようと思っていた、昨日の「あなたの人生は誰のもの?」の件だけれど、2000字近く書いたところで、どうも焦点が定まらず、没にした。もう少し寝かせてから、書き直すことにする。悪しからず。
代わりにといってはなんだけれど、大昔に書いた文章をここに再掲しておく。この文章そのものは本サイトのarchive、旧GarbageCollectionの過去ログ(2001.01.10?2001.07.16)に置いてあるもの。ちょうど2年前の文章だけれど、今もこの意見は変わっていない。
プライバシーの話をしよう。
どうもこの言葉は、ひとを過敏にさせるみたいだ。でも、プライバシーって何だ? 人に知られたくないもの、うん、それも一つの答えだろう。昨日の彼女との楽しい一夜、うんうん。おとといの恥ずかしい失敗、そーいうのもあるね。今朝のうんちのサイズ・・・。でも、こーいうものって、他人にとってはかなりどーでもいいことだ。あまりに個人的で他の不特定多数の人にはあんまり意味がない。そう、興味を示すのはきみの知りあいぐらい。あるいは、君が有名人なら話は別かもしれない(有名人は"知ってる人"が多いからね)。
じゃあ、あなたの住所や電話番号やクレジットカード番号はプライバシー? そう、こう書けば解るけど「それはプライバシーの侵害だ」っていう台詞にはある種の無責任さが感じられる気がするんだよね。
インターネットだから個人情報が漏洩するんじゃない。レンタルビデオの会員証や宅急便の発送票からだって個人情報は漏れる(レンタルビデオ店の収入の一つが名簿を売ることだっていうのは誰もが知ってるよね)。店先でクレジットカードを渡す、「少々お預かりさせていただきます」店員が店の奥に消える。そこで彼がカードのナンバーをメモしていないと誰がいえる? じつはちゃんと作りさえすれば、オンラインの取り引きのほうが安全なのかもしれないんだ。
個人情報は漏洩する可能性がある。そのリスクにちゃんと意識的になれるかどうかが問題なんだ。完全なセキュリティってのは存在しない。どんなに強固なセキュリティでも必ずアクセスルートがある。だってどんな金庫だって少なくとも1つは開ける方法があるんだから。鍵と暗証番号を持っていれば金庫は簡単に開けることができる。そのことを忘れるべきじゃない。リスクは下がりはしても決してゼロにはならない。
これまでは、個人から外へ出て行く情報は限られていた(そう思っていただけなんだけどね)。たいがいの個人情報は「何時、何処で、誰に渡したか」がはっきりしていた。いいかえるなら、情報のやりとりがちゃんとシチュエーション(状況)を持っていたといってもいい。そして、ぼくらはそのシチュエーションを読むことで、無意識に情報開示のリスクコントロールをしていた。
OAショップのカウンターで携帯電話の申し込みをするのは何の抵抗もないけれど、道端のアンケートに電話番号を書き込むのはかなり不安。逆にいえば、リスクを感じれば人はそのリターンを求める。道端の怪しいアンケートにはそれ相応の対価がないと答えられない。
ネットワークでの情報のやりとりにはシチュエーションがない(あるいは無いようにみえる)。のっぺりしたメールの文面や、きらびやかに飾りたてられたWEBサイトはどれも同じようにみえて、どれを信用すべきなのか分からない。その中でちゃんとリスクコントロールするのはとても難しい。まして、サイトにアクセスするだけで、メールを送るだけで、ある種の情報がサーバへと流れていく。
あなたがどんなにネット上でハンドルを使ったとしても、あなたが加入しているプロバイダはあなたが誰で、あなたが今日ネット上で何をしたか全部知っている。メールだって読めるし、チャットの中身だって筒抜け。あなたが送ったメールは、経由したサーバの数だけコピーがある。携帯電話はつねに自分の位置を基地局に送信している。サーバ上のメールを盗み見ることも、携帯電話を盗み聞きすることも、どちらもそれだけならば犯罪でもなんでもない。
こう考えよう、プライバシーっていうのは自分がどんな情報を人に見せているのかをちゃんと把握する権利のことだ。自分が何を発信しているのかを知ることができれば、それをコントロールするのは難しいことじゃない。
意識するしないに関らず、自分がいつどこでどんなペルソナを公共の場にさらしているのか、そのことについて僕らはあまりに無意識だったんじゃないだろうか? 日常生活にもセキュリティポリシーが必要なんだ。そして、そのポリシーを守るのは決して法律家やサーバ管理者の仕事じゃないはずだ。
今読むと、ずいぶん穴があるし、何より態度が横柄だなあ。
書きかけた文章の公開を思いとどまったのは、実は以下の文章を読んだから。ただし、これらのページに書かれている意見に賛成したからではなく、逆に、これらの意見の中にも先の文章と同じ「ゆがみ」を感じたからだ。
http://www.jca.ax.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/jdf_recruit_inv_privacy.htm
http://www.jca.ax.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/juki_net.htm
これらの文章は、国家陰謀論的思想に溢れたずいぶん極端な意見であることは確かだけれど、その裏側で、彼らの「プライバシー」に対する考え方が、どこか歪んでいるような気がする。一言でいえば、「無責任」な感じがするんだよね。なにが?どうして?といわれるとよく分からないんだけど・・・。
住基ネットが抱える危険性は承知しているつもりだし、あれに反対する理由もよく分かる(僕だって賛成しているわけじゃない)。でも、住基ネットの整備と個人のプライバシーの議論が結びつくところで、うっすらとプライバシーに関する無責任さが見え隠れするのが凄く気になる。ただ、彼らの意見に反論するだけでは、反論の反論を呼ぶだけで、ちっとも面白くない。さて、どーしたものかな。
ああ、こういう内容を「やわらかく、しなやかに」書けるようになりたいなあ。
. Date: 20030619 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [excel] Excelで遊ぶ3http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starchart_test03.xls
某所で紹介していただいたようなので、『Excelで星図』の最新版をアップしておきます。
見栄えを整えて、天体を足したぐらいしか大きな変化はありません。
これは、Excelと天体計算の勉強をかねて作っているものです。参考書を片手にひーひーいいながら変換式を作っているので、間違っているかもしれません。ご了承ください。もともとは著作権を気にせずに使える、ごく簡単な星の配置図が欲しいという要求から作り始めたものです。「裸眼で星を見るための星の配置図」が目標なので、精度も情報の密度もゆるゆるです。今後、必要と気分に応じて星座を追加するつもりです。バージョンアップしたら、ここで随時公開します。いつになるか分かりませんけどね。
それから、このファイルは将来に渡って著作権を主張するつもりはありません。ぜひ、好きに遊んでください。クレジットも作者への連絡も気にしなくていいです。そんなにたいそうなものじゃありませんし、なにしろ、「ややこしいことを気にしなくていい」が目的ですから。
いい機会なので、ちょっとファイルの説明をしておきます。
星座データを追加する際、変更が必要なのは以下のデータだけです。
あとの部分には数式が入っていますので、上の行をコピー&ペーストすればOKです。
(観測日時には、today()が入れてあるのでコピぺすれば現在時間が入ります)
観測日時
観測地の経度:(d,m)
観測地の緯度:(d,m)
星の座標(赤経):(h,m)
星の座標(赤緯):(d,m)
星座を追加したら、データの一番右側にあるX軸Y軸のデータを
グラフに新しい系列として追加すればオッケーです。
グラフの範囲や表示を弄れば拡大や回転もできると思います。
火星のデータは見ての通り、スタティックな赤経と赤緯が並べてあるだけです。
やっぱりちょっとかっこ悪いですねえ。でも、テキストでラベルつけちゃうと、星と一緒に回ってくれないんです。正確な現在位置が出せればいいんですが、まだそこまで知識が追いついていません。もう少し細かくデータを拾うと、地球が火星を追い越すときの「逆行」が再現できるはずなんですが。
ということで、次の課題は、太陽系内天体の軌道要素から任意の日付の赤経と赤緯を出すことです。それが出来れば、惑星だろうと、彗星だろうと、探査機だろうと、この配置図の中にマッピングできるはずです。
火星探査機「のぞみ」の現況(ISAS)
探査機「のぞみ」、本日2度目の地球スイングバイ。
宇宙輸送系のロードマップについて(NASDA)
要するにロケット開発ロードマップ
. Date: 20030625 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingNASA Announces Exobiology Teams(SciScoop)
NASAの宇宙生物学協会が新たに12の研究チームが協会に加入したことを発表したというニュース。
面白そうな研究が目白押しですな。おお、SETI Instituteが入ってるねえ。
No Link Seen Between Power Lines, Cancer(NewYorkTimes)※要登録無料
ロングアイランドで調査されていた、高圧電線とガンの発生率に関する調査で、因果関係なしとの結果が出たというニュース。当の昔に立証されたものと思ってましたが、まだやってるんですねえ。
NEW SPACE SHUTTLE COLUMBIA IMAGES RELEASED(NASA)
NASAは現地時間の6/24、回収されたシャトルの残骸の中から発見された写真とビデオテープを公開。
STS-107 Shuttle Mission Imagery Recovered
ここから辿れる地上で受信されたイメージと何処が違うかといえば全然違わないんだけどね。
パリエアショー:宇宙弾道飛行の費用「一人2万ドルに」、ルータン氏(NikkeiBP)
少し前に、JunkyardReviewで紹介しに「SpaceShipOne」についてのバートルータン氏の講演が、パリのエアショーで行われた。
そのためには、政治的な要請でも科学上の要求でもなく、「冒険」と「楽しみ」のための技術開発が必要ではないかと思う。個人的な見解だが、技術開発に「楽しみ」という要素はとても重要だ。
じーん。
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030525142357
恒例のColumbia Lost 更新、ここ1ヶ月のまとめ。
さほど大きな動きはない、ハイライトはRCCパネルへの衝突実験、シャトルの運用再開は早くて12月、遅くて明けて3月、という感じ。
ずっと懸案事項になっている、Columbia Lostシリーズのまとめは、そろそろJunkyardReview上でスタートする予定。ずっと迷っていたけれど、ジャーナリスティックにファクトベースでまとめを作ってもつまらないし、こんなところでやる意味も無いので、あくまで個人的なReviewとして(私見をたくさん入れて)、この事故の周辺を巡る文章を何本か書いてみようと思っている。が、さてどうなりますやら。
初期シャトル計画に関する参考文献:
SP-4221 The Space Shuttle Decision
SP-432 The Space Shuttle At Work
. Date: 20030627 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping軌道エレベーターが2018年4月12日より運行開始、とのこと。
いや、米国宇宙協会が進めている軌道エレベーターの建設計画に、この会社が参加を表明したというだけなんだけど・・・。気の早いことにトップページで運行開始までの時間がカウントダウンされている。
日本語記事(MYCOM PCWEB)
参考)Junkyard Review 『Jacob's Ladder』
日本語記事には、「実際の建設作業を担う」と書いてあるけれど、会社の説明を読む限りは、当面、ファンディングと広報活動と技術移転が仕事みたい。ま、そりゃそうか。
おや?以前紹介した時と会社も出資元も違うなあ・・・前の記事には、NASAの先端技術研究所がHighLiftSystemsに資金提供をしたと書いてある。と、同社のサイトを見ると「共同設立者のマイケル・レインがLifePortって会社を作ったけど、うちとは関係ないよ」とある。あー、さては、喧嘩別れしましたね。よく見ると、コンセプトイラストも全然違うし。もう少し探ってみようか。
参考)Hotwired
→Junkyard Review掲載予定?
Junkyard Review更新http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030527145735
上記の軌道エレベーター関連ベンチャーのお話。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030703 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryちょっと、間があきましたね。ま、ゆるりとやりましょう。
[clip]Daily ClippingGerms Begone: New technology cleans dangerous water(ScienceNews)
低コストで、非常に性能のいい、水の浄化剤が開発されたというニュース。水の浄化剤は、汚れを沈殿させることでフィルターにかかりやすくする。真っ黒に汚れ、病原菌が発生し、悪臭がする水に、10リットルあたり4g加えるだけで、水道水なみにきれいになるらしい。おお、すごい。
. Date: 20030710 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingWomen May Ovulate More Than Once a Month, Study Says(reuters)
女性は、一ヶ月に2回以上排卵することが結構あるというニュース。1ヶ月毎日超音波スキャナーで観察したら、63人中13人という高確率で2回の排卵があったそうな。
. Date: 20030715 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 黒川紀章がThinkPadを語る!――「早く人間に追いついてみろ!」(ASCII24)[黒川] 建築はもっと思想とか情念とか、宇宙観であるとか、哲学であるとか、そういうものを込めて作っている。僕は名建築、古代の名建築なんか見たとき、それは何を意図してどういう思想がここに詰め込まれているのか、感じることができるわけでね。でも、それをPCと比較してもらったんじゃ迷惑だね。その歴史的な長さがまるで違う。
名建築にしか思想を読めないのか?おまいは?
ずぶの素人だって、プロダクトデザインの歴史が建築から始まってることぐらい知っているぞ。NotePCを開いた瞬間、ユーザーの手元には確かに「空間」が生まれている。その空間の中でユーザーがどう行動するかという「機能」と、見た目の「美しさ」を両立していく中には、確かに建築と同じロジックが働いているはずじゃないか。ThinkPadのデザインは、ずいぶん建築的だと思うけどねえ(当方TPs30ユーザー)。
PCのデザインを旧来の「機能的、機械的な建築」と対比して、自分の「共生的な建築」の考え方と重ねてみせるとか、もう少し自分を賢そうに見せる方法ならいくらでもあるだろうに・・・。ミースやコルビジェとThinkPadを並べて論じるくらいのことは、しれっとやっていただきたい。そういえば「住むための機械」って言ったのはコルビジェだったっけ。だとすると、Appleのiシリーズはさしずめポストモダンか。
PCの環境に空間のメタファーを引用することも出来ずに、ただ「操作」と切り捨ててしまっている時点で、視野の狭さがうかがえるってモノですな。
. Date: 20030717 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping事故調査委員会とNASAが作った、コロンビア事故のワーキングシナリオ。
全部で189ページ(3分割版)。この文書は最終報告書にも添付される予定。これがずっと待ち望んでいた、公式のシナリオ。
大きな流れはこれまで伝えられたとおり、打ち上げ時の外部燃料タンク断熱材の剥落と左翼への衝突、軌道上での破片の分離、突入時の異常な温度上昇と空力不安定。この文書には、それらに関する非常に細かい分析が掲載されている。
. Date: 20030722 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新三浦半島に風車を見に行ってきた。一年半ぶりの2度目。こんどは太洋さんとinoshoさんとmasaの4人。inoshoさんの愛車でわいわい出かけて、三崎漁港で魚を食ってから、宮川公園へ。しばし呆然とぐるぐる回る風車を見上げた後、城ヶ島へウミネコをからかいに。全然居ないウミネコの代わりにとんびを見上げ、やたら居た猫をからかい、帰途に着く。
とても楽しかったです。いつか、千葉方面にも参りませう。
太洋さんの風車も参照のこと(GIF Movie有り)
追記)Junkyardとここに画像を追加
右の写真、大きいのはここに
. Date: 20030729 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [food]アボガドの食べ方アボガドは熟れているやつと、熟れていないやつでは雲泥の差です。→某氏。
手で軽く押すとへこむぐらいが吉(やわらかすぎると切るのが大変だけどね)。しっかりしているやつは、青臭くて固いスポンジみたいな食感で食えたもんじゃありません。店によって熟れているのを売っているところと、まだのやつを売っているところがあります。店員さんの目を盗んで、手にとって、ぐにぐにと押してみるのがよろしいかと。適正価格は100円から150円ってとこですかね。
そのまま食べるなら、スライスしなくても半分に割って、種が入ってた凹みにわさび醤油を入れてスプーンですくって食べればいい(これが一番メジャーな食べ方だと思っていたよ)。切り方は、手のひらの上で、アボガドの長い軸に対して水平、真ん中に包丁の歯を入れて、種に当たったところでぐるっと一周回し切りする。つまり二つに割れたアボガドが、種でつながっている状態。ここで、左右に分かれたアボガドをねじると、すっと外れる。片一方に残った種を取り出して出来上がり。
わさび醤油でそのままもよろしいが、マグロ丼に混ぜ込んで食べると美味です。
マグロをづけにする時に一緒につけて置けばオッケー(←間違いです)。マグロをつけるたれは、醤油、わさびに、ちょっとだけ牡蠣油とごま油を足して、お好みで少しだけみりんを追加。ほんのり甘辛くして胡麻かけて食べると、ユッケ丼みたいで美味しい。
※一緒に漬け込んだら、アボガドの色が悪くなるやろがい!食べる前に混ぜれば充分や、あほかおまいは!という連れの鋭い突っ込みが入りました。その通りです。すみません、アボガドは、食べる前にボールか何かの中でたれに漬け込んだマグロと、ぐるぐるっと混ぜてください。混ぜる時にアボガドの種を一緒に投げ込んで混ぜると、色変わりを防げるそうです(当たり前だけど、食べる時には取ってね)。
表題作で、不覚にも泣きそうになった。僕がこの人が好きなのは、ロジックのウルトラCや目もくらむようなビジョンより、むしろその隙間にすっと差し込まれた、淡い感情のほうだ。僕はSFはアイディアではなく人を描くものだと信じているけれど、その意味でも、この人は天才だと思う。
イーガンの作品に登場する人々は、圧倒的な「現実」を前に翻弄され、打ちのめされながら、静かにそれを受け入れる。どんなに人々がもがいても、現実は変わらない。時に、彼らは物語が終焉を迎えても、結局何一つ変わらない現実の前に立たされる。静かな悲しみと諦念の中で、それでもなお彼らは顔を上げる。その姿が、どこまでも悲しくて、どこまでも美しい。
SF作家は、「現実にはありえない世界」を精緻に創り上げ、その世界を生きるキャラクターたちを描いてみせる。作家の作る世界が破綻無く強固であればあるほど、キャラクターたちが生きる現実は、ゆるぎなく、退けようのないものになっていく。キャラクターたちの喜びや悲しみはその世界に深く根ざし、その世界が揺らぐ時、彼らの心もまた大きく揺らぐ。現実にはありえない世界の、現実にはありえない喜びや悲しみは、時に現実を越える感動を与えてくれることがある。僕にとってSFというのはそういうジャンルだ。
表題作のラストシーン、主人公たちがかわす何気ない会話への震えるような感動は、紛れも無くSFのそれだと思う。
. Date: 20030730 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daliy Clipping2003 Goddard Rocket Replica Project
ロバート・ゴダードの史上初の液体燃料ロケットを復元するプロジェクト。どこの好き者かとおもったら、NASAのヒストリーオフィスだった。
ゴダードのロケットは、この写真が有名。下についているロケットっぽい形をしているやつがエンジンだと思っている人が多いけれど、エンジンは上についているちっちゃくて細いやつ。下のは燃料タンクとポンプ。脇を2本通っている針金みたいなやつが、ノズルに燃料を送り込むパイプ。つまりこのロケットは「牽引式」なのだ。重量物が下にあったほうが姿勢が安定すると考えたんでしょう。その後のロケットの形を見ても分かるように、この形はとても効率が悪い上に、危ない(だってノズルからの噴射を燃料タンクがもろに被るんだから)。ゴダードもロケットを大型化する過程で、この設計はすぐに改めたはず。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030811 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]Junkyard Review更新ものすごく久しぶりの更新。しまった、結局7月は1本しか書いてない・・・。
ビョルン・ロンボルグ『環境危機をあおってはいけない 地球環境のホントの実態』のレビュー。暗いし、説教臭い。
この間ずーっと気になっている、「自分にはどうしても知りえないことがあって、それゆえに、自分の善意が何かを傷つけているかもしれない」という不安に関するお話。そういう意味では、言っていることはずいぶん前にarchiveにこっそり上げたこの文章と殆ど同じだし、結局「宣言」に行き着いてしまう。全然成長していないなあ。
あんまりにも殺伐としているので、こちらを
下ごしらえ
・茄子のへたを取って、皮を剥き、1cm幅ぐらいに切る。
・数分塩水につける(灰汁取りです)
・塩水で茹でる。臭みが抜けて、食べられそうになったら上げる。
あんまり茹でると、どろどろになってしまうので注意のこと。
はい、ここからは2種類。
たれの配分は好みで、どちらも塩辛くなりすぎないように注意
たれで和えると結構水が出るので、味を見ながらたれを追加するのがよいかも。
○タイ料理風
たれ:ナンプラー(魚醤)、酢、砂糖、塩、レモン汁
薬味:胡麻
たれで和えて、冷蔵庫で冷やして、薬味をかけていただく。さっぱり。
鷹の爪か、一味を加えるのもいいかもしれない。青じそを加えるとさらに美味い、はず。
○韓国料理風
たれ:おろしにんにく、ごま油、醤油、砂糖、塩、豆板醤
薬味:ごま
こちらも、たれで和えていただく。冷やしてもおいしい。
薬味に、細く切った白ねぎを加えるのもいいかも。まだ、試したことないけど。
. Date: 20030818 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary会社のPCがクラッシュ。大変にへこむ。こういうのは、物理的なショックより精神的なショックが大きいなあ。それなりにバックアップは取ってあるし、殆どのデータは、NotePCとで2重になってるから何とかなるんだけどね。でも、あれとあれは作り直しだなあ。しくしく。
. Date: 20030826 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary メダカを見に行くhttp://www.mori.co.jp/companyInfo/press/2003/0716_2003071719144303375.html
六本木ヒルズに宇宙めだかを見に行ってきました。えーと、普通のめだかでしたよ。やっぱり。これが宇宙に行ったメダカたちの子孫なんだと自分に言い聞かさなければ、ただあまりに普通の風景に心和むばかり。
でも、いまやメダカはレッドデータブックにも記載されている希少種です。こんな都会の池の中で普通に泳いでいるのが見られることそのものが実は稀有なことです。それに、ここにいるメダカたちが、紛れもなくごく普通のメダカであることが、僕たちがいつか宇宙へ出て行けるということを支えています。
ここにいるメダカは、1994年7月に打ち上げられたスペースシャトルコロンビアに搭載され、無重力環境での生殖やその後の世代間の影響を調べる実験に利用された4匹の子孫、約1万匹。全国の学校や希望者の下で繁殖されたものです。これらのメダカには異常はまったく認められていません。
もし、六本木ヒルズに行かれることがあれば、ぜひ中庭の池に足を運んでみてください。なかなかきれいな所です。
. Date: 20030827 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新火星のお話です。ちなみに今日、午後6時57分が最接近です。この時間だとちょっと低すぎるかもしれません。8時ぐらいに外に出て、南東の空を見上げてみてください。とても綺麗です。
なんだか、火星大接近特需で天体望遠鏡がバカ売れしているみたいですねえ。Junkyard Reviewでは「星を眺めるのに必要なのは想像力だけ」というポリシーを取っているので、使いません。こーいうのは、方角を覚えておいて、会社の帰りかなんかに、ちょっと立ち止まってボーっと眺めるぐらいがいいんです。いや、あれはあれで感動的なんですけどね。
昨夜、最終報告書がCAIBのサイトにアップされました。NASAの歴史や組織文化まで突っ込んだ非常に深い内容です。細かい内容はいずれご紹介します。
. Date: 20030828 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新久しぶりにコロンビア事故関連の話題、26日に発表された最終報告書のお話です。報告書は、まだ読んでいる最中ですが、とても素晴らしい資料です。報告書に先立って発表されたワーキング・シナリオがかなり専門性の高いものだったので、かなり覚悟していたんですが、いい意味で裏切られました。冒頭に追悼が掲げられていたり、各章の扉ページと最終ページには本文とは無関係に大判のコロンビアの写真があしらわれていたり、なんだかメモリアルブックのような作りです。
いかんせんページ数が多いので、ぜひどうぞと勧めにくいのがなんですが、Introductionだけでものぞいてみる価値はあると思います。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030902 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書エグゼクティブサマリ(仮訳)
ざーっと訳しただけなので、まだ文章がとっちらかってますが、しまっておくのもなんなので、公開します。
リンクを辿っていくと、目次が全部載ってたり、イントロダクションがHTML化されてたりしますが、全部埋まるかどうかはまったく未定です。280ページもあるし・・・。イントロダクションぐらいは全部やるつもりです。ちなみに、coversheetは終わってます。今は、Board Statementを翻訳中です(途中のまま上がってますね)。
今回、個人訳ということで、報告書文体ではなくなるべくやわらかめに訳す事にしました。分かりにくい言い回しや表現を勝手に置き換えている部分もありますので、引用などの際にはご注意ください。今は仮訳なので、まだ少々堅めですが、もう少しやわらかくするつもりです。
ちなみに、このHTMLファイルはCSSで英文を隠してあるだけなので、スタイルシートを切るか、ソースを覗くと英文も確認できると思います。訳文が分かりにくかったり、間違いを見つけたらぜひご指摘ください。
追記Bord Statementの仮訳をアップしました。
現在訳が終わっているのは以下の4本です。
さらに追記
日本語版の表紙をつけました。更新情報はこちらにも掲載します。
. Date: 20030903 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 日本語訳NASDA版http://www.nasda.go.jp/press/2003/09/columbia_20030903_j.html
キタ━━━━(゜∀゜)━━━━ッ!!
公開されたのはExecutive SummaryとReport Synopsis。これに加えて、前回のリリースで、11章が訳されています。
予想通り、堅めの訳文ですねえ。それに、事故原因と直接関係ない部分が省略されたりしているようです。ただ、専門家のチェックも入っているでしょうし、なによりプロが訳しているので、むこうのほうがスピードが速く正確なはずです。いよいよ、「無駄なことをやっている感」がひしひしとしてきましたねえ。あはははは、はあ。
まあ、そもそも競争するつもりはこれっぽっちもありませんし、目指しているところが全然違うことが分かりましたから、これで安心して独自路線を歩めるというものですね(←強がりもいいかげんにしなさいって)。
REPORT SYNOPSISを翻訳中。けっこう、楽しい。
訳文は途中段階のものでも、バックアップ代わりに随時アップしていくつもりです。章ごとにまとめてから上げていると、間が開きすぎてすぐに挫折しそうなんです。でも、NASDAから翻訳が出たら一気に萎えそうな予感もするなあ。
まあ、まじめに翻訳に取り組むのはほとんど初めての経験ですし、半ば練習のつもりで少しづつ進めるつもりです。あまり期待せずに、気長にお付き合いください。
2月(ほぼ全ての記事が事故関連)
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=200301
3月
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030210173756
4月
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030303140109
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030310201131
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030323203346
5月
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030412143159
6月
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030525142357
8月
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030728192555
自分用にメモ。今から読み返すと、最初の混乱から徐々に状況が分かり始めて、事故原因が2転3転していく様子がよくわかりますねえ。すでに、リンク先がNotFoundになっていたり、画像のリンクが切れていたりしますが、とりあえずままにしておきます。悪しからず。
. Date: 20030904 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故調査報告書 翻訳日記http://lts.coco.co.jp/isana/final_report/index.html
Report Synopsis 終了。やっぱり1日あたり原文1ページのペースだなあ。
この要約を読む限り、今回の事故の根本的な原因は、NASAのマネージメントの不備にあるというのが調査委員会の見解のようです。後半部分に行くにしたがって、何となく「あんたら何をやっとんのや、えーかげんにせーよ」という空気が行間から滲み出してきてます。要約でこの調子ですから、本文はさぞかし凄いことになっているんでしょうね。
さて、これでイントロダクションの主要部分が終わったことになります。報告書には「スペースシャトルに関する基礎知識」と「NASAに関する基礎知識」が掲載されていますが、これは囲み記事扱いになっていて原文の目次には掲載されていません。次は、これに取り掛かかります。
. Date: 20030908 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 引越し某氏のおかげで、8割がた終了。ありがとう、大変助かりました。また今度、遊びませう。
膨大な量の本。半分近く手放すことにしたがそれでも、本棚4本に収まるかどうか怪しい。PC系のマニュアル本は全部Netで済ます、漫画は漫画喫茶で読むことにして(めったに行かないけど)ほとんど全部廃棄/売却、もう手に入らない科学書、人文書、SFを残すと・・・。うあー、全然減らない。
新居まで100m、近所で借りたリヤカーを引きながら、私の貯金はみんなこれに化けたのかと、深く深く反省。だって、本の寿命が短すぎるんだもの、私の読む本は文庫に落ちたりしないんだもの、図書館にもあんまり入ってないんだもの・・・。ひーん。
後は、壁紙の張替え、照明の交換、本の整理、本の整理、本の整理・・・本当に8割か?
というわけで、あまり進んでません。『スペースシャトルの基礎知識』半分ぐらいをアップ。
. Date: 20030909 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『スペースシャトルの基礎知識』終了。
土日と引越しをはさんでペースが落ちていますが・・・。あ、マイルとポンドの直しをやってない。画像もでかすぎるし、あああ。
何人かの方から、誤字のご指摘をいただきました。本当にありがとうございます。メールで伝わったかどうか分かりませんが、私、感動に打ち震えております。素人訳/片手間仕事のため、ペースも遅く、お見苦しい点多々あるかと思いますが、どうぞご容赦ください。訳については、仮訳ということで今後もどんどん手を入れていくつもりです。誤訳、誤字の指摘は、どんなに些細なことでも結構です、どうぞご遠慮なく。いただければ、顔を真っ赤にして身もだえしながら直します。
すぐに挫折するかと思っていましたが、もう少し続きそうです。いや、結構楽しいんですよ、これが。
※追記:単位と画像サイズを修正、画像を追加、CSS修正
今日は夜空で月と火星が一番近づく日だった。
今なら(22:00)まだ、綺麗に見えますよ。
. Date: 20030911 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『AN INTRODUCTION TO NASA―NASAの基礎知識―』終了。
わーい、イントロダクション全て終了
後半、集中力が無くなって、訳文がへろへろしているのはご愛嬌(後で直します)。最後の章は固有名詞が多くて困った。もしかしたら、一般的ではない呼称をしてしまっているところがあるかもしれない。Michoudとか、Ling-Temco-Voughtとか、Thiokolとか・・・。
もっと、がしがし訳注をつけるべきかな。うむむ。
某所で褒めてもらったので、調子に乗ってFaveletsの「Toggle CSS style sheets」を使って、各ページの最下端にJavaScriptでCSSのon/offを切り替えるスクリプトを埋め込んでみた。おお、便利・・・なのか?IE5.0以上、NS7.0以上なら動作するはずだけど。どうだろう。
ちなみに、CSSを切ると、隠しておいた原文が見える。これは、もともとこういう用途を考えていたわけじゃなくて、作業上の効率から半ば必然的にこうなったもの。
今回、ローカルで作業するのに、PDFから抜いたテキストファイルに、段落ごとに直接和文を書きこんでいくというスタイルを取っている(これは、重要な作業時間のなかに「電車の中」が含まれているせい)。そのうちに、アップ用と作業用の複数のファイルを作るのが馬鹿馬鹿しくなって、「あ、CSSで英文隠せばこのままアップできるじゃないか」ということでこういう仕様になっている。
だから、アップされているHTMLファイルがそのまま作業ファイル。定型のヘッダとフッダを付けて、ざっくりタグ打ちした原文ファイルにざくざく訳文を書き込んで、そのつど英文と和文を振り分けるタグを打ちながら、サーバに随時アップロードする。この方法でずいぶん作業が楽になったし、途中のものでもあまり気にせずに公開できるようになった。手前味噌ながら、なかなかいい方法だと思う。
※追記
いや、ちゃんとCSS2つ作って切り替えるほうが美しいのは分かってるんですけど、あまりむやみにJavaScriptをソースに埋めたくないもので・・・。今回、リンクタグにスクリプトを押し込んでいるのもそういう理由です。
. Date: 20030913 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記第1部『The Accident―事故―』の前書きをアップ。かなり短め。
実は、既に原文のファイルは全部アップされて、目次からもリンクされています。
(翻訳済みのものだけ色がつくように、CSSでリンク色を抑制してあります)
. Date: 20030916 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記いいかげんに、違うネタを書けー、という声が聞こえてきそうですが・・・
『CHAPTER 1 The Evolution of the Space Shuttle Program』
今回も短めです。第1章の前書きにあたる文章です。
いよいよ、本編の始まりです。
続く第1章では、アポロ計画の狂乱の日々を忘れることができなかったNASAが、壮大な宇宙計画に固執し、徐々に現実から目をそらしていく悲しい過程が切々と、毒気に満ちた言葉で語られていきます。シャトル計画は生まれた時から、到達不可能な目標を背負わされていました。そして、その現実と理想のギャップは徐々にシャトル計画そのものを蝕んでいきます。なぜ、彼らはそこまでシャトル計画に固執したのか、物語はそこから始まります。
. Date: 20030917 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]松浦晋也『われらの有人宇宙船―日本独自の宇宙輸送システム「ふじ」』(amazon)日本の宇宙開発の良心がぎっちりつまった本。おすすめ。
シャトルの事故報告書の先にあるものを見通すために必要な最低限の知識が、ここには全部書かれている。
コロンビア事故の報告書を訳しながら、彼らの「私たちは間違っていたのかもしれない」という、どこか悲痛な声を聞いていると、出口の無い迷路に投げ込まれたような気分になる。僕達はここからどこへ向かって足を踏み出せばいいんだろう。
20年以上も前に、25トンものペイロードと7人の宇宙飛行士を軌道上まで打ち上げる能力をもった宇宙船を創り上げたのは、まさしく偉業といっていいと思う。いまだかつて、こんな能力を持った宇宙船は存在したことがない。いや確かに、設計はタコだったかもしれないさ、運用はへぼだったかもしれないさ、組織は腐っていたかもしれないさ、でもこの20年間、あれを飛ばしてきたのは、本当に凄いことだよ。
その宇宙船を作り、飛ばしてきた彼らが、「私たちは間違っていたのかもしれない」とつぶやいている。あの事故は、夢と希望が妥協と打算にまみれていく姿を見ないように、後ろ向きのまま全力疾走した結果なんだ。夢と希望はいつも僕たちの前にあるとは限らない。もしかしたら、僕たちは後ろを向いているのかもしれない。
では、本当に前を見るために、僕達が考えなきゃいけないことはなんなのか?この本は、そのためのヒントを見せてくれる。そう、夢や希望じゃロケットは飛ばないけれど、ロケットは夢や希望を乗せて飛ぶ。これは、きちんと前を向いた、もうひとつの夢の形だ。
『 1.1 Genesis of the Space Transportation System 』 終了
. Date: 20030925 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clippingコメントは後ほど
California Team Conducts First Powered Liquid Propellant Aerospike Flight Test(SpaceRef)
カルフォルニア州立大学ロングビーチ校とガーベイスペースクラフト社が共同で、初の液体燃料を使用したエアロスパイクエンジンの飛行テストに成功したというニュース。
Electronic paper reaches video speed(Nature)
フィリップス研究所がビデオ映像を表示できる電子インクを開発したというニュース。
『1.3 Shuttle Development, Testing, and Qualification』 終了
『 1.2 Merging Conflicting Interests』 終了
と、とりあえずアップ。日本語がとっちらかっているのと、訳が怪しいのは随時直します。
さて、今回アップ分について若干補足をしておきましょう。
第一章前半(1-1,1-2)の内容は以下の通り。
-アポロ以後冷めてしまった宇宙開発への機運と財政難の中で、シャトル計画がポストアポロの壮大な計画の唯一の落とし子として残った。
-唯一残された有人飛行計画であり、今後の計画の足がかりとして、NASAはどうしてもシャトル計画の予算を通す必要があった。
-NASAはコスト的なメリットと、あらゆる用途に使えるシャトルの性能を売り込んだが、それは机上の空論でしかなかった。
-当面の予算を低く押さえるために、シャトルは運用コストや信頼性よりも、開発コストを押さえることを優先して設計が進められた。
-結果として、リスクが高く運用コストのかさむ機体が出来上がってしまった。
実は、この報告書では触れられていませんが、NASAがシャトル計画を議会に通す時に、実はもう一ひねりあったんです。報告書の中で、「シャトルの性能に国防総省が興味を持ち・・・」というくだりがありますが、じつは、ペンタゴンがシャトルに興味を持っていることを知ったNASAはこういう提案をしているんです。「開発とそのための資金はNASA持ち、その上で空軍の要求を満たすようにシャトルをデザインする。その代わり、議会でシャトル計画を通すための後押しをして欲しい」
60年代の後半から独自の宇宙計画を進め、それが頓挫していた空軍にとってはこれは願っても見ないチャンスでした。当然ながら空軍はこれに飛びつき、NASAは軍の法外な要求を聞き入れざるを得なくなったんです。(この話は、NASAのHistory OfficeのWebサイトに掲載されている文書に載っています)。
この頃、NASAはとにかくシャトル計画を存続させるために、なりふり構わず行動していました。彼らがなぜここまでシャトルプロジェクトに固執したのか、本当のところは良く分かりません。ポストアポロの夢が捨てられなかった、という「いい話」ばかりではないでしょう。緊縮財政で予算が押さえられる中、アポロで築いたポジションから滑り落ちるのをどうしても防ぐ必要があり、そのための旗印が必要だったというのが正直なところかもしれません。
さて、このあとお話はシャトルの開発そのものに移ります。ここでも、相変わらずごたごたしていたりするんですが・・・。まあ、それは本編で。
. Date: 20030926 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping日が変わってしまったので、再掲
California Team Conducts First Powered Liquid Propellant Aerospike Flight Test(SpaceRef)
カルフォルニア州立大学ロングビーチ校とガーベイスペースクラフト社が共同で初の液体燃料を使用したエアロスパイクエンジンの飛行テストに成功したというニュース。機体は無事に回収され、解析が行われるとのこと。
エアロスパイクといえば、軽い燃料タンクが作れずに挫折したX-33が思い出されるけれど、こんなところで学生の手で開発が行われていたとは驚き。いや、素晴らしい試みだと思います。ちなみに、X-33は小さいノズルが直線に並んだリニアスパイクエンジンだったけれど、このロケットは円形をした「普通の」エアロスパイクエンジン。
エアロスパイクエンジンというのは・・・えーと、長くなりそうなので久しぶりにJunkyard Reviewのほうでやろうかな。
Electronic paper reaches video speed(Nature)
フィリップス研究所がビデオ映像を表示できる電子インクを開発したというニュース。
従来の電子インクは電気泳動方式と呼ばれ、球形のカプセルの中に帯電した微粒子と色付の液体を封入し、電流を流すことで、微粒子と液体が相互に入れ替わることで表示を行う。今回の新しい電子インクは、油性のインクを細かいセルに封入し、そこに電圧をかけることで表面張力を変化させ、「テフロンのフライパンの上の水滴のように」インクが丸くなることを利用する。平たく広がっていたインクが丸くなることで、背景の白が見え「白」が表現される。この方法だと非常に高速に画面の書き換えがおこなえるだけでなく、電圧のかけ方によって、表面張力の度合いが変化するため、非常に滑らかなグラデーションが表現できる。
でもねえ、電子ペーパーのメリットは動画が見られることじゃないはずなんだけどね。解像度が非常に高く、書き換え時以外に電力を使わない。このやり方だと、自然放電でインクが「だれて」きそうな気がするが、どうなんだろう。まあ、実用化に向けて、これからさらに研究という感じらしいので、実際に目にするのはずいぶん先になるんじゃないかな。
. Date: 20030929 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『1.4 The Shuttle Becomes "Operational"』 終了
ようやく最初のオービター『コロンビア』が完成し、シャトルの運用を始めてみたものの・・・というお話。
NASAの目論みはボロボロと崩壊し、運用はだんだんいいかげんになっていきます。そして・・・。
次回は、『チャレンジャー事故』
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20031001 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『1.5 The Challenger Accident』、『1.6 Concluding Thoughts』をアップ。第1章終了。
全然「でいりー」じゃないっすね
ずいぶんまえに『落書き宣言』を登録してみたことがあるけれど(このねじれた皮肉に気付いた人はいるんだろうか)、僕がクリエティブコモンズに期待したのは、明示的に著作権を放棄する手段になりうるかもしれないと思ったからだ。
残念なことに、現行の著作権法には、明示的に著作権を放棄する手段がない。もちろん、訴えを起こさなければいいという考え方もあるけれど、これは著作物を利用する側のことを何も考えていない。「これは安心して自由に利用できる著作物である」ということを第3者を通じて明示することができなければ、利用者は自分が著作権違反をしているのかもしれないという不安から逃れることができないはずだ。個人的にそういう思いを何度もしてきたし、少なくとも自分の作ったものは、そういうしがらみから自由にしておきたいと思ってきた。本サイトのaboutにも、進めている翻訳にも、繰り返し繰り返しそのことを主張しているのは、そういう思いがあるからだ(まあ、そんなに偉そうなものを作っているわけじゃないけどね)。
画面にチラッと映っただけの椅子にたいして著作権料を払わなければ、その映像を上映できないっていうのは、その椅子の作者にとっても不利益なんじゃないかと思う。もちろん、俺のものを勝手に使うなと主張するのは悪いことじゃない。でも、どうぞご自由にお使いください、と「正しく」言う方法がないというのは何か間違っているような気がする。
僕には「copyright reserved」の文字は「危険、取扱い注意」に見える(これはおそらく、正しい認識のはずだ)。僕はただ、自分の作ったものに「安全」というラベルが張りたい。もしいつの日か、そのまだ見ぬラベルがcopyrightと同じくらいの市民権を得たならば、それは少なからず著作物の付加価値になりうるんじゃないだろうか。
本日より、NASDA、NAL、ISASの宇宙関連3機関が統合され、「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」になる。
おい、この立花隆のインタビューはなんだ?こんなこと言わせていていいのか?有人なんかいらない、ロボットにやらせろとか言ってますけど・・・。いや、まあそういう考え方も有るんだけど、一発目にこれはどうかと思うぞ。宇宙開発のケインズ政策効果って話も、かなり異論があるしねえ。重要なことも沢山言っているんだけど、むむむ。
宇宙開発は、産業としてGDPを左右するような利益をバンバン生み出すにはパイが小さすぎるし、スピンアウトを狙うには特殊すぎる。ロケットは国家経済を左右する産業にはならない。
たとえば、自動車業界にとって、F1レースは金を食うばかりで、実質的な利益を生んでいない。あまりに特殊すぎて一般車へのフィードバックは殆どないといわれているし、自動車産業そのものへの直接的な広告効果もあまりない。でも、それなりに参加企業があるのは、F1参加企業というイメージがまだそれなりの価値を持っているからだ。技術力の高さのアピールになるし、企業のモチベーションの一部(ごく一部かもしれないけれど)を担っている。
同じ理屈を宇宙開発に当てはめるなら、「宇宙開発参加国家」が国のイメージの一部を形成しているとすれば、それを捨てるのはあまり得策ではない。いつか、宇宙開発が本当に産業になりうる日が来た時に、そのイメージはその後の成長をかなり大きく左右するはず。夢や希望じゃお腹は一杯にならないけれど、夢や希望がないのはずいぶん寂しい。そして、その寂しさはいつかボディーブローのように効いてくる。それは国家というレベルでもたぶん同じだ(たとえば、中国はきっとそれをずーっと味わってきたんじゃないだろうか)。
国民に夢と希望を与える。大義名分にはならないかもしれないけれど、恥ずかしがらずにそのことをもう少し議論してもいいような気がする。僕らが「国の強さ」を感じるのは、経済力や軍事力だけではない。そして、歪んだ優越感にならなければ、みんながそれを感じるのは悪いことじゃないはずだ。
. Date: 20031003 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『CHAPTER 2 Columbias Final Flight』 終了。第2章の前書きです。
第2章の英文ファイルを全てアップ。
さて、第2章に突入です。「STS-107のすべて -計画から事故調査まで-」という感じでしょうか。事故原因の分析ではなく、STS-107で行われたこと/起きたことが時系列順に説明されていきます。実は、この章には「事故時の通信記録」という難物(専門用語が山ほど出てくる)が控えているんですが・・・。まあ、そのとき考えましょうか。
. Date: 20031006 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 教室天井60センチ低くなると…生徒の9割「不快感」学校の建築コスト削減のために、天井高を60cm下げて2.4mの教室を作って実験したところ、クラスの9割近くの生徒が不快感を訴えたというニュース。これは、文部科学省の委託を受けて日本建築学界が実験を行ったもの。
曲がりなりにも舞台美術をかじった人間から言わせてもらえば、これは当たり前、気分が悪くならないほうがおかしい。日本建築学界って所は、そんなことも実験しなくちゃ分からんのかね。それとも子供は背が小さいから天井低くてもオッケーじゃぁん!とか言ったバカがいたのか?
ごく普通の人でも、天井高が15cm違えば誰でも「違う感じ」がする。天井高3mというのはごく一般的な高さ、みんながこの高さに慣れているから、この規格から少し外してあげるだけで人はその空間に対して違和感を感じる。舞台美術屋はこれを利用して「圧迫感のある空間」なんてのを作ったりするわけです。
そういう意味で言えば、天井高を60cm下げるというのは犯罪だと思うぞ。だって、天井高240cmって言ったら、身長約180cmの人が手で触れられるぐらいの高さだよ。気分が悪くなるのも当然ですがな。誰か止めろよ。
百聞は一見にしかず。3mと、2.4mというのはこれぐらい違う(稚拙なCGで申し訳ない)。


これは、ほぼ5m X 5mの正方形の部屋、人型は身長165cm。教室はもっとサイズが大きいから天井の面積がもっと広くなる。天井の圧迫感は相当なものだろう。もっと言えば、これにさらに窓やロッカーや黒板があれば、もっと圧迫感は大きくなるはず(比較対照があるから)。こういう提案をする人間は、想像力が欠如しているとしか思えない。頭がつっかえなければいいとでも思っているのかね?
. Date: 20031008 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.1 Mission Objectives and Their Rationales』をアップ。
長い、テンションが持たない、日本語くちゃくちゃだし、あああ。
Junkyard Reviewの方も・・・いや、サイトのリニューアルが・・・あー。
. Date: 20031009 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『COLUMBIA』をアップ。2-1の囲み記事にあたるテキストです。
この記事の中に、「コロンビア」の名前の由来として、コロンビア川を発見し、アメリカで始めて地球一周を行ったロバート・グレイの「コロンビア号」が出てきますが、もともと「コロンビア」はコロンブスに由来し、アメリカ合衆国を擬人化したときの女性名として知られています。グレイのコロンビア号はこれに由来しています。ちなみに、初めて月に人類を送り込んだアポロ11号のコマンドモジュールの名前も「コロンビア」でした。
※続いて、『THE CREW』もアップ。
. Date: 20031010 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingトキ絶滅
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/science/toki.html
いつかは、こういう日が来ると思っていたけれど、やっぱりショックが大きいなあ。なぜだろう?微生物を含めば、世界中で毎日いくつも絶滅種が出ているし、日本だって人知れず絶滅していく生物もいるはずだし、トキだけが特別視される理由もないはずなんだけど、純粋に個人的感情としてやっぱり寂しい。
DNA鑑定がされて、中国のトキと遺伝的に同一種であるということになったらしいけど、そういう問題じゃないしねえ。
ここしばらく、ずいぶん前にビデオにとってあった『デビッド・アッテンボロー哺乳類の世界』を、おゆはんを食べながら順番に見ている。昔からこの人のシリースは大好きなんだけれど、今回もすごくおもしろい。
この人のシリーズは、とにかく「いい絵」がものすごく多い。あまりに自然に撮ってあるので、気を抜くとつるっと過ぎてしまうけれど、よく考えるとものすごいカットが次から次へとつないであったりする。
うろ覚えだけれど、ちょっと再現してみよう。
・真夜中、真っ暗闇の中(赤外線カメラの撮影)、これから狩りに出かけようとするライオンの前4,5メートルのところで、ライオンの狩りについて説明するデビッド爺さん。いやー、さすがに緊張しますね、じゃないでしょう。喰われても知らんぞ爺さん。
・左右に激しく蛇行しながら追っ手のチーターから全速力で逃げるガゼルを、超望遠でびたっとセンターに入れたまま微動だにさせないカメラマン。超スロー、走るガゼルの首から上だけを捉えたショット、そこに飛び掛るチーター。この映像がまったくぶれない。このワンショットで、ガゼルとチーターは急減速してるはずなんだけど・・・。
・何の変哲もない木の幹が写っている。そこへ隣の木から飛び移ってきた猿がフレームインしてくる。えーと、この場所に猿が飛んでくるのが何でわかるんですか?いや、ある程度引いた絵ならわかるんだけど、猿が画面からはみ出そうなぐらいのアップだったりするんですけど・・・。
・月夜の晩に歩きながら交尾をしているハリモグラ、カメラが引くとデビッド爺さんが嬉しそうにそれを見ている。えー、だってカメラは歩いているハリモグラを追ってたんですが・・・なんで爺さんそこにいるの?
・カヌーに乗ったまま、ビーバーの説明を続けるデビッド爺さん、その前をキューでも入れたかのように素晴らしいタイミングでフレームインしてくるビーバー。って、おいどーやって撮ったんだ?
とにかくデビッド爺さんの「ほら、見てください、?が、ちょうど?をしていますよ」という台詞がものすごく多い。で、カットを切り替えずに、遠景にちゃんとその動物がその行動を取っている姿が写っている。このワンカットをとるために、いったいどれくらいの時間をかけているのか・・・。対象となる動物がその行動を取るほんのわずかな瞬間に、完璧な構図とタイミングで、デビッド爺さんとのツーショットを撮る。そのために、いったいどれほどの労力がつぎ込まれているのか、考えるだに恐ろしい。
というわけで、最近、連れとの間で『デビッドアッテンボローCG説』が、まことしやかに語られている。いや、本当にすごいんだってば。
※ちなみに、映画監督/俳優のリチャード・アッテンボローは実のお兄さん。
. Date: 20031014 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book] Ted Nelson "The Future of Information"この間、ちまちまと本の整理をしながら発掘したものを見分していると、とても懐かしいものが出てきたのでホクホクとめくる。おお、今読んでも結構面白い。これは、卒論を書いていた時期にダウンロードして、苦労しながら全部プリントアウトしてファイルしてあったものです(なにしろ元がFAXフォーマットなので)。
Book: The Future of Information (scanned)
ちなみに、私の卒論のタイトルは『History of Writing Technology』でした。97年ですから、WWWがハイパーテキストの具現化だ、これからは、デジタルテキストの時代だ!紙なんていらねー!といってデジタルメディア論がずいぶん流行った時期です。メディアの変遷が『書くこと』をどう変えてきたのか、その一番先のところにまだ見ぬ「ハイパーテキスト的な著述」がありうるんじゃないか、そんな妄想がまだ現実味を帯びていた頃です。
知っている人も多いでしょう、彼はWWWが現れる25年以上前に、リンクとノードからなるドキュメント管理システムを構想し「ハイパーテキスト」と名づけた人です。彼はハイパーテキストを書き、閲覧するシステムを『ザナドゥ』と名づけ、その研究に一生を捧げました(ってまだ生きてますけどね)。
僕が彼の議論に惹かれたのは、彼のザナドゥでは「書き手」が議論の対象になっていたからです。それがWWWを作ったティム・バーナーズ・リーとの一番の違いでした(WWWは読むためのもの、ファイルをストックしておくためのものとして作られました)。ハイパーテキストは、書き手にとって理想のシステムになりうる。彼がリソースを自由に相互利用するための著作権管理システムにこだわったのも、ハイパーテキストが読むためのシステムではなく、著述のためのシステムだと考えていたからです。
あの頃、もうすでにテッド・ネルソンは過去の人でした。Hotじゃない方のWIREDで叩かれたりしていたのも確かこの前後です。彼はTCP/IPとWWWを攻撃しながら、自らの理想を頑なに追い求め、Xanaduプロジェクトに固執するあまり、世間から取り残されていました。その後、彼と共に「著述のためのハイパーテキスト」は姿を消しました。彼の話を漏れ聞くたびに、「ハイパーテキスト」という言葉を聞くたびに、何となく寂しい思いをしたものです。ああ、やっぱり僕達の脳みそはリニアにできているんだろうか?
さて、今彼は何をやっているんだろう(ついこの間まで慶応SFCに居たはずですが)・・・ありました。
どうやら、いまだにWWWに恨みごとを言っているようですねえ。
彼のサイトにはWWWへの呪詛の言葉が、ご丁寧にテキストファイルでリンクされています。
すげー、何も変わってないよこの人・・・。
"We fight on. More later."
おー、まだやる気だ。
. Date: 20031015 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingTokyo on One Cliche a Day By Seth? Stevenson
"Gaijin"による渋谷『鯨屋』訪問記。大笑い。(from montreal life 閾値以下)。
そのトーンからわかるように、決して擁護を目的としたものではなく「おふざけ50%+珍奇さ45%+問題提起5%)という感じだけれど、ふざけながら、ちくちくと「常識」をつついてみせる、なかなかいい記事だと思う。どう書いても日本人が語っていると感情的に見えてしまう以上、こういうアプローチで鯨食がパブリシティを得るのは悪いことではないんじゃないかな。
日本人がみんな狂信的に「鯨を食わせろ!」と叫んでいるわけじゃない。鯨がいなくなってしまうのはどうかと思うけれど、余裕があるならたまには食べたいなあ、って所じゃないだろうか。逆にいえば、欧米にも「うーん、増えているんなら食べてもいいんじゃない。私は食べないけど」みたいな人はそれなりにいるんじゃないだろうか?いや、調べたわけじゃないけどね。
どうしても声の大きい人の意見が目立ってしまうけれど、そういう「まあ、いいんじゃない」みたいな態度の人たちが、お互いをチラッと見ながら、あーそういう人もいるんだねえと思ったり、あるいはお互いに軽く手を振ったりできれば、もう少し幸せになれそうな気がするんだけど、甘いかなあ。それで何が変わるわけじゃないけどね。
本日午前9時、打上げ成功。無事軌道に乗ったとのこと。
色々賛否両論あるみたいだけれど、間違いなく成功はめでたいことです。おめでとうございます。
打上げの写真(xinhuanet)
一方日本の宇宙関連はこういう状態
既にあちこちで報道されていますが、大雑把にまとめるとこんな感じ。
1)スーパー301に絡んで、アメリカがひまわり後継機の入札をごり押し。結果、アメリカの米国スペースシステムズ/ロラールが受注。
2)再三にわたり、納期が延びる
3)ひまわりの寿命が切れ、アメリカにGOSEを月額1600万円で借りる。
4)7月、スペースシステムズ/ロラールが会社更生法を申請
5)これまでの遅れに対する保証金の免除、損害賠償請求の放棄、それから追加で33億円払ってくれないと続きを作らない、と突然言って来る。
6)気象庁が米国連邦破産裁判所に緊急救済をするよう訴える←却下(理由は内緒)
えーと、聞いているだけで怒りが込み上げてくるような感じですねえ。でも、この問題の根本原因は再三の要求に対して「予備機、んなもんいらん」という判断を下し続けた旧運輸省の危機意識のなさにあるような気がします。
国家安全保障というのはこういうときに使う言葉じゃないですか?国民の生活がかなり脅かされているような気がしますけど・・・2500億も情報収集衛星に使っている余裕があるなら、なぜ日常のインフラに直結したこっちに出し渋るんでしょうねえ。
一番いやーんなシナリオは、残りの申請も却下され、33億の予算は下りず、GOSEのレンタルも続けられず、旧ひまわりを引っ張り出してきて来年末まで綱渡り運用を続けながら、三菱で作っている2号機の打上げを待つ、というやり方。あああ、ありそう。
運輸多目的衛星新1号の製造請負契約等の緊急救済命令申し立てに対する米国連邦破産裁判所の判断について(気象庁)※PDF直リンク注意
. Date: 20031016 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary なぜ殺してはいけないのか? (from svnseeds’ghoti!)―Sense of Wonderの法則―
自分自身のことを世界に向けて問うてはいけない、
むしろ、世界のことを自らに向けて問いなさい。
世界はそのほうがずっと楽しくなるように出来ているんだ。
想像力は世界を拒絶するためでも、
ただ、世界を受け入れるためでもなく、
世界と自分をつなぐために使うべきだよ。
. Date: 20031020 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記先週はお休みしていましたが(日記の文章がやたら長いのはご愛嬌)、そろそろ復帰です。
『2.2 Flight Preparation』をアップしました。
それにしてもこのセクション、会議の名前や役職名が次から次へと出てきて訳に迷う迷う。あまりうまくいっていませんが、とりあえず先に進むことにします。たぶん後でにちょこちょこ直します。(迷ったあげく、結局「レビュー」にしましたよ> zundaさん)
※追記
続いて『NASA Time』をアップ。2-2の囲み記事です。
NASAで使われている時間の単位のお話。Tマイナス○○ってやつですね。
さて、次は打上げです。
. Date: 20031023 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingBranson in flight record attempt
英ヴァージンアトランティックとヴァージンの社長リチャード・ブランソンが「僕らは世界初の単独世界無給油無着陸飛行に挑戦する」と発表した、というニュース。
無給油無着陸世界一周は、バート・ルータン設計のボイジャーが1986年に果たしているけれどあの時は、ディック・ルータン(バートルータンの弟)とジーナ・イェーガー(チャックイェーガーとはこれっぽっちも関係ない)の2人が操縦していました。
この『グローバル・フライヤー』を造るのは他でもない、バートルータン率いるスケールド・コンポジットです(まあ、機体のデザイン見ればわかりますけど)。カスタムメイドのヘンな飛行機作らせたら、あそこの右に出る会社はありません。今は観光用弾道宇宙飛行機作ってるので有名です。
操縦するのはスティーブ・フォセット。去年の6月に熱気球で単独世界一周をやった人です、あの時もヴァージンがスポンサードしてました。なんだか、「ま、世界一周ならいつものメンバーでやりますか」っていう感じですねえ。
. Date: 20031024 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 海の中を流れ落ちる滝のお話上京してきた親父と飲みながら『地球規模の海流循環』の話を聞く(親父は海洋学者)。ものすごく面白い。普段教科書なんかで見ている2次元的な海流の図が立体的になって頭の中でぐるぐると動き出すのがとても気持ちがいい。

南極とグリーンランド付近で、冬季に凍結した海水は温度が下がり塩分濃度が高まることで非常に重くなる。この「世界で最も重い海水」が水深4,000m海底まで一気に沈み、北太平洋からインド洋へと深海を南下し、喜望峰を越えて、さらに太平洋を北上し、日本沿岸を抜けて北太平洋でようやく海面へと浮き上がる。
今度は表層のいわゆる「海流」と合流し、海面近くを太平洋を時計回りに回りこむように一周しながら、東南アジアとオーストラリアの間を抜け、インド洋を通り過ぎ、再び喜望峰を越えて大西洋を北上してグリーンランドへと戻る。
この間1500年から2000年。
どうやら、この海流の動きが地球の気候の変動に大きな影響を与えたり、海底のリン酸を海面近くへ運び上げることで生物循環にも寄与しているらしい。
南極とグリーンランドの付近から重い海水が数千メートルの海底まで滝のように流れ落ちる光景を想像しながら、しばし呆然とサイエンティストの言葉に酔う。なかなかいい夜だった。
. Date: 20031027 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingChopsticks may cause arthritis (Reuters)
箸は関節炎の原因になるかもしれない、というニュース。
どうやら、箸を使う手とそうでない手をひたすらX線で撮って比べたらしい。親指と人差し指・中指の第2関節と第3関節での関節炎の発生率がごくわずかに上がっていたらしい。
んー、ごくわずかにってところが気になるなあ。ナイフやフォークと違って、持ち方によってずいぶん負荷も変わるしねえ。ていうか、箸を持っているとき親指にそんなに負荷がかかっているかな。人差し指や中指もそんなに大きく/強く動いてないと思うけどなあ。まあ、かなり長い間この形に慣れているから、今さら負荷を云々行っていてもわからないのかもしれないけどね。まあ、確かに動かしている頻度が問題なら、箸を使っている方の手と逆の手では確かに差はあるかもしれないなあ。
実は、今、鉛筆で箸の代わりをやっていて気付いたんだけど。ペンや鉛筆で字を書くほうが、よっぽどこれらの関節に負荷がかかっているような気がするんだけど。気のせいかな?箸を使う手とペンを持つ手は同じですよねえ・・・。
ナイフとフォークを主に使っている人との比較調査はまだやっていないみたいだし。追試を希望。箸を持つときの持ち方の差と、ペンで字を書くときの筆圧の調査も忘れないでね。あるいは横書き文化と縦書き文化では指の関節や手首の関節に負荷が違うと思うぞ。
知り合いから、本体サイトのほうが更新されていないけれど、生きてますか?と聞かれる。むー、ついこっちのエディット画面に書き込みするのが癖になってるなあ(翻訳もやってるし)。少し長めのやつはあっちにまとめることにしよう。そうしよう。
. Date: 20031028 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記ちょっと間が開きましたが、『2.3 Launch Sequence』をアップしました。
打上げの時のお話です。ただ、事実関係を追っていくだけなので、打上げ時の断熱材の衝突についてはさらっと触れられている程度です。これについてはあとの章でこってり扱うことになります。
さて、次はSTS-107の軌道上での活動と出来事を追っていきます。
※今夜NASAから最終報告書の残りが発表される予定です。Appendixということですが、内容的には関連文書を束にしたものなので、かなりの量の関連専門文書がアップされるはずです。い、一応ダウンロードくらいはしようかな。
昨日ぼんやりニュースを見ていたら、ただの株価情報を伝えるニュースの中で「視聴率を金で買うような卑劣な真似をしていた日本テレビは・・・」という紹介をしていた。いや、確かに君らから見れば「卑劣」かもしれないけど、そーいうことを言う放送局もどうかと思うぞ。キャスターのアドリブには見えなかったし、その後謝罪も無かったから、普通に原稿として書かれたものみたいだったけど。なんで普通に「視聴率操作事件の影響で」と言えないのかね。ニュースと銘打つなら、せめて中立な「ふり」ぐらいしてほしい。なんか、いやーなものを見せられたような気になるから。
もちろん、偏向していない報道があるなんて幻想を持っているわけじゃない。でも、少なくとも視聴者に「我々は偏向しています!」と叫ぶような真似をするのは止めた方がいいんじゃないか。「この人殺し野郎○○○は」って殺人犯を紹介するのと同じっすよ。自分達の発言が視聴者にどういう印象を与えるのかってことを考えてないのかな。考えてないんだろうなあ。マスコミの人間ならそれを第一に考えるべきじゃないか?わざわざ自分から信用を投げ捨てるような真似してどうするんだろう。
まあ、こういう例はいくらでもある。最近は食べ物系がちょっとひどめ。
口に食べ物を入れたまま商品名(だったかな)を叫ぶお酒のコマーシャルとか、カウンターに肘をついて食事をするタレントの写真を堂々と店に張り出す大手丼物チェーンとか、コマーシャルで口からだらっと肉をはみ出させたまま呆然とする映像を使う某ステーキチェーンとか・・・。
べつに、人がどんな食べかたしていようがそんなに気になるほうじゃないけれど、仮にも食べ物を扱っている人たちが平気でそういうビジュアルを使ってしまうのがあまりに信じられない。自分のところの商品を貶めるようなことをしているのに、それに対してダメが出せないというのはどういうことなんだろう?自分なら粗編集が上がってきた時にプロデューサーを張り倒すけどなあ。で、二度と頼まない。
だって、たとえばラーメン屋の親父が目の前で出来上がったラーメンを手づかみで食べ始めたら引きませんか?そんなラーメン屋に次も行こうと思うか?手づかみで食べるのは自由だけれど、ラーメン屋の親父がやっちゃダメでしょう。
ちまたのビジネスマンからものすごく受けの悪い某缶コーヒーのコマーシャルとか
「たくさん入れても美味しい」という思わず突っ込みたくなるようなコピーとか
こんなことが気になるのは、わしがおやぢになったからじゃろうか?
最近の若いもんはぷんすかぴー。
. Date: 20031030 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] Columbia 事故調査最終報告 Vol. II?VI 発表これで報告書の全てのページが公開されたことになります。予想通り、膨大な量の文書が公開されました。ほとんどが技術的な専門文書とデータ集です。
※NASAのほうには関連ムービーや第1部の高解像度データも上がっています。
落としましたよ、ええ落としましたとも。NASAのサイトのほうで公開されているムービーとVol.1も併せて800M以上ありました。CD-ROMに入りません。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20031101 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新約2ヶ月ぶり、コロンビア事故報告書について。
事故の翌日、Junkyard Reviewにこういう文章を載せました。
とりあえず、自分への宿題として、もう一度ゆっくり考えたいと思います。なぜ、私たちはあそこに行かなければいけないのか?なぜ、こんなにもあそこに行きたいと望むのか?人類の新たなフロンティア、なんてわけのわからないお題目に生命を賭してまで挑む理由があるんだろうか?いまは何もかもが陳腐に聞こえます。
それでも、宇宙飛行士たちはロケットに乗るでしょう、夢と希望を口にしながら。それは分かっています。純粋に個人的な望みとして、ぼくは胸をはって彼らに「いってらっしゃい」と手を振りたい。そのための宿題です。それが、ただの「ロケットフェチ」にできる、せめてもの弔いです。
宿題の答えは、少なくともあのつぶやきに答えることなしには見つからないんじゃないか、今はそんな気がしています。
. Date: 20031104 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.4 On-Orbit Events』をアップしました。
本章では、軌道上の出来事が日を追って説明されています。淡々としたものだけに、端々に登場する飛行士達の日常が心に刺さります。特に1月28日のアポロ1号とチャレンジャーの乗員に黙祷を捧げたと言う記述にはぐっときました。この日はチャレンジャー事故が起きた日です。コロンビアの空中分解はこの5日後のことです。
次はいよいよ、といいたいところですが。その前に断熱材の衝突の画像解析についての説明が入ります。
. Date: 20031105 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.5 Debris Strike Analysis and Requests for Imagery』をアップしました。
シャトルの打上げ後に行われた、断熱材の脱落に関する調査の話です。調査委員会が今回の事故はNASAの組織文化的な問題がその根幹をなしていると結論付けたのが頷ける内容です。ちなみに、後の章でふれられますが「勧告」の中には軌道上でシャトルを撮影することを義務付ける内容が含まれています。
さて、いよいよシャトルは軌道離脱のための噴射を行い大気圏へと突入します。
. Date: 20031111 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.6 De-Orbit Burn and Re-Entry Events』をアップしました。
大気圏突入時の出来事を時系列順に追っていったものです。本章ではテレメトリやセンサーのデータ、地上からの観測によるイベントのみを扱い、細かい事故のプロセスや事故原因の分析などは行われていません。
※参考
『Shuttle Track日本語版 FlashVersion』
http://lts.coco.co.jp/isana/review/shuttle/shuttle_track.html
NASAの発表した地図があまりに見難いので、ずいぶん前に作ったものです。
作った本人も存在を忘れてました。あはは。同PDF版
. Date: 20031113 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Mozilla Firebird衝動的にWindows上のデフォルトブラウザを変えたくなったので、Mozilla Firebird0.7を落としてくる。うむ、悪くない。本格的に乗り換えるべく環境を整える。(ちなみにこれまではSleipnir)
まず、タブブラウジング環境の整備。
Mozilla Firebird: 使用上のヒントのこのあたりを参照しながらTabbrowserExtentionを入れる。もろもろ設定。
タイトルとリンクのコピーをなるべく簡単になるように機能拡張を入れる。
jsActionsを入れてCamino べんりセットのスクリプト集から『リンクタグ作成(07_LinkTag.js)』を持ってきて普段使っているスタイルに書き換えたものを幾つか放り込む。本当は一気にクリップボードに取り込みたいのだが・・・まあいいや。
Search Extentionは以下のURLから
http://mycroft.mozdev.org/
Google、AllTheWeb、Amazonあたりを、とりあえず。
プラグインはとりあえずFlashとJAVAを以下のURLにしたがって入れる。
http://plugindoc.mozdev.org/ja-JP/windows.html
よし、これでとりあえずはオッケーかな。
雑このあいだ聞かれたのでメモ
Windowsでの翻訳/原稿書き/HTMLコーディングに使っているのは以下のソフト。
色々試したけれど、今のところ以下の構成で安定している。
TeraPad (でもJWordのバンドルは止めて欲しい)
王様の辞書引き(翻訳の王様/Thinkpadの付録)
PDIC+英辞郎
全部TeraPadのツールに登録してショートカットで呼べるようにしてある。
まとまった文章を書く時は、BasiliskII+漢字トーク7.5.5でmiを使う。
PerlのコーディングはLinux上でApache動かしながら。
辞書は動作が軽快ならオッケー。用例を引かなきゃいけないような単語は家で紙の辞書を引く。
翻訳ソフトはThinkPadの付録についてきたけれど、まともに使えたためしがない。
もしMac上に移すなら、上の4つはmiでいい。辞書はコトノコ、下の二つはMac版がある。
Linux上だと・・・Xemacs+Lookup かな? なんにしてもLinux上で長い文章を書く気にはならない。
. Date: 20031118 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記(訳文修正)※訳文の追加はありません。
修正したセクションは以下の通りです。
『2.4 On Orbit Event』『2.5 Debris Strike Analysis and Requests for Imagery』『2.6 De-Orbit Burn and Re-Entry Events』
ずんだあんのzunda氏(ドイツの風物とLinuxとサイエンスが微妙に混じった「おまぬけ活動日記」がおすすめ)に指摘してもらった訳文の修正を追加。いつもいつもありがとうございます。これまでも毎回指摘してもらっていて、そのつど直していたけれど、まとめて修正したときはここに記録しておくことにします。穴に潜りたくなるような間違いが毎回結構たくさんあります。あああ。
The Challenger: An Information Disaster
zundaさんに教えてもらった『チャレンジャー事故は図表の描き方いかんで防げたかもしれない』というお話(知りませんでした^^;)。統計情報の可視化のエキスパートEdward Tufteのエッセイ。(Sotto Voice経由)。面白いので、ちょっと理屈をこねてみましょう。
チャレンジャー事故の直接の原因は、低い気温の中で打ち上げを行ったせいで、固体燃料ロケットブースターのユニットのつなぎ目に入っていたO-リング(要するにパッキンです)が柔軟性を失い、そこから燃料と高温のガスが漏れたこと。この漏れたガスが、外部燃料タンクを外側からあぶり、さらに不安定になったブースターがオービターや燃料タンクに衝突したことで機体が破壊されました。
ここで、タフトが議論の対象にしているのはこのO-リングの破損と気温の相関関係を示すチャート。悪例としてあげているものは、ブースターの絵がずらっと並べられ、破損箇所と状態、気温が並べられたものになっています(細かいところはつぶれてしまってよくわからないけど)。代わりにタフトが好例として示すのは、温度とO-リングの破損箇所の数の相関関係を示すグラフ。つまり、後者のようなグラフになっていれば、O-リングと気温の相関関係が明らかになり、チャレンジャー事故は防げたかもしれない、ということみたい。
でも、これで図表の作成者の責任を問うのはどうかと思います。よく見てください。タフトが悪例としている図は「O-リング破損箇所の数と気温の相関関係」を示すためのものではありません。むしろこれはただ単純に「O-リングの破損の履歴」を記録したものです。だから、打上げごとに破損の場所や状態が一つ一つ記録されたものになっています。逆に、タフトの示した好例のほうには破損の場所や状態の情報は乗っていません。どちらが総合的な情報かは言わずもがなじゃないでしょうか?
事故が起きた後なら、「O-リング破損箇所の数と気温の相関関係」が事故の原因を示唆するものとして目にとまったかもしれません。でも事故が起きる前に、それが事故につながる可能性を指摘し、その両者の相関関係をグラフにするのは極めて困難です。それに、その能力はデータの可視化とはまったく別のような気がします。
実は、このO-リングの破損の危険は、かなり以前から指摘されていました(だから、事故以前にもああいうチャートが書かれていたんです)。さらに、チャレンジャーの打上げの際には現場のスタッフによって「気温が低すぎる」ことが危険要因として指摘されていました。チャレンジャーの事故調査でも、なぜこれらの指摘を考慮せずに打上げが行われたのかがかなり問題になっていましたね。でも、これもずいぶん難しい話です。スペースシャトルの打上げはまだ、せいぜい100回ちょっとしかありません。毎回の打ち上げの中に何らかの「初めて」があるはずです。じゃあ、どこまでが安全で、どこまでが危険なのか。ロケットブースターの破損も上に示されたチャートを見る限り、どこかしらで毎回起きています。シャトルシステム全体ならもっと故障や破損箇所があるはず。それらを全て直して、まったく故障やエラーのないシステムを作るのは不可能に近いはずです。
今回のコロンビア事故で問題点として指摘されていることのひとつは、この安全と危険を事前に判断するためのクライテリアがNASAの内部で明確になっておらず、それを評価する手段も無かったというものです。これまで、誰も明確に安全だという判断が下せないまま、「これまで大丈夫だったから」という判断基準で、打ち上げが行われてきました。今回の勧告の1つには、これらの安全性を評価する独立機関の設立が含まれています。
このチャートとグラフの話は、お話としては面白いけれど、ちょっと大げさですね。問題はグラフの描き方じゃありません。たとえあのグラフが描けたとしても、それが打上げを止められるような組織にNASAがなっていなかったことが問題なんです。
. Date: 20031119 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新えーと、スカパー入れました。それだけです。
. Date: 20031127 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『Mission Control Center Communication』をアップしました。2-6の囲み記事にあたる内容です。
事故の時にミッションコントロールセンターで交わされていた交信を記録したものです。
なんと言うか、訳していると胸が詰まります。次回は、事故後の調査の概略です。
ずいぶん間があいてしまいました。今回は、専門用語と会話体が混ざっていたので、訳すのにとても手間取りました。(いや、正直に言うと途中でいやになって放り出してあったんですが・・・)やむを得ず、専門用語をそのまま残した部分や、逆にニュアンスで訳している個所が結構あります。ご了承ください。
どうやら、ボーっとしている間にあちこちからリンクして頂いているようです。ありがとうございます。
いつのまにか、Yahooのディレクトリに追加されていたのには驚きましたが・・・
亀のように遅い更新ですが、気長にお待ちください。今後ともよろしくお願いします。
※追記
誤字・訳文を若干修正。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20031201 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Reveiew更新H-IIAの打ち上げ失敗に関するお話。
此処を見ている方なら、タイトル見ただけで予想がつくかと思いますが、そういう内容です。
NotePC故障再びまた液晶のバックライトがつかなくなる、2度目。同一個所だが、間かあきすぎているので、無料修理とはならないみたい。延長保証が効いているので修理にお金を払う必要はないはず。一瞬、マックに還る時が来たのかと思ったが、大丈夫そう。ごめんよs30。
というわけで、翻訳はあまり進んでいません。悪しからず。
. Date: 20031215 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 帰郷思いのほかThinkPadの故障は根が深く、修理代金の合計が買値を超えるというよくわからない結果になった。いろいろ考えたけれど、結局MacOSに戻ることにした。約3年ぶりに戻った故郷はずいぶん様変わりしていたけれど、それでもやっぱりここは懐かしい香りがする。
. Date: 20031225 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryご無沙汰しております。ようやく復活です。
[final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.7 Events Immediately Following the Accident』をアップしました。事故後の破片回収に関するお話です。
結局、前回の更新から、一ヶ月近く空いてしまいました。ずいぶんたくさんの方に見ていただいているようなのに、こんなていたらくで本当に申し訳ありません。
ようやく新しい環境への移行(WinからOSXへのSwitch)もほぼ終了し。前のペースに戻せそうです (ってホントか?)。
予定よりもずいぶん遅れてしまいました(予告している訳じゃありませんが)。
あー、1周年までにはせめて第1部を終わらせたいなあ。
. Date: 20031226 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記(レイアウト修正)※訳文の追加はありません。
スタイルシートおよび、原文表示切替用のスクリプトを修正しました。
これまで、スタイルシートを切ることで原文を表示していましたが、
日英両方を表示するCSSを別途用意して、切り替える形式に改めました。
これまでと同じく、ページ最下端のリンク「toggle English」で切り替わります。
MacOS、Safariでも動作するかと思います。
※Mac版のIEだけはエレメントがまともに拾えないので、
とりあえずスタイルシートをON/OFFすることで対応しています。
本文のHTMLはいじっていないので、これまでどおりCSSを切ると両方見えるはずです。
また、代替CSSに対応したブラウザならブラウザ側から切り替えられます。
『CHAPTER 3 Accident Analysis』をアップしました。第3章の前書きに当たる文章です。
あわせて、第3章の原文をすべてアップしました。
目次ではCSSでリンク色を抑制してありますが、すでにクリッカブルになっているはずです。画像はまだ入っていません。
さて、亀のような歩みですが、ようやく第3章に突入です。
この報告書の1つ目のクライマックス、事故原因に関する調査の詳細が述べられます。
長い!専門用語沢山!うぁー。
確かにSafariだとあちこち微妙に不具合がありますねえ。CSSを含めてちょこちょこ直します。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040107 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary あけましておめでとうございます見ての通り、本体サイトにあわせてこちらもデザインを変更しました。
今度は{ #ffffff & #33333 }です。基本的に、色を変えて、マージンだのバディングだのをひたすら調整しただけなんですが、ずいぶんさっぱりしましたねえ。
立ち上げ当初は黒いサイトだったんですが、最初のリニューアルで灰色に、とうとう真っ白になりました。
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、このレイアウトはコロンビア事故報告書のものがベースです(というより、元々リニューアル用に組んだものを報告書で先にお披露目しただけ)。
では、ことしもゆるゆると、はじめましょうか。
. Date: 20040109 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryさて、年末年始惚けていたうちに、ビーグル2が不調だったり、スピリットがすばらしい画像を送ってきたり、火星方面がにぎやかになってますねえ。では、いつものごとく備忘録から。
Daily Clipping以前、「月へ行くぞ」と発表するという情報がリークされていましたが、信憑性が高まってきました。しかも最終的には火星まで行くそうな。本当に実現すればすばらしいんですが、なにしろ親父さんのときもおんなじ発表してポシャってますからねえ。
いや、まあ、何にしても楽しみです。
うぉ、ほんとに見つかったよ。すごいなあ。まあ、飛行経路も落下位置もだいたいわかってるから、捜索範囲はそんなに大きくないとは思うけど。今回は6000mですか...よく発信機が生きてたなあ。
関係者の皆さん、本当にご苦労様です。
それでも、高度1800メートル以下でしか使えないんですね。ちなみに、コロンビア事故が起きたのは高度60km前後です。
『3.1 The Physical Cause』をアップしました。訳文で300字程度の短い文章です。
特に目新しい内容ではありませんが、これが公式の事故原因の要約になります。
. Date: 20040116 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily Clipping2015年にも月への有人飛行再開…米大統領が発表(Yomiuri Online)
正式に大統領の口から発表されましたね。2008年までに新しい有人探査機を開発、早ければ2015年、遅くとも2020年に月へというスケジュール。スペースシャトルは2010年には退役とのこと。
当然のことながら国内では反発の声もあり、他に金を使えと言う論調が半数を占めるようです。ただ、半数でとどまっているというのは、この間の事故が後押しになっていることは間違いないでしょうね。記事でも触れられていますが、本当に実現するのかどうかはまだわかりません。
まあ、何にしても予算がつき、計画がスタートするのはすばらしいことだと思います。
演説の結びの言葉はこうです。
Mankind is drawn to the heavens for the same reason we were once drawn into unknown lands and across the open sea. We choose to explore space because doing so improves our lives and lifts our national spirit.
So let us continue the journey.
(NASA - President Bush Offers New Vision For NASA)
※スピーチ原稿とファクトシートへのリンク有り
"So let us continue the journey"
この言葉が、歴史に残ることを願いたいですね。
http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/Safari_Scripts.zip
URLクリッピング作業の効率化のために簡単なAppleScriptを作りました。なかなか便利なので、ここにさらしておきます。Safariでしか動きません。
・Link(URL/Selection):当該ページのURLと同ページ内の選択範囲からリンクタグを生成
・Link(URL/Title):当該ページのURLとタイトルからリンクタグを生成
・Link(Clipboard/Selection):クリップボード内の文字列をURL、選択範囲をリンク先とするリンクタグを生成
生成されたリンクタグは再度クリップボード内に格納されます。お好きなところにペーストを。
生成されるリンクに「target="_blank"」が指定してあったりしますが、スクリプトエディタで好きにいじるなりしてください。ものすごく短くて簡単なスクリプトです。
スクリプトメニューをインストールして(~/アプリケーション/AppleScript/にインストーラーがあります)、解凍したスクリプトを~/ライブラリ/Scripts/にいれておけば、メニューからアクセスできるのでさほどストレス無く使えると思います。
. Date: 20040120 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新下の「Maestro」の紹介。
アプリケーションを触って、こんなにどきどきしたのは初めてかもしれない。
NASA ジェット推進研究所が提供している、火星ローバーから送られてくる画像を解析するためのソフト。基本的にはNASAで実際に使用しているものとほぼ同じ。Windows、MacOSX、Linux、Solarisで動作する。(※MacOSX版にはJava3Dが必要)
すげー。でも、激烈に重いなあ。
何かと思ったら、ローバーに搭載された2台のカメラ画像から地形を読み取って3Dのメッシュつくって立体化するツールがメイン。写真の中の一点をポイントすると、かなり正確に3D地形上の点に対応してその位置情報がシステム内に記憶されて、他の写真に移動しても同じ場所がプロットされる。
他にも、ローバーの行動予定を組んだり、画像解析したり、いろいろできる。
「Conductor」のナビゲーションに従って順番に画像を見ているだけでもたのしい。ものすごく重いけど。
. Date: 20040122 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingEmpty Nest (NASA)
火星『コロンビア記念基地』の肉眼で見た色に近い画像。
BBC (詳しい解説が掲載されています)
maestro - Mars Dataset #2 Downloads
Maestroの新しいデータがアップされました。今回は、スピリットが走り出すところまでです。上の画像の元になったデータが含まれています。
. Date: 20040126 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily Clipping二つ目のローバー、オポチュニティ着陸成功!おめでとう。
これは最初の画像。おお、この写真「遺跡」が写ってる...(と、人心を惑わすようなこといってみる)
Spirit upgraded to 'serious' condition
1つ目のローバーは、故障中。うまく行けば、なおるかもしれない、というお話。がんばれ!
. Date: 20040128 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記ずいぶんご無沙汰していました。実質ひと月ぶりの更新です。
『3.2 The External Tank and Foam』をアップしました。内容は、空中分解の原因と考えられている打ち上げ時の断熱材の脱落について、外部燃料タンクの耐熱システムの概説と脱落原因の調査です。
何が原因ということは特定できなかったものの、断熱材の付加作業について不備があった訳ではなさそうです。むしろ、設計時の都合が作業行程の複雑化を招き、断熱材のクオリティコントロールを難しくしたということが遠因として強調されています。
次は、本章の囲み記事。断熱材の脱落理由として最も有望とされていた「クライオインジェスチョン」と「クライオポンピング」(断熱材の中に閉じ込められた液体が急激に気化することで破壊が起きる)を脱落の原因から外すに至った調査についてのお話です。
maestro - Maestro Mars Data Updates
おなじみ?火星ローバー画像解析ソフトMaestroのデータアップデートです。
今回は、走り出したスピリットが火星の石や地面のクローズアップを撮っているはず。ちょうど、通信が途絶する前あたりまででしょうか。
多分次のアップデートでオポチュニティのデータが追加されるんじゃないでしょうか。来週ですね。
. Date: 20040129 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingButterflies boast ultrablack wings (Nature)
雄のオオルリアゲハ(Papilio ulysses)の羽は、ただ黒いだけではなく、物理的に光をトラップすることで光を反射せず「黒より黒い」というお話。
NASA: Second Mars rover having problems (CNN)
2台目の火星ローバー「オポチュニティ」にも異常があるらしい。動作は順調に行われているものの、電力消費が異常に大きいとのこと。どうやらヒーターがつきっぱなしになっているらしい。あああ。
Spirit seeks early return to work (BBC)
スピリットの方は思ったより早く復帰できるかもしれないとのこと。
そうそう、スピリットの着陸地点から見える3つの丘に、地上でのテスト中に亡くなったアポロ1号のクルーの名前が付けられましたね。
. Date: 20040130 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingHealthier Spirit Gets Back to Work While Opportunity Prepares to Roll (NASA)
スピリットが機能を回復し、画像を送信してきました。やったー。
オポチュニティは順調、どうやら「立ち上がった」ようです。昨日のヒーターの件は触れられていませんね。
Frying pan fumes 'kill canaries' (BBC)
環境保護団体が、家庭で飼われている鳥が死ぬのはテフロンフライパンのせいだ。と主張しているというお話。テフロンの危険性についてはずいぶん前に書きましたね。
『こびりつかない、焦げ付かない 』(Junkyard Review)
「必要以上に強火にしない」「空焼きしない」この2点を守れば安全だと思います。
New form of matter created in lab(BBC)
物質の新しい様態が発見された、というお話。気体、液体、固体、プラズマ、ボーズ・アインシュタイン凝縮に次ぐ6番目。本当なら、ノーベル賞ものの研究です。
カリウムを絶対0度近くまで冷やしたら変な挙動を示した(としか記事には書かれてません)。これはボーズ・アインシュタイン凝縮のフェルミ粒子版?超伝導の説明なんかで見かけるやつじゃないのか?実証したということなんだろうか?うーんよく分からないな。
ちなみに、プラズマというのは高熱で物質から電子が分離してしまった状態。オーロラとか稲妻とか蛍光灯の中とかです。ボーズ・アインシュタイン凝縮は本来統計的にしか把握できないはずの粒子の集団が、超低温で量子的な振る舞いが同一になって、まるで1つの巨大な粒子であるかのような挙動を示す状態(ものすごくいい加減な説明だな)。ボーズ粒子と呼ばれる粒子で起きる現象です。あまり身近にはありません。「超流動ヘリウム」なんていうのがこれだといわれてますね。2001年にノーベル賞を取ったコーネルとワイマンはこの状態を実際に作り出したことを受けての受賞でした。
「年間100万分の1以下」原発大事故のリスク目標値案 (ASAHI.COM)
えーと、何が、何の100万分の1なんでしょう?「目標値はがんによって国民が死亡する確率の約1000分の1」らしいので、全国で年間100万人に1人は原発事故で死ぬということですか? 日本の人口は1億2000万人だから、年間120人?あ、「周辺住民」か、10000人として全国に50箇所強だから、年間0.5人。10年で5人か、結構多いな。どーいう計算をしたんだろう。
「有人宇宙飛行」目指す…政府、宇宙開発政策を見直し (読売)
おー、前言撤回ですね。中国に負けてられないということでしょうか、アメリカに追従ということでしょうか。変な方に転ばなければいいんですけどね。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040203 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review 更新少し遅れましたが、いつぞやの宿題への1つの答えです。一年もかけて結局それかい!という感じですが、少なくともこの視点だけは忘れないでおきたいと思います。
Daily Clippingmaestro - Maestro Mars Data Updates
今週も無事に出ました、週刊Maestro第4号。今回はオポチュニティの着陸です。
. Date: 20040205 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingNASA Opportunity Rover Microscopic View of Mars in Color (SpaceRef)
オポチュニティから撮影された、火星表面のクローズアップ写真。対角線が3cm位です。
おー、球形の石が混じっているあたり、いかにもクレーターという感じですね。
The physics of haute couture (Nature)
布の挙動を表現するための新しい数学的解法が見つかった、というお話。ドレープの入った布がどのように折り畳まれるかということに関する計算がより正確にできるということのようです。んー、リアルなリアルタイムクロスシミュレーターとかができたりするんだろうか。CGの布って「柔らかすぎる」感じがしますからねえ。
. Date: 20040216 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clippingmaestro - Maestro Mars Data Updates
火星探検アプリ、Maestro のデータアップデート。わーい。
今回はオポチュニティとスピリット両方のデータがアップされています。スピリットは不具合から回復し、岩に孔をあけるところまで。オポチュニティは走り出し、クレーター内を調査し始めるところまでです。
どうでもいいけど、この"mars.telascience.org"サーバ、先週末落ちてなかったか?
「スナップ/スナックエンドウ」はどっちが正しいのか?
晩ごはんにもう一品という時に、「ゆでるだけ」という簡単さ、でもほうれん草のおひたしとは違う、という微妙な線を実現してくれる「スナッ○エンドウ」。でも、この豆表記が統一されていない。「スナップエンドウ」「スナックエンドウ」が混在。市場ではなんとなく「スナップ」の方が多いけれど、Google検索では「スナップ」1,810件、「スナック」3,160件と、スナック派の方が多い。さて、正しいのはどっちか?
調べました。これは、スナップエンドウが正式名称。輸入された当初、各農家で様々な名前で呼ばれていたが、昭和58年に農林水産省が「スナップエンドウ」と定めたとのこと。あーすっきり。でも、いまだに「スナック」の名前を使っているところも多いということらしい。
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/qa/alt/altqa030707.htm
. Date: 20040227 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingちょっと眉唾。「睡眠時間が長い/短い人の平均死亡率が高い」という結果は必ずしも「7時間寝れば長生きできる」あるいは「睡眠7時間じゃないと長生きできない」という結果にはつながらない。こういう統計上のトリック(?)はよく見るけれど、引っかからないように。この結果だけでは何ともいえない、というのが誠実な結論だと思います。
このネタは、アメリカの研究結果が発表されたときにJunkyard Reviewでネタにしています。
http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20020118222456
ひと月ぶりの更新です。忙しさにかまけているうちに、ちょっと間が開きすぎました。いかんなあ。
『FOAM FRACTURE UNDER HYDROSTATIC PRESSURE』をアップしました。3-2の囲み記事に当たる文章です。
断熱材の脱落理由として最も有望とされていた「クライオインジェスチョン」と「クライオポンピング」(断熱材の中に閉じ込められた液体が急激に気化することで破壊が起きる)を脱落の原因から外すに至った調査のお話。
ご家庭で出来る簡単断熱材テスト、という感じですね。
次は、オービターの主翼前縁部分の構造とダメージについてです。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040301 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book] 松浦 晋也 『国産ロケットはなぜ墜ちるのか』日経BP社 (amazon)ずっと、日本の宇宙開発を追い続けてきた、日本随一の宇宙開発ジャーナリスト松浦晋也氏渾身のルポ。前作では、日本独自の有人宇宙飛行計画を巡って「日本の宇宙開発の夢と現実」が語られていましたが、今作では、日本の宇宙開発を巡る政治と組織の問題に迫っています。
日本の宇宙開発の現状が知りたいのなら、今のところこれ以上の本はないと思います。ただ、作者自身が「日本独自の有人宇宙計画」に思い入れが深いので、どうしても議論がそっちに傾いてしまうきらいはありますけどね。
と、上の本にそっくりのタイトルの本が、店頭に並んでいました。作者は中冨信夫氏。普段ならこの人の本は買わないんですが、いつもの似非NASA紹介本じゃなかったので、出来心で読んでみました。これは、ちょっと、ひどいです。一言で言えば、「日本の宇宙開発の設計思想 Design Ideas の無さを糾弾する」という主旨の本。同じ内容を書いているのにこうも読後感が違うのは、中富氏には日本の宇宙開発に対してこれっぽっちも愛がないからなんでしょう。
日本の話だと「設計思想が悪い」になり、アメリカの話だと「設計思想は素晴らしいが、組織と予算の少なさが原因」になるのはなぜでしょうか?本当に事故調査報告書を読みましたか?イントロダクションにすら、まずい設計を騙し騙し運用してきたことに根本的な原因がある、って書いてあるんですが...。アメリカの宇宙開発の記述には、予算の切り詰めが技術を圧迫なんて書いてあるのに、日本の場合は税金の無駄遣いだ!という記述ばかりで、日本の宇宙開発予算の少なさに対する言及はほとんどありません。ESAやNASAの開発初期段階の失敗には「失敗から学び」となるのに、日本の開発初期段階のH-II、H-IIAだと「愚かにも」とか「ぶざまにも」っていう単語が踊ります。どうしても、必要以上にNASAやESAの技術を称揚し、日本の宇宙開発をおとしめているようにしか読めません。
政治的な思惑の中で予算や組織が技術開発を圧迫していく。ルーティン化してしまったプロセスや責任の不在が安全性や信頼性を脅かしていく。一歩引いてみれば、NASAもJAXAも抱えている病は同じに見えます。この両者を丁寧に分析するだけで、第一級の技術-組織論が書けると思うんですけどねえ。これだけ豊富な材料を用意しておきながら、冷静にその両者を比べることをせずに、「アメリカは素晴らしく、日本はダメだ」という結論だけを声高に叫ぶだけになってしまっているのが、作者の視野の狭さを表しているような気がします。
両方読むとなかなか趣が深いんですが、どちらか一冊をということならば、迷わず松浦氏の本をお進めします。
それにしても、この光文社ペーバーバックスシリーズの「英語まじり4重表記」はただひたすら読みにくいだけだねえ。日本語だと意味がぶれる単語に英語表記が付加されているわけでもなく、時事英語というわけでもなく、なんだか思いついたように単語に英文表記が付加 add されているのでイライラさせられる irritated こと甚だしい very much。
これを評して「日本語表記の未来形」とはちゃんちゃらおかしい。同じ意味を二度繰り返してどうするよ。やるんならもっと、boldly に cutting off the words すべきだyo ! yo ! はあ、たった1文なのに、この文体はものすごく疲れる ne !
. Date: 20040302 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping彗星探査機ロゼッタ打ち上げ (Spaceflght Now : Mission Status)
2002年12月のアリアン5の失敗により、打ち上げが延期。当初の目標だった46P/ワータネン彗星に到達できなくなったため、軌道計算から何から全部やり直して67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に変更。あげくのはてに打ち上げ寸前にアリアン5の断熱材の脱落が発見されて、再び一週間近く延期。紆余曲折を経てようやく打ち上げられ、無事探査機の切り離しが確認されました。
この探査機の最大の特徴は、彗星本体への着陸機を備えていること。彗星の核は、太陽系創世時の物質がほとんど変性せずに保存されていると言われており、研究対象としては非常に魅力的です。
この後、ロゼッタは2005年、2007年に地球をフライバイ、2007年に火星をフライバイ、2009年に再び地球をフライバイし加速をつけます。アステロイドベルトをくぐり抜け、徐々に軌道を変更、その後2011年から3年間冬眠状態に入り、ようやく2014年1月に目標である彗星に到着します。約10年の道のりですね。
よい旅を、ご無事をお祈りします。
Major news from Mars rover to be announced Tuesday (Spaceflight Now)
火星ローバー、オポチュニティの「重要な発見」に関する会見がアメリカ東部標準時2日午後2時から行われるそうです。なんだ、なんだ?そのもったい付けたリリースは。水か?それとも生き物の痕跡でも見つかったか?緑の小人か?
少しまじめに書いておくと、この間オポチュニティはクレーター内の岩石に関する観察をずっと行ってきましたから、その分析結果から「何か」が分かったということでしょう。会見を開くほどの重大発表だとすれば、過去ないし現在、液体の水が存在したことを立証する結果が出たというのが一番有力じゃないでしょうか。さすがに、いきなり「生命」はないと思いますが...
※NASA Watchによると、このカンファレンスは二週間前に予定が組まれており、遠隔会議システムやストリーミングサーバなどの準備が行われてきたとのこと。ですから、少なくとも「緊急会見」ではありませんね。先週末の段階で、NASAの科学者が「水の存在についてそろそろ結果が出せそうだ」「火曜日頃には発表できる」なんてことを言っていましたから、予定していたプレスカンファレンスに合わせて、この結果を発表というところでしょう。
いやー、楽しみですねえ。わくわく。
Shattered eggs reveal secrets of explosions (Nature)
密閉物が爆発した時の破片の大きさは爆発時の圧力によって決まる、ということが卵の殻を使った実験で明らかになった。というお話。卵に小さな穴をあけて酸素と水素を吹き込み火をつけて吹き飛ばすという、中学生の自由研究みたいなやりかたで実験を行い、爆発力が強ければ強いほど破片は小さくなるということを明らかにしたとのこと。ゴムで飛ばしてぶつけてみたりしたが、爆発の時ほど破片は大きくならなかったそうな。楽しそうな実験だなあ。
元論文 : Fragmentation of shells
※Nature のサイトに記載されているアドレスは間違ってます。
. Date: 20040303 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Science@Nasa記事翻訳火星にかつて液体の水があった証拠が発見されたというニュースについて、Science@NASA に簡単にまとめた文書があったので、ざっと訳してみました。訳文の乱れはご了承ください。
Meridiani Planum: "Drenched"
http://lts.coco.co.jp/isana/archives/mars/mars_water040302.html
※例のごとく、ページ最下端のtoggle Englishで原文参照可能です。
Mars Rover Scientists Wring Water Story from Rocks (NASA)
火星にかつて水が存在した証拠が発見されました。素晴らしいニュースです。
地球外で液体の水の存在が実証されたのは、これが初めてです。
マーズローバーによって観測された岩石から硫黄、ジェロサイトと呼ばれる硫酸鉄和輪物、硫酸塩の存在が確認されました。地球では、これらの物質は水の中で形成されたか、長期間水にさらされていたことを示します。この岩石は、酸性の湖か、酸性の温泉の中にあったことを示唆するものです。
これまでも、かつて火星には大量に水が存在した可能性が高いと言われていました。30億?40億年前火星がずっと若く活発だった頃、大気圧は火山性の二酸化炭素によって今よりずっと高かったはずです。さらに、その二酸化炭素による温室効果のために、平均気温もいまより高かったでしょう。このような環境下で液体の水が存在し、一部では河が流れていた可能性があると考えられていました(海があったとする説さえあります)。これは、このときに出来た水による浸食地形の跡とされる地形がが火星表面に数多く残っているためでした。ただ、地形の観測だけでは、本当にそれが水の浸食によるものかどうかははっきりしていなかったんです。それが、今回の発見によって、かつて液体の水が存在したとする確証が得られたということです。
現在の火星について水の存在が確認されているのは、両極と大気中の僅かな水蒸気だけです。両極は大半が固体の二酸化炭素、つまりドライアイスからなっていますが、その中心部分に夏にも消えない領域があり、これが氷からなっていると考えられています。また、火星を周回しているマーズオデッセイは、ガンマ線スペクトロメーターという装置を用いて、火星の表面および地球の浅い不部分の水素濃度を観測し、南緯60度以南では永久凍土層があり大量の水が氷という形で存在する可能性が高いことを示しました。
現在の火星は気圧が低く(地球の1000分の6です)液体の水は存在が難しいとされています。火星の平均気温は-55度で水の凍結点より低いですが、最高気温は27度になることもあり、必ずしも何もかもが凍りついているという感じではありません。ごく短期間ならば地表に液体の水が存在する可能性は十分にありますし、地下水という形で保持されている可能性もあるでしょう。
一部ですが、最近水が流れた跡とされる地形も見つかっています。
MOC Images Suggest Recent Sources of Liquid Water on Mars
これは、火星周回軌道上の衛星から撮影した写真に写っていた「ごく最近まで液体の水が地表に存在していたことを示す証拠」とされる画像です。たしかに、水によって作られたとしか思えない地形ですし、浸食作用のことを考えれば大昔の水の痕跡というわけでもなさそうです。ただ、これには異論もあって、地下で凍った二酸化炭素が春に暖められて気体になる過程で、地表の土と混ざり「あたかも液体のように」流れ落ちたものという説もあります。
平たく言ってしまえば、「かつて液体の水が存在したことはまず間違いなさそう、今も水は何らかの形で存在している可能性が高い、でも液体の水の存在についてはまだよくわからない」という感じです。
こうなると次に気になるのは、その水がいつ頃存在していたのか?そしてもちろん、火星人、じゃない火星の生命の痕跡ですね。わくわくわくわく。
. Date: 20040304 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingNew IMAX 3-D film project goes lunar with Tom Hanks (SpaceFlightNow)
SPACE STATIONに続く、IMAX3Dの宇宙シリーズはアポロ月面着陸ものだそうな(もちろん実際の映像)。きゃー、きゃー。これから作るんだけどね。
. Date: 20040308 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clippingmaestro - Maestro Mars Data Updates
しばらく間が開きましたが、火星ローバーデータ解析ソフト『Maestro』がデータアップデートがありました。今回は、スピリットのデータが2本、オポチュニティのデータが1本の計3本です。スピリットは着陸地を離れボンネビルクレーターへと向かい、オポチュニティは着陸地で岩石のクローズアップなどを撮影しています(水が見つかった証拠とされるデータも含まれていますね)
. Date: 20040311 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clippingmaestro - Maestro Mars Data Updates
えーと、誤投稿じゃありません。火星探検アプリMaestroのデータアップデートがありました、今回はスピリットが1本、オポチュニティが2本です。スピリットはあちこち寄り道をしながらボンネビルクレーターに向かってひた走り、オポチュニティは水の存在の証拠を求めて、着陸地を仔細に調査しています。
このソフト、本当に画期的だと思うんですが...あんまり注目されていませんねえ。ちょっとマニアックすぎるかなあ。ガイダンスに従ってクリックしているだけでもかなり楽しめるんですけどね。コンスタントにデータのアップデートが行われているため、今やデータだけでも100Mを越える一大アーカイブとなりつつあります。
. Date: 20040312 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingYou are here. (NASA)
きたきた、これです、これが見たかったんです。スピリットから「火星から見た地球」の画像が届きました。遠いですねえ。
もう何枚か写真を紹介しましょう。
A Deep Dish for Discovery (NASA)
これは、スピリットが目的地としていた、着陸点から300m以上離れたところにあるボンネビルクレーターを覗き込んだ画像。この間、平坦な地形がずっと続いていましたから、この画像はなかなか壮観です。
A Long Way From Home (NASA)
そして、これが後ろを振り返った画像。解像度の高いデータを見ると、画面中央、タイヤの跡の彼方に小さく着陸地点の『コロンビア記念ステーション』が見えます。
私たちは、あの惑星から来て、あそこに降り立ち、ここまでやってきました。
なかなか感動的な画像です。
Concrete casts new light in dull rooms (optics.org /from slashdot.org )
光を透過するコンクリート。すげー。
どうやら、光ファイバーを一定方向に並べてコンクリで固めたものみたい。
. Date: 20040316 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingMost Distant Object In Solar System Discovered (NASA)
さて、各所ですでに話題になっている「第10番目の惑星」。新しい惑星発見、という形で報じられているようですが、本当にそうなるかどうかはまだ分かりません(ならないんじゃないかなあ)。なにしろ、冥王星でさえ「惑星とするには小さすぎる、あれは小惑星だ」との意見が多く、つい先頃の国際会議で「慣例から一応惑星とする」と決まったくらいです。冥王星より小さく、近くても距離が地球-冥王星間の3倍という天体が「惑星」の認定を得られるかどうかはかなり疑問です。ちなみに、発見者のMichael E. Brown教授(Caltech)のサイトには、はっきり「惑星ではない」とかいてあります。同チームは2002年にもクワオワと呼ばれる天体を発見しており、この時も10番惑星がと騒がれていました。
でも、このセドナがとても興味深いのは、惑星かどうかという議論よりも、その軌道です。セドナの周期は2万年、長楕円軌道でこれからの72年が最接近期になります。太陽系の他の惑星系よりもかなり遠く、彗星の巣とよばれる小惑星帯「オールトの雲」よりはずっと近いという微妙な距離を周回しており、このような軌道を描く天体の観測は初めてです(遠日点はハレー彗星よりずっと遠くです)。これは太陽系の形成過程に「オールトの雲よりも近く惑星系よりも遠い」何らかの天体群があった(今もある?)ことを示唆するのかもしれません。太陽系の形成にまた1つ謎が増えたともいえますし、セドナを詳しく研究することで、太陽系形成の過程が詳しく分かってくるかもしれないんです。わくわくしますねえ、あー、しませんか?
※Science@NASAのページと発見者のページを混同してました。修正済み。
'New planet' may have a moon (BBC)
セドナには月があるかも、というお話。ちなみに「月がある=惑星」ではありません。
衛星を持った小惑星イダの画像 (日本惑星協会)
. Date: 20040317 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingSix-terabyte sky catalog released to public (Spaceflight Now)
スローンデジタルスカイサーベイの成果が発表(まだ、一部だと思う)。データファイルは6テラバイトだそうな。
スローンデジタルスカイサーベイというのは、全天の1/4の範囲について、5つの波長を使って、1億個以上の天体の位置と明るさ、100万個の銀河までの距離を計測し、極めて子細な深宇宙の3次元地図を作るという計画です。専用の天文台を持ち、数カ国の研究者が共同で行っています。簡単なようですが、大げさにいえば、顕微鏡で地球の表面を全部写真に撮る、という位のとんでもない規模で行われているんです。
何がすごいかっていうと、これで「宇宙の一般的な性質」というのが分かる。何が特殊で、何が一般的なのか。宇宙というのはどんな形をしていて、何がどんな風に分布しているのか、ということが分かるわけです。これまでの天体観測は、今見ている現象が宇宙全体で特殊なのか一般的なのかが分からなかったわけです。近くなら沢山観測結果がありますからそれなりに分かるんですが、クエーサーなんていうのがいるような、見えるか見えないかの限界みたいな領域では、いまいちよく分からなかった。それを一気に地図にすることで明らかにしてしまおうというわけです。この地図が出来ることで、宇宙の大規模な構造が明らかになれば、宇宙がどうやって成長してきたかということが分かるかもしれません。
Distant Sedna Raises Possibility of Another Earth-Sized Planet in Our Solar System
タイトルは「セドナは地球サイズの他の天体の存在を示唆するかもしれない」。おぉ!と思ったけれど、そういう説もあるという程度みたいですね。カイパーベルト(冥王星付近の小惑星帯)とオールトの雲(太陽系最外辺部の小惑星帯)の間の空間で、長楕円軌道を描く天体、というとても特殊なセドナの生い立ちについて学者達が喧々諤々やっているようです。太陽系の外の天体の重力に引かれた説、太陽系内の未知の天体の影響説など、まだまだ盛り上がりそうです。楽しみだなあ。
. Date: 20040322 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新すっかり月一更新状態だなあ。今回は(ロケットから少し離れて)磁石のお話。なんだかまとまりの無い文章になってしまった。まあ、いいか。
そうそう、ネオジム磁石はとても楽しいけれど、電子機器や磁性製品にとっては大変な危険物なのでくれぐれもご注意を。よもやポケットに入れて持ち歩いたりしないように。クレジットカードがパーになっても知りません。
あまり関係ないけれど、地磁気の話を調べているとトンデモ系のサイトがざくざく引っかかる。地磁気消失で人類破滅!みたいなのばっかり(ついこの間そういう映画があったみたいですが)。確かに、地磁気が弱まると地球の大気が直接太陽風に曝されることになる。ただ、それによって何が起きるかはよく分かっていない。これまで、何度となく地磁気が弱くなったり逆転したりしているはずだけれど、大量絶滅と地磁気の消失の因果関係は今のところ発見されていない。で...
地磁気が消えると宇宙線がバシバシ... たぶん来ない(太陽風と宇宙線は別もの)。
地磁気が消えるとオゾン層が... 消えません。
地磁気が消えると地球温暖化が... 進んだりしません。
地磁気が消えると自転が... 止まりません!
地磁気が消えると重力が... 消えるわけ無いでしょう!うがぁ!
. Date: 20040323 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingIt's a Bird, It's a Plane, It's a... Spacecraft? (NASA)
スピリットのカメラが捉えた、謎の光点。軌道から考えて、おそらくバイキング2号のオービター(軌道船)だろうとのこと。バイキング2号が運用を停止したのは、1978年7月25日。現在位置ははっきり分かっていません。もちろん、全く未知の飛行物体という可能性もなくはないですが...
Rover Sees a UFO? (Universe Today)
いや、だから、そういう誤解を呼ぶようなタイトルはどうかと...
冗談はともかく、火星の空をよぎる機能を停止した人工衛星、というシチュエーションは、「えすえふ心」をみしみし刺激しますねえ。J・G・バラードですな。
maestro - Maestro Mars Data Updates
火星探検アプリMaestro、恒例のデータアップデートです。スピリット、オポチュニティそれぞれ一本ずつですね。スピリットは「ハンフリー」に接近、オポチュニティは岩をドリルで削ります。
. Date: 20040324 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clippingえー、ほんとかなあ。地上から分かるぐらいの距離を離して衛星を配置したら、軌道速度が全然違うから安定した「絵」にはならないと思うぞ。それとも、衛星どうしを何らかの方法で接続するんだろうか。完成したISSでさえ地上からは光点にしか見えないのに、どんな巨大構造物になるんだろう?潮汐力でちぎれたりしないかなあ?たとえ強度が持ったとしても、放っとくと潮汐力で地球に対して立っちゃうはずだから、結構頻繁に姿勢制御をしなきゃいけないしなあ。立方体の頂点に人工衛星を配置すれば...なんとなく安定しなさそうだなあ。
どう考えても、コストパフォーマンスが悪すぎますね。莫大なコストがかかるし、空気抵抗で高度が下がるからそう長くは持たないはず(うろ覚えだけれど高度200kmで1週間持たないんじゃないかな)。こんなものを維持するコストをかけられるなら、世界中のチャンネルで枠が買えるはず。そうまでして宣伝しなきゃいけないものって何だろう?話題性を狙うにしても、高い買い物だと思うけど。
Standing Body Of Water Left Its Mark In Mars Rocks (NASA)
火星ローバー、オポチュニティが着陸した場所はかつて「渚」だったらしい、という発表がNASAかありました。岩の上に見つかった波紋状の模様は打ち寄せる波によって形成されたようです。
. Date: 20040325 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingScientists create fifth form of carbon (Nature)
5番目の炭素の形態を発見というお話。「ナノフォーム」と名付けられ、スポンジ状をしており、非常に軽く、磁気に引かれる性質があるとのこと。応用範囲が広そうな物質ですねえ。
グラファイト、ダイヤモンド、ナノチューブ、バックミンスターフラーレンに次ぐ5つ目。おや、ナノホーンは?ナノチューブの一種という扱いなのかな(※調べました、ナノホーンはナノチューブの片方が閉じたものとのこと)。
そういえば、先日こういうニュースもありましたね。
Yarn spun from nanotubes: Tiny tubes may yield ultrastrong fibres.
ナノチューブを寄り合わせて長くする技術が開発されたというニュース
Cat Cloning Offered to Pet Owners(National Geographic)
猫のクローンが商売に、というお話。2年前ぐらいに「猫のクローンに成功」というニュースが流れましたが、同じ会社が同技術を実用化したとのこと。1回50,000$。結構安いですねえ、ただし、姿も性格も全然似ていない可能性があるそうですが...
1 year later: Cat, clone differ (USA Today) ※2003年の記事
クローンについては、まさしくこのニュースに反応する形で2003年の1月にJunkyard Reviewにかなり感情的な文章を書きました。今もあまり変わってません。問題は作るか作らないかではなく、作った後どうするかだと思います。
火星ローバー「オポチュニティ」が着陸したクレーターから外に出ました。 (NASA)
いろんな意味ですごい画像です。カラー画像が公開されたらまた紹介しましょう。
. Date: 20040327 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記えーと、お忘れかもしれませんが、まだやっています。またもひと月ぶりの更新です。うーむ。
『3.3 Wing Leading Edge Structural Subsystem』をアップしました。
主翼前縁部に使用されている強化カーボンカーボンパネルのお話です。事故の原因はここに断熱材が衝突したこととされていますが、事故以前にも何度か損傷が確認されていたようです。その経緯とパネルの状態を計る手法についての報告です。
次は本章の囲み記事2本。強化カーボンカーボンの説明とオービターの翼に使われている材料のお話。
. Date: 20040330 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingMethane on Mars could signal life (BBC)
火星の大気にメタンが発見されました。もしかしたら、これは生命の兆候かもしれません。ま、まじですか。
この発見は話題の火星ローバーではなく、火星の衛星軌道を周回するESAのマーズエクスプレスと地上の望遠鏡からなされました。マーズエクスプレスが大気中に微量のメタンを検出。次いで、ハワイとチリのジェミニ望遠鏡(この望遠鏡は2台1組で観測を行い、1台は南米に、1台は北米にあります)によって、さらに高解像度で火星の大気を観測した結果、メタンの存在が確かめられました。
メタンは紫外線で分解してしまうため、火星の大気内では長期間存在できません。大気中にメタンがあるということは、つい最近何らかの理由で作り出されたはずなのです。考えられる理由は2つ、火山か生命です。これまで、火星で活火山は発見されていません。とすれば・・・。
もちろん、火山の可能性もありますし、もっと他の原因かもしれません。でも、メタンの発見が事実なら、あそこで今も何か活発な活動が起きていることは確かです。わくわく。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040401 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping火星にメタン、生命体が放出?…欧州探査機が検出 (読売新聞) (infoseek)
日本でも紹介され始めましたね。でも、「げっぷ」じゃないでしょう、「げっぷ」じゃ。
地球上では、メタンは動物のげっぷなど生命体による活動でも発生するため、同氏は「火星で生命活動が営まれている可能性も捨てきれない」としている。
エイプリルフールのジョークかな?とはいえ、げっぷと火星の生命の間に全く関係がないかというと、そうでもありません。ちょっと面白いので書いておきます。
火星には酸素がほとんどありませんから、生命が存在するとしても嫌気性(酸素を必要としない)微生物だと考えられています。地球では地中や火山などの「極限環境」でも嫌気性微生物があちこちで発見されており、火星をはじめとする地球外の惑星でも条件さえ整えば生命維持が可能だといわれています。
嫌気性微生物の中でも有力視されているのが、水素と二酸化炭素からブドウ糖を合成し水とメタンを放出するという化学合成を行う種類です(ちなみに光合成は二酸化炭素と水からブドウ糖を合成し酸素を放出する過程のことです)。だから、メタンと生命が結びつくんです。この種類は結構あちこちにいて、酸素の少ない湖や沼、水田、海、牛の反芻胃、シロアリの後腸などにも住んでいます。この種の嫌気性微生物が火星にいれば、メタンが検出される可能性があります。
そう、牛が出てきましたね。実は、牛のげっぷに含まれるメタンは体内の嫌気性微生物が、水素+二酸化炭素=ブドウ糖+水+メタンをやっているせいです。だから、確かに「げっぷ」と火星の生命の間には関係があるんです。
記事には「動物のげっぷなど生命活動でも」と書いてありますから、嘘はついてません。でも、ちょっと間をはしょり過ぎですね。どうしても、火星の赤い大地で白黒の生き物が「もー」とか言っているのを想像してしまいます。
ただ、この間も書いたように「メタン」=「生命」ではありません。今回の場合、むしろ火山性のメタンガスの可能性が高いでしょう。活火山じゃなくても、地中にたまっていたガスが放出されただけかもしれませんし、隕石の衝突によるものかもしれません。それでも、大気中にメタンがあるということは「あそこで何かがおきた、あるいは今もおきている」ことを示唆するんです。それは充分にスリリングなことだと思います。
嫌気性生物や極限環境生物に関して、最近とても良い本が出ました。
この本は、表題とは裏腹にむしろ嫌気性微生物をはじめとする「極限環境生物」のお話です。地球の極限環境生物を紹介しながら、木星の衛星エウロパに存在するといわれる海の中で生命が誕生している可能性について語った本です。著者の長沼氏は深海生物学の専門家。読み進むうちに、どんどん「生命観」がぐらぐらし始めるとても良い本です。おすすめです。
. Date: 20040404 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『REINFORCED CARBON-CARBON (RCC)』をアップしました。
3-3の囲み記事に当たる短い文章です(更新というほど長さじゃありませんね)。
あわせて、3-3の誤字と誤訳を修正しました。>zundaさん、いつもありがとうございます。
さて、次も3-3の囲み記事。左主翼と主翼前縁部の構造と素材の短い説明です。
. Date: 20040412 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary そういえば、今日は記念日今日はユーリ・ガガーリンが宇宙を飛んでから、43年目。
スペースシャトルコロンビアの最初の飛行から23年目の記念すべき日です。
. Date: 20040415 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 雑なんだか、風邪を引いて倒れているうちに、いろいろタイミングを逃しているような...
微熱がある中で、何となく『エレガントな宇宙』を読み直していたら、世界が不確定性のもやの中に霞んで消えたり、微細なひもがうねうねしたり、時空と一緒に自分もくちゃくちゃ折り畳まれたり、あげくの果てに膜がびろびろしたりして、大変寝付きが悪かったです。風邪の時はあまりおすすめしません。とても面白いんですけどね。
『LEFT WING AND WING LEADING EDGE 』をアップしました。
4/4日に続き、3-3の囲み記事に当たる短い文章です。
シャトルの主翼の構造に関するお話。特筆するような内容ではありませんね。
次は、打ち上げ時の断熱材の衝突に関する画像分析のお話です。
国民の科学技術離れ、ここ5年で進む…内閣府調査(Yomiuri Online)
「太陽は地球の周りを回っている」…小学生の4割 (Yomiuri Online)<%= fn '実は「自転や公転は中学まで習わない」らしい(この街の空にも星は瞬く)そうだったっけ、そうならこの結果はある意味健全なのか。あ、本当だ。ネタ元の「この町の空にも...」で書かれていますが、この調査をしている縣秀彦助教授もこのことはご承知で、どうやら小学校で教えることと、学校以外で教わる事実のギャップが理科離れを生んでいるのではないかという議論をされているようです。なんだか報道とニュアンスが違いますね。' %>
そう、こうなったら何度でも何度でも言うそ。
サイエンスは、人の役に立ったり、儲かったりする前に、まず世界を楽しむための方法なんだ。
実は、30すぎて星空を眺めてどきどきするには、それなりの努力がいる。
何も天文学の基礎知識が必要だなんて言うつもりはない。
雨が上がった空に光る星を見て「おぉ」と思った瞬間を逃さないための努力。
その小さな何かに、水を与えて、息を吹き込んで、無理矢理にでも膨らます力だ。
個人的な経験から言うと、30すぎてからこれをやるにはトレーニングがいる。
居合い抜きの刀みたいに、常に構えておいて、すかさず感嘆符を繰り出す!
「何だこれはっ!」「おぉ!」「すげー!」「きれー!」
これはねえ、心の中で叫んでも、かなり照れくさいよ。
はっきり言って、バカみたいだし。
でも、世界はきっと、今よりずっと楽しいものになるはず。
まず、帰り道に星を見つけたら、嘘でもいいから「おぉ、きれいだ」って、
小さく声に出して言ってご覧よ。いや、ほんとに人生変わるよ。ほんの少しだけどね。
PIA05755: Opportunity Captures "Lion King" Panorama(NASA)
火星、メリディアニ平原、イーグルクレーター。オポチュニティ着陸地のフルカラー360度パノラマ写真です。
これはぜひ、フル解像度のデータ(同ページ写真の右端にリンクがあります)をスクロールしながら見てください。素晴らしい映像です。ちなみに、「ライオンキング」はこの写真につけられた名前です。
この写真、まず驚くのは広大なメリディアニ平原とこのクレーターの小ささです。火星ローバーがこの小さいクレーターの中に落ちたことは、驚異的な偶然です。ご存知かもしれませんが、火星ローバーの着陸の最終段階はコントロールされていません。地表ぎりぎりでパラシュートを切り離しエアバックを開いて、火星の大地を何度もバウンドした後、停止したところでぱかっと開く、というやり方をとっています。これは、細かい姿勢制御をするための機構を省略することで、かなり多くの機材が省略でき、コストを下げペイロードを増やすことが出来るというメリットがあります。この写真にもローバーをおさめていたケース(今は、「チャレンジャー記念基地」という名前がついています)が写っていますが。ほとんどただのケースであることが分かるかと思います。
つまり、オポチュニティの場合、メリディアニ平原がターゲットにはなっていましたが、その何処に落ちるかはほぼ偶然にまかされていたわけです。そして、オポチュニティは、ぽーん、ぽーん、と転がったあげく、この極めて小さなクレーターの中で停止しました。写真をよく見るとクレーターの右側に、転々とエアバックがはねた跡が残っています。
この写真に写っている場所の中で、クレーターであるのこの場所だけが、砂がえぐれ、わずかながら地表下の岩石が露出しています。ご存知のように、「水の痕跡」の第一報は、ここからもたらされました。このパノラマ写真を見るとその発見のすごさが分かります。今は砂に覆われていますが、ここはかつて渚だったんです。
. Date: 20040420 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingFirst aerospike engine flight test successful (SpaceFlightNow)
『エアロスパイクエンジンのフライトテストに初めて成功』と見出しには書いてありますが、ちょっと嘘があります。正確には、初の固体燃料エアロスパイクエンジンのテストに成功したというニュースですね。液体燃料によるエアロスパイクエンジンはカルフォルニア州立大の学生とガーベイ・スペースクラフトが共同で開発、2003年10月に実験に成功しています。
California Team Conducts First Powered Liquid Propellant Aerospike Flight Test (SpaceRef.com)
NASAのドライデン飛行研究センター、アメリカ空軍フライトテストセンター、ブラックスカイコーポレーションが共同で開発を行ったとのこと。開発者は例のごとく「革命だ!」と叫んでいるようです。どうやら、大型ロケットに応用するよりも、とりあえず各種飛行テスト用のプラットフォームとして使うことを狙っているようです。まあ、作ったのがNASAで航空機開発を行っているドライデン飛行研究センターですから、当たり前と言えば当たり前なのかもしれません。
前回、Junkyard Reviewでやろうかな、なんて言ったまま放ったらかしだったので、少し解説しておきましょう。

NASA Dryden Flight Research Center
上の写真がエアロスパイクエンジンです、見ての通りロケットエンジンに特徴的なベル型のノズルがありません。代わりに、円錐形の金属のパーツがロケットの最後部についています。これがエアロスパイクエンジンの最大の特徴です。ロケットエンジンのノズルは、噴射されるガスの圧力と外気圧で最適の形状が決まります。細かい説明は省きますが、ベル型をしているノズルは、地表付近では細長い形の方が効率がよく、逆に高空では出口の方が広い、横に広い形の方が効率が良くなります。
つまり、従来型の固定されたベル型のノズルでは最大の効率が得られるのは飛行中のごく限られた時間だけなのです。このロスをなるべく少なくする方法の1つが、このエアロスパイクエンジンです(エンジンそのものは既存の物と大きく違わないので、エアロスパイクノズルという言い方もします)。
エアロスパイクエンジンは、従来のノズルの代わりを空気が果たします。上記の写真の中で、ガスの噴出口は円錐形のパーツの根元、円周上のスリットの中にあります。従来のロケットエンジンのようにガスの流れを導くノズルがありませんから、ここから吹き出したガスは傘のように水平に広がろうとします。しかし、ロケットが前進しているために、噴射ガスは前方からの空気の抵抗を受けて後方に向かって押し曲げられ、結果的にガスが理想的な形を保つのです。高度が上がって気圧が低くなればなるほど、前方からの空気の流れが薄くなり、ガスはより大きく広がるようになります。この、吹き出すガスが広がろうとする力と、上昇するに従って薄くなる空気による圧力のバランスが取れれば、どの高度でも最大の効率を発揮するエンジンが出来るはず、これがエアロスパイクエンジンの原理です。
NASAの次世代シャトル候補として開発が進んでいたX-33は、このエアロスパイクエンジンを搭載し、外部のブースターなどに頼らずに軌道までの飛行を行う完全再使用型を目指していましたが、初飛行を待たずに予算を切られてプロジェクトが中止されてしまいました。ちなみに、X-33に搭載されていたのはガスの噴出口を円周上ではなく一列に並べた、リニアエアロスパイクエンジンというやつです。参考)Junkyard Review
今のところ、ようやく飛行テストに成功したというレベルで、どれくらいの効率が出ているかもはっきりしていません。予想されている性能が出せるのなら、整備コストが下げられたり、重量が軽減できたり、いいこと尽くめなんですが、まだかなり先のことになりそうです。
. Date: 20040423 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clippingmaestro - Maestro Mars Data Updates
ぼーっとしているうちに、データのアップデートがあったようです。それから悪いニュースといいニュースが1つづつ。
4/16日付で、スピリットのデータが2本、オポチュニティのデータが2本アップされています。
さて、悪いニュースは「データのアップデートはこれで最後」というニュース。両ローバーが活動予定期間の90日を越えたためとのこと。えー、まだデータが70火星日ぐらいまでしかないじゃないかー。と思ったら、4/21日付でいいニュース。「新しいスポンサーがついたよ。復活!」ということらしい。わーい。「あんまり頻繁に更新できないけどごめんね」だそうな。いいです、ゆっくりで。
この貴重なデータが世界中に共有されていることに改めて感謝したいと思います。
関係者の皆様、ご苦労様です。本当にありがとうございます。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040511 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryえーと、人生がもの凄い音を立てて動き始めたりしたので、しばし呆然としておりました。
[clip] Daily ClippingPIA05389: Saturn in Color (NASA Planetary Photojournal)
土星に向かっているカッシーニが、最後の「土星の全体像」を送ってきました。ここから先は、土星が近すぎてカメラの画角からはみ出してしまいます。ぜひ、上にリンクしたページから高解像度の画像をどうぞ。息をのむような画像です。
カッシーニはこれから、さらに土星に近づきます。これから、もっと美しい画像が送られてくるでしょう。
How Mars got its rust: Model explains why the red planet is so red. (Nature)
「なんで火星はあんなに赤いのか?」という疑問に答える学説のお話。
火星が赤いのは、地表に大量に存在する酸化鉄のせいです。要するに錆びているわけですね。ただ、地球と比べるとその量が極端に多い、これはなぜか? 今の太陽系形成理論では、地球と火星はほぼ同じ時期に同じ材料から形成されたとされており、本来の組成はほぼ同じはず。ここまで表面の性質が違うためにはなんらかの理由が必要なんです。
さて、この記事は「地球では、惑星形成直後に酸化鉄が液体金属鉄となって中心部に沈んだのだ」とする仮説が出されたとのこと。火星は小さかったために充分な熱量が保てずに、地表に酸化鉄が残ったということのようです。
NASA Genesis Spacecraft On Final Lap Toward Home (ScienceDaily)
太陽探査機ジェネシスが帰ってくるというニュース。
太陽-地球のラグランジュポイントで太陽風の観測とサンプルの採集を行っていたジェネシスが帰途についています。予定通りなら、2004年9月8日に地球に帰還、ヘリコプターを使って空中収容します。
ジェネシスは2001年8月8日に打ち上げられ、30ヶ月に渡って太陽と地球の重力が均衡する点(ラグランジュ点)にとどまって、太陽の観測を行ってきました。この探査機は太陽風のサンプルを採集して持ち帰ることを主目的としており、今回観測を終えて帰途についたというわけです。
太陽風は、太陽を取り巻く外周部分から吹いています。この部分は太陽系が出来てから50億年間組成が変化しておらず、太陽そのものと、太陽系の全惑星を形成した物質と同じものと考えられます。つまり、このジェネシスが持ち帰るサンプルは太陽系の起源を探る上で非常に重要な資料なんです。無事に回収されるといいなあ。
打ち上げのときに、Junkyard Reviewでちょっとだけ言及してます。ラグランジェポイントの説明をしてますね。
. Date: 20040512 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingComputer chip noise may betray code (New Scientist)
CPUが発するノイズから、暗号化されたキーを破るために有用な情報を取り出すことができるというお話。
ノイズの周波数の違いから、CPUが異なる暗号キーを処理していることを判別できただけでなく、その文字列の長さが特定できたらしい。もちろんこれだけでは暗号を破ることは出来ないけれど、文字列の長さが分かるだけでも大きなヒントになる。ほかにも、CPUが使用している電力を計測することでも分かるとか。
上の記事に「素晴らしい研究だ」なんていうコメントを寄せているクーン博士は、2002年に壁などを照らすモニターの反射光から、そこに映っているものを再現することに成功しているらしい。
むかし、モニターから出ている電磁波を拾うことで、となりの部屋から画面に映し出されているものが再現できるというまことしやかな話を思い出す。どう考えても、かなり無理がある都市伝説だと思うけど、こういう話を聞くとあながち嘘じゃないかもという気がするねえ。
追記:
あ、都市伝説じゃないや。ちゃんと出来るみたい。このクーン博士がまさしくその研究をやってますね。
TAMPER Laboratoryからリンクされている同氏の論文を参照。PDFなので直リンクはしません。
Markus G. Kuhn: "Compromising emanations: eavesdropping risks of computer displays"
論文読まなくても、中の図版を見るだけでやってることはだいたい分かります。結構再現性が高いなあ。
さらに追記:
「まことしやかな話」の方をたどると、「テンペスト」のお話が出てきますね。米国家安全保障局(NSA)が発表した書類の中に、そういう技術が存在することを示唆するものがあったというお話です。そういえば、そんな話があったねえ。
清水建設でも研究しているみたいですね(Nikkei Net)
あー、常識?
あとは、こんな話も。
LEDランプの点滅で転送データをハッキング? (Hotwired Japan)
お、ここにもクーンさんが出てくる(上のhotwiredの記事にも登場)。
. Date: 20040513 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingHubble sees 'planet' around star (BBC)
ハッブルが太陽系外惑星の撮影に成功というニュース。ま、まじですか!
発見された惑星は、太陽系から100光年ほど離れたところにある白色矮星を巡る、木星の5?10倍の星。これが本当に惑星かどうかはまだ追試の必要があるとのこと。これまで系外惑星は120ぐらい発見されていますが、どれも中心星の軌道のぶれや、明るさの変化、ガスの分布などで間接的にその存在が確認されているだけです。ほんとだとすれば歴史的快挙ですね。
普通ならば、中心星が明るすぎて、暗い惑星を捉えることは出来ません。そこで、星の寿命が最終段階に達し、暗くなった白色矮星に注目することで、今回の発見につながったとのこと。
. Date: 20040517 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping宇宙の最前線に一歩 (東京新聞)
ハワイ、マウナケア山頂のすばる望遠鏡が一般公開を予定。うぉー行きたい!行きたい!行きたい!
とてもいいことだとは思うけれど、でも現場の人には迷惑かな。本当は、こういうパブリシティーのための時間や労力がちゃんと実績として評価されるような仕組み(メンタリティかな)が必要なんだと思うけど、なかなかそうはいかないみたいだし(一般向け科学書を書こうとすると「なにを遊んでいるのか」といわれるそうな)。うーん。
Private spaceship almost in space (BBC)
バートルータン氏のSpace Ship Oneがテストの採取段階に入り、高度212,000フィート(64km) に達したというお話。ちなみにX-prizeは民間資金、高度100km、2週間以内にもう一回。もうすぐです。
ずいぶん久しぶりです。石田五郎『天文台日記』中公文庫BIBLO (amazon)の紹介。とても美しい本です。おすすめ。
. Date: 20040519 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingAmateur rocket fired into space (BBC)
アマチュアが製作したロケットが高度100kmに到達しました。つまり、アマチュアによる初の宇宙ロケットです。
製作したのはCivilian Space eXploration Team (CSTX) 、30人の民間人からなるチームです。95年から何度も打ち上げを繰り返しながら徐々に高度をあげ、今回とうとう高度100kmを越えたとのこと。
これは、めでたい!昨日のエントリにも書きましたが、おそらく今年中に最初の民間宇宙飛行が行われるはずです。まず、間違いなく、今年は宇宙開発史上記念すべき年になるでしょう。
. Date: 20040520 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping電通、米社と国際宇宙ステーションへの著名人飛行プロジェクトを推進 (電通リリース)
電通が、スペースアドベンチャーズを通じて「日本のセレブ」を国際宇宙ステーションに送り込む計画を立てている、というお話。さすがは世界最大の広告代理店ですな(普通は広告代理店はある特定の分野に特化していて、こんな複合型の代理店は他の国にはないそうな)。
お忘れかもしれませんが、「日本人初の民間人による宇宙飛行」は秋山さんがやっているのでこれが2人目です。ちなみに日本初の「宇宙飛行士」は毛利さん。日本では、JAXAの選抜を受け正式トレーニングを受けた人が「宇宙飛行士」として認定されます(参考:JAXA)。NASAではミッションスペシャリストとして搭乗した人が「宇宙飛行士」です。秋山さんは当時のNASDAの認定を受けていないので、日本では正式な宇宙飛行士とは認められていません。 (微妙、追記参照)
ちなみに、宇宙探検家協会の入会資格は高度100km到達。当然秋山さんも会員です。
追記
JAXAのサイト内に「日本人初の宇宙飛行士」の文言を発見 (参考: JAXA Kids)。JAXAサイトに一言も記述が無いあたりが、なんとなく、大人の事情を感じますねえ。
Might Russia join ESA?: Talks pave way for new space partnership. (Nature)
ロシアがESA(欧州宇宙機関)入りか?というニュース。実現すれば、ESAもNASAに頼らずに独自に宇宙へ人を送る手段が得られるということです(ロシアが持っている宇宙ステーションの人員枠にESAが人を送れる)。
小惑星探査機:「はやぶさ」スイングバイ成功 (MSN-Mainichi INTERACTIVE)
めでたい!最後のスイングバイを終え、小惑星イトカワとの邂逅軌道に乗りました。予定通り飛行を継続中。到着は2005年の夏です。
JAXA の「はやぶさ(MUSES-C)」プロジェクトページ
それにしてもはやぶさ公式サイトはひどいことになってるなあ (いちおう報告済み)。
. Date: 20040521 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [excel] 天体の方位と高度を求めるVBスクリプト※本プロジェクトは、PHPによる簡易プラネタリウムOpen Planisphereに引き継がれています。
HDの奥底に眠っていた『Excelで星図』プロジェクトをお蔵だし。
とりあえず、セル内で行っていた計算をVBに移し、場当たり的な処理を汎用化しました。星図本体への組み込みはまだですが、スクリプトとサンプルファイルを上げておきます。
スクリプト
http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starPosition040521.txt
サンプルファイル
http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starPosition_sample.xls
いちおう動いているらしいという確認はしましたが、本当にまともな数字が出ているのかどうかはよく分かりません。また、VBのユーザー定義関数をまともに触ったのは今回が初めてなので、もしかしたらすごく変なことをやっているかもしれません。悪しからず。
参考までに、現状のExcel 星図(以前のエントリからアップデートされていません)
http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starchart_test03.xls
さて、次は「任意の時間の惑星の方位と高度を求めるVBスクリプト」だけど...いつになることやら。
先日、高度64km に達した民間宇宙機SpaceShipOneから撮影された画像 (Scaled Composit)
もうすぐそこじゃないか
. Date: 20040524 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『3.4 Image and Transport Analyses 』および『THE ORBITER "RAN INTO" THE FOAM 』をアップしました。
またもや、ひと月ぶりの更新ですね。この調子じゃいつまでたっても終わらないなあ。
今回は、打ち上げ時の断熱材の衝突に関する画像分析のお話。同時にアップしたのは同チャプターの囲み記事です。
次は、軌道上でシャトルから脱落したと思われる物体についての話。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040601 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping絶滅危惧種の細胞・遺伝子を保存、タイムカプセルが完成 (asahi.com)
レッドデータブックに記載された200種以上の鳥類、ほ乳類、魚類などの細胞や遺伝子を冷凍保存する施設が完成、一般公開された、というお話。
でも、もし仮に技術が進んでこれらの遺伝子から絶滅種が再生できたとして、本当に彼らを自然に帰すことが出来るんだろうか?僕は少し悲観的だ。たとえば、絶滅危機種がごく普通に繁殖できる環境全体を再生することは限りなく不可能に近いんじゃないだろうか。なにしろ、今の環境を丸ごと保存しても意味がない。今、その種が危機に瀕しているということは、もうすでにその種が生きていくのが難しい環境になっているということだ。たとえば今から50年前、100年前の環境を丸ごと再生するなんてことが出来るようになるだろうか?やっぱりちょっと、無理がある。
あるいは、首尾よく再生に成功し、彼らが繁殖できるだけの力を持ち得たとしても、その頃には彼らはすでに「外来種」になってしまっているはずだ。かつてその種が抜けた穴にはすでに他の種がそのニッチを埋めているはず。そこに再生された種を投げ込んだりすれば、再び生態系のバランスが崩れて複数の種が危機にさらされることになる。
結局、再生された彼らを待っているのは、動物園なのかもしれない。それでも、絶滅してしまうよりはいいのかな?うーん。
雑たとえば、太陽系に最も近い恒星から、光が地球に届くまでにかかる時間とほぼ同じ。
. Date: 20040604 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip ]Daily ClippingPuckish robots pull together: Air hockey helps joint techniques for work in space. (BBC)
宇宙で建設作業を行うロボットの開発にエアホッケー台が使われているというお話。無重力環境でロボットのテストをするにはとてもコストがかかる。実際に軌道上に上げるか、自由落下状態の飛行機を使ってほんの数十秒しか得られない。そこで、摩擦の少ないエアホッケーの台を使って無重力状態のシミュレーションをやろう、というアイディア。もちろんに時限的なモデルでしかないけれど、基礎研究には充分だし、何より安い。おぉ、頭いいなぁ。
Historic Space Launch Attempt Scheduled for June 21(Scaled Composites)
世界初の民間有人宇宙飛行は6/21、というニュース。順調にテストを重ねてきたスケールドコンポジット社のスペースシップワンが6/21に高度100kmに挑戦するとのこと。2週間以内に再飛行すればX-Prizeに一番乗りだけど、いきなりはないかな。
. Date: 20040616 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Music on the net -reprise友人とチャットで話しながら、つらつらと考える。
僕はこの件については、少し戸惑っている。個人的に、語気荒く「CCCD反対!還流防止法反対!」と叫ぶことに抵抗感がある。何かまとまったことがいえるとは思わないけれど、この戸惑いを表明しておくのは、たぶん無駄にはならないだろう。
CCCDはどうかと思うし、還流防止で輸入CDがターゲットになる(本当にそうなのか?)のも解せない。でも「搾取をむさぼるレコード会社ゆるすまじ」みたいな議論はもっと賛同できない。レコード会社は何もやっていないか?僕はそうは思わない。アーティストを発掘し、売れるかどうか分からない彼らにそれなりに宣伝費をかけて(もちろん新人にそんなに巨額な宣伝費がつくわけじゃないけれど、決して安くはないはず)、人々の目に触れさせ、CDをプレスして...。これだけでも、なかなか大変な仕事だと思う。ミリオンセラーを出せるようなアーティストが、そういう形で利益を新人アーティストに分配しているからこそ彼らがメジャーになっていく可能性もある。
楽曲がすべてネットワーク上で提供され、誰もが自由に自分の作った作品を流通させられる。一見理想的な世界に見えるけれど、本当だろうか?ユーザーから直接アーティストにお金が落ちるような仕組みがあればいい?僕はそうは思わない。想像してご覧よ、アーティストにとってはずいぶん殺伐とした世界じゃないか?たとえば、1曲100円としようか、1万回のダウンロードで100万円。これは大もうけだろうか?このお金で何人が何ヶ月暮らせる?レコーディングや配信のための費用がここから出せる?売れているアーチストならあり得ない数字じゃない。じゃあ、売れてないアーティストは?彼らが売れるためにかけなきゃいけないお金は誰が出す?
だれかが、彼らに「先行投資」をして、育てる必要がある。今の方法がいい方法なのかは分からないけれど、少なくとも今はレコード会社がその役割を果たしているはずだ。聞いたこともない音楽に触れて「あ、いいな」と思う、そういう体験の多くをレコード会社が担っている(彼らはそのためにずいぶん博打をやっている)。日本は世界でもまれに見るぐらい多くの楽曲をCDで手に入れることができる国なんだ。いや、正直悪くない仕事をしていると思うけどなあ。
でも、誰もCDの価格の中にそういう目利き料やアーティストの養育費が入っているとは思っていない。こんなことを言っている僕だってCD買うときに「ああ、この2千幾らかのお金の中に、次世代のアーチストを育てるためのお金が含まれているんだ。うんうん」なんて思わない。頭では分かっていても、結局の所「CDってやっぱり高いよ」とか思っている。このギャップはなかなか埋めがたい。
問題は、状況が変わりつつあるということだ。まず、CDが売れていない。それから合法/非合法問わず高品位の楽曲データがネット上からダウンロードできるようになりつつある。これは、レコード会社の既得権が脅かされるというだけの問題じゃない。レコード会社が持っている「アーティストの利益を再分配する」という仕組みが崩壊の危機に瀕しているということだ。これは、本当に由々しき事態だよ。
まあ、そうはいっても、この状況に対応する方法として、CCCDはスマートじゃないと思う。なにより後ろ向きだしね。他に何か上手い仕組みがあればいいんだけど、今はまだこれという方法はなさそうだ。あ、勘違いしないで欲しい、僕が言っているのはコピーコントロールの方法じゃなくて、楽曲のダウンロード販売で音楽業界全体が成り立ちうる方法のことだ。解決策は価格設定だろうか、あるいはもっと違う利益分配方法があるんだろうか。この楽曲ダウンロードの隆盛が止められないなら、何か他の方法を考える必要がある。今すぐに。
僕はCCCDには反対だ。還流防止が輸入CD規制につながるとすれば賛成するわけにはいかない。やっぱりCDは高いと思うし、もっと気軽にネットから楽曲が落とせるようになればいいと思う。でも、僕が不安なのは、自分が半ば無自覚にアーティストに向かって「パンがないのならば、ケーキを食べればいい」と言っていないかということ。僕がこのことについてどうしても強い口調になれないのは、こういう理由だ。
さて、言いっぱなしじゃなんなので、最後に思いつきを書いておくと、「ネットに常時接続していてネットラジオが聞ける携帯プレーヤーに購入ボタンがついている」というのが僕の考える理想型。
参考) Junkyard Review "Music on the net"
. Date: 20040617 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [Clip] Daily ClippingAPOD: 2004 June 10 - Venus at the Edge
先日の金星の太陽面通過の超クローズアップ画像。金星の大気が輝いているのが見える。なんと言うか、SF魂を震わせる絵だなあ。
フランス在住の友人に紹介されて、見たくてみたくてしょうがなかった映画。7月17日公開。わーい。
. Date: 20040618 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]チャールズ・ダーウィン『種の起原』岩波文庫(上 下 /amazon)最近、進化論系の本を読みあさっていて、とりあえず始祖は何を言っているのか知りたくて読み始める。訳が典型的な学者訳でごにょごにょしているのは置いておいて、なかなか面白い。書きっぷりからすると論文というよりエッセイに近い感じ。
少し長くなるけれど、とりあえず思いつくままにメモ。
ダーウィンの主張ダーウィンが言っていることを大雑把に箇条書きするとこんな感じ
・生物にはわずかながら個体差がある。
・その個体差は親から子へと受け継がれる。
・生まれた子供が全て生き残るわけではない。
・個体差には生き残るのに有利なものと、不利なものがある(はずだ)。
・平均すれば、有利な身体的特徴を持った個体が生き残る可能性が高い(はずだ)。
・だとすれば、環境に有利な身体的特徴が世代をへて蓄積する(のではないか)。
注意すべきなのは、「自然淘汰」も「適者生存」も「生存競争」も個体に対する概念だということ。淘汰や競争という言葉は「種」に対して使ってはいけない。同様に「適者生存」と「弱肉強食」はまるで違う概念。進化論に関する大半の勘違いは、ここに起因する。そもそも、『種の起原』はその名の通り、種の多様性はどうやって生まれたかを説明する本。種どうしの関係性を議論の中に持ち込んだらトートロジーになってしまう。個体と環境の関係だけで種の多様性が説明できるというのが、ダーウィン進化論のすごい所。
ダーウィンは進化が実際に起きているという実証をしていない結局の所、ダーウィンは家畜の品種改良の例を挙げて、これが自然界でも起きているはずと言っているだけ。だから"Natural Selection"という用語になる。ダーウィンは、個体差があること、生物が環境に対して見事に適応していることなどについては例証しているけれど、「環境に優位な身体的特徴が蓄積される」という証拠は挙げていない。彼は同書の中で、進化は非常にゆっくりとおこるため観察はできないと主張している。ここは、創造論者にさんざんたたかれている所だけれど、実際の所どうなんや!という方はジョナサン・ワイナー『フィンチの嘴』早川文庫(amazon)をどうぞ。進化はすでに観測された事実です。
「進化」を言い出したのはダーウィンが最初ではないダーウィンが『種の起原』を発表する以前から、長い時間をかけて生物が変化してきたとする考え方はあった。全然見た目の違う動物の間に相似があったり、明らかに退化したと思われる器官の痕跡があったり、古い地層から化石が次々と見つかったり。生物の多様性が一発で作られたと考えるより、単純な生物から複雑な生物へという変化があったと考える方が自然じゃないだろうか?こういう考え方は、決してメジャーではなかったものの、考え方としては当時の自然科学者の中に広く浸透していた。そもそもダーウィンのじいさん、エラスムス・ダーウィン(詩人、医者、哲学者、博物学者)も進化論者。自作の詩の中でも「生命は海に生まれ、次第に発達してきた」と書いている。孫のチャールズが彼の主張を知らないはずがない。
Organic life beneath the shoreless waves
Was born and nurs'd in ocean's pearly caves;
First forms minute, unseen by spheric glass,
Move on the mud, or pierce the watery mass;
These, as successive generations bloom,
New powers acquire and larger limbs assume;
Whence countless groups of vegetation spring,
And breathing realms of fin and feet and wing.
Erasmus Darwin. The Temple of Nature. 1802.
ダーウィン以前の進化論者で有名なのは、ラマルク先生(フルネームは Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck、長いっちゅーねん)。彼は生物は最も複雑なものを頂点として、最も下等な生物まである階梯をなしていて、生物は下等なものから高等なものへと進化してきたと述べた。ただし、ラマルク先生によれば、単純なものが分岐しながら徐々に種が増えたのではなく、ただ高等なものは古く(つまり年月をへて高等なものに進化している)、単純なものは新しい種(まだ変化の途中)というだけのこと。少し考えれば分かるけれど、ラマルク先生はどうやって生物が変化してきたかを述べているだけで、どうやって種の多様性が生まれたかを説明していない。ダーウィンの『種の起原』というタイトルがいかにセンセーショナルだったのが分かるというもの。
進化の要因として、ラマルク先生が主張したのが有名な「用不用論」と「獲得形質の遺伝」。個体の器官はよく使うものが発達し、使わないものは縮小する。こうして後天的に獲得したものが受け継がれることで進化が起きる。「キリンは高い所の葉を食べようと首をのばしているうちによく使われる首が発達し、その形質が子孫に受け継がれる中でどんどん首が長くなった」という例はあまりに有名。
ダーウィンがすごかったのは、「進化(変化を伴う継承)には方向や目的はない」と喝破したこと。進化はランダムで個体の意思は関係ないし、生命には階梯なんてものはない。彼は、完全にランダムな変異に環境によってわずかな偏りが生じ、長い時間を経てその偏りが蓄積することで種の分化が起きると主張した。だから、ダーウィンはキリスト教文化から猛烈な反発を食らった。だって、生命の多様性は神様抜きで説明できるし、人間は万物の霊長なんかじゃないよ、って言っちゃったんだから。
ダーウィンは「進化(evolution)」という言葉を使っていないダーウィンが使っているのは「変化を伴う由来(descent with modification)」という言葉(っていうかdescentの訳語は「由来」じゃなくて「継承」のほうがしっくりこないか?※decentには相続の意味がある)。『種の起原』の中に「進化」という言葉は出てこない。これは当時、evolutionという言葉がホムンクルス説の「精子の中の小人が次々と世代交代していくこと」を表す言葉だったかららしい(スティーブン・J・グールド『ダーウィン以来』)。そもそも、「進歩」や「発達」というニュアンスを持つevolutionという言葉はダーウィン進化論とは全くそぐわない。むしろダーウィンは「進化は進歩じゃない、進化には方向なんかない」と主張したんだから。
ちなみに、進化論にevolutionという言葉を持ち込んだのは社会学者のハーバート・スペンサー。「適者生存(survival of the fittest)」も彼の造語。かれは社会も進化するという主張の中で、evolutionという言葉を使った。ただ、スペンサーの進化はダーウィン的な「方向のない進化」じゃなくて、どちらかといえばラマルクっぽい「社会はどんどん複雑なものになる」という考え方。
(h2gs)
. Date: 20040621 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 初の民間有人宇宙飛行リアルタイム更新スケールドコンポジット社の「SpaceShipOne」が今日、高度100kmに到達する予定です。成功すれば、民間資金による初の有人宇宙飛行になります。
10:46
たった今、15分遅れて母機のWhiteKnightにぶら下げられてSpaceShipOneがモハービ砂漠の飛行場から離陸しました。WhiteKnightは、これから1時間近くかけて、高度を15000mまで上げ、そこでSpaceShipOneを切り離します。
11:36
33,000フィートに到達。全システムが正常に動作しているとのこと。
11:55
切り離された、かな?
11:58
無事切り離しは終わり、SpaceShipOneは順調に上昇中とのこと
0:00
どうやら最大高度に達し、下降を開始したようです。きゃー!
0:05
SpaceShipOneは順調に滑空しているとのこと。チェイス機が機首部分に若干熱の影響が見られる以外は、外見は問題ないとの報告をしています。
0:10
到達高度62マイルと発表がありました。目標達成です。わー、ばんざーい!おめでとうございます!
0:15
そろそろ着陸してくるはずです。
0:15
SpaceShipOneは無事モハーベ砂漠の空港にタッチダウンしました。
まさしく、歴史的な一瞬です。
ここから始まる歴史が、きっとあるはずです。
10年後、50年後に、ここから歴史が始まったんだと、いわれる日が来るでしょう。
今日は、いい夢が見られそうです。関係者の皆さんに、心からの賞讃と、感謝を。
本当におめでとうございます。そして、ありがとう。
付記)
CNNが着陸時の画像を掲載しています。
http://edition.cnn.com/2004/TECH/space/06/21/suborbital.test/index.html
[clip] Daily ClippingScaled Composites - Tier One / SpaceShipOne Home Page
予定通りなら、本日、アメリカ東部標準時午前6時半(日本時間午後10半)、歴史的なフライトが行われます。
脳の電位で、コンピューターを制御するという話。何をいまさら。この手の商品はもうずいぶん前から市販されてます。しかも、頭にバンドを巻くだけなんていうシステムがごろごろしてるんですが、今回の話は何が新しいんだろう?
5年も前に書いたエントリだけれど、リンク先は全部生きてました。「Brain-Computer Interface」で検索かければ山ほど事例が出てきます。バッタもんも多そうですけど。
. Date: 20040628 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryこんなことやってる場合じゃないんだけどね
「バーニャ」の謎イタリアの名物料理「バーニャ・カウダ」は、オリーブオイルとニンニクとアンチョビの暖かいソース。イタリア語の「バーニャ」には「入浴・お風呂」の意味がある(バーニャ・カウダで暖かいお風呂の意)。
ロシア名物のサウナ(あの白樺の枝でばんばん叩くやつ)も「バーニャ」という。
南フランスには「パン・バーニャ」というサンドイッチがある。意味は「湿ったパン」。
ウズベキスタンやキルギスでも公衆浴場を「バーニャ」というらしい。
ブルガリアのソフィアには「バーニャ・バシ・モスク」がある。これは、オスマン帝国時代のモスクで敷地内に温泉が湧き出ており、トルコ語で風呂を意味する「バーニャ」が名前に入っているとのこと。
さて、「バーニャ」はどこから来たのか?
ここに上がっている断片的な情報から類推すると、やっぱりオスマン帝国辺りに端を発すると考えるのが順当かもしれない。とすれば、言葉そのものの起源はトルコ語にあるのかな。じゃあ、ヨーロッパでのお風呂文化の起源は?なんて考えるといろいろ面白いかもしれない。たぶんヨーロッパの風呂には、歴史とスタイルの違ういくつかの潮流があるんだろう。沐浴なんてのは古代からやっていただろうし、古代ギリシャに浴場があったのも確か、ヨーロッパには湯治の風習もあるし、サウナ(これは確かフィンランド起源、形式はバーニャに近い)なんてのもある。
「バーニャ」という言葉(シニフィアンというと喜ぶ人がいるかな)と「風呂」や「湿った」という意味(シニフィエですな)が、歴史を追って、距離感を変えながらヨーロッパの南部であちこちに伝わり、変化していっているはず。国家の興亡や文化の伝播、歴史的なイベントとシンクロしていないはずがないから、もう少し突っ込んで調べれば、面白い文化史になるかもしれないなあ(っていうか誰かきっとやってそうだ)。ネットにも結構いろいろ情報があるんだけど、ちょっと断片的でまとまらない感じ。
えーと、気が向いたらまた調べます。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040707 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review 更新 . Date: 20040708 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clippingどうやらジョーク記事のようですね。わはは。だまされたよ。
. Date: 20040714 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingBlue Moon (Science@NASA)
「青い月」のお話。ちょっと面白かったので、要約。
「Blue Moon」というのは、英語の言い回しで、その月2回目の満月のこと。直近では、7月31日(月の満ち欠けの周期は28日だから、月初めに満月があれば同じ月にもう一度満月が来る)。もちろん、ほんとに月が青くなるわけじゃない。でも、かつて本当に月が青くなったことがあった。それは、1883年の有名なクラカトワ火山の噴火の時。約一ヶ月に渡って、月が青くなったり、緑になったりしたらしい。これは、火山灰の粒子のサイズがちょうど1ミクロンという小さいサイズで、赤色の光の波長0.7ミクロンよりもほんのわずかに大きかったから。つまり、火山灰が月からの光のうち赤の成分を反射してしまい、それより小さい波長の光(つまり緑から青にかけて)を透過したわけです。この現象、珍しいけれど全く起きないというわけではなく、火山の噴火や山火事などのときにみられることがあるそうな。
青い月か、見てみたいなあ。
Voyager 1: Prepare for Action(Science@NASA)
こちらも、Science@NASAの記事。ボイジャー1号は、今太陽系の縁、太陽から放出された物質が星間物質とぶつかっているあたりにいる。去年の10月?11月にかけて起きた太陽嵐を覚えているでしょうか?地球近傍でも衛星がいくつか壊れたりしましたが、あのときに太陽から放出された、大量のプラズマが今、ボイジャー1号に届いているそうです。
ボイジャー1号は最も遠い人工物です。本当に、遠くまで行きましたねえ。
参考:此処から一番遠い場所
久しぶりに、数値を2004年1月を基点にアップデートしました。Safariで数値がおかしかったのも直しました。ついでに、地球が基点になっていた距離を太陽基点に修正しました。地球基点だと季節で若干数値がずれてしまいます(平均ではさほど違わないんですけどね)。
さて、この記事の中で気になったのは、ボイジャー1号と太陽の距離。記事中では145億kmになっていますが、NASAのボイジャーのサイトにある資料(PDF)では、2004年7月の時点では太陽-ボイジャー1号は138億kmのはずなんですが…どっちが正しいんだろう?
. Date: 20040715 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping人類進化のカギは「おばあちゃん効果」米研究 (CNNj)
後期旧石器時代に、孫のいる老人世代が急増、同時期に芸術や埋葬文化が発達しているそうな。うむ、知識は山のようにあるが、からだの動かないやつが暇になると、いろいろくだらないことを考える、ということかな。
Hawking cracks black hole paradox (New Scientist)
「ブラックホールに吸い込まれた物質の情報は永久に失われてしまうのか?」という、かの有名な賭けの結果は、ホーキングの負けだそうな。7/21にホーキング自身が学会で発表するとのこと。
有名な賭けの文章は以下を参照("Another bet"のリンクが今回該当分)
http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/bets.html
これでホーキングは二敗目。前回は、「裸の特異点は存在するか?」というやつ。裸の特異点の存在が理論的に証明されてホーキングの負け。キップソーンにメッセージ入りのTシャツをプレゼントしている。刺繍の文句は「自然は裸の特異点を嫌う」。往生際が悪いな、わはは。
え、何のことか分からない?。
おー、これの説明は大変だ。僕もちゃんと理解してるわけじゃないし、うーん。
よし、やってみよう(暇だしな)。しばしお待ちを。
Junkyard Review 更新えーと、書いてみました。すごく長い割に、結局ありきたりの説明ですねえ。まあ、勉強になったからいいや。
ホーキング博士「自説は誤り」ブラックホール巡る理論 (asahi.com)
自説は誤り、はちょっと大げさだねえ。彼はこれまで情報消失問題に関して理論の展開はほとんどしてなかった。ただ、「たぶん消えるんじゃないかなあ」と言ってただけ。今回ちゃんと理論的に検証してみたら、やっぱ消えないわ、いうことになったという感じ。
. Date: 20040721 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingBlack holes turned 'inside out' (BBC)
ホーキング博士の件の発表のニュース。
Professor Hawking's new black holes never completely destroy everything that falls in. Instead, they continue to emit radiation for extended periods, and eventually open up to reveal the information within them.
"The black hole only appears to form but later opens up and releases information about what fell in, so we can be sure of the past and we can predict the future."
「 ブラックホールは最終的に開いて、落ちた物質の情報を開放する」
タイトルの "inside out(裏返る)"ってなんだ?これでは何も分からん。うーん。
Stephen Hawking (Cambridge)
The information paradox for black holes
The Euclidean path integral over all topologically trivial metrics can be done by time slicing and so is unitary when analytically continued to the Lorentzian. On the other hand, the path integral over all topologically non-trivial metrics is asymptotically independent of the initial state. Thus the total path integral is unitary and information is not lost in the formation and evaporation of black holes. The way the information gets out seems to be that a true event horizon never forms, just an apparent horizon.
こちらは、今回の発表が行われたInternational Conference on General Relativity and Gravitationのサイトに掲載されているホーキング博士の発表内容の概要。最後のところに「事象の地平線は本当には形成されず、見かけ上の地平線が形成されるだけである」と書いてありますね。その手前に書いてあることは私にはさっぱり分かりません。
Hawking: Black Holes Mangle Matter, Energy(ABCNEWS)
Famed astrophysicist Stephen Hawking said Wednesday that black holes, the mysterious massive vortexes formed from collapsed stars, do not destroy everything they consume but instead eventually fire out matter and energy "in a mangled form."
(中略)
Hawking's answer is that the black holes hold their contents for eons but themselves eventually deteriorate and die. As the black hole disintegrates, they send their transformed contents back out into the infinite universal horizons from whence they came.
Previously, Hawking, 62, had held out the possibility that disappearing matter travels through the black hole to a new parallel universe the very stuff of most visionary science fiction.
"There is no baby universe branching off, as I once thought. The information remains firmly in our universe," Hawking said in a copy of his speech distributed just before he appeared at the conference.
"I'm sorry to disappoint science fiction fans, but if information is preserved, there is no possibility of using black holes to travel to other universes," he said. "If you jump into a black hole, your mass energy will be returned to our universe, but in a mangled form, which contains the information about what you were like, but in an unrecognizable state."
ABCニュースの記事。
「ブラックホールは全てを飲み込んでしまうのではなく、最終的には物質やエネルギーをmangled(バラバラの/引き延ばされた)形で開放する。ブラックホールが蒸発するに従って、飲み込まれた物質の情報は情報は我々の宇宙へ戻ってくる。ただし、その情報はmangled(バラバラになって/引き延ばされて)いるため、認識することはできない。今回の結果は、SFによくあるブラックホールが別の宇宙へつながっているという考えを否定するものだ。SFファンのみなさん、がっかりさせてごめんね。」
やっぱり、どういう理屈で情報が戻ってくるのかは分かりませんねえ。カンファレンスの後に配られたというホーキング博士のスピーチ原稿が読みたいなあ。
参考)ホーキング、また賭けに負ける(Junkyard Review)
. Date: 20040726 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『3.5 On-Orbit Debris Separation - The "Flight Day 2" Object』をアップしました。
えーと、2月ぶりの更新です、あああ。いちおう続けてます。
今回は、コロンビアの飛行2日目に軌道上で観察された「コロンビアから離脱していく物体に関する分析のお話です。
この間、コロンビア事故調査報告書の印刷版(amazon)を手に入れたんですが、先の長さに思わず呆然としてしまいました。全部で240ページ中、翻訳済みが60ページ弱、やっと1/4てとこですね。飛行再開までにはなんとかしたいと思ってたんだけど、うーん。少しペース上げるかな、時間あるし。
失業中だからです。
. Date: 20040730 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingMan who helped unlock DNA dies
分子生物学者フランシス・クリック死去。モーリス・ウィルキンス<%= fn 'ワトソン→ウィルキンスですね' %>のX線回折写真を参考にジェームズ・ワトソンと共同でDNAの二重螺旋構造を解析。ご冥福をお祈りします。
現代版「ノアの箱舟」、絶滅危機のDNA保存へ 英機関 (asahi.com)
これについては、以前も書いたので、あまり言うべきことは残っていないけれど、絶滅危機種のDNA保存は「種の保存」という意味ではほとんど役に立たないと思うなあ。進化史研究のためのDNAアーカイブとしてならそれなりに意味はあると思うけど。
今のところ、日本語で読める書店で手に入る唯一の著作。彼は、70年代以降DNAの研究を退き脳化学の研究に従事していた。これはその頃の著作。中身とDNAの話は全く関係がない。中身は当然というべきか「魂なんてものはない」という内容。脳科学の本としては、かなり面白い。約10年前の本なので最新のというわけにはいかないけれど、この分野のもの凄くいいスナップショットになっていると思う。
それにしても、タイトルはちょっとひどすぎる。著者がクリックじゃなきゃ手にも取ってないぞ。
"The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul"『驚異の仮説-魂の科学的探求』
うーん、原題も似たり寄ったりだねえ。「DNA」が入ってないだけまだましか。
. Date: 20040731 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『ON-ORBIT COLLISION AVOIDANCE』をアップしました。
シャトルの運用時の軌道上での衝突防止に関する、3-5の囲み記事です。
さて、次はいよいよ軌道離脱と大気圏突入に関する内容です。な、長いな。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040804 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping水星探査機メッセンジャーが2004年3日午前2時15分(アメリカ東部標準時)ケープカナベラルから無事打ち上げられました。水星は30年前にマリナ?10号が近傍をフライバイしながら探査を行って以来、探査は行われていません。水星軌道に探査機が投入されるのは始めてのことです。
Junkyard Review更新上に関連して、なぜ水星探査機メッセンジャーは水星に行くのに7年もかけるのかというお話。自分で計算してみて驚きました。水星の公転軌道に探査機を直接投入するのは不可能に近いんじゃないかな。
. Date: 20040810 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingHubble Instrument Fails (Universe Today)
ハッブル故障。ぎゃー、タイミングが悪すぎるぞ。
世界で初めてソーラーセイル用の薄膜帆展開に成功(内之浦) (JAXA)
ずいぶん前に惑星協会のやつが失敗したからなあ。実際に軌道投入して帆走テストするのはいつになるんだろう。楽しみ。
Article: Chances of aliens finding Earth disappearing?(New Scientist)
衛星放送とインターネットが優勢になっちゃったから、「地球は電波を発信しない星」になりつつあるというお話。もし、宇宙人が「電波で交信できる相手」を探してたら見つけてくれなくなるかもしれない。
Venerable deep-sea sub to be replaced (Nature)
深海探査船アルビン号退役。ごくろうさまです。
. Date: 20040811 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary ペルセウス座流星群極大さて、8/11・8/12の夜はペルセウス座流星群です。折角ですから外に出ましょう。お祭りですから、参加しない手はありません。今年は月も細く条件はかなり良さそうです。多ければ1時間に50個ぐらいは見えるとのこと。突発出現も予測されており、もっとたくさん出る可能性もあります。
ピークの予測が各機関から出されていますが、日本流星研究会では12日20時、国際流星機構では12日22時となっています。また、流星群の出現予測で有名なライチネン氏は、突発的な出現の可能性が高い時刻として12日6時頃をあげています。なんにしても1 1日、12日の2夜は夜更かしですね。
ペルセウス座流星群という名前は、流星が流れる中心点である放射点がペルセウス座にあるためです(これは流星群の標準的な命名法です)、ペルセウス座は北北東の空、カシオペヤの「W」のすぐ隣です。まあ、流星は全天に見えますから、放射点はあんまり関係ないんですけどね。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040902 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingBBC NEWS | Science/Nature | Alien probe 'best way to find ET'
ET探しをするなら、電波源を探すより宇宙人の探査機を探す方が早いかも、というお話。根拠は、送信する情報の1ビットあたりのエネルギーコストは探査機を直接送る方が少ないから。つまり、電波はいったん発信されると、放射状ないし円錐状に広がり、しかも目標の星系を一瞬で通り過ぎてしまうため、ほとんどのエネルギーが無駄になってしまう。しかし物体はほとんど損失することなく相手の元に届く。このため、情報のエネルギー効率は直接送る方がいいということらしい。たとえるなら、宅急便でDVDを箱にぎっちり詰めて送る方が、ネット越しにちまちま送るよりもコストは安くなるということか。
確かにその通り。でも、SETIの場合は、確実に相手に情報を届けることじゃなくて、いるかどうかも分からない相手にたとえ一部でもメッセージが届く可能性を高めることが目的のはず。それから、当然ながら、物理的な媒体はかなり速度の制限を受ける。情報の量と質じゃなくて、交信の可能性に対するコストはやっぱり電波(あるいは光を含む電磁波)のほうが少ないんじゃないかなあ。
この発表をしたChristopher Rose博士は、結構前からこの主張をしているみたい。
. Date: 20040903 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily Clipping昨日に引き続きSETIの話題
Mysterious signals from 1000 light years away (New Scientist)
2003年2月にアレシボ天文台で行われたSETI@homeの追試結果から非常に興味深いシグナルが見つかった、というお話。うおー!まじですか。シグナルは全く別のユーザ?が解析したデータから2回検出されており、今回の追試でも同様の結果が出た。データの改ざんや人工衛星などからの電波を捉えたものとは考えにくい。
候補となっているのは、太陽系から1000光年離れた魚座と牡牛座の間にあるSHGb02+14a。この星から出ていた電波は、一秒間に37ヘルツの割合で周波数が変化していたとのこと。もし、ある惑星上に電波源があって、そこから発信された電波が自転の影響を考慮していないとすると、このような周波数の変化が見られる可能性がある(おそらくドップラー効果による周波数の変化)。
もし、地球を他の惑星から見ると、地表の電波源は1秒間に1.5ヘルツの割合で周波数が変化して見えるはず。もしSHGb02+14a空の電波が惑星の表面から発信されているものだとすれば、地球の40倍以上の自転速度を持っている計算になる。
もちろん未知のの自然現象の可能性もあるけれど、それはそれで大変な発見であることには違いない。わくわくわくわく。
(KIMさん、ありがとうございます →昨日コメント欄参照)
. Date: 20040909 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping 2004.09.09 - 2Genesis capsule crashes in Utah (Spaceflight Now)
太陽風のサンプルを収集、地球へと持ち帰る予定だった探査機ジェネシスの突入カプセルがパラシュートの展開に失敗。地表へと激突しました。
本来ならば、カプセルの大気圏突入後2分で姿勢制御用の小さなパラシュートが展開、その4分後には減速、回収用のパラシュートを展開し、待機したヘリコプターによって空中で回収される予定でした(これは、なるべく接地時の衝撃を少なくし、サンプルを保護するための措置です)。しかし、望遠カメラがカプセルを捉えたときにはパラシュートが開いておらず、カプセルはそのまま減速できずに約時速160kmで地表に叩き付けられました。
カプセルの中のサンプルが無事かどうかはまだ分かりませんが、中継ではカプセルが大破している様子が映し出されていました。ただし、カプセルはパラシュートが開かなかった場合でも、衝撃に耐えうるように設計されているとのことです。今後、カプセルは回収されクリーンルームで調査・分析が行われ、再突入時のデータとあわせて事故原因の究明が行われる予定です。
何とも残念な結果になってしまいました。サンプルが無事だといいんですが…
中継画像の連続キャプチャを作成しました。
静止画像ですが、くるくる回転しながら落下してくる様子が分かると思います。
(2004.09.09 3:00)
Genesisの公式サイトに衝突時のムービーがアップされました。
NASA - Genesis and the Search for Origins (NASA)
(2004.09.09 4:30)
Genesis and the Search for Origins
今日、Genesisが帰ってきます。NASAでは、空中回収の様子を中継するそうな。
Genesisについては下記参照のこと。
を、中継が始まってる。0:35
回収用のヘリコプターは3機体制ですね。
ヘリコプターは待機位置に到達。旋回しながらカプセルの到達を待機しています。0:45
カプセルの大気圏突入まであと5分弱。0:50
カプセルを確認? ミッションコントロールで拍手が起きました。0:55
超望遠カメラがカプセルを捉えました。0:57
ありゃ、パラシュートが開かなかったみたい。がーん。1:00
地面にカプセルがめり込んでます。大丈夫かな?
ディレクターから簡単な説明がありました。
「望遠カメラでカプセルを捉えたが、パラシュートが開かなかったので、時速100マイルで地面に衝突した。回収し、一週間程度で原因を明らかにする」。
上空からのクローズアップでは、カプセルの一部が破損しているように見えます。
再びディレクターから説明。
「カプセルは大破。衛星からの切り離し時に問題が起きた可能性もある。サンプルが無事かどうかは不明。突入時のデータなどを検討して、原因が分かり次第発表する」
NASAからの中継が終了しました。1:35
. Date: 20040911 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingTelescope snaps distant 'planet' (BBC)
太陽系外惑星が始めて望遠鏡で直接捉えられたというニュース。まじ?うぉおおおお。
これまで、惑星の重力による母星のふらつきや、惑星が前面を通過することによる母星が減光、母星を取り巻くガスの密度の変化などから間接的に存在が確認されていた太陽系外惑星が始めて望遠鏡で直接観測されたとのこと。これが本当に惑星なのかどうかはまだはっきりと分かっていませんが、スペクトル分析から水の分子が検出されており、この天体が非常に小さく軽いことから惑星である可能性が高いと考えられます。
これが本当に惑星だとすれば、単に存在することが分かったというだけでなく、スペクトル分析などによって更に細かい組成などを観測することができることを意味します。これは系外惑星探査が新しい時代に入ったといえる革命的な出来事です。
観測に成功したのは、南米チリのパラナル山にある欧州南天天文台(ESO:European Southern Observatory)のVery Large Telescope (VLT)です。これは、4台の口径8.2mの望遠鏡を組み合わせて分解能を上げる光学干渉計とよばれるシステムで、理論的には口径130メートルの望遠鏡に匹敵する能力を持っているといわれています。
Is This Speck of Light an Exoplanet? (ESO Press Release 23/04)
(追記)
コメント欄にてzundaさんから、今回の観測はVLTの1つにつけられたNACOという観測装置によるものとのご指摘がありました。これは近赤外線領域の観測装置に補償光学システムを組み合わせたものですね。補償光学(Adaptive Optics)というのは、リアルタイムで大気による像の揺らぎを補正する技術のこと。ハワイのすばる望遠鏡でも使用され、素晴らしい成果を上げています。
Subaru Adaptive Optics - すばる補償光学
. Date: 20040917 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book] In Their Own Words: The Space Race (The Apollo, Gemini, and Mercury Missions) (amazon)Bookカテゴリになってますが、これはオーディオブック。上記リンクはAmazonのCDバージョンへのリンクですが、Audible.comでダウンロード購入できます。
50年代から70年代、米ソが宇宙開発競争を繰り返していた頃のお話。当時の通信記録やインタビュー、演説などをナレーションでつないでいくという構成。CD7枚組で7時間半(MP3クオリティで100M強)。マーキュリー、ジェミニ、アポロのそれぞれのミッションについてこと細かく解説が入ります。"Eagle has landed !" も "one small step for man, one giant leap for mankind." も "Huston, we have a problem." も全部当時の音源で収録されてます。ロケット好きにはたまらない内容です。
英語のリスニングの勉強にと思って聞きはじめましたが、ナレーションのところはともかく、交信記録はノイズが乗ってて、私の英語力では殆ど何言ってるか分かりません。どちらかというと、英語力よりも「3, 2, 1, Retro fire !」なんていう台詞にどれぐらいワクワクできるかが 楽しめるかどうかを決めると思います。もちろん、「英会話」の勉強にはなりませんね。
今回、始めてAudible.comを使いましたが、これはハマりそうです。驚いたのは、「作者が読む」シリーズが結構多いこと、レイ・ブラッドベリ本人が読む『火星年代記』なんてのもありました(次はこれに挑戦しようかな)。ほとんど全てタイトルでサンプルが聞けるので、立ち読み(聴き?)だけでもかなり楽しめます(中には10分を越えるサンプルもあります)サンプルだけなら登録は必要ありません。
始めてiPodが欲しい、と(ちょっとだけ)思いました。結局家の外ではiTunesからCDに焼いて聞いてます。ま、これでいいかな。
How Genesis Crash Impacts Mars Sample Return (Space.com)
どうやら、ジェネシスに搭載されていたサンプルは一部が無事に回収されたようですが、今回の失敗はあちこちで論議を呼んでいるようです。この記事は、予定されている火星からのサンプルリターンのときに失敗したらどうするんだ?というお話。
さすがに太陽風のサンプルに生命が混入している可能性は非常に低いけれど、火星からのサンプルには含まれている可能性がある。今回のような事故が起きるとサンプルが汚染される危険性だけじゃなく、火星由来の物質によって地球の環境が汚染される可能性があるんじゃないか?どーすんだよ。ということらしい。
『アンドロメダ...』を思い出しますねえ。あれはいい映画だったなあ。
. Date: 20040921 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping太陽が地球のまわりを回っている、との天動説が正しいと答えた児童も4割に達した。(中略) 月が満ち欠けする理由について「地球から見て太陽と月の位置関係が変わるから」と正しく答えた児童は47%にとどまった。
危うくないって。むしろ、四割が正しく答えているという方が、驚きなんだけどなあ。
だって、「月が満ち欠けする理由」は中学生、「地動説」は高校生にならないと習わないんだから。
上の、「小学生の天文知識」に関する話。
. Date: 20040925 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary東京ローカルで申し訳ない
雑PARCO ART.COM - LOGOS GALLERY - 印刷解体
渋谷バルコLOGOSギャラリーに『印刷解体』を見に行ってきた。
渋谷パルコ地下の書店LIBRO/LOGOSの一角にあるLOGOSギャラリーで開催している活版活字と写植の文字盤の展示。ギャラリーには活字棚がそのまま置かれ、好きな活字を拾って購入することができる。9/27まで。
書店の一角に活字棚が置かれただけの、ギャラリー/展示というにはずいぶんささやかなスペース。それでも、なんとなく活字を拾ったり棚に戻したりしながら、ずいぶん長居をしていたような気がする。失われゆくものへの郷愁というより、ものとしての存在感に圧倒される。なんというか、奥の方からじわじわと効いてくる感じ。
おみやげに、少し大きめの活字を2つ、文選箱といっしょに買って帰った。
朱肉につけて紙に押したら、とてもきれいな文字が出た。
もう1つ、渋谷パルコギャラリーで知る人ぞ知るカルトエアライン「ブラニフ・エアライン」のデザイン展をやっていたので、こちらにも足を伸ばす(っていうか隣のビルだけどな)。こちらは10/11まで(名古屋、広島に巡回予定)。
「ブラニフ・エアライン」というのは、70年代、当代一流のデザイナーがよってたかって、飛行機からゴミ袋までありとあらゆるものをデザインしまくったという奇跡のような航空会社。82年に倒産し、今はもう存在しない。
目玉からいろんなものが、ぼろぼろ落ちました。「デザインコンセプトがあーたら」「クリエイティビティがこーたら」言っているデザイナーやディレクターは、日参して目の玉洗ってこい!といいたい。
The History of Braniff International Airways
. Date: 20040928 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingScaled Composites - Tier One / SpaceShipOne Home Page
明日、9/29にSpaceShipOneの二階目の飛行が行われます。今回は、2週間後にも飛行を予定しておりX-Prizeの条件を満たす「本番」の飛行になります。
今回も報道機関がストリーミングを予定しているようです。各機関とも日本では29日23:00頃からの放送ですね。
Ansari X Prize: Live Coverage (Space.com)
日本ではライブドアがストリーミングをやるみたいですね。
BBC NEWS | Science/Nature | Virgin boss in space tourism bid
またやってくれました。ヴァージンの道楽社長リチャード・ブランソンが、SpaceShipOneのモハーベ・エアロスペース・ベンチャーズと提携、"Virgin Galactic" 設立を目指して宇宙機開発を行うそうな。
New $50 Million Prize for Private Orbiting Spacecraft
こちらは、民間宇宙機で軌道周回飛行をやったら50万ドルというお話。X-Prizeの次はこちら?
. Date: 20040930 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingSpaceShipOne News | Mission Status Center (Spaceflight Now )
どうやら、SpaceShipOneが二度目の飛行に成功したようです。わーい。
途中で、操縦ミスがあり予定より若干早くエンジンをカットしたようですが、高度100kmは達成しているとのこと。X-Prizeには、二週間以内にもう一度同じ機体で飛行という条件がついていますから、次の飛行を成功させると、賞金1000万ドルが確定します。次の飛行の予定は10/4ですね。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20041005 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingSpeceShipOneが二度目の飛行に成功し、正式にANSARI X PRIZEを受賞しました。おめでとうございます。
個人的には、賞の受賞はもちろんですが、同機体で2週間のタイムラグで宇宙飛行を行うという偉業をなし得たことを賞賛したいと思います。たとえば、スペースシャトルは一度飛行を終えると、次に飛べるようになるまでに2ヶ月以上かかります。もちろん、規模が全然違いますし、SpaceShipOneは弾道飛行するだけですけどね。これは本当にすごいことだと思います。
Mercury Astronaut Gordon Cooper Dies at 77 (Reuters)
マーキュリー7の一人、ゴードン・クーパー氏が亡くなりました。享年77歳。ご冥福をお祈りします。
彼は、アメリカ初の有人宇宙飛行計画であるマーキュリー計画で最年少のパイロットとして計画最後のフライトで地球を22周、続くジェミニ計画でも飛行を行い199時間55分の飛行時間を記録しました。
" Who was the best pilot I ever saw? Well, uh, you're lookin' at 'im. " -The Right Stuff
Nobel honours sub-atomic world (BBC)
今年のノーベル物理学賞はアメリカの物理学者、David Gross、David Politzer、Frank Wilczekの3名に決定。
素粒子の「強い相互作用」(これを研究する学問が量子色力学:QCD)は、近距離ないし高エネルギー下では相互作用が弱くなるという「漸近的自由(asymptotic freedom)」という性質を発見したことによる受賞。
あが、これじゃ何のことだか分からないな。
世界には、距離を隔てて伝わる力には4つしかありません。「重力」「電磁気力」「弱い力(弱い相互作用)」「強い力(強い相互作用)」です。「重力」は知ってますよね。質量を持つものは一定の力で引き合っています。もちろん重力は全ての粒子に対して働きますが、弱すぎて天体のスケールじゃないと効いてきません。「電磁気力」もおなじみですね。プラスとマイナスが引き合うやつです。静電気や磁石の力がそうですね。電子と原子核を結びつけたり、原子と原子をむすびつけて分子を作っているのもこの力です。重力に比べればずっと力は強いんですが、いかんせん届く距離が小さいんです。
「弱い力」「強い力」というのは原子を構成する素粒子に働いている力です。「弱い力」というのは中性子の自然崩壊(ベータ崩壊)を引き起こす力(詳しい話は割愛します、分からないし)。で、「強い力」というのは素粒子どうしを結びつけて原子核として安定させている力です。両者ともに届くのは極めて短い距離だけです。
さて、この「強い力」には「距離が離れると強くなる」という奇妙な性質があるんです。えーと、ゴムを想像して下さい。ある一定の距離では、ゴムの張力がほとんど掛からず、かなり自由に動けますよね。そしてゴムを引っ張れば引っ張るほど張力は増していきます。まあ、こんな感じの力だと思えばあながち間違っていないと思います。素粒子どうしは、こんな力でびよーんと結びついているわけです。で、この「強い力」の「距離が離れると強くなる」という性質のことを「漸近的自由(asymptotic freedom)」というんです。
今回、ノーベル賞を受賞した3人は、さらに、この「強い力」が素粒子の「色」と呼ばれる性質(素粒子の3種類の性質を赤、緑、青の三原色になぞらえているだけです。本当にそういう色をしているわけじゃありません)から生まれることを明らかにし、量子色力学(QCD : quantum chromodynamics)の基礎を作りました。
そういうわけで、彼らはノーベル賞を取ったわけです。
論文が発表されたのは1973年ですから、30年越しの受賞ですね。おめでとうございます。
. Date: 20041022 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryあんなところやこんなところ、こんなところへ行ってきました。ご報告はそのうち。
[clip]Daily Clipping国が育てる「サイエンスライター」文科省部会が提言 (asahi.com )
えー、国のお金でジャーナリストを育てるんですか?国がお金を出して育てたジャーナリストに、国がお金を出して作ったメディアで記事を書かせて、ちゃんと批評的な記事がかけるのかな。
そんなことするより、科学者が一般向けの科学書を書いたり公演をすることを正当に評価するシステムを作る方がいいと思うなあ。日本のポピュラーサイエンスの悲劇は、いまだ日本にカール・セーガンがいないことだと思うぞ。寺田 寅彦(@青空文庫)はさすがにちょっと古いしねえ。
BBC NEWS | Health | UN begins delicate cloning debate (BBC)
国連で、クローニングに関する異なる2つの見解に着いて議論が行われるという話。
この2つの見解というのは「あらゆるクローニングを完全禁止」と「治療目的なら許可」のこと。なにしろこれは答えのでない議論だからなあ。私?わたしは「全面禁止」はすぐに形骸化するに決まっているので、さっさと作ってしまったときのことを考えるべきだと思います。人権問題あたりを特にね。
参考)遺伝子が運ぶもの (Junkyard Review)
Article: Drama of shark feast scoops photo prize? (New Scientist)
英国国立自然史博物館主催のネイチャー写真アワードが決定。あああ、あそこでやってたやつだ。見て来ればよかった。がっくり。
Relativity tested on a shoestring budget (New Scientist)
NASAが60億かけて打ち上げたGravity Probe Bを差し置いて、既存の衛星のデータを解析することでアインシュタインが予見した時空の歪みを検証した、というお話。まあ、gp-bが無駄になるわけじゃないし、ね。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20041110 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary転職しました、ようやく。
Junkyard Review 更新ちなみに、文章中に出てくる「ある海洋学者」というのは父。そういえば、前回はこんな話をしてたっけ。
A DART Near Miss: Infighting at Orbital - and Deceiving NASA (SpaceRef)
木曜日に打ち上げを予定していたDART(Demonstration for Autonomous Rendezvous Technology)は、打ち上げに使用されるDARTとペガサスロケットの不具合により延期になりそう。
といっても少し話がややこしい。DARTとペガサスロケットを作ったオービタルサイエンスは、今年の始めペガサスの第2段を改良したんだけど、古いペガサスに合わせて作られたDARTはその負荷に耐えられないかもしれないらしい。この事実が発覚したのが先週の金曜日(ってことは、打ち上げの一週間前!)。前からNASAはオービタルサイエンスに「大丈夫?」って聞いていたらしいんだけど、オービタルサイエンスはこれまで「大丈夫よーん」と言っていたそうな。
NASAのサイトにプレスリリースが上がっている(この短さがたまらなく寒いな)。
NASA - NASA's DART Launch Postponed
Half of European bird species in danger(New Scientist)
BirdLife International の調査によると、ヨーロッパにいる524の鳥の約半数が絶滅の危機にある、というお話。集約農業のため低木の伐採と化学肥料の大量使用が行われたことが原因じゃないかと考えられているそうな。
Northrop Grumman, Boeing Plan Space Exploration Team (SpaceRef)
ノースロップグラマンとボーイングが次世代有人宇宙機の開発で共同チームを組むかもというお話。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20041207 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryご無沙汰しております。さほど忙しいというわけじゃないんですけどね...
[clip] Daily ClippingNext-generation Russian spaceship unveiled (MSNBC)
ロシアのエネルギア・ロケットアンドスペース社が開発している新型宇宙機が発表されたとのこと。スペースシャトルによく似た再使用型宇宙往還機+軌道モジュールという構成らしい(リンク先に写真あり)。2010年の初飛行を目指しているが資金的に開発を完了するのは難しいかもしれないそうな。
Nature's Canvas (NASA via BBC)
「土星を背景にした惑星ミマス」
カッシーニが送ってきた、息を呑むほど美しい土星の写真。
The write stuff(Nature)
ネイチャーに論文を載せたいなら、文学の勉強をして、文章をもう少し上手く書けるようになるといいかもよ、という元Nature編集者のコラム。後半にいくにしたがってどんどん愚痴っぽくなっていく。「(ねじくれ曲がった文章を読んでいると)グローブをはめたままバナナを剥こうとしているボクサーになった気がするよ」
ちなみに、「私たちが受け取るものの中でも、最も明晰な文章で書かれている論文は、英語を第一国語としていない人々のもの」だそうです。
Language of Prairie Dogs Includes Words for Humans
もしかしたら、プレーリードックはかなり複雑な言葉を喋っているのかもしれない、というお話。「緑の服を着た背の低い人間」と「黄色い服を着た背の高い人間」では違う表現をしたそうな。少なくとも20以上の語彙を持っているらしい。
研究者達はせいぜい、「わぉ」「腹減った」「きゃー」ぐらいだと思っていた、って君たちプレーリードックを過小評価し過ぎ。
. Date: 20041208 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingShuttle repair techniques not required for return to flight (Spaceflignt Now)
5月に打ち上げられるシャトルは、耐熱タイルやRCCパネルの修理キットを積まずに飛ぶようです。開発と承認が間に合わないというのがその理由のようですね。まあ、修理キットについてはCAIBのレポートでも「搭載が望ましい」という表現だったと思います。
えーと、ちなみに事故報告書の翻訳はカタツムリのような速度で今も継続中です(というと、カタツムリに悪いかな)。
'Tis the Season to Find Exoplanets (Sky&Telescope)
2004.12.26?2005.1.3にかけて、世界中のアマチュア天文学者が太陽系外惑星探査に協力する、というお話。
この期間、海蛇座のHD37605とオリオン座のHD74156という星の前をそれぞれの星系に属する惑星が通過する可能性が高いとされており、これを受けてTransitsearch.orgと American Association of Variable Star Observers (AAVSO)が「みんなで太陽系外惑星を見つけよう!」というキャンペーンをしているそうです。
これまでも、太陽系外惑星の存在の追試は、アマチュア天文学者が成功させていますが、新たな発見はまだ行われたことがありません。発見者は、論文に共同研究者として名前が載るそうです。それに、まずまちがいなく天文学史に残るでしょうね。
The Martian Methane Surprise (Astrobiology Magazine)
4月に少し話題になった、火星の大気で検出されたメタンガスについての専門家へのインタビュー。気になる生命の存在については、可能性は高いが必ずしも生命現象によるものとは限らないとのこと。
つい先日、火星ローバーの最初の90日分のレビューも出されたようです。かつて液体の水は間違いなく存在したようです。問題は、いつごろ、どれくらいあったか、そして今はどうなのか、というところでしょうか。
Second space Christmas for ESA: Huygens to begin its final journey to Titan (ESA)
土星の軌道で次々とすばらしい成果を挙げているカッシーニ・ホイヘンス探査機が、日本時間の12月25日13:08にタイタンに向かってホイヘンスプローブを切り離すとのこと。記事は、去年の12月のMars Expressの火星軌道への投入がやはり25日(CET)だったことから「2度目のクリスマスプレゼントだ、わーい」という内容。ちなみに、ホイヘンスがタイタンに突入するのは来年の1月14日19:15(JST)。
こちらもものすごく楽しみですね。すでにカッシーニは、何度かタイタンをフライバイして、謎の現象を観測したりしています。なにしろ、太陽系で唯一大気を持つ衛星ですから、不思議なことの一つや二つあっても不思議はありません。ホイヘンスプローブを大気圏内に降ろすせば、大気の組成や雲に隠れた地表の様子がもっと詳しくわかるはずです。わくわく。
Plastic eye mimics octopus vision(Nature)
蛸の視覚を模倣するプラスティックレンズのお話。
ガラスのレンズは、より短い焦点距離を得る(より拡大する)ためにレンズの厚みを増す必要があるけれど、生体のレンズは、微妙に異なる材質が何万も重なっているせいで(人間で約22000層)、さほどレンズの厚みを増さなくても有効な焦点距離が得られます。水中にすむ生物はさらにこの能力が高く、蛸は人間の5倍もの能力を持っているんだそうな。上は、この蛸の超多層構造のレンズをまねたプラスチックレンズが開発されたというニュース。
レンズが薄くてすめば、小さく軽いだけでなく、やわらかいレンズが作れるということです。もし実用化されるなら、その工学的な可能性はかなり高いんじゃないでしょうか。
. Date: 20041210 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]DailyClippingHungry monkeys can dig it (Nature)
野生のサルが日常的に道具を使用しているのが確認された、というお話。
ブラジル北東部の森林地帯に生息するオマキザルの仲間は、石を使って、土に埋まった根を掘り出す、木の実などの硬い殻を割る、それらを食べやすいサイズに砕く、トカゲをばらばらにするといった複数の作業をこなし、さらに木の枝を使って昆虫が隠れていそうな場所を探ることもするらしい。これまで、石を使って種や貝の殻を割るサルは観察されていたが、「道具を使うこと」がここまで日常化している例は初めて。
記事中でリンクされているビデオは必見。確かにこんなにスムーズに道具を使うサルは初めて見た。
サイエンスの何がすばらしいって、僕たちが特別な存在じゃないということを教えてくれるところです。
Hot laptops may reduce male fertility (NewScientist)
ラップトップの熱のせいで、男性の生殖機能に異常が出る、というお話。ひざの上でラップトップPCを使っていると、生殖器が暖められて、生殖機能が低下するかもしれない、がーん。かとおもったら、これから確かめるのかよ!でも、この弁でいくとコタツは危険極まりない暖房器具ということに・・・。
日本語記事 (CNN.co.jp)
Shuttle Should Service Hubble: NAS Report (BBC)
予算をきられたり、なかなかシャトルが打ちあがらないなどの理由から、「ロボットを使って遠隔操作で直す」という案が浮上していたハッブル宇宙望遠鏡ですが、米国科学アカデミーは「シャトルで出かけていって有人で直したほうがいいよ」という報告書をまとめたとのこと。
うん、それが確実だと思うな。ちょっと残念だけど。
Mission to Neptune Under Study (UniverseToday)
2016年?2018年ごろ打ち上げて、2035年の到着を目指すという計画。海王星は主に岩石と氷からなる硬く冷えた惑星で、木星や土星が巨大なガス惑星なのとは対照的。太陽からの放出物の影響をあまり受けていないと考えられるため、原始太陽系の名残が残っているかもしれない。探査対象としては、かなり興味深い。
※海王星と冥王星を勘違いしていました。記述が間違っていないところだけを残し、残りは削除しました。お恥ずかしい。 > Digituneさんありがとう
. Date: 20041214 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingA chance to imagine the future (ESA)
クラーク、ブラッドベリの名前を冠したSF賞が2005年に開催されます。この「Clarke-Bradbury International Science Fiction competition」は2003年にも開催され、36の国から104の作品が集まったとのこと。今年はイラスト部門も新設です。
2005年のテーマは「宇宙エレベーター」。2500ワード(英語)の短編もしくはイラスト、あるいはその両方が公募対象。一人一作で、国籍や年齢の制限はありません。締め切りは2005年2月。評価基準は以下のとおり。
-technology: convincing use (テクノロジー:説得力のある使い方)
-imagination: innovative ideas and the ability to think ‘outside the box’ (想像力:革新的なアイディアと独創的な思考)
-structure: development of storyline, plot, characters(構造:ストーリー、プロット、キャラクター)
-skill: clarity of expression, style, degree of realism(テクニック:表現、スタイル、リアリティ)
-visualisation: convincing depiction of the space elevator (可視化:宇宙エレベーターの説得力のある描写)
大賞には600ドル、次点には300ドルの賞金が出ます。また、受賞作および優秀作は出版されるとのこと。
詳しくは、コンペティションの公式サイトを参照してください。
ITSF - Innovative Technologies From Science Fiction For Space Applications
2003年の内容もここに掲載されています(ダウンロードできるPDFには受賞作を含む31作品が収録されてます。わぁ)。
2500wordということは、日本語訳で約6500字ぐらいですね。腕に自信のある方は応募してみては?一気に世界デビューのチャンスかも。イラスト部門なら英語ができなくても大丈夫。応募ぐらいは辞書片手でもいけるでしょう(Web上でフォームから送信することになります)。受賞しちゃったら、まあ勉強するしかありませんね。
個人的に注目したいのは、このコンペティションの後ろ盾になっているのが、ヨーロッパの公的宇宙開発機関である「ESA(欧州宇宙機関)」だということですね。JAXAもこれくらい気の利いたことをやってくれないかなあ。
とおもったら、こんなキャンペーンをやってました。いいですねえ。
宇宙の音楽募集キャンペーン (JAXA)
Secret of Bird Flight Revealed (Hint: Think Fighter Jets) (LiveScience)
鳥は、ジェット戦闘機と同じように翼で渦を作り出すことで飛行をコントロールしている、というお話。これが鳥が空中で虫を捕まえ、安全に木に止まれる秘密だそうな。
そういえば、鳥は木に止まるときに羽ばたかずに羽をぐいっと曲げて、ふわっと降りるんだよね。そのうち飛行機があんなふうに着陸するようになるんだろうか?
次期システム用に開発中のJunkyard Reviewの記事検索。まだバグが多いのでそっと使ってくださいね。
. Date: 20041219 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] DailyClippingMystery of 'chirping' pyramid decoded (Nature)
マヤ文明のピラミッドは、巨大な共鳴器として設計されているんじゃないか?というお話。エルカスティリオピラミッドの階段の基礎部分のところで手を叩くと、マヤで神聖とされているケツァール鳥のさえずりのような音がすることは、前から知られていたけれど(知らない知らない)、建物自体が音響学的にかなり巧妙に設計されており、他にもいろいろ変わった反響音がするらしい。聞いてみたいなあ。
Slick trick could save marine ecosystems (NewScientist)
沈没したタンカーからオイルを抜くために、あらかじめ専用のバルブを付けとこう、という話。普通、沈没しタンカーからオイルを抜くためには、ダイバーが潜っていって船体にドリルで穴をあけてバルブを取り付ける必要があるけれど、最適な場所を見つけるのにはとても時間がかかる。あらかじめ、何ヵ所かにバルブを付けておけば、その時間がずっと短縮されるから、原油で海が汚染されるのを最小限に抑えることができるかもしれない。逆に言えば、なんで今までついてなかったんだ、と思うような簡単な方法。つけとけ、いいからつけとけ。
Space no place for cheap satellites (NewScientist)
去年の10月から11月にかけて起きた太陽嵐の記録を調べた結果、強烈な太陽嵐の際に放出される荷電粒子が地球の磁場をゆがめてしまうために、これまで安全と思われていたバンアレン帯の内側まで荷電粒子が届いてしまうことが分かった。もしかしたら十分に対策の取られていない最近流行の安価なミニ衛星は破壊されてしまうかもしれない。
Giant Mars rover will search for life (NewScientist)
水がの次は生き物を探しにいくぜ!ということで、次の火星ローバーは、重量が3倍、積み込む観測機器は2倍になるそうな。2009年12月打ち上げ予定。まあ、あくまで予定だけどね。
. Date: 20041223 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [translation] archiveにScience@NASAの翻訳記事を追加太陽系の外から吹いてくるヘリウム原子の風についてのお話。恒星間を吹き渡る風、というイメージが何とも美しい。
※例のごとく、ページ最下端のtoggle Englishで、原文併記に切り替わります。
コロンビア事故報告書の方をしばらくさぼっていたら、すっかりなまってしまったので、リハビリ代わりに翻訳。いや、ちょっと軽いものが訳したくなっただけなんですけどね。あっちは、今ちょうど第一部の佳境にさしかかっているところだけど、何番センサーがいつ落ちたとか、○○桁がこうなっているから、これが燃えるのが先とか、そんな話がひたすら続くんだもの。
. Date: 20041224 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingFirst cloned pet revives ethical debate (NewScientist)
件の、猫のクローンサービスが最初のお客に「商品」を渡したとのこと。この件については、以前にも書いたけれど、言いたいことはさほど変わっていない。
「もし仮に不幸になる人(生き物)がいないのならクローンには反対しない。でも、一番幸せになるべきなのは「クローン体」自身であって、その親や飼い主じゃない。とにかく、「クローン体」が不幸になる事態だけは絶対に避けるべきだ。だから、作っていいかどうかじゃなくて、作った後のことを早く考えたほうがいいんじゃないですか?」
参考)
Garbage Collection : 2004.03.25
遺伝子が運ぶもの (Junkyard Review)
Mystery of Mars rover's 'carwash' rolls on (NewScientist)
火星ローバー「オポチュニティ」の太陽電池が突然きれいになって性能が向上したとのこと。そりゃもちろん、緑色の小人が拭いていったに決まってるじゃないか。
...冗談はさておき、さすがに雨が降ったわけじゃなさそうだけれど、と思って本文を読んでみたら「きっと、クレーターの縁を登るために何度も傾いたせいだよ、後は風だね、風」って、つまらんなあ。
. Date: 20041226 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingCassini Mission Status Report December 24, 2004 (NASA)
カッシーニ探査機から、ホイヘンスプローブが無事切り離されました。わーい。
タイタン大気内への突入は年明けの1月14日です。
. Date: 20041227 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新ちょっと気が早いかもしれないけれど今年のまとめ。実はこういうことをするのは初めて。なかなか楽しい。
Cassini takes picture of departing Huygens probe (SpacefligntNow)
カッシーニから捉えられた、離脱していくホイヘンスの画像。おぉ!
Sperm whales suffer the bends (Nature)
マッコウクジラも減圧症に悩まされているかもしれない、というお話。多数のマッコウクジラの骨にその兆候があったとのこと。マッコウクジラは無呼吸潜水してるはずなのになんで減圧症に?と思ったが、繰り返し潜っていると人間でも閉息潜水で減圧症にかかるそうな。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20050106 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary明けましておめでとうございます。今年もそろそろ始めましょうか。
[clip]Daily Clipping地球外知的生命からのメッセージは、認識不可能か (Astroarts)
たとえ、地球外生物からの通信が受信できたとしても、それらはランダムなノイズや星の発する熱放射と見分けがつかないだろうという研究結果が発表された、とのこと。
がーん、夢のない話だなあ。でも、「じゃあ見分けがつく方法は何だろう」と考れば、新しいSETIの手法が開発できるかもしれない。
Shuttle tank arrives at Kennedy Space Center (SpacefligntNow)
コロンビア事故を受け改良を行っていたスペースシャトルの外部燃料タンクが完成、KSCに到着したそうです。"the safest and most reliable tank that's ever been produced" とのこと。
あー、あのカウントダウンクロックの前を通るんだねえ。プレス用にわざわざそうしたのかな。
Snowflakes made easy (Nature)
驚くほど簡単な数学的なアルゴリズムで、雪の結晶の形状を作り出すことができた、というお話。でも肝心のアルゴリズムは書いてない。上記ページからリンクされているビデオを見ると、確かに雪の結晶が生成される過程を捉えた映像にそっくりに見える。
参考)A local cellular model for snow crystal growth (ScienceDirect)
Terror shows only in the eyes (Nature)
「恐怖の表情」は、実は「目」に現れている、というお話。
人の表情を読み取る能力をつかさどる小脳扁桃と呼ばれる部位に損傷がある患者さん(どうやらこの分野ではかなりの有名人みたい)にさまざまな表情を映した写真を見せて反応を調べたところ「恐怖」だけ認識することができなかったそうな。これまでは、この症状の原因は異なる感情は異なる脳の回路で処理されるためだと考えられていたんだけど、ある研究者が写真の一部を隠す実験をしてみたら、彼女は「目」に現れる感情を読み取ることができなかった。幸福や悲しみ、怒りなどの表情は鼻と口の周辺の表情が重要な役割を果たしているけれど、「恐怖」はそれらの部位よりも目が重要な役割を果たしているために、彼女はその表情を読み取ることができないんじゃなかろうか、ということみたい。
一般の人の正答率はどれくらいだったんだろう?「驚き」の表情と「恐怖」の表情は見分けがつくんだろうか?単純に考えれば、声とかシチュエーションにかなり依存すると思うんだけどなあ。
Displaced dangers complicate tsunami rescue work (NewScientist)
スマトラ沖地震の津波災害によって思いもしなかった危険が持ち上がっている、という話。スリランカでは地雷が津波で押し流されてこれまで安全だとされてきた地域に入り込んでいるそうな。また、アンダマン諸島では巨大なワニが生息地を追われ、これまですみ分けられていた人間の居住地に入り込んでいるとのこと。ワニたちは死体を食べて人間の味を覚えてしまっており、今後人が襲われる危険があるという指摘もあるらしい。
Tsunami's salt water may leave islands uninhabitable (NewScientist)
もうひとつ津波の話題。津波によって海水をかぶってしまった地域は、地下水や土壌が塩分で汚染されているために今後長期に渡って人が住むことができなくなるかもしれない、というお話。
. Date: 20050111 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping月の向こうに「深宇宙」港を 宇宙機構が構想 (asahi.com)
うーん、その「深宇宙」港に資源をどうやって運ぶんだろう?港まで資源を運んで、そこで探査機を建造して送り出す...そんなに大きなメリットあるかなあ。確かに港から探査機を飛ばすのは楽だけど、港に物資を補給するためにかなりコストがかかってしまうような気がする。そんなことするより、直接火星に人を送り込む方が楽なんじゃないだろうか?
Earth Is Still Ringing From Quake (SpaceDaily)
多数の犠牲者を出したスマトラ沖地震ですが、2週間たった今もまだ「地球が全体が揺れている」とのこと。これは、余震のことではなく、あのときの揺れが、まるで鐘の余音のように、今も地球をごくわずかながら揺らし続けているという意味です。
How the Earthquake affected Earth (NASA)
もうひとつ地震の話題。あの地震で地球の地軸が2.5cmずれ、100億分の一ほど平らになり、一日の長さが2.68マイクロセカンド短くなったとのこと。
. Date: 20050112 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingNASA謹製、フリーウェアの気象シミュレーター。こ、これ、凄くないか?
参考)News Release(NASA)
はい、ダウンロードしてみました。チュートリアルにしたがって地球温暖化のシミュレーションを走らせてみると...えー、いつまでたっても終わりません。どうやら、日ごとのデータを200年分吐き出しているらしい。えーと、一日分を出力するのに約5秒かかってるから...100時間?ストーップ!やめやめ。チュートリアルにそんなでかいシミュレーションを使うなー。ためしに5年分でやってみよう...それでも2時間以上かかるのか。うーん。
. Date: 20050114 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary ホイヘンスプローブタッチダウン!ESA - Cassini-Huygens (ESA)
どうやら、ホイヘンスプローブは無事にタイタンの表面に到達したようです。わーい。
ホイヘンスは、タッチダウンの衝撃に耐え、未だに信号を送り続けているとのこと。もともと「運がよければタッチダウン後も観測が続けられるかも」と言っていたぐらいなので、これは予想以上の素晴らしい結果と言えます。
どうやら、観測データの受信も始まったようです。 まだですね。「未だにシグナルを受信している=プローブは生きている」ということのようです。順調なら、一時間以内にはカッシーニ経由のデータが受信されはずです。 - 0:00 JST
カッシーニと地球の間の通信が確立されたとのこと。間もなくデータの受信が始まります。どきどき。 - 0:35 JST
始まったかな? 管制室ではぼーっと雑談をしていた人々がしきりにスクリーンを気にしはじめました。 -1:15 JST
"We have !"の声とともに管制室に拍手が起こりました 1:20 JST
ホイヘンスは予想よりずっと長く、2時間以上もタイタンの地表からデータを送信してきました。それらのデータはいったん土星軌道上のカッシーニ探査機に蓄えられ、その後、地球に送信されてきました。一見、簡単そうですが、土星と地球の間は13億キロ離れています。タイムラグは約1時間。何かコマンドを送っても、レスポンスがあるまでに2時間以上かかるんです。
歴史的な快挙、これ以上ないほどの成功です。関係者の皆さん、本当におめでとうございます。
参考)
Cassini Mission Status Center (SpaceflightNow)
NASA - NASA TV Landing Page (NASA)
注)
カッシーニはNASAに所属する探査機ですが、ホイヘンスプローブはESA(欧州宇宙機関)の所属です。開発はもちろん管制やデータの取得もESAの主導で行われています。
NASA - Cassini-Huygens: Close Encounter with Saturn (NASA)
今日、ホイヘンスプローブが土星の衛星タイタンに突入します。予定時間は日本時間午後6時。地表への到達は同午後8時の予定です。ただし、土星はとても遠いので、地球にその知らせが届くのは約1時間後です。ESA TV/NASA TV、ではストリーミング放送が予定されています。詳しくは上記ページを参照してください。
わくわく、わくわく。
Deep Impact (NASA)
日本時間で昨日午前3時47分、水星探査機『ディープインパクト』が打ち上げられました。わーい。
彗星へのプローブ突入は今年の7/4の予定です。
→Junkyard Review掲載予定
そういえば、ずいぶん前に紹介していましたね。
Echoes of Big Bang found in galaxies (Nature)
宇宙の大規模構造を明らかにすべく、「夜空の地図」を作っていた二つの計画、The Two-Degree Field Galaxy Redshift Survey(2dFGRS)とSloan Digital Sky Survey (SDSS)の結果から、マイクロ波の背景放射と現在の銀河の配置に関連性があるかもしれないという結果が出たとのこと。
うぉ!これはすごい。すごい、よねえ?
たとえるなら、「ダイナマイトが爆発した時の音」と「残った破片」に対応関係があったということ。もう少し「音」を詳しく分析すれば今の宇宙の姿が分かるかもしれないし、「破片」をもっと詳しく調べれば、宇宙が生まれた瞬間のことがもっと詳しく分かるかもしれない。
この間紹介したEdGCMですが、結局4時間シミュレーションを回して分析ツールにかけたら、「データが足りない」と言われてしまった。がーん。な、なぜ?うーん、もう少し心の余裕があるときに弄ってみよう。
. Date: 20050116 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary ホイヘンスプローブ続報ESA - Cassini-Huygens (ESA)
昨日、タッチダウンとデータの送信を成功させたホイヘンスプローブですが、ESAから次々とデータが公表されています。細かい内容はまだ分析を待たねばなりませんが、上空からの画像には川のような地形や海岸線のような地形が写っており、地表からの画像には液体に浸食されたかのような丸い岩石が写っています。
うわー、うわー、うわー。
First images from Titan (ESA)
一番上はタイタンの地表の様子。氷なのか岩石なのか分かりませんが、角が落ちているのに注目です。浸食によるものかな。
2番目は降下中の画像、高度は16.2km。まるで「海に流れ込む川」のようです。本当にメタンの海があるんでしょうか?
3番目も降下中の画像。高度は8km。丘状の部分と海岸線を挟んで平坦な海とおぼしき部分が写っている、とのことですが。え、どこ?
ESA Portal - New images from Titan (ESA)
一番上は、降下中の画像をつなぎ合わせたもの。高度は約8km。白く雲状に見えるのは、メタンかエタンの「霧」らしい。
2番目も降下中の画像。荒れた丘状の地形に溝状のパターンが走っているのが見える。画面下の暗いエリアはまるで海みたいだけれど...
下の二枚は、「地表画像」のサイズ入り画像と、同画像をカラー化したもの。写っている岩石状の物体の下部には浸食のあとが見られ、液体の存在を示唆しています。
Sounds of an alien world (ESA)
これは、タイタンの大気中で録音された音声ファイル。ごーごーいってるだけですが、これが土星の衛星で録音されたものだと思うとドキドキしますね。
. Date: 20050120 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『3.6 De-Orbit/Re-Entry』をアップしました。
約半年ぶりの更新です。実は、事象の順序と相関関係が複雑すぎて、途中で放り出していたんですが、ようやく終わりました。
今回は、第1部のハイライト、再突入開始から空中分解までに機体に起きたことの分析です。主翼内部に無数に走るセンサーのケーブルの配置とその信号喪失のタイミングから、時間を追ってシャトルに起きたことが明らかにされていきます。
同ページの図版や以下のセクションの図版などを参照しながら一つ一つイベントを追っていくと、損傷箇所から高温の大気が進入し、各種センサーのケーブルを焼ききりながら、主翼の内部構造を破壊していく様子が「見えて」きます。
3.3 Wing Leading Edge Structural Subsystem
LEFT WING AND WING LEADING EDGE
続いて『THE KIRTLAND IMAGE』をアップしました。
カートランド空軍基地で撮影されたコロンビアの画像に関する3-6の囲み記事にあたる文章です。
次は、回収された破片の分析に関するお話です。
. Date: 20050124 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingSeeing, touching and smelling the extraordinarily Earth-like world of Titan (ESA)
タイタンでは、水の替わりにメタンの川が流れ、メタンの雨が降り、石の替わりに氷がごろごろと転がり、土の替わりに炭化水素が地表を覆い、火山は溶岩じゃなくて氷とアンモニアを噴出しているそうな。また、ホイヘンスの着陸地にはつい数日前に液体メタンの雨が降っていた、とのこと。ぎょー。
日本語記事)衛星タイタンは可燃世界=ホイヘンス着陸2日前に「降雨」 (時事通信 via Goo News)
Iron Meteorite on Mars (NASA)
オポチュニティが発見した火星表面の隕石の画像。地球以外の天体上で発見された初めての隕石です。何がすごいかというと、この石がわれわれがよく知っているものと同じであるということ。つまり、地球で発見されているものと違いが分かれば、地球と火星の違いが分かるかもしれないということです。
あんまり関係ないですが、この写真を見ると火星の赤茶けた色(酸化している)のはほんの表面だけなんだということがよくわかりますねえ。
White House Cuts Hubble Servicing Mission from 2006 Budget Request (SPACE.COM)
ハッブル宇宙望遠鏡を修理するための予算はやっぱりカットになるかもしれない、とのこと。ええぇぇぇえ!!ホントに!
ただし、まだ公式な発表は無く「ある筋からの情報によると」というやつです。それに、正式な予算決定は議会での承認を得なければならないので最終決定ではありません。
シャトルで出かけていって軌道修正用のブースターを取り付けて太平洋に落とすそうです。「直すのは大変だけど、落とすだけなら簡単」うん、まあ、そうだろうなあ。つい先日、「ロボットで直す」案が撤回されて「やっぱりシャトルで直す」案が浮上していたところだったんですが・・・。しょんぼり。
Astronomers Surprised by White House Plan to Scuttle Hubble (SPACE.COM)
天文学者はびっくりしているとのこと。そりゃそうでしょう。
日本語記事)ハッブル望遠鏡、米が廃棄へ…太平洋上落下の割安策で (YOMIURI ON-LINE)
Full Moon Names for 2005 (SPACE.COM)
2005年の満月と、その名前。欧米では、季節ごとの満月にいろいろな名前がついている。上記ページでは今年の満月と、それぞれの名前を紹介。ちなみに今月の満月は25日"The Full Wolf Moon"だそうな。うおぉーん!
. Date: 20050126 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingNASA To Use Outer Planets Data Analysis Funds for Other Purposes (SpaceRef)
NASAの2004年度の予算申請のうち、外惑星の分析に使われる予定で組まれた予算について、「ごめんよ、やっぱ無しね」という内容のメールが担当者に届いている、というお話。うう、出す方も受け取る方もつらいメールだなあ。
Cosmic birth theory gets support (BBC)
太陽系は希薄な星間ガスやチリがゆっくりと集積して生まれたとする従来の説に代わって、超新星爆発などの残りかすが充満した濃密な星間ガス(つまり星雲ですな)の中で生まれたとする説が脚光を浴びているけれど、この新しい説を支持する結果が隕石の分析で分かったよ、というお話。隕石中で見つかった塩素36(塩素の放射性同位体)の起源として最も妥当と思われるのが、超新星爆発ないしそれによって生じた星間ガスによるものだということらしい。
Pilfering crab has insect's nose (BBC)
かつてヤシガニは海での生活を捨て陸へと上がり、新しい環境に適応するために陸上で使える鼻を進化させた。その鼻の構造が、昆虫のものとそっくりだったよ、というお話。つまり、ヤシガニは昆虫の鼻を再発明したことになる。これは収斂進化と呼ばれ、同じ環境下にさらされ、同じ淘汰圧がかかった結果、まったく別の系統の生物であるにもかかわらず体の構造や習性が似てしまう現象のこと。
Search for life signal on Titan (BBC)
タイタンで検出されたメタンは、生物由来のものじゃないか?というお話。
タイタンの地下100km?300kmには液体の水が存在しており、そこには生命がいるかも知れない、と考える学者もいるそうな。
NASA Mars Picture of the Day: Opportunity Rover As Seen From Orbit (SpaceRef)
マーズグローバルサーベイヤーから撮影された、軌道上から見たオポチュニティの画像。うぉ、ローバーのつけた轍まで写ってる。
ちなみに、国定忠治は悪代官を切って追われる身になった渡世人。飢えで苦しむ人々に食べ物や金を分け与えたともいわれている。「赤城の山も今宵限り?」は、根城にしていた赤城山を幕府に追われて降りざるを得なくなったときの台詞。
. Date: 20050127 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingSMART-1's first images from the Moon (ESA)
2004年11月15日に月の軌道に乗り、徐々に高度を落としながら観測の準備をしていたSMART-1が、予定していた地表から300km?3000kmを回る楕円軌道に到達。最初の月の表面の画像を送信してきました。本格的な観測はこれからですが、月の軌道上から観測を行うのは、1998?1999年の年のルナプロスペクター以来です。ルナプロスペクターは月に大量の水(氷)が存在する可能性を示唆するデータを送ってきました。次は何が見つかるんでしょうか?報告が楽しみですねえ。
Antigravity has feet of clay (Nature)
ESAは2001から重力制御技術に関する研究評価を行ってきたけれど、「もし仮に重力制御が可能だったとしても、宇宙船を飛ばす方法としては役に立たないので研究するに値しない」とする報告書が提出されたとのこと。えー、そうなの?
報告書が公開されていたのでざっと読んでみたけれど、つまり「今研究されている方法は、宇宙船を飛ばすにはあまりに効率が悪く、お金をかけて研究するほどのものじゃないよ」ということみたい。
以下、簡単に要約部分を訳してみた(ちょっと意訳)。
「重力を遮断する」とか、「重力の方向を変える」と称する研究は、みんな口をそろえて「宇宙船の推進方法に革命が起きる!」なんて言っているよね。ちょっと調べてみたんだけど、もし百歩譲って今考えている方法で重力がコントロールできるとしても、どいつもこいつも推進方法にするにはあまりにパワーが小さくて「革命」なんてチャンチャラおかしい。それにねえ、みんな大雑把過ぎるよ。(未来の、じゃなくて)今の物理学から考えて一番近道に見えるやつだって、ぜんぜんお話ににならないんだもの。意味なーし!
Hypothecial Gravity Control and Possible Influence on Space Propulsion (M. Tajmar, O. Bertolami)
この報告書、すごく面白い。
. Date: 20050130 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記コロンビア事故最終報告書 非公式日本語版 ※新しい翻訳のアップはありません。
先日アップした3-6について、zundaさんから指摘していただいたタイプミス(お恥ずかしい)と訳の修正などを反映しました。
zundaさん、いつも本当にありがとうございます。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20050203 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingH-IIAロケット7号機の打上げについて (JAXA)
正式なリリースが出ました。2/24、17:06?18:34です。わくわく。
こちらは、ロケットの組み立て整備や、第2段ロケットの再々着火テストに向けてのデータ取得などを担当する株式会社ロケットシステムのカウントダウンサイト。JAXAのページでも公式ページとしてこちらが紹介されている。
どうやら、今回の打ち上げは、国土交通省から(株)ロケットシステムに製造および打ち上げを委託、さらに(株)ロケットシステムからJAXAに打ち上げを委託という契約になっているらしい。打ち上げ計画書はこの両者の名前で発行されていて、それぞれの責任と分担がきっちり書いてある。
うう、結局これが今年最初の更新になってしまった。
参考)
Landing:None. (2003.01.28)
事故の3日前に書いた文章。これを書いたときには、まさか軌道上のコロンビアがあんなことになるとは思ってもいなかった。
Columbia Lost 2003.02.03 (2003.02.03)
事故の2日後、ちょうど2年前の今日書いた文章。個人的には、この時の「宿題」はまだ終わっていない。
宇宙飛行士という仕事 (2003.02.06)
事故の5日後、ブッシュの演説に触発されて書いた文章。結局ここから一歩も進んでいない。
Columbia Lost 2003.11.01 (2003.11.01)
報告書の翻訳を始めて、しばらくしてから書いたもの。
Dear Rocketeer. (2004.02.03)
去年の今日。「宿題」に答えるつもりで書いたもの。
2年間かけて、ほんの少しだけ前に進んだような気もするけれど、まだよく分からない。
. Date: 20050207 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping直すか、破棄するかで喧々諤々の議論になっているハッブル宇宙望遠鏡ですが、こちらは、わざわざ直しに行くより、おんなじ設計で少しだけバージョンアップしたものをもう一機打ち上げる方が早くないか?という提案。なるほど。
Science Made Stupid(via SciScoop)
1986年ヒューゴー賞ノンフィクション部門受賞作『Science Made Stupid』の全文が公開。うわはははは。
Volvo and Virgin Galactic Team Up in Space (CommercialSpaceWatch)
VolvoのSUVを買って宇宙へ行こうキャンペーン。この手のキャンペーンはもう食傷気味なんですが、今回はあの「Virgin Galactic」が連れて行ってくれるそうです。スーパーボールで広告を打つそうな。っていうかCMに社長出てるし。
. Date: 20050215 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [prog]starchart-050214.phphttp://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/starchart-050214.php
以前、Excelで作っていた星図をPHPにポートしました。PNG形式の画像を出力するPHPスクリプトです。まだ作り始めたばかりでまともに検証していませんが、それなりに見られる夜空になってきたのでちょっとご紹介。
現状では天頂を中心とする半球表示のみで、等級は4.0未満。見えているのは200個から250個ぐらい(全天で500個弱)だと思います。街中ではさすがに無理ですが、条件のいい日に少し郊外に出ればこれぐらいの星は見ることができます。「機材を必要とせず、あまり遠出をしなくても見られる夜空」を再現するのが目標なのでこれで十分でしょう。
薄いグレーのラインは地平線、色がついているのはテスト用のマーカーです。赤が北極星、青がおおいぬ座のシリウス、黄がこと座のベガです。北斗七星は結構簡単に見つかるでしょう。シリウスとベガを目安にすれば白鳥座やオリオンも見つかるはずです。今の季節だとシリウスが昇ってくるのは夕方ですね。
動いているところが見たいという方は以下のGIFムービーをどうぞ。24時間分の動きをまとめたものです。
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/movie.gif
デフォルトでは、東京の現在の空を表示します。
URLでクエリを指定すれば各パラメーターを可変できるようになっています。
指定できるパラメーターは以下のとおり。
year : 年。小数点以下指定可能。
month : 月。小数点以下指定可能。
day : 日。小数点以下指定可能。
hour : 時。小数点以下指定可能。
minute : 分。小数点以下指定可能。
timeoffset : 指定時間からの経過時間。単位は時。マイナスの値も受け付けます。
sitelong : 観測地の経度。単位は度、東経なら+、西経なら-。デフォルトは139.75。
sitelat : 観測地の緯度。単位は度。デフォルトは35.65。
img_w : 画像幅。単位はピクセル。デフォルトは800。
img_h : 画像高。単位はピクセル。デフォルトは800。
例えば、本日、午前零時、シドニー、画像サイズ1200x1200ならこんな感じ。み、南十字星はどれ?
サイズを1600X1600ぐらいにしてスクロールしながら見るのも一興かと。
ソースコード
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/starchart-050214.txt
PHP+GDライブラリで動作します(たいていのプロバイダは大丈夫だと思いますが...)。
データ
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/data2.csv
元データは「Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed.」
必要のないデータを削除し、座標の単位をそろえて、CSV形式に変換したものです。
元データは以下のFTPサイトから。
ftp://dbc.nao.ac.jp/DBC/CDS/cats/V/50/
ちなみに、星の数を減らしたファイルと増やしたファイルも作ってあります。
等級3.5以下(街中ならこれくらい、ちょっと寂しい)。
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/data.csv
等級6.5以下(肉眼で見られる最大。プラネタリウムはこれくらい、ちょっと多すぎる)。
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/data3.csv
えーと、そのうちちゃんと書きますが、著作権はありません。それが開発の目的なので。
次は惑星かな?
※随時更新中です。
最新のものは[prog]のリンクで確認してください。
. Date: 20050216 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping謎の惑星、冥王星の正体は彗星か (LivedoorNews)
なんか、意味不明の記事だな。彗星は元カイパーベルト天体だけど、カイパーベルト天体=彗星じゃない。えーと、例えるなら「謎の刺身、中トロの正体はツナ缶か?」という感じ。いや、違うでしょ、どっちもマグロだけどな。
冥王星は惑星とすべきか、小惑星とするべきかについては、これまでも何度も議論の対象になってきた。確か「本来なら小惑星と区分すべきところだかもしれないけれど、慣習からとりあえず惑星とする」というのが今の方針だったと思う。こういう声はこれまでも何度もあったし、何をいまさらという感じ。
確かに、1997年に天文学者からの声明が出た後、「格下げか」といううわさが飛び交った。それを受けてIAUは1999年にプレスリリースを出している。「うちじゃそんなことは言ってない。いい加減なことを書くな。今後も変更の予定無し、以上。」だそうな。
おそらく元ネタはこれ。
Pluto discovered 75 years ago, but what is it? (CNN)
内容は、冥王星が惑星か否かについてのこれまでの議論をまとめたもの。論調はむしろ、カイパーベルト天体にしては特殊だよね、という感じ。「将来格下げになるかも」とは書いてない(もし、なったとしたらという一文はあるけどね)。
ちょっと適当すぎるんじゃないか?LivedoorNews
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/starchart-050216.php
等級による描画を3段階から5段階に細かくし、明るい星のエッジが滑らかになるように調整。また、星の数を全天で500個だったのを1000個弱まで増やしました。かなりそれっぽくなったと思います。
ただし、これまで同じ明るさで描画されていた星の一部が暗くなっているので、むしろ星の数が減ったような印象を受けるはず。4.0等級を超えるものはかなり暗くしてあるので、条件が悪いと見えません。モニターをきれいに拭いて、部屋を暗くしてご覧ください。
ソースコード
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/starchart-050216.txt
※随時更新中です。
最新のものは[prog]のリンクで確認してください。
. Date: 20050217 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [prog]starchart-050217.phphttp://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/starchart-050217.php
・星名を追加(1.5等級以上+北極星)
・星座線の表示(北斗七星・カシオペア、白鳥座、今後随時追加)
・太陽を追加(starchart-050216.phpでテスト)
星名はランドマークになればいいので、これぐらいで十分でしょう。
星座線は、例のごとく、かなり見難くしてあります。
「そこに星座があることを知っていれば見える」くらい。
星名と星座線は以下オプション指定で非表示
starchart-050217.php?line=n&name=n
ソースコード
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/starchart-050217.txt
データファイル
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/data5.csv
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/line.csv
あ、南半球で星座線が破綻してる。がーん。→対応済み(だと思う)
※随時更新中です。
最新のものは記事タイトルの[prog]のリンクで確認してください。
. Date: 20050219 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryすっかり、開発日記になってしまった。
[prog]Open Planisphere (Pre-alpha)http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/chart.php
・インターフェイスをつけました。
・CCライセンスをつけました
・プロジェクト名をつけました
ソースコード
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/chart.txt
何やらごちゃごちゃやってますが、中身はstarchart.phpに渡すURLを生成しているだけです。
「回転」と「ズーム」をつけたらPreを取ろう。そうしよう。
※随時更新中です。
最新のものは記事タイトルの[prog]のリンクで確認してください。
. Date: 20050221 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [prog]Open Planisphere (Alpha)http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/chart.php
・方角別の表示機能をつけました。
・表示関連のON/OFFを拡張しました。
インターフェイス部分(chart.php)ソース
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/chart-050220.txt
画像描画部分(starchart-050219.php)のソース
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/starchart-050219.txt
データ
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/data5.csv
思いついてから2週間強(2/4作業開始、同日mixiで公開、2/14はてなで公開)、一気に作業を進めてきましたが、これで当初予定していた機能はすべて入ったことになります。今後は、ちくちくと惑星の追加や星座線の追加など、データの追加作業をやっていくことになります。惑星と月が全部入って、寂しくない程度に星座線が追加できたらBetaに移行します。
この2週間、久しぶりにプログラミングを堪能しました(まだ終わってませんが)。作っているあいだ、いろいろ思うところはありましたが(ライセンスとか、星の運行のこととか)、まあ、それはそのうちに。
. Date: 20050224 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingMTSAT-1R/H-IIA・F7の打上げ日について (JAXA)
延期になっていたH2A-F7の打ち上げ日程が発表になりました、26日(土)17時09分?18時33分とのこと。
ほら、あそこにぼくらの未来が、少なくともその一部が立っている。さあ、手に汗を握りながらカウントダウンを待とう。ぼくらがロケットを大好きなのは、あの機械がいつも夢を見せてくれるからだ。だって、あの機械は宇宙へ行くんだぜ。それだけでも、ぼくらを興奮させるにあまりあるじゃないか。
子供の頃、「宇宙」と「未来」は同義だった。きらきら光る宇宙船に乗って星の世界を旅する夢を何度見ただろう。いま、ぼくらはその未来に手を掛けようとしている。あの頃とはずいぶん形を変えてしまったけれど、それでも確かに、あそこに「ぼくらの未来」が立っているんだ。
何度も言うようだけど、ロケットは想像力を乗せるための最良の乗り物だと思う。
H2A-F3の立っている場所 (Junkyard Review)
これは、コロンビアが落ちるずっと前、H2A-F6が落ちるより前の、H2A-F3(2002)の時に書いた文章。なんてお気楽なんだろう。ロケットが落ちるかもしれない、ましてそれで人が死ぬかもしれないなんていうことを、微塵も想像していない。今読み返すと、この言葉はずいぶん重い。僕らの夢や希望のために、命を賭する人々がいるということだから。
でも、だからこそ、もう一度言うことにしよう。
夢や希望じゃロケットは飛ばないけれど、ロケットは夢や希望をのせて飛ぶ。
何度も、何度も言うようだけど、ロケットは想像力を乗せるための最良の乗り物だと思う。
打ち上げの成功を心からお祈りします。
携帯用URL
[http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/starchart-050222.php?img_w=240&img_h=240&name=y&line=y&mode=all&horizon=y&d_sign=y:barcode]
[]http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/starchart-050222.php[]
?img_w=240&img_h=240&name=y&line=y&mode=all&horizon=y&d_sign=y
これは、携帯用のシステムを新たに作ったんじゃなくて、URLの指定を変えただけのもの。
これまでに、星座線と火星の追加、太陽の表示の修正、いくつかのバグフィックスを行いました。
http://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/chart.php
. Date: 20050226 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary MTSAT-1R/H-IIA・F7http://mtsat1r.rocketsystem.co.jp/
さて、そろそろ中継が始まってますね。
16:00には最終カウントダウンへのゴーサインが出て、打ち上げの最終段階に入っています。
17:00 通信トラブルでカウントダウンが中断しているみたいですね。
機体と施設間の通信にトラブルがあったとのこと。T-60分でホールドになっているようです。
17:30 作業が再開されました。変更後の打ち上げ予定は18:25の予定です。
18:00 しばらく前から、ストリーミングの本放送が始まり、今回のミッションに関する説明映像が流されています。
18:10 カメラが射点に戻されました。15分前です。
18:12 打ち上げへの最終ゴーサインが出た模様、アナウンスがありました。
18:15 10分前。随分日が落ちてきましたね。わくわくわくわく。
18:18 秒読み開始
18:20 5分前。きゃー。
18:21 自動カウントダウンシーケンス開始。
:22 内部パワーに切り替え、3分前。
:24 一分前 きゃー
:25 打ち上げ
:30 正常に飛行中。既に固体燃料ロケットブースターが切り離されました。衛星フェアリング分離
:32 第一弾燃焼終了、切り離し、第2段第一回燃焼開始。
:35 今のところ、非常に順調に飛行中。わーい。
:38 第2段第1回燃焼停止。
:40 種子島からの管制終了、クリスマス島からの管制開始は5分後。
:45 クリスマス島での受信を開始。
:50 第2段第2回燃焼開始。順調に飛行中。
:53 第2段第2回燃焼終了
:55 クリスマス島からの管制終了、次はサンチャゴ。何分後かな?
19:04 サンチャゴからの管制開始。順調に飛行中。
19:06 衛星切り離し!!!
H2AF7の打ち上げは無事成功したようです。ばんざーい!
--
関係者の皆さん、打ち上げ成功おめでとうございます。
なんだかひさしぶりにとてもわくわくしました。本当にありがとうございます。
. Date: 20050228 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingみんなでジャンプして地球の軌道を変えて地球温暖化を阻止しよう!うわはははは。でも、当たり前だけどその瞬間に地球の内側に位置する国々の人々しか参加できない。つまり、日本からの参加はだめ。ちっ!
でも、ジャンプしただけじゃ軌道は変わら...まあ、やめときましょうね。
Virgin Atlantic Global Flyer : Home Page
単独無着陸世界一周飛行を目指すグローバルフライヤーですが、離陸がカウントダウンに入っているようです。
天候は良好、20:00UTC?00:00UTC(日本時間1日5:00?9:00)には離陸できるかもしれないとのこと。わくわくわくわく。
Anti-wind farm report dismissed (BBC)
ドイツで発表された、風力発電は非効率であるというレポートに関するお話。記事の内容はイギリスでは無視されたというニュース(BBCだからね)。木になる報告書の内容は、「風力発電にコストをかけるくらいなら、既存の火力発電所にフィルターをつける方がずっと安上がりで効果が高い」という内容らしい。
うん、まあ、そうだろね。
なんてことを言うとすぐに目くじらを立てる人がいるので、説明をしておきましょう。風力発電というのは、実はとても効率が悪いんです。細かく言うと、風力タービンの発電能力というのは大雑把に言ってタービンの風上側の風力の3乗に比例します。つまり、風力が2倍になると発電能力は8倍に上がり、逆に風速が半分になれば発電力は1/8に下がります。要するに風の強さが少し変化するだけで、出力が大きく変化してしまうんですね。設計時に想定した最適な風力の範囲から、少し弱くなると十分な電力を生まなくなります。少し強くなるとブレードや発電施設に負荷がかかってしまうために止めなければなりません。風の力で定常的な電力を生み出すのは結構難しいんです。
もしかりに、温暖化ガスの排出を抑制するため「だけに」に風力発電機を設置するとしたら、火力発電所が生み出す電力を補うだけのタービンを設置しなきゃいけません。電力を安定供給するためには、おそらく膨大な数のタービンが必要になるはずです。建設費用や配電コスト、メンテナンスコストなんかを考えれば、火力発電所にフィルターをつける方が安いというのは、至極当然の結果でしょう。
でも、個人的な感想をいうなら、火力発電所のような一極集中型の発電システムと、風力発電のような分散型の発電システムを比べるのはそもそも無理があると思います。温暖化ガス抑制「だけに」とカッコつきで書きましたが、風力発電には、火力発電に比べて小規模での発電が可能で継続的な燃料の供給がいらない、太陽光発電に比べて太陽が出てなくても発電できるというメリットがありますから、これを生かせる場所ならかなり有効な発電方法になるはずです(例えば、離島とかね)。
近年の電力開発は、太陽光発電やコジェネなどの例を出すまでもなく小規模分散化に向かう方向で開発が進んでいるようです(これにも異論があるんですけどね、あまりに分散化しすぎると温暖化ガスなどの排出をコントロールするのが難しくなりますから)。適材適所というのはあまりに当たり前の結論ですが、まあ、そいういうことです。
ちなみに、私は風力タービン大好きです。だって美しいじゃないですか。
先日、H2AF7によってぶじ打ち上げられた運輸多目的衛星ですが、一度目の軌道変更に成功したようです。後2回の軌道修正を行い、所定の静止軌道に乗るのは3/8の予定です。
横で打ち上げの中継を見ていた連れが、遠いんだねえ、といってました。そう、[http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20031019101213:title=静止軌道はとても遠いんです]。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20050301 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingVirgin Atlantic Global Flyer : Home Page
昨日の段階で、今日飛べるかも、なんていう予告が出ていたGlobal Flyerですが、本日00:47UTC(日本時間9:47)に無事飛び立ったようです。がんばれー。途中、日本上空を通過する予定。高度4000mとのことですので、上を通れば見えるかもしれません。
最新情報は、以下のページでどうぞ。
Virgin Atlantic Global Flyer : Flight Tracker
知らない人のために書いておくと、グローバルフライヤーは無給油単独無着陸世界一周を目指すプロジェクト。名前を見れば分かるようにスポンサーはバージンアトランティックです。
機体を設計したのは、初の無着陸世界一周を成し遂げたボイジャーの設計を行ったバートルータン率いるスケールド・コンポジット。最近では初の民間有人宇宙飛行で有名になりましたね。
パイロットはスティーブ・フォセット。2002年にこれまたヴァージンアトランティックのスポンサードで気球による単独世界一周を成功させた人です。
. Date: 20050303 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daliy ClippingVirgin Atlantic Global Flyer : Flight Tracker
燃料切れが懸念されていたようですが、ハワイを通過して、飛び続けることにしたようです。あと、もう少し!
H2Aロケット打ち上げ成功率と理科教育【埼玉県】 (livedoor)
日本のH2Aロケットの打ち上げ成功率は78%であり、欧州、中国、アメリカなどの海外の打ち上げ成功率約90%と比べて劣っている。その理由の一つとして、日本の理科教育において、宇宙への興味やロマンをかきたてられるような授業内容が不足していることが挙げられよう。
挙げられないと思います。
「みんなが宇宙のことを考えるようになれば、予算もたくさん回されるようになって、失敗が少なくなると思います!」ってことかなぁ?H2Aロケットの打ち上げ成功率が低いのは、単純に打ち上げ数が少ないからだと思いますが...。
H2Aは今回でまだ7機目。この1機種だけ、しかも開発から7機目という「技術が枯れていない」状況での成功率と、数十年にわたって打ち上げ続けているアメリカやロシアのロケット全部の成功率を比べるのはナンセンスでしょう。
たとえば、ESAアリアンVの初飛行から10機を見ると、完全な成功は7機だけ。1機はコントロールエラーで発射後40秒で爆破、残りの2機はトラブルで予定の高度に達しなかった。初期の頃なんかもっとひどくて、ロシアのプロトンシリーズやアメリカのレッドストーンは最初の10機のうち5機が失敗しています。ちなみに、レッドストーンは初の有人飛行に使われたんだけど、その前までに71回中13回失敗。アランシェパードは、成功率81.6%の機体に乗っていたんですねえ。
まあ、もう少し成功率の高い機体もあるんだけど、技術的に新しいことに挑戦した機体っていうのは最初の頃はだいたい成功率が低い。確かに、7回のうち2回失敗は決していい数字とはいえないし、失敗を正当化する理由にはならないけれど、純粋に数字だけ比べるならさほど驚くほどのことじゃないと思う。
. Date: 20050304 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingAviation history has been made! (GlobalFlyer)
無事飛び立ったSalinaに着陸したようです。わーい。おめでとうございます!
. Date: 20050307 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [prog]Open Planispherehttp://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/chart.php
前回の報告(2/24)以降、以下の機能を追加しました。
・readmeを作りました。
・月を追加しました
・月の満ち欠けを再現しました(ただし、傾きは再現していません)
・木星を追加しました
・新月を丸く切り抜きました(日食対策なので新月だけです)
ということで、追加した機能が全部見られるイベントをひとつ。
※全天に対する月と太陽のサイズが正しくないので、日食の開始時刻や終了時刻は正しく再現されません。
ちなみに、次に全国で日食が見られるのは2009年7月22日のお昼前です。
Twin Mars rovers in instrument mix-up (NewScientist)
メールでタレこんでいただいたニュース(yamaさんありがとうございます)。
予定の観測期間を大幅に超えて元気にデータを送り続けている2台のローバーですが、オポチュニティに組み込まれるべき機材がスピリットに、スピリットに組み込まれるべき機材がオポチュニティに組み込まれていたようです。
ほとんど同型のローバーのまったく同じ機材が入れ替わっていただけなので、一見何の問題も無いような感じがしますが、同じ機械であっても、微妙に癖が違うため、得られるデータが違ってきます。つまりこれまで公表されていたデータはかなりの誤差を含んでいるということになります。
生データが残っているので、両者の違いを補正するのは難しくないとのことですが、発表されたデータを元に研究をしていた世界中の研究者の心境やいかに、という感じですね。まあ、「かつて火星に水が存在した」という事実が覆されるとは思えませんが...
. Date: 20050308 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping運輸多目的衛星新1号(MTSAT?1R)の静止化完了及び愛称について(国土交通省航空局・気象庁)
http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jma/press/0503/08a/nickname.pdf
先日H2A-F7で打ち上げられたMTSAT-1Rですが、無事静止軌道に乗ったようです。一時期はもめていたようですが、愛称は「ひまわり6号」とすることに決まったそうな。回ってないけど...
気象衛星としての運用開始は早ければ5月、遅くとも夏ごろまでにはという感じでしょうか。航空管制衛星としては、来年頭に運用開始の予定です。
関係者の皆さん、おめでとうございます。
H2A補助ロケットの捜索中止…現場海域のマグロ漁で (YOMIURI ON-LINE)
打ち上げ成功で、政府内に「失敗原因を究明するわけでもないのに、数千万円をかけてまで探す必要があるのか」という雰囲気が強まったことも、捜索断念の流れを後押しした。
ある!おおあり!多少予算かけてでも回収するべきだと思います。
ロケットっていうのは、基本的に打ち上げたら終わり。本番でなにがおこってるかを知る方法がほとんど無い。失敗したときに部品を回収するのは当然だけど、成功したときのデータが無ければ、改良するにも効率が悪いし、万が一失敗したときの原因究明が難しくなる。まして、今回は改良後最初の打ち上げだよ。改良にちゃんと効果があったかどうかを検証するためにはSRBを拾ってくるのが一番いい。ここで数千万円かけたものが、後で数億円を救うかもしれないのに...
意思決定をする人たちは、事故から何を学んだのかな?それとも、あの事故が起きるに至った膨大なフォルトツリーの中に、自分たちの意思決定が含まれていることに思い至っていないのか。いないんだろうなあ。どんなに無駄にお金が使われていたとしても、予算を切れば何らかの変化が起きる。そのリスクを読んだ上でコストカットしているなら同じ予算カットにしてもこういう風潮にはならないはず。「リスクに対する読みの確かさ」が政治家の力量だと思うけどなあ(っていうか他にあるかな?)。
危機意識は、つねひごろから「危ない、危ない」といい続けていることじゃないし、危機管理は危うさを0%に下げることじゃない。むしろ、危機意識というのは「危うさ」は決してゼロにはならないということ受け入れた上で、その「危うさ」とどうにかうまくやっていく、というマインドセットのことじゃないか?危機管理というのは、その危うさをなるべく分散させて、いったん発現してしまったときのリソースの損失を最小限にとどめることじゃないだろうか?「事故を起こすな」という一言だけで済ませるのは、まさしく危機意識の無さの露呈でしかないし、危機管理の放棄でしかないよ。
New Horizons (via 星が好きな人のための新着情報)
探査機にあなたの名前を乗せようキャンペーン。今度は冥王星!
. Date: 20050316 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary The Hitch Hiker's Guide to「サイエンスを楽しむためのリソースガイド」このサイトは、他の誰でもなく、僕が一番欲しかったサイト。ずいぶん待ったけれど、誰も作ってくれそうにないので、自分で作ることにした。
実は一年ぐらい前に立ち上げて、ずーっといじっていたんだけど、そのまま腐ってしまいそうなので、とりあえず公開(映画も公開されるみたいだし)。さて、どこまで行けるだろうか。
何度も言ってきたことだけれど、「科学を楽しむ」ことは「科学を楽しく学ぶ」こととは違う。サッカーをプレイするのに必要なスキルと、サッカーを観戦するために必要なスキルはまるで違う(もちろん一部は重なっているけれど)。ボールをうまく蹴るのはなかなか大変だけれど、観客席から選手を応援するのはそこまで難しくない。ボールが蹴れなくても、サッカーを楽しむことは出来るはず(もちろん蹴れた方がもっといいのかもしれないけどね)。僕がこのサイトでやってみたいのは、ボールを蹴ることじゃなくて、サッカーを見て楽しむことの方。
トップページにも書いたけれど、このサイトは「科学を分かりやすく」とか「便利で役に立つ」とか「すべてを網羅」なんてことはこれっぽっちも考えていない。ただ、そこに書かれたリンクの先で何か面白いことがおきていること、そしてそれに対して誰かがわくわくしていることだけは保証できる。
ここからどこへ行くやら分かりませんが、どうぞごひいきに。
実は、もう編集に参加してくださっている方もいます。ありがとうございます。
「後ろのtheはいらないのでは」という指摘がどこからともなく聞こえてきたよ。
うー、元ネタにそろえたんだけど、やっぱり変か、変だよねえ。
うー、よし、取ろう
. Date: 20050318 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping土星の衛星エンケラドスに大気 「生きた衛星」の可能性 (asahi.com)
えええ、ほんとに!
これが本当なら、太陽系で2つ目の大気を持つ衛星ということになる。何で土星ばっかりなんだ?
しれっと、「火山の噴火や間欠泉の噴出のようなものがあるとすれば...」なんて書いてあるけど、直径500kmじゃ小さすぎて地熱を維持できずにとっくの昔に冷えているはず。もっとも疑わしいのは氷の火山。
エンケラドスは、太陽系で最も高い反射率を持つ天体。なんと、太陽光の90%を反射する。どうやら「氷でつるつる」だかららしい。土星のE-リングの元になった物質を放出したのではないかと言われていて、氷の火山の存在する可能性が高い。ただし、そのメカニズムについてはよくわかっていない。
もうちょっと詳しい記事は以下を参照のこと
Cassini finds an atmosphere on Saturn's moon Enceladus (SpacefligntNow)
Atmosphere found on Saturn moon (BBC)
VLTI First Fringes with Two Auxiliary Telescopes at Paranal (via 星が好きな人のための新着情報)
南米チリにあるヨーロッパ南天天文台が1.8m補助望遠鏡による光学干渉に成功というニュース。ニュースリリースによると、もし仮に補助望遠鏡を最大幅まで展開すれば200mの距離をとることができて、そうすると月面の宇宙飛行士が見られるほどの解像度が得られるそうな。えー、これは「解像度だけなら」という話なのかな。補正光学と光学干渉の合わせ技でほんとに見えたりするんだろうか。
えーと、分解能は116÷口径だから、口径200mで月までの距離を38万キロとすると...
atan(((116/200000)/3600)*degree)*380000000 = 1.06852935 (Googleで計算)
確かに、分解能だけなら月の上の1mの物体が見分けられることになるね。
でも、分解能0.00058秒って...こんな精度で大気の揺らぎを補正できるのかな。
参考)Astronomy/大型望遠鏡(h2gs)
. Date: 20050323 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingNASA'S Spitzer Marks Beginning of New Age of Planetary Science (SpaceRef)
宇宙赤外線望遠鏡スピッツアーが太陽系外の惑星からの光を直接観測することに成功した、というニュース。ひょー!
えーと、これはものすごい進展。どれくらいすごいかというと、「冷蔵庫があるかどうか分かる」という状態から、「冷蔵庫の中身が見える」という状態になったぐらいにすごい。
追記)
h2gsにdtomono氏による解説記事がアップされています。
http://www.lizard-tail.com/h2gs/index.php?PlanetarySciencewithSpitzer
なるほど、明るさが変化したのの差分を取っただけなんですね。
宇宙ステーション、来春から日米の利用ピンチ (YOMIURI ON-LINE)
2000年に発行されたロシアの大量破壊兵器と弾道ミサイル技術のイランへの流出を防止する「イラン不拡散法」には、国際宇宙ステーションを通じた技術拡散を防ぐために、ロシアの宇宙開発機関がイランにミサイル技術を拡散させないという確約をしない限り、ロシアへの資金提供をしない、という条項が含まれている。
イランをはさんで米ロの関係が焦げ臭くなっている上に、今秋でロシアとのソユーズ無償運用の契約が切れるというかなりバッドタイミング。このまま関係悪化が続くと、ソユーズには金出さんもーん、ということになるかもしれない。しばらくはシャトルが飛んでいるから何とかなるかもしれないけど、2009年のシャトル退役から次世代機が飛ぶ2014年までの5年間、ISSへ行く方法がなくなってしまう。
解決手段は二つ。
アメリカが法改正をする→ブッシュ君が強硬そうなので、難しいかも。
ロシアが拡散させませんと確約する→これができないのは、やっぱり大人の理由なのかな。
この件に関しては以前から問題が指摘されていた<%= fn 'リンク先は、法律制定時のNASAからのコメント。「アメリカの勝手でロシアへの資金をカットしたら、他の国の資金負担が増えて、みんな逃げてまうで」という内容' %>。
「夢や希望じゃロケットは飛ばない」というのは分かってるつもりだけど、やっぱり、げんなりするなあ。
で、日本の宇宙開発はというと...まるで間に合いませんね (YOMIURI ON-LINE)。補給機は何とか間に合うかな?ていうか、無人機を有人機に改造なんていうばかなこといってないで、最初から有人目指して開発すればいいのに。無人機を有人機に改造するのは、たらいを風呂桶に改造するようなもんだぞ。新しく作った方が早いって。
. Date: 20050328 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingフリーマン・ダイソン、宇宙開発計画の継続を訴える (ITmedia)
ああ、ダイソン先生まだ元気なんだ。最近話題がなかったので、すっかり隠遁生活をしているんだと思っていたけど...。大言壮語は相変わらずだなあ。個人的に「最も尊敬する科学者」の一人なので、元気な言葉が聞けただけでも大変うれしい。
関係ないが、原文のタイトルの方がずっといい。
Let's colonize space for fun, noted physicist says (CNET News)
How to Waste $300,000 (NASA Watch)
Astronaut Space Safety 2005 という報告書の出自が非常に怪しげだというお話。どうやら中身もでたらめらしい。続報1、続報2。もしかしたら、スペースシャトル事故に便乗した詐欺事件かもしれない。
この報告書はSpace Shuttle Children's Trust Fundから300,000ドルの資金を得て作られたとされている。でも、この基金の公的な記録を見ると、「災害援助」と「孤児院などの子供たちへの援助」を目的として設立されたにもかかわらず、これまでコロンビアとチャレンジャーの遺族にわずかな金額が支払われただけで、ほとんど支出が計上されていない。なのに、突然30万ドル(約3200万円)ものお金が、報告書を作るためだけに支出されているのは、かなりおかしいんじゃないの?ということらしい。
しかも、続報によると、この報告書にはまったく新しい事実が含まれていないうえに、あまりに間違いが多く、きわめてお粗末な代物だという。
うーん、限りなく黒に近いような気が...
. Date: 20050329 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 3月30日深夜はアンタレス食3月31日(3月30日深夜)午前0時台から1時台にかけて、月がさそり座のアンタレスを隠します。月を見つけるのは、えーと簡単ですね。南東の空の低いところに出ているはず。1等星が月に隠されるのは、14年ぶりの出来事。次におきるのは11年後のアルデバランになります。かなり貴重な機会なので、晴れていたら外に出てみましょう。ただ、月の位置が低いので開けたところに行かないと見えないかもしれません。
月に隠されるアンタレスはとても赤く、さそりの心臓であるとされています。ちなみに、あの星を称して「ルビーよりも赤く透き通り、リチウムよりも美しく酔ったようになってその火は燃えている」といったのは宮沢賢治。
僕はもうあのさそりのようにほんとうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない。
宮沢賢治『銀河鉄道の夜』
いつぞや書いたような気もしますが、あの星を見上げて、オリオンを刺し殺した蠍や、火星に反抗する星(アンタレスの語源、アンチ・アーレス)の姿ではなく、2人の少年の旅路とその勇気を思うことが出来るのは、とても幸せなことだと思います。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20050401 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary好奇心は猫を殺す
First Confirmed Picture of a Planet Beyond the Solar System (SPACE.COM)
初めて太陽系外惑星の直接映像が撮影された、というお話。何回「はじめて」があるんじゃい!と突っ込みを入れたくなりますねえ。私の知る限り、「始めて写真」はこれで3枚目ですが...今回は「First Confirmed」だそうです。どうやら、惑星の質量が測定できたため「初めて確認」となった模様。
103AUってことは太陽から冥王星までの距離の約3倍、「彗星の巣」カイパーベルトよりさらに遠いところです。ついこの間話題になったセドナが76?850AUという長楕円軌道でしたが、ちょうどこれくらいでしょうか?ずいぶん遠いですねえ。
本来なら、こんなに遠い惑星は暗くて見えないはずなんですが、まだできたての若い系だったために観測ができたようです。
同日本語記事:
太陽系外惑星:独チームが初撮影 チリにある望遠鏡で (Mainichi-MSN)
It's Mainly Just for Fun (Reason Online)
Virgin GalacticのCEOリチャードブライソンへのインタビュー。商業宇宙飛行で一番大切なのは「安全」。ごもっとも。Virginはすでに商業宇宙飛行のための規約を作るべくFAAに働きかけをしているそうな。
「僕は、ライト兄弟が飛んだ1903年じゃなく、1908年から1912年の3.5年間の方に注目したい。このたった3.5年の間に飛行経験者が10人から数千人に増えた。まだ定期旅客もなく、第1次大戦の飛行機もなく、郵便飛行機もなかった時代。かれらはただ楽しみのためだけに飛んでいたんだ」
そういえば、日本にも、宇宙を目指すぜなんていっていたCEOがいたけど。どうせばかなことを言い出すなら、これぐらい本気でやってほしいなあ。
Malaysia car thieves steal finger (BBC)
指紋認証キーがついたベンツを盗むために、持ち主の指まで盗まれたという話。
僕はなんとなく生体認証には不安がある。いくら強固だとはいえ鍵には必ず開ける方法がある以上、100%安全なんてことはありえない。だとすれば、リスクの分散がとても難しい生体認証は「危ない」気がするんだよね。だって、「鍵」をコピーされたらどうするの?鍵はあけにくいに越したことはないけれど、あけられちゃったときのことも考えないと。
Animal laughs no joke says expert (BBC)
動物も笑うよ、という話。もしかしたら、彼らも声に出して笑っているのかも、でも僕たちにはそれが笑いだと分からないだけかもしれない。いや、普通に笑ってるだろ、犬とか猿とか。
. Date: 20050407 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Open Planisherehttp://lts.coco.co.jp/isana/lab/starchart/chart.php
最近、OPのコーディングをしながら、おとめ座とヘラクレス座を見ていると、
おとめ座 :「ほらほら、捕まえてごらんなさーい、うふふふ(はぁと)」
ヘラクレス座:「まてまてぇー、あははー (はぁと)」
と、やっているようにしか見えなくて困る。
↓こいつらの浮かれ具合はちょっとおかしいと思うぞ。
http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starchart.png
いつもなら「ドーキンスは間違っている」本はスルーするんだけど、「もう一人の断続並行説論者」エルドリッジ先生の著作と知って読んでみた。かなりとほほな内容だった。
作者のナイルズ・エルドリッジ氏は故スティーブン・J・グールド氏と一緒に「断続並行説」を唱えた人。グールド氏の陰に隠れて日本では余り知られていないけれど、向こうではリチャードドーキンスを筆頭とするネオダーウィニズム(エルドリッジ氏は「ウルトラダーウィニズム」と呼ぶ)に片っ端からけんかを売っているので有名。
Dr. Niles Eldredge (AMNH research)
ちょっと長くなるけど、帯の文章を引用しよう。さすがに名の知れた進化論学者なんだから、まさかこの内容じゃないだろう(また出版社が中身を曲解して煽ってるんだろう)と思ったけれど、本当にこのまんまの内容だった...orz
ドーキンスの「利己的遺伝子」はまったくのフィクションだ!
ヒトは遺伝子を残すためだけにセックスするのではありません。男と女の関係は“遺伝子の欲求”で片付けられるほどシンプルでもないし、セックスの目的も多岐にわたります。われわれの行動は遺伝子に支配されてなどいないし、そしてもちろん、浮気も遺伝子のせいではないのです。
遺伝子決定論者によれば人間のオスは遺伝子をばらまくために浮気をするのだそう。けれども子どもを作るために浮気をする男女はほとんどない。なぜならヒトは遺伝子を残すためだけにセックスをしているわけではないから。ましてやヒトの一生が遺伝子の運搬だけに捧げられているなんてあり得ない。本書はドーキンスの「利己的遺伝子」の矛盾を指摘して、何のためにヒトが生き、セックスするのか、その真実を解き明かします。
進化論系の話を読みなれた人なら、この文章が突っ込みどころだらけなのが分かると思う。この本のドーキンス批判は前提からして間違ってる。だってドーキンスはこんなこと言ってないんだもの(彼は遺伝子決定論には否定的)。エルドリッジ先生、利己的遺伝子への憎さのあまり、ネオダーウィニズムと遺伝子決定論が完全にごっちゃになってます。平たく言えばこの本は「竹○久美子の言っていることは間違っている、つまりドーキンスは間違っている」と言っているようなもの。そりゃドーキンス先生に失礼だよ。
ドーキンスは「ダーウィン進化論の『子供の残しやすさ』の部分を『遺伝子の残しやすさ』と言い換えた方が、進化論のいろんな問題(たとえば利他行為とか)が説明できるよ」と言っただけ。この観点に立つと、あたかも生物は遺伝子の乗り物であるかのように見える(生物=生存機械論)。彼が「利己的」という言葉を使ったのは、「個体は種に奉仕する」という群淘汰論の「利他主義」に対応して、「個体の利他主義は『遺伝子の残りやすさ』(遺伝子の利己主義)で説明できるよ」という主張をしているから。<%= fn 'まあ、彼自身「あの本はちょっと比喩を使いすぎたよ」と反省していたりするんだけど...' %>
さすがに第一線の進化論学者だけあって、各論にはあまりトンデモはないけど、ページごとに「いや、ドーキンスはそんなこと言ってないから」「いや、ダーウィンだってそんなこといってないから」と突っ込みを入れたくなる。だんだんあきれるのを通り越して、微笑ましいやら、気の毒やら。エルドリッジ先生はドーキンス一派の「ありもしない極論」を次々と論破していく。後ろから見ているわれわれは「いや、先生、それ違うから」「あの、先生、少しおちつかれた方が...」とおろおろするばかり...そんな感じの本(どんな本だ?)。
えー、1つ上の「進化論間違い探し」が楽しめること請け合いです。オススメはしませんが...
. Date: 20050408 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingButterflies 'follow flightpaths' (BBC)
蝶はランダムに飛んでいるわけじゃなく、かなり計画性を持って飛行経路を決めている、というお話。
蝶たちは、すばやい直線的な飛行と、ゆっくりした飛行を組み合わせて飛んでおり、200m前から茂みなどの障害物を避け、100m前から花や冬眠などに適した場所を識別しているらしい。
「蝶道」なんていう言葉があるくらいだから、それなりのパターンがあるだろうとは思っていたけれど...やっぱり、これは記憶による飛行パターンなのかな、それとも何らかの認知能力でリアルタイムにナビゲーションしているのか...まあ、両方か。
Solar Plane Planned for Around-the-World Flight (NationalGeographic)
ソーラープレーンで世界一周を狙っている男の話。彼、Bertrand Piccardは1999年に「Breitling Orbiter 3」で熱気球世界一周を成功させている。次はソーラーパワーで、というわけやね。2007年にテスト飛行、2009年に記録に挑戦という予定。がんばれー!
JAXA長期ビジョンについて (JAXA)
を、ようやく出ましたね。後で読もうっと。
ディスカバリーが発射台に移動 最終準備に (asahi.com)
いよいよですね、といいたいところですが...
50-50 Chance Of Late Discovery Launch (SpaceDaily)
すでに、トラブルシュート用の予備時間を使いきっているので、これ以上何かトラブルがあると打上げが延びるそうです。
2006年宇宙の旅の概要が発表! 7人乗りで、複数機の旅行プランを次々と計画 (PCWeb)
えー、ベンチャー企業ができてもいないプロダクトの将来計画をぶち上げるのは、かなり危ない兆候だと思います。
. Date: 20050411 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]Aventis - Prizes for Science Booksサイエンスブックアワード『アヴェンティス賞』の今年のノミネート作品。受賞作の発表は5月12日。
2005 General Prize:
Ball,Philip. Critical Mass: How One Thing Leads to Another (William Heinemann, 2004).(amazon)
Dawkins, Richard. The Ancestor's Tale (Weidenfeld & Nicholson,2004). (amazon)
Draaisma, Douwe. Why Life Speeds Up As You Get Older (Cambridge University Press, 2004). (amazon)
Edwards, Griffith. Matters Of Substance: Drugs - And Why Everyone's A User (Penguin, Allen Lane,2004) .(amazon)
Fortey, Richard. The Earth: An Intimate History (HarperCollins,2004). (amazon)
Winston, Robert. The Human Mind (Bantam Press/ Transworld Publishers,2004). (amazon)
2005 Junior Prize:
Burnie,David. Kingfisher Knowledge: Endangered Planet (Kingfisher,2004). (amazon)
Clarke,Phillip.,Howell,Laura.,Khan,Sarah. Mysteries And Marvels Of Science(Usborne,2004). (amazon)
Harris,Nicholas. Leap Through Time: Earthquake (Orpheus,2004). (Orpheus)<%= fn 'amazonで買えないので、出版社へリンク' %>
Scagell,Robin. Night Sky Atlas (Dorling Kindersley,2004).(amazon)
Walker,Richard. Kingfisher Knowledge: Microscopic Life (Kingfisher,2004) .(amazon)
Winston,Robert. What Makes Me, Me? (Dorling Kindersley,2004).(amazon)
アヴェンティス賞は毎年前年に発表されたサイエンス分野のノンフィクションに対して与えられる賞で、サイエンスライティングでは最も権威のある賞のひとつ。
去年の受賞作 Bill BrysonのA Short History Of Nearly Everything(amazon)は大変面白かったので、今年も期待。
日本にもこういうアワードが必要だと思います。
[clip]Daily ClippingGround telescopes to 'super-size' (BBC)
ESOが計画している口径100mの超巨大望遠鏡の話。わはは、こういうの大好き。
100mの主鏡は直径1.6mの鏡を3048枚組み合わせて作り、副鏡は直径25.6mで216枚の組み合わせ、補正鏡は、8mが2枚に4mと2.4mが一枚づつ。NAOのすばる望遠鏡の「主鏡」が8mだからその規模が知れるというもの。
気になる予算は、1000Mユーロ、日本円にして1400億円。お、意外と少ないな。イージス艦1隻分ぐらいか。ねぇねぇ、ミサイル護衛艦なんて要らないから、こっち作ろうよ。<%= fn 'ちなみに、すばる望遠鏡の建設費用は400億円' %>
世界の大型望遠鏡については以下を参照のこと。
Astronomy - The Hitch Hiker's Guide to Science (h2gs)
h2gsのAstronomyカテゴリの望遠鏡関連項目はdtomono氏のおかけでとても充実。owlももちろん載ってます。
. Date: 20050414 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingすばる望遠鏡、最も重元素の少ない星を発見 ?第一世代星の元素合成に迫る? (NAO Subaru Telescope)
これまで見つかった中で、最も鉄の含有量の少ない星が見つかった、というお話。
鉄は恒星内部でしか生まれない。そして恒星の死→新たな星の誕生を繰り返す中で、鉄はどんどん蓄積されていく。鉄の含有量が少ないということは、宇宙が誕生してからほとんど世代を経ていないことを示している。今のところまだ議論が分かれているけど、第2世代の星である可能性が高いとのこと。
お、YOMIURIが記事にしてますね。でも...
130億歳=銀河系最古の星、国立天文台などが発見 (YOMIURI)
んー、センセーショナルにしたいのは分かるけど、「銀河系最古」はちょっと言いすぎ。第一世代の超新星から、鉄含有量の少ない星が生まれるメカニズムが分かっていない以上、鉄の含有量がそのまま星の古さを表すとは言えないはず。この結果からは「とても古い」ということは分かるけど、一番古いかどうかは分からないんじゃないかな。
そんなことより、この星の組成が他の低金属星と違って炭素の含有量がとても多いというところが注目すべき部分(地味だけどな)。鉄の含有量が少なく炭素の含有量が多い星が生まれるメカニズムが分かれば、生まれたばかりの宇宙がどんな様子だったか分かるかもしれない。
Autonomous military satellite to inspect others in orbit (NewScientist)
アメリカ空軍が昨日(4/13)打ち上げたXSS-11の話。この衛星は軌道上で衛星を修理するための技術を実証するための実験を行う。
軌道上で衛星を修理したり燃料を最充填できれば、衛星の寿命を飛躍的に延ばすことができる。さらに、この衛星は「自分で考えて」行動する能力を持っていて、「行け!XSS-11」と命令すれば、自分で考えて目標衛星とランデブーするそうな。
この前NASAが同じような目的でDARTSという衛星を上げていたけれど、軍も同じような研究をしているということですね。まあ、軍事衛星は軌道も低くて頻繁に軌道修正する必要があるため、燃料の消費が多くて寿命が短いから、この技術に注目するのは当たり前といえば当たり前の話。でも、小さく(みつかりにくい)、自分で動く(余計な通信がいらない)この衛星は、敵国の衛星を行動不能にするのにもとっても便利だったりする。
Prepared Statement of NASA Administrator Nominee Michael Griffin (SpaceDaily)
NASAの時期長官に任命されたマイケルグリフィンの議会演説。「えーと、いろいろやることはあるけど、がんばりまっす」という内容。
「やること」は以下のとおり。
-シャトルを安全に運行させます。ま、2010年までには退役させるけどな。
-その後、次の有人機をなるべく早く就役させます。
-「有人での宇宙探検」を目標に、宇宙関連、航空関連、科学研究のバランスをとります。
-みんなと協力して、国際宇宙ステーションを完成させます。
-民間の宇宙開発事業との連携を推進させます。
-火星やそれ以外の惑星へ行くことを念頭において、とりあえず月へ行くぞ。
前長官のオキーフ氏は、くちゃくちゃで無駄の多かったNASAを立て直すために、その財務管理能力を買われてブッシュが送り込んだ人物。予算の縮小とそれに伴うリストラを着々とこなしていたが、コロンビアが事故を起こし、彼のもくろんでいた「NASAの建て直し」は予想もしなかった形で成就することになった。
で、オキーフさん、事故のごたごたもひと段落し、そろそろ役目も終わりかなと思ったんでしょうね。「子供の学費が払えないから、もっとお給料のいい仕事をします」といって、ルイジアナ大学の学長になっちゃった(そ、そんなに給料安いのかNASAの長官って)。
そんなオキーフ氏の後釜に雇われたこのグリフィン氏はバリバリのエンジニア。リストラはすんだから今度は技術畑の人を雇って「月へ行くぜ!」というわけですね。
関係ないけど、最初にこの人の写真を見たとき、「びりー・くりすたる?」と思ったのは本人には内緒。
「科学しよう」第一回 ? すばる望遠鏡で科学しよう ? (NAO)
最先端の科学施設を訪問し、最先端の研究の参加するというイベント「科学しよう」の第一回は『すばる望遠鏡』。すばらしい!といいたいところだけど...がぁ、なんで高校生対象なんだー!大人だって科学したいぞー!
Look out for giant triangles in space (NewScientist)
地球外知的生命体探査(SETI)の新手法に関するお話。異星からの電波に耳を澄ますなんてまどろっこしいことをしてないで、太陽系外惑星の軌道上にある巨大な人工物を探した方が早いぜ!ということらしい。
どうやら、次世代の宇宙望遠鏡の性能を持ってすれば、太陽系外惑星の軌道上にある惑星サイズの「あからさまに三角」とか、「どうみても四角」だったりする物体を検知することができるかも、ってことみたい。
Moon images reveal bright spots for lunar base (Nature)
月に基地を作るならどこがいいか?という話。
月は自転軸に対して、1.5度しか傾いていないために、一年中ずーっと太陽の沈まない場所がある。将来、月に恒常的な基地を作るならここがよかろう、という話。その場所は、月の北極にあるピアリークレーターの尾根にある。ここなら、太陽は常に地平線上にあり、決して沈まない。気温は一年を通じて-50度ぐらい、寒すぎもせず暑すぎもせず、とてもいい「気候」らしい。
Polymer sniffs out explosives (Nature)
従来の30倍もの検知能力を持った「爆発物検知物質」が作られた、というお話。このポリマーは紫外線で励起しておくとレーザーみたいに光を発する。でも、近くにTNTがあるとその分子がポリマーにくっついて光が出なくなる。これの性質を利用して爆発物を検知するらしい。
でも、まだ犬にはかなわないみたい。「将来的には、犬並みに」だそうな。
人類の広がりをDNA分析で調査する「ジェノグラフィック・プロジェクト」 (NationalGeoglaphicJapan)
数十万人のDNAを分析して、人類がどこで生まれどう広がって行ったかを明らかにしよう、というプロジェクト。100ドル弱だせば、誰でも参加できる。
うー、試してみたいけど、一万円かぁ。
. Date: 20050416 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review 更新ある人々とお酒を飲んだ(それはたまたま、会社の上司だったり、その奥様だったりするけれど、とりあえずそれは関係ない)。とてもいい夜だった。あんまりいい夜だったので、忘れないうちに書いておこう。若干アルコールが入っているので、筆がつるつる滑っているけれど、まあ、いいや。たぶん、明日になったら書けないと思う。
. Date: 20050418 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingNASA Launches DART Spacecraft to Demonstrate Automated Rendezvous Capability (SpaceRef)
NASAは地上からのコントロール無しで、自立的にターゲットとランデブーを行う実験衛星を打ち上げました(これは先日紹介したXSS-11とは別の衛星)。
NASA Tracks Navigation Errors, Fuel Shortage in DART Rendezvous Mission (SPACE.COM)
が、うまくいきませんでした。どうやら、ガス欠だったみたい。くぅー、残念。ミッションコントロールでは、燃料タンクが本当に空っぽになる前に軌道を変更。10年以内に大気圏に突入する軌道に乗せられたそうです。
DARTは実験機ですから、打上げの失敗ならともかく、「失敗→成果なし」ではありません。うまくいかなかったということは、予想外の何かかが起きていたということです。その原因が分かれば次はもっとうまくいくでしょう。それでいいんです。
Fear of reprisals - NASA LANGLEY PILOTS STRUGGLE WITH SAFETY VERSUS SILENCE (Daily Press)
NASAは本当に変わったのか?というお話。NASAの中にはまだテストする機体の安全性について議論するのがはばかられる風潮があるかもしれないそうな。うーむ。
ただ、注意すべきはこのお話の中心になっているGerry Brown氏が首を切られたのは2年前。これはコロンビア事故による改革の前です。彼は「まだ変わってないよ」と主張していますが、本当のところはこの記事からはあまり分かりません。ただ、人の気持ちというのは早々変わるものじゃないでしょう。仕組みはともかく「安全を問題にすると首を切られるかも」という恐怖感はもしかしたら抜けていないかもしれません。
Future spacecraft to carry 'black boxes' (NewScientist)
ロケットや宇宙船に、飛行中のデータを記録し、再突入にも耐えられるカーボンファイバーで覆われた「ブラックボックス」を積もう、というお話。賛成!このブラックボックスは30cm四方で1kg。1gでも軽くしたいロケットにとってはそれなりのコストだけれど、コロンビア事故で、オンボードの記録があれだけ事故原因の解明に役立ったことを考えれば、払う価値のあるコストだと思います。
. Date: 20050421 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingシャトル打ち上げ再開は独自判断で 新長官会見 (mainich-msn)
いや、そりゃまずいでしょ、グリフィンさん。せめて委員会が答えを出すまで保留できなかったのかな?現場の士気が下がったりしてるんだろうか。あるいはもっと大人の理由かしら?あの事故の後で外部機関による監査が強調されていたのに、就任直後にそれを反故にするような発言はどうかと思うなあ。うーむ。
プレスキット - JAXA STS-114 (JAXA)
来ました!STS-114のプレスキットの日本語訳です。わーい。
大入り満員!第24回宇宙科学講演と映画の会 (JAXA/ISAS)
イベントで使用されたプレゼン資料が公開されています。どちらもすばらしい資料。
実は、この間このイベントに行ってきました。えーと感想は「ものすごく面白かった!!!」的川教授のペンシルロケットの話もよかったけれど、井上教授のX線天文学の話はかなりどきどきしました。関東近辺にお住まいのかたがた、もし機会があればぜひ参加されることをおすすめします。こんな公演が電車賃だけで見られるなんて!
この公演の中の一連の3枚のスライドに目からうろこが落ちたので、再現するべくチャートを書いていたけれど公開されてしまった。がーん。その3枚というのは、これとこれとこれ。この3枚で天文学者たちが「何を使って、何を、どうやってみようとしているか」がすっぱりと分かる。
まあ、作っているのはこの3枚をマージしたものなので、それはそれで役に立つかな。
. Date: 20050422 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 観測機材、大気による電磁波の吸収、観測波長、温度、天体現象の相関図http://www.lizard-tail.com/isana/tmp/spectrum_050422.png
2005.04.21の日記に書いた、「目からうろこが落ちるチャート」。
まだあちこち怪しいところがあるけれど、とりあえず公開。
手前味噌ながら、なかなか面白いチャートになったと思う。
え、面白くない?うろこ落ちない?...はい、解説書きます。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20050510 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryおくさんに「ぶんどき」と「さんかくじょうぎ」をかってもらった。わーい。
つかいかたをかんがえているだけでわくわくするよ。
なんにつかおうかな。
2005.04.22のエントリで書いた「目からうろこが落ちるチャート」の解説文。時間がかかったわりに、なんだか取りとめのない文章になってしまった...
ちなみに、チャートを書くのに使ったのはExpression3。ドローとペイントをあわせたような変なソフト。とてもおもしろい。
以前は別な会社からパッケージソフトとして売られていたけれど、いつの間にかマイクロソフトに買われてフリーウェアになっていた(ダウンロードにユーザー登録が必要)。Mac版はそのままでも日本語が通る。Win版は同じくMicrosoftが配布しているMicrosoft AppLocale UtilityというツールでLocaleをUnicodeにして起動すると日本語が通るようになる。
On detecting terrestrial planets with timing of giant planet transits(astro-ph via SpaceRef)
すでに発見されている系外惑星が恒星の前を通り過ぎるタイミングを計測することで、同星系の地球サイズの惑星を検出できるかもしれない、という論文。おぉ、これはできそうな気がするぞ。過去のデータにすでに実例があったりしないかな?
Buying time through 'hibernation on demand (SpaceRef)
ネズミを冬眠状態にする方法が発見された、というお話。哺乳類での成功は初めて。
「つまり、われわれが発見したのは、本来恒温動物であるネズミを、一時的に変温動物にする方法なんです。これは冬眠中の哺乳類に起きているのとまったく同じ現象です」ぎょー、すげー!硫化水素を80ppm含む空気中にマウスを曝すことで冬眠を引き起こしたとのこと。
「すわ、宇宙旅行に!」なんてつい思ってしまうけれど、それ以前に、代謝を極めて低く保てるため、救急医療や臓器移植に適用することが考えられているみたい。
それから、がんの治療に効果があるかもしれない、とのこと。がん細胞は成長に酸素を必要とせず、正常な細胞に比べて放射線への耐性が高い。そのため、高い放射線を当てると、がん細胞を死滅させる前に周辺の正常細胞が死滅してしまう。もし細胞を冬眠状態にすることで正常な酸素の供給量が下げられれば、高い放射線でも細胞が傷つきにくくなる。ということらしい。ほー。
でも、硫化水素って毒ですよねえ...火山性ガスの「卵の腐ったようなにおい」が確か硫化水素だったと思う。。80ppmぐらいなら大丈夫なのかな?
. Date: 20050512 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary プラネタリウムを見たひょんなことから、名古屋でプラネタリウムを見る。「年間来場者数日本一」を誇る名古屋市科学館のプラネタリウム。ここの特徴はなんといっても「生解説」。解説員の方が操作をしながらリアルタイムで星空の解説をしてくれる(流れは決めてあるけれど、台本は一切ないそうな)。
その昔舞台関係の仕事をしていたこともあって、つい裏方の目で見てしまうので、純粋な観客としての評価ではないけれど、なにより「見ている人間の想いを邪魔しない絶妙な間」に感動する。見ている人を素人扱いせず、解説することと解説せずにお客さんにゆだねるところのバランス感覚が絶妙だった。
投影中、お客さんと解説員の方の直接のやり取りはまったくなかったけれど、「そうそう、インタラクティブってこういうことだよ」と思う。
「ボタンを押しました、はい何か動きました」なんていうのは、インタラクティブでもなんでもない。ユーザー興味や関心を引き出す、それをふくらます、それに答える。こういうプロセスの中で、コンテンツとその受け手は実に濃密な「会話」を交わしている。この「会話」のないものはインタラクティブとはいえない。この「会話」を支えているのは「言葉の選び方」とか「間」とか「距離感」といったどうにもあいまいなものだ。誤解を恐れずにいえば、実はユーザーがボタンを押せるかどうかは、そのコンテンツの「インタラクティブ性」とはまったく関係がない。
ユーザーからの物理的なインタラクションが一切ないごく普通のプラネタリウムが、並みの体感ゲームが束になってもかなわないようなインタラクティブ性を発揮することだってある。
あのプラネタリウムの中で、僕は50分間たっぷり星空と会話を楽しんだ。なかなか得がたい体験だと思う。
. Date: 20050520 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingNew Monkey Species Discovered in East Africa (NationalGeographic)
アフリカで新種のサルが見つかったというお話。発見されたのは霊長類オナガザル科マンガベイ属の新種。アフリカで新種のサルが発見されたのは20年ぶり。この発見はまったく異なる二つのチームによって行われた。
一つ目のチームは、Tim Davenport率いるWildlife Conservation Society (WCS)のチーム。彼らは2003年1月、地元の人々にkipunjiという名前で知られるサルの話を聞いて調査を開始。同年5月と12月に観察に成功し新種と特定。
もうひとつのチームは、Udzungwa Mountains National ParkのTrevor Jonesを中心とするグループ。彼らは2004年7月、絶滅しかかっているサンジェマンガベイを調査するためのプロジェクトに参加中、探しているサルとはまったく別の種類のサルを発見、新種と特定した。
NASA Competition to Get Air from Lunar Soil (UniverseToday)
NASA Announces New Centennial Challenge (NASA)
月の土壌から酸素を作り出す方法を開発したら賞金25万ドル、というNASA主催のMoon Regolith Oxygen challenge (MoonROx) のお話。
月の土を模したJSC-1と呼ばれる物質から8時間以内に5kgの呼吸可能な酸素を取り出す、機器の重さは25kg以内、必要とされる電力にも制限がある。タイムリミットは2008年6月1日。腕に覚えのある型は試してみては?
でも、25トンあったJSC-1のストックはもうなくなった、という話を聞いたような気が...
http://www.lpi.usra.edu/meetings/roundtable2004/pdf/6023.pdf
このリリースを読む限りは、目下JSC-2を作成中と書いてあるけど、どうなったのかな?
Mars Global Surveyor Sees Mars Odyssey and Mars Express (NASA)
火星の軌道上を周回しているマーズオデッセイとマーズエクスプレスが、同じく火星軌道上のマーズグローバルサーベイヤーの撮影に成功、というお話。他の惑星の軌道上で、他の宇宙船の撮影に成功したのはこれが初めて。
JAXA 宇宙教育センター (JAXA)
JAXAが蓄積してきた知識やリソースを教育活動に利用することを目的に、5月1日付で設立された『宇宙教育センター』の公式サイト。的川泰宣氏の夢がまたひとつ実現しましたね。サイト上でも積極的に情報発信などが行われていくそうな。とても楽しみ。
日本の宇宙ジャーナリストの雄、松浦晋也氏の新刊が2冊続けて出るらしい、楽しみ。
『スペースシャトルの落日~失われた24年間の真実~』(amazon)
『恐るべき旅路 ―火星探査機「のぞみ」のたどった12年―』(amazon)
お、『スペースシャトル?』は今日発売だ。
そういえば、あの人は何やっているんだろうと思って調べてみたら...わー、新刊だ。また、狙っているとしか思えないタイミングだよ。しかし、このタイトルは...うーむ。
. Date: 20050523 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]松浦晋也『スペースシャトルの落日~失われた24年間の真実~』エクスナレッジ(amazon)日本を代表するロケットジャーナリスト松浦晋也氏によるスペースシャトル本。スペースシャトルがどこで間違い、その結果としてアメリカのみならず世界の宇宙開発がどんな影響を受けてきたのかについて、きっちりとまとめられている。有人宇宙飛行の今がどうなっているのかを知る上では最良の本だと思う。
ただ、不満がないでもない。
ひとつは、何でもかんでもスペースシャトルのせいにしすぎてないか?ということ。
「そろそろ目を覚まして次に行こうよ」というせっかくの主張があまり目立たず、スペースシャトルさえ無ければ宇宙開発はもっとうまくいっていたのに...という愚痴しか聞こえてこないのはとても残念。たとえば、打上げ機に事故があったり仕様変更があれば、打上げ予定が延びるのは当然。アリアンだってH2だって同じことがおきている。それをスペースシャトルが欠陥だったばかりにみんなが迷惑した!とあげつらうのは、ちょっと言い過ぎじゃないかな。
それでも、僕はシャトルはそれほど悪い仕事をしたとは思わない。まったく視点を変えてみれば、スペースシャトルは2回しか失敗していないともいえる。試作段階から今まで100回以上のミッションをこなして軌道投入に失敗したのが1回、大気圏突入に失敗したのが1回。事故で人命が失われているという事実に目をつぶるなら(つぶるべきじゃないのは重々承知だけど)、これは打上げ機としてはかなりいい成績じゃないか?
無理のある設計、無理のある運用、コストに対する締め付け、安全性に関する軽視...そういう条件の下で24年間飛ばし続けられたにもかかわらず、ミッション成功率98%というそれなりの成績を収めているプロジェクトを「虚妄」の一言で切り捨てるのはどうかと思う。
もうひとつは、本書で紹介されている「一人乗り宇宙船」<%= fn '一人の乗員を24時間軌道上にとどまらせることを目的とした一人乗りカプセルと小型で安価な打ち上げロケットによる打ち上げシステム' %>について。
ぼくは「ふじ」が提唱されたとき、心からすばらしいプロジェクトだと思った。発展性があり、実現の可能性があり、そしてなによりわくわくするプロジェクトだったからだ。でも、今回の本で紹介されている「一人乗り宇宙船(ピッコロ/スニーカー)」には賛同しかねる。いや、わくわくするよ。あれはぼくが子供の頃夢に描いていたロケットそのものだ。ぼくだって一機欲しい。いやほんとに欲しい。でも、だからこそあの「一人乗り宇宙船」には違和感を覚える。だって、あれはロケットマニアの願望そのものだもの。思考実験としてはとても面白いけれど、日本の宇宙開発が目指すべき未来像として提示するにはちょっと無理があると思う。なにしろ、「ピッコロ/スニーカー」は、宇宙に行って何をするのかという問いに全く答えてくれない。
松浦氏は繰り返し「いまできることから始めよう」と言っているけれど、なぜ彼が本書で商業宇宙飛行に関して一言も触れなかったのか、僕には不思議でならない。「誰もが宇宙にいける」という未来を想定するなら、間違いなくSpaceShipOneとVirgin Galactic <%= fn '知らないうちに日本語サイトができてる!' %>はその未来に一番近いところにいる。「弾道飛行なんて宇宙に行ったことにならないよ」「パック旅行なんてつまらない」と笑い飛ばすのは簡単だ。でも、彼らは誰もが宇宙に行くために、何から始めなきゃいけないかをよく知っている。彼らはいきなり軌道周回飛行を目指すのではなく、弾道飛行を実用化することから始めた。彼らはまず、自分たちの宇宙船にお客さんを乗せて飛ばすために、安全基準をどうすべきかFAAと検討することから始めた。これこそ「いまできることから」の好例じゃないだろうか。
宇宙に行きたいと思っている人が、みんなロケットの運転手になりたいと思っているわけじゃない。「いつか誰もが宇宙にいけるように」という目標を立てるのなら、最初に目指すべきは「庭から打ち上げられる僕のロケット」じゃないと思う。
. Date: 20050525 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 距離が遠くても天体の見かけの大きさがそれほど変化しない理由※下記の内容は、誤りを含んでいる可能性があります。以下のエントリを参照してください。
http://d.hatena.ne.jp/isana/20050615/p1
少し前に、マツドサイエンティスト・研究日誌の『遠近法が通用しない!?』というエントリが話題になっていました。
遠くに行けば行くほど小さく見えるのは、50億光年位までで、それ以上遠くなっても、物は小さく見えなくなる
えええええ!マジですか!宇宙の曲率?後退速度の相対論的効果?
と、かく言う私も目ン玉が飛び出るぐらいびっくりしたんだけど...
でも、よーく考えてみると、天体の見かけのサイズは距離に反比例しますよね。
反比例のグラフはもともとこういう形をしているんじゃないでしょうか。
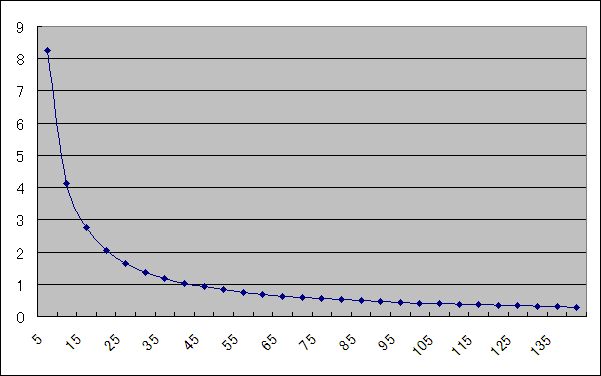
これは、直径10万光年の天体<%= fn 'ちょうど銀河系と同じぐらい' %>の見かけのサイズを以下の式で計算したもの。
θ = atan ( r / d ) * 2
縦軸が見かけのサイズ(秒角)、横軸が距離(億光年)。
つまり、これは「ある程度の距離になると、それ以上距離が広がっても視線角度はほとんど変化しない」というごく当たり前の遠近法では?
じつは、ここ数日、宇宙論的赤方偏移の値が「距離による空間の歪曲の率」を表すことに気づいて、おぉ!これであの「遠くのものが小さくならない現象」が計算で導けるのでは、とExcelを弄り回していたのです。
で、勢い込んでグラフにしてみたら、偏移はグラフの形にはほとんど影響しない。そりゃそうだよ、赤方偏移と距離は比例するんだからその分を上乗せしてもグラフの形は変わらない。
そこで初めて、「遠くのものは小さく見えるけど、決して見えなくなることはない」という当たり前の事実に気づいたのでした。<%= fn '嘘だと思ったら、外に出て等間隔に並んでいる電柱かなにかで確かめてみてください' %>。
ちなみに、宇宙論的な空間の歪曲を考慮した(と思われる)「天体の見かけのサイズのグラフ」は以下のとおり。
http://www.lizard-tail.com/isana/tmp/virtual_height2.jpg
傑作。一機の探査機が計画され、紆余曲折を経て設計・製作に至り、打上げのときを迎え、軌道上で思わぬトラブルに見舞われ、それでもなおエンジニアの懸命の努力によって延命し、最後の最後、あと一歩というところで目標の軌道への投入に失敗、プロジェクトの断念が決定される。そのプロセスを克明に追ったルポ。
読後、震えるような感動を覚えた。
ひたすら地道な取材と調査、そしてなにより当事者の言葉を丁寧に丁寧に拾いながら、この極めて複雑で長期にわたるプロジェクトの全貌を描き出した作者の努力と力量には、ただただ頭が下がる。
日本のノンフィクション史に残る傑作だと思う。いや、まじで。
. Date: 20050527 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Open Planisphere「4.5等級以上の星」と「土星より内側の惑星」がすべて入ったのでβへ移行。
これで「機材を必要とせず、あまり遠出をしなくても見られる夜空」を表示するのに必要な要素が全部揃ったことになる。
現在、赤経、赤緯の指定でマーカーを表示する機能を実装中。
インターフェイスに加わった探査機の表示はこの機能のテスト用に組み込んだもの。
OpenPlanispere作業中に、ずーっとまえに書いた『此処から一番遠い場所』の記述に誤りがあることが発覚。ぎょー!
「向かっている方向」と「今見えている位置」は当然違う。この両者を混同するような書き方になっていたのを修正。ごめんなさい。
ちなみに、本来は、あまり古い文章を修正することはしないんだけど、あの文章に関してだけは、文章の内容を含めて定期的にメンテナンスをしている。なにしろ相手は空を飛んでいるので、ほっておくと実際のデータとの誤差が無視できなくなっちゃうのだ。
. Date: 20050531 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingNew Scientist SPACE - International News, Ideas, Innovation
いつの間にか、NewScientistに宇宙関連ニュース専門サイトができていた。すばらしすぎる。
Cost overruns put squeeze on Hubble’s successor (NewScientist)
ハッブルの改修、スペースシャトルの後継機開発、月計画など次期計画が大きくなるにつれ、次期ハッブルであるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の予算が圧迫されるかもしれないというお話。しかもNASAが「うちのアリアン5で打上げへん?」というESAの申し出を断れば、更なる予算増につながる。まあ、予算が限られている以上何かを削らなきゃいけないのはわかるんだけど...
実はハッブルは冷却能力が低いので赤外線領域が苦手。後継機であるジェームズウェッブはこのあたりが改善されて、現行の宇宙赤外線望遠鏡スピッツアーがカバーできていない近赤外線領域での観測ができるようになる。予算への圧迫が性能を犠牲にしないといいなあ。
'Slime worlds' may reflect signs of life (NewScientist)
地球外生命を見つけるには「泥まみれの星」を探すのがいいかもしれない、というお話。
少し前まで地球は、藻類やバクテリアや粘菌に覆われたぐちゃぐちゃ、ぬちょぬちょした星だった。宇宙に生命を探すならこういう星を探すのがいいかもしれないということらしい。植物や微生物は近赤外線領域のある波長域をとてもよく反射するので、これを検知すればいい。赤外線で見ると植物は可視光領域の金属並みの反射率を持っているそうな。
とはいうものの、記事中でも指摘されているように、必ずしも地球外生命が光合成をしているとはいえないし、逆に他の理由で近赤外線領域の光を反射しているかもしれない。この波長にピークが見つかれば生命活動の可能性があるとはいえるけれど、その証拠とまでは行かないというのが結論。うむむ、いまだ決定的な方法はない、という感じですね。
Printing press spells out bugs' behaviour (NewScientist)
半導体を作るのに使われる、フォトリソグラフィという「印刷技術」を使って、生きたバクテリアをフィルム上に「印刷」する技術が開発されたというお話。
これができると何がいいかっていうと、バクテリア同士の相互作用を研究するときに、実験の環境の再現性がとても高まるので、かなり厳密な評価ができるようになる。これまでにも、仕切りを使ってバクテリアをあるパターンで配置することはできたけれど、厳密に同じパターンを作り出すことはできなかったんだそうな。
NASA Sees Orbiting Stars Flooding Space With Gravitational Waves (SpaceRef)
チャンドラX線望遠鏡が、白色矮星の連星が重力波を発している間接的な証拠を検出したというお話。今回発見された連星系はかなり大きな重力波を発生していると見られ、将来的に重力波検出の有力候補になるかもしれない、とのこと。
これはこれまでも知られていた現象で、重力波が出ていると連星系はその分エネルギーを失なって公転周期がわずかづつ短くなる。この公転周期の減少は重力波理論が予測する値と観測値が一致していて、重力波が存在する有力な証拠のひとつとなっている。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20050601 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Science Podcast最近流行のPodcastに手を出す。理由は聞きたかった海外のラジオ局のサイエンス関連番組が、いつの間にか軒並みPodcastに対応していたから。
え、ネイティブの英語を聞いて分かるのかって?ほとんど分かりません。わはは。
ただ、トランスクリプト(放送を文字に起こしたもの)が用意されているプログラムも結構あるから、それを眺めながら聞いていればなんとかついていける。トランスクリプト無しで内容がなんとなく理解できるのは、その内容を知っているときだけ。あとは単語を拾いながら「あー、DNAの話?」「ダークマターとか言ってるから、きっと宇宙論の話をしているに違いない」ぐらい。
でも、すごく面白いよ。
ラジオ番組のPodcastからおすすめをいくつか紹介。ちなみに下の番組を全部聞くと1週間で約7時間、ファイルサイズで約100M overになる。
Feed: http://www.sciencefriday.com/audio/scifriaudio.xml
アメリカのNPRラジオのサイエンス系ラジオ番組。週1回、Part1と2に分かれていて、それぞれ1時間弱。Poscastでもファイルが分かれているので注意。サイエンス関連ニュース、サイエンティストへのインタビュー、視聴者との質疑応答など。何を隠そう、Podcastに手を出したのはこの番組がPodcastに対応したから。
WebSite: http://www.sciencefriday.com/
プログラムのサマリーと関連情報へのリンクを掲載。
Feed: http://www.abc.net.au/rn/podcast/feeds/science.xml
オーストラリアABCラジオのサイエンス番組。週1回約1時間。短いインタビューをつないでいくような構成。
WebSite: http://www.abc.net.au/rn/science/ss/
一部のコーナーを除き、ほぼすべてのトランスクリプトが閲覧可能。
Feed: http://www.twis.org/audio/podcast.rss
こちらはUC Davisのラジオ局KDVSのサイエンス番組。週1回約1時間。その週のサイエンスニュースの紹介とインタビューが半分づつ。この分野でキャスターが女性なのは珍しいかもしれない。きゃらきゃらと楽しそうに話しているのが印象的。聞いていてとても楽しい。
Website: http://www.twis.org/
トランスクリプトなし。サマリーらしきものは載っているけれど、ほとんど役に立たない。注目はキャスターのBio。どうやら彼女はオルデラン生まれらしい。まさかレイア姫と同郷だとは思わなかったよ。
Feed: http://www.groks.net/groks.rss
こちらはUC Berkeleyのラジオ局KALXのサイエンス番組。週1回約30分。メインはゲストへのインタビュー、有名科学者もしばしば登場する。
Website: http://www.groks.net/
最新のものはゲストとプログラムの内容ぐらいしか載っていない。ただ、一部過去のプログラムについてはトランスクリプトが公開されている。
Feed: http://www.cbc.ca/quirks/quirks.xml
カナダCBCラジオのサイエンス番組。週1回30分。カナダで20年以上続いている科学ラジオ番組。サイエンスニュースとインタビュー。
Website: http://www.cbc.ca/quirks/
各回サマリーと関連情報へのリンクを掲載。
Feed: http://www.gigadial.net/public/station/11253/rss.xml
宇宙開発専門ラジオ番組。週2回それぞれ約1時間?1時間半。
Website: http://www.thespaceshow.com/
各回長めのサマリーを掲載。
こちらは、Webサイトの記事をCastしているもの。短くて、ちゃんとトランスクリプトがあるので英語の勉強にいいかもしれない。
Feed: http://science.nasa.gov/podcast.xml
NASAの一般向け科学啓蒙サイト。ここはずーっと前からすべての記事の朗読ファイルをmp3で提供していたんだけど、このたびPodcastに対応。当然すべての記事にトランスクリプトがある。放送時間は約10分。月1回ぐらいのペース。
Website: http://science.nasa.gov/
Feed: http://universetoday.com/audio.xml
有名な宇宙関連ニュースサイト。Castされているのはインタビュー記事だけ。もちろんトランスクリプトが読める。
Website: http://universetoday.com/
. Date: 20050607 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary DARPA Grand Challenge 2005昨年も行われた、米国国防省研究開発部門DARPAが主催する完全自立型ロボットカーによる自動車レース『DARPA Grand Challenge』が今年も行われます。優勝賞金は去年の賞金が持ち越され200万ドルになっています。つい先日、5/2?5/15に掛けて行われた、各チームが実際にデモンストレーションを行うサイトビジットの結果を受けて、エントリーした118台からセミファイナリスト40台が選ばれました。今後、出場チームは9/27?10/6にカルフォルニアスピードウェイで行われるセミファイナルで20チームに絞られます。
最終レースは10/8 LAとラスベガスを結ぶ約250kmの「とあるルート」を使って行われます。詳細なコースはレース当日2時間前に発表され、事前にコースをプログラムしたり、試走することはできません。コースは砂漠などの荒地を含み、単なるナビゲーションだけでなく障害物の回避やトラブルに対するリカバリー能力などかなり高度な技術を必要とします。このコースを10時間以内に、外部からのコントロールがまったくない状態で走破するのがレースの最終目的です。去年は全車ゴールに達することなくリタイア。トップの成績のカーネギーメロン大のチームもたった12kmしか走れませんでした。
ちなみに、参加資格は「チームリーダーが21歳以上で大会当日に米国国籍を持っていること」、逆に言えば、チームリーダーがこの条件を満たしていれば、海外国籍の人間でも参加が可能ということです。
[http://www.darpa.mil/grandchallenge/:title=DARPA Grand Challenge]
※上記サイトは、特定のIPないしドメインからのアクセスをどうやらアジア方面のIPアドレスを弾いているようです(プロバイダからのアクセスが蹴られるようです)。どうしても閲覧したい方は海外設置のプロキシサーバを利用してください。
優勝候補はやっぱり去年の優勝車カーネギーメロン大のRed Teamでしょうか、今年は出場車両を2台に増やしてやる気満々です。一方去年2番手のSciAutonicsは台数を減らし1台での出場ですね。去年話題をさらったロボットバイクBlue Team、現役高校生チームPalos Verdes High School Road Warriorsも健在です。
新規出場では、なんと言ってもロボット研究のもうひとつの雄、スタンフォード大のStanford Racing Teamが要注目ですね。
去年のファイナリストのサイトを見る限りでは、各チームとも相当レベルを上げているような感じです。今年はどこまで行くでしょうか?
主催者の素性を見れば分かるように、このレースは軍事技術の基礎研究の一部として位置づけられています。コンペティションで技術競争を促進し、軍用目的で利用できる技術の芽を育てることが本来の目的、という感じでしょうか。ただ、DARPAのフィールドは軍事に直結した技術というよりも基礎技術や将来技術開発が主で、民間の研究機関や大学などともかなり密接な協力関係を持っています。そうそう、インターネットの原型になったといわれるARPANETを作ったARPAは今のDARPAの前身です。
括弧がついているのが昨年のファイナリスト、括弧内は最終順位
Axion Racing(6)
Blue Team(15)
CIMAR(9)
Gray Team メンバーの中心はThe Gray Insurance Companyのオーナー
Intelligent Vehicle Safety Technologies I
Palos Verdes High School Road Warriors(10)
Red Team (1) 去年は一台のみ出場
Red Team Too (1)
SciAutonics/Auburn Engineering(2)(10) 去年は2台出場
Team Caltech(3)
Team DAD(4)
Team ENSCO(8)
Team TerraMax(11)
Team UCF(16)
Terra Engineering (13)
Virginia Tech Grand Challenge Team(5) 去年は一台のみ出場
. Date: 20050608 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingInside Tornadoes Multimedia @ National Geographic Magazine (National Geographic)
竜巻の中心部からの映像。す、すごい。
Martian methane could come from rocks (Nature)
火星の大気中のメタンはカンラン石によるものかもしれないというお話。以前、火星の大気からメタンが発見され、もしかしたらバクテリア由来のものかも、なんていうニュースがありましたが、これは「メタンなんてカンラン石でも作れるじゃないか」という反論。カンラン石は、高圧力高熱下で水と二酸化炭素と反応しメタンを生成する。火星大気のメタンはこの反応によるものじゃないの?ということみたい。
ってことは、地中に「カンラン石」と「高温」と「水」と「二酸化炭素」が存在するということかな?だとすれば、少なくともかつては火星にもマグマが存在し、現在でもカンラン石からメタンを生じさせるような熱源が地中にあるということになるなあ。それはそれで大ニュースでは?
Marburg and Ebola vaccine success in monkeys (NewScientist)
マールブルグとエボラ出血熱のワクチンが開発され、マカクザルを使った実験に成功というニュース。まじで!これまでことごとく失敗していたはずだけど...
えーと、どうやらエボラやマールブルグウイルスの表面を構成するたんぱく質を遺伝子操作によって他のウィルス表面に生成させることで、抗体を作り出すことに成功した、ということみたい。なるほど、これならワクチンによってほんとのエボラやマールブルグにかかる心配はないやね。
貨物100トン、シャトル改造で巨大無人ロケットに (読売新聞 via YahooNews)
この計画は、ものすごく既視感があるぞ。っていうかShuttle C?
Shuttle Cは、シャトルの就航当初に予定されていた貨物専用シャトルのこと。予算もついて実物大モックアップも作られたけど、結局ぽしゃった。今回発表された想像図は、当時のものとほとんど同じ。たぶん関係者にしてみれば「荷物運ぶだけなら、あれがあるじゃん」ってとこだと思う。
Definition of a Space Transportation Systems Cargo Element (リンク先はPDF)
日本の宇宙ステーション、セントリフュージ開発中止の懸念 (SpaceRefJP)
えーと、ここにも書いてあるように「日本がセントレフュージを開発してくれたら、代わりに『きぼう』モジュールをただで上げてあげる」という約束になっていたはず。もし、この契約が破棄されるとすると、日本が「きぼう」の打ち上げミッションの資金負担をしなきゃいけなくなるのでは?まあ、全額じゃないだろうけど...
Mission to build a simulated brain begins (NewScientist)
分子レベルの働きまで脳の構造を丸ごとシミュレーションする計画についてのお話。IBMとスイス大学が共同で、脳を丸ごと再現するコンピューター・シミュレーションの開発に着手したらしい。名づけて「Blue Brain」なんてワンパターンなネーミング。科学者はこのシミュレーションによって脳の働きや意識の仕組みが明らかになることを期待しているそうな。
でも、脳をシミュレーションするのは大変だけど、自己意識のあるプログラムなら簡単に作れる。
いや、冗談じゃなく。ウィンドウを閉じる前に少し考えて欲しい。僕たちは自らに自己意識があると主張する物体に、本当に自己意識があるかどうかを判断する方法を持っていない。確かに、このウィンドウに、自己意識が宿っていると考えるのはばかげているけれど、いつか「Blue Brain」が同じメッセージを出力したら。僕たちはどう答えればいいんだろう?
Andromeda Galaxy Three Times Bigger in Diameter Than Previously Thought (Caltech Press Release)
実は3倍の大きさだった、M31アンドロメダ座大銀河 (AstroArts)
ちゃんと測ってみたら、アンドロメダ銀河の周辺に分散していた天体も、アンドロメダ銀河と同期して回転していた、というお話。おぉ!銀河ハロー!ダークマター!おぉぉおぉ!
えーと、この話はものすごく面白いので、あとでちゃんと紹介します。->Junkyard Review 掲載予定
. Date: 20050609 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新昨日、予告していた、「アンドロメダ大銀河のサイズ」に関するお話し。
「銀河の回転」に話題をとどめようと思ったら、なんだか寸止め感あふれる文章になってしまった。
. Date: 20050615 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 遠方天体の距離と見かけのサイズの関係http://www.lizard-tail.com/isana/lab/redshift/redshift-distance.php
以前、『距離が遠くても天体の見かけの大きさがそれほど変化しない理由』というエントリで、マツドサイエンティスト・研究日誌の『遠近法が通用しない!?』というエントリに対して、「普通の遠近法では?」というツッコミを入れましたが、どーしても腑に落ちないので再検討した結果、
遠くに行けば行くほど小さく見えるのは、50億光年位までで、それ以上遠くなっても、物は小さく見えなくなる
という現象がちゃんと起こりうることがわかりました。いい加減なエントリをして申し訳ありませんでした。
距離と見かけのサイズの関係を表すグラフ
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/redshift/distance-size.gif
(紺色の線が実際の値、ピンク色の線は宇宙の膨張を考慮しない値)
っていうか、むしろ大きく見えてるし!
このグラフは、直径10万光年の天体(ちょうど我々の銀河系がこれくらいのサイズ)が、どれくらいのサイズに見えるかを距離に応じてプロットしたもの。青いラインが50億光年ぐらいの所から緩やかな上昇に転じている。これはつまり、50億光年から向こうでは遠ざかれば遠ざかるほどものが大きく見えるということを意味している。
で、なぜこんなことが起きるのか、というのは説明し始めるとものすごく長くなるんだけど、一言でいうと宇宙が膨張しているから。天体から出た光が地球に届くまでの間に宇宙が膨張して、その分だけ星の像が広がってしまうのだ。
. Date: 20050617 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary XMLからWWWサイトを作るPHPスクリプトおまぬけ活動日誌の 簡単にカッコイイWWWサイトを作る道具がほしいに反応。
スクリプト:
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/xml/opml_view.php
データ:
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/xml/data.xml
ソース
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/xml/opml_view.txt
これは、そのむかしWebサイトを作る仕事をしていた頃にRADが欲しくて作ったもの。XMLファイルを読み込んで、Webページもどきを生成する<%= fn 'ここでは、静的なHTMLじゃなくて動的な生成' %>。100行ぐらいの簡単なスクリプトだけど、あっという間にプロトタイプができるよ。まあ、このままフィニッシュワークに持っていくにはちょっと問題があるんだけどね。
このままだとちっともかっこよくないけど、ページごとに別のテンプレートとCSSを指定できるから、やろうと思えばそれなりの見栄えになるはず。
ちなみに、スクリプトの名前にはOPMLの文字が入っているけれど、OPMLは読めない。
本文の見た目をいじれるようにしてみた。
他のスクリプト用に作っていた文字列フィルタをくっつけただけ。
記述ルールは調整中。XMLを手書きするのに一番楽な記法がいいんだけど...
スクリプト:
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/xml/opml_view2.php
データ:
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/xml/data2.xml
っていうか、やっぱりプロトタイピングぐらいにしか使えないや。
. Date: 20050621 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Musical Baton困ったことになった。ずいぶん前に「チェーンメールの性格を持つものは...」と書いてしまった手前、これを他人に回していいのかどうかとても悩んだ。どう考えてもこの企画が誰かに迷惑を掛けることはないような気もするんだけど、そういう問題じゃないし...
実際、僕はこのエントリを書きながらとても楽しい思いをした。kzysさんからこれが回ってきたときはとても驚いたけれど、とてもうれしかった。誰かが僕の思うことに興味を持ってくれていると知るのはすごくうれしい。この楽しさを誰かに分けてあげたいと心から思う。あの人が何を聞いているのか知りたいと思う人はたくさんいるし、バトンを渡せばにこにこと快く受け取ってくれそうな人も5人くらいなら...いるかなあ?でも、いざTrackbackを送ろうという段になってどうしても躊躇してしまう。
最初は、次に渡すつもりがないなら最初から参加しないほうがいいかとも思ったけれど、せっかくTrackbackをもらったのをスルーするのも、やっぱり気が引ける。散々迷った挙句、今回は「エントリは書くけれど次に回さない」という一番ずるい方法をとることにした。本当に申し訳ない。自分でもなんと無粋で身勝手なという気がするけれど、どうかお許しを。
せっかくだから普段書かないことを書いてみよう。
平均して3G?4Gぐらい。容量を食っているのは、オーディオブックや宇宙開発関連のサウンドファイル、PodCastの過去ログ、イベント用BGMのバックアップ。純粋にmusic filesといえるのは1Gぐらい。それもiPod転送用に一時的においてあるだけなので常に入れ替わっている。もともとPCではほとんど音は聞かないし、リッピングしたデータもあまりHDに残さないので、iPodに入っているファイルの方がずっと多い。
THE FUTURE SOUND OF LONDON "We have Explosive" (Wipeout2097)
iPodの中に『Lounge、Electronica、Jazz-Funkのジャンルに属する曲全部』というプレイリストが入れてあって、300曲ぐらいリストアップされている中の一曲。iPodではラジオやオーディオブックじゃなければ、このプレイリストがかかっていることが一番多い。たまたまだけれど、僕が今でもこの曲を聴いていると知ったら、にやっとする友人が何人かいると思う。実は僕が役者として最後に舞台に立ったとき使われていた曲。
Gwen Stefani "Love.Angel.Music.Baby"
GORILLASを買いにいったらCCCDでむかついたのでこっちを買った<%= fn 'なんでiPodのCM曲がCCCDなんだ?理解に苦しむ。' %>。笑ってしまうぐらい良質の80年代Pop。"Harajuku-Girl"はちょっといただけないが...
その時々で気に入った曲はあるけれど、あまり特定のアーティストや曲に執着がないので、5曲選ぶのは難しい。仕方がないので、なんとなくあちこち曲がり角でかかっていた曲を選んだ。この中でいつも聞いているのは最後の一曲(?)だけ。
遊佐未森 "東京の空の下" (桃と耳)
中学・高校時代、おそらく、はじめて「このアーティストが好きだ」と言えるようになったのはこの人。彼女の曲がというより、当時彼女のイメージを作っていたクリエイターチームの世界観が好きだったんだと思う。数多あるなかこの曲を選んだのは、これが僕にとっての最後の曲だったから。いまでも、この曲を聴くたびにもう帰れないであろう場所のことを思い出して、すこし切なくなる。遊佐未森というアーティストは僕にとってそういう場所の象徴みたいな人。今はもうあまり聞かない。
近藤房之介 "Dock Of The Bay" (Unchained Rhythm)
浪人時代中。初めて聞いたとき、なんて楽しそうに歌を歌う人なんだろうと思った記憶がある。彼の歌で人生が変わったりはこれっぽっちもしなかったけれど、今でも、楽しそうに歌う人の曲がその理由だけで好きになってしまうのはたぶんこの人のせいだ。この曲は原曲も大好きだけれど、あの頃予備校の机の上で辞書を片手に歌詞を読んで「はやくこういうじじいになりたい」と思っていた。われながらなんとも青い。でも、やっぱり今でもこういうじーさんにはあこがれる。
Solar Quest "Save the Whale" (Orgship)
これは芝居にうつつを抜かしていた大学時代、唯一の演出作品のエンディングに使った曲。ある著名な作家の作品を無許可で戯曲化して上演したら、原作者の奥様が見に来られて滝のような冷や汗が出たのを覚えている<%= fn 'まあ、いまさら隠すこともないかな。上演したのは池澤夏樹氏の『スティルライフ』' %>。もう今では手に入らないかもしれない。別にどうということも無いアンビエントテクノだけれど、去年あるイベント用に選曲していたときにこの曲を聴いて泣きそうになったのは内緒。
RCサクセション『いいことばかりはありゃしない』(PLEASE)
自分から進んでは行かないけれど、ごくたまにカラオケに連れて行かれると清志郎を歌う。好きだからなのもあるけれど、なぜか「受ける」からだ。どうやら歌声がよく似ているらしい。いまいち認知度が低い上にやたらと長いのでカラオケでは歌わないけれど、一番好きなのはこの曲。『最終電車でこの街に着いた/背中丸めて帰り道/何も変わっちゃいないことに気がついて/坂の途中で立ち止まる』本当に最終電車で家に帰ることが多かった頃、このフレーズを聞くたびに胸が熱くなった。まあ結局、何も変わっちゃいないんだけどね。
This Week in Science (www.twis.org)
これはsongでもtunesでもないけれど、今、毎週楽しみにしているラジオ番組(Podcastで聞いている)。今まで出会った中で、最も理想に近い「サイエンスを楽しむためのメディア」。サイエンスの楽しさをわかりやすく語ることより、ただ楽しそうにサイエンスを語ることの方がずっと魅力的だという、あまりに当たり前の事実に頭をハンマーで殴られたような衝撃を受けた。このGarbege CollectionもJunkyard ReviewもHitch Hiker's Guideも、ひたすらそれがやりたくて更新しているようなものだけれど、いまだにうまくいったためしがない。
というわけで、僕からのリレーはありません。ごめんなさい。
. Date: 20050622 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingSuccess of solar sail launch unknown (SpacefligntNow)
世界初のソーラーセールの打上げが日本時間の今朝4:46に行われました...が、軌道投入の確認ができていないとのこと。えー、また?
軌道投入のキックモーターが作動したことは確認したけれど、その後コンタクトが取れていないみたい。打上げ機の主エンジンが発射84秒後に止まったという情報もあり、何らかのトラブルで軌道投入に失敗した可能性が高い。
もちろん、コンタクトが取れてないということは、まだ軌道上を回っている可能性もゼロじゃない、けど...うー、がんばれー!
生きてる!!!! (14:00)
ペトロパブロフスク(北太平洋)とマジュロ島(南太平洋)の追跡ステーションが、かすかなシグナルを捉えたらしい。
ただ、地球周回軌道には乗っているものの、目標の軌道ではないかもしれないとのこと。
また、このシグナルがCosmos1からのものではない可能性も残されている。
Russian Space Agency: Solar Sail Launch Failed (Space.com)
再び失敗との報が流れ始めました。どうやら、打ち上げを担当したロシア宇宙局から打ち上げ失敗の公式発表があったようです。件の84秒後のエンジン失火が原因とのこと。ただ、運用を担当している惑星協会からの発表はまだありません。だとすれば、先に報じられた「かすかなシグナル」の正体が気になる所です。 (0:10)
The Planetary Society's Cosmos 1 Weblog
ブログに経緯のまとめがあがってますね。どうやら、上の失敗の報は惑星協会とのコンセンサスによる発表ではなく、ロシア宇宙局の見解としてエンジン失火→打ち上げ失敗という結論を出したということのようです。記事にも書かれていますが、今回使われたVolnaロケットは失敗したときの破壊システムがありません。記事を読む限りでは、失火による墜落ないし破壊があったことが改めて確認された訳ではなさそうです。結局、まだ最終的な結論は出ていない、というのが現状のようですね。(0:30)
惑星協会からも失敗との声明が出ました。結論はロシア宇宙局とほぼ同じです。
...しょんぼり。
参考)
The Planetary Society's Cosmos 1 Weblog
. Date: 20050623 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 「世界で最も有名なコーヒーメーカー」のその後どうやら、大昔の記事がかなり上位にヒットするようです。検索エンジンからの無言のリクエストにお答えして、ちょっと調べてみました。
The Trojan Room Coffee Pot Resources
このコーヒーメーカーはケンブリッジ大学コンピューター研究所のTrojan Roomに置かれていたもの。1991年、延々廊下を歩いていったにもかかわらずコーヒーがなくなっていることが頻発したため、業を煮やした研究所内のメンバーがカメラを研究所内ネットワークに接続しその状態を監視することのできる簡単なUNIXアプリケーション「xcoffee」を書きました。
やがて、1993年3月にはじめてWebページに画像を埋め込む機能を持ったNCSA Mosaic 0.10のベータ版がリリース。その8ヵ月後にこのカメラはウェブサーバと接続され、世界で初めてのWebCamとなり「世界一有名なコーヒーメーカー」になったのです。
しかし、2001年「僕たちは新しいエスプレッソマシンが欲しいんだ。だって水が漏るんだもの。」との理由から、このコーヒーメーカーはeBeyでオークションに掛けられました。結局、ドイツの週刊誌『シュピーゲル』が約58万円で競り落とし、2001年8月22日に惜しまれつつスイッチが切られました。
しかし、このコーヒーメーカーを製造したKrups社の好意で無償で修理された後、同年12月、シュピーゲルのサイトでオンラインに復活。実は、今でもシュピーゲルのサイトで見ることができます。
Coffee Cam Index Seite - Netzwelt - SPIEGEL ONLINE (SPIEGEL)
...といいたいところですが、このWebcamの映像はリアルタイムのものじゃなさそうです。なにしろ、いつ行っても同じ画像が表示されます。どこへやった?シュピーゲル。
参考)
Stalking the Cambridge Coffeepot
Abroadview Magazine2001年秋号、Nancy Eichornによる"潜入"レポート
XCoffeeの開発者の一人、Quentin Stafford-Fraserの公式サイト。同 Weblog
あとは、"Trojan Room Coffee Pot"とか"XCoffee"で検索すれば、e-Bay出品、スイッチオフに関する2001年当時の記事が山ほど出てきます。
http://7acha.jp/
最近街中で目にする『七色亜茶』というウーロン茶のポスターの月の欠け方がどうにも気持ち悪い。
このポスター作った関係者は月を見たことがなかったんだろうか?
28日周期の月の満ち欠けはこんな形にはならないし、月食だとすると並び方がおかしい<%= fn '実は月食だとしても形が少しおかしい。地球の影は月よりもずっと大きいからこういう形にはならない。' %>。サイトを見ると、「七色の味を持ったお茶を七つの月の形になぞらえた」ということなので、どちらかといえば前者を意図しているみたいだけど...あしらい程度に使うならともかく、商品そのもののキーイメージにしたいなら、リリースする前に少し調べた方がいいのでは。
月の形は昔からずいぶんいろんなものにたとえられてきたし、すこし探せばいろいろな月の形に複数の名前が見つけられるはず。もちろん月の形に関する逸話も山のようにある。クリエイター/プランナーならこれを利用しない手はないと思うぞ<%= fn 'すくなくとも、月の形とは何の関係もない織姫と牽牛の話をサイトで紹介するよりもずっといいと思うけどなあ' %>。もったいないなあ。
まあ、夜空好きの愚痴なのは重々承知しているけれど、月の形に商品をなぞらえるなら、せめて月の形ぐらい知っていてもいいんじゃないかと思うのは、多くを望みすぎですか?そうですか。しょんぼり。
. Date: 20050628 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary サイト移転http://www.lizard-tail.com/isana/
お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、数ヶ月前に新しいサーバを借りてドメインを取得しました。これ以上寝かせておいても意味が無いので、メインサイトを新しいドメインの方に移行します。デザインは少しいじりましたが、入っているコンテンツは基本的に同じです。
旧サイトは少なくとも半年以上は残しておくつもりですが、これ以上の更新はありません。ブックマークやアンテナなどにご登録の方は、お手数ですが切り替えをお願いします。
なお、このはてなダイアリーは当面このまま運用します。
えー、デザインは...とうとう「無くなりました」。わはは。
おかしい、凝りに凝ってマークアップしたはずなのに、なぜだ?
「それはデザインセンスがないから」(by連れ)
ああ、無いさ!俺にはセンスなんかないさ!<%= fn 'いや、なんとなく文章を「静かなところ」に置いてみたくなっただけなんだけどね' %>
というわけで、どうぞ今後ともごひいきに。
. Date: 20050629 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [prog]Summertime夏やし、まあ、そんなに悪うないやろ?
魚は跳ねとるし、綿花はそろそろええ時期やし、
おとんは金持ちで、おかんも美人やないか。
せやからもう泣かんとき、な?
- George Gershwin
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/clock.php
知人からのリクエストで作った世界時計(リロードは手動で)。唯一の機能は、かなり正確にサマータイムを判定すること<%= fn '例えば、ニューヨークなら4月の最初の日曜日午前2時にちゃんと切り替わる...はず' %>。
自分でやってみてよーくわかったよ。ただ時刻を表示するだけなのに、ものすごくめんどくさい。国によって開始日や開始時刻がぜんぜん違うし、たいてい曜日指定だから毎年切り替え日が変わるし<%= fn '今回イランが入ってなくて本当によかった。なにしろあの国では春分の日に始まって、秋分の日に終わる。' %>、ひとつの国の中でも採用してたりしなかったりする地域があるし、しかもルールが時々変わる<%= fn 'ブラジルの「毎年若干変動」ってなんだよ!' %>。
廃止しろとはいわない、導入するなともいわない。できれば、ルールは北半球でひとつ、南半球でひとつ、北半球と南半球で開始日と終了日を入れ替えるぐらいの違いにしませんか? 曜日を基準にするんじゃなくて日付を固定しませんか? それからできれば切り替えのタイミングはGMTで午前0時にしませんか? それだけでトラブルが激減すると思うぞ。
参考)
Time Zone Tools and Information (timeanddate.com)
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20050704 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary ディープインパクト!!(2005.07.05追記)
衝突から一晩あけて、あちこちから報告が上がっていますね。衝突そのものは「これ以上ないくらい狙ったとおり」とのこと。もろもろの観測結果が出るのが楽しみです。
NASA - Deep Impact (NASA)
公式サイトにも、写真や動画などが公開されています。動画は必見。
ディープ・インパクトの衝突現象観測 (Subaru Telescope, NAOJ)
衝突によって増光している様子を捉えた写真が公開されています。
Deep Impact at ESO - Looking for Water (ESO)
欧州南天文台からは、衝突前の分光結果が出てますね。水が見つかったとのこと。彗星の姿の最有力候補とされる「汚れた雪だまモデル」を支持する結果がここでも得られたということですね。
Comets a Smash at JPL(JPL/NASA)※RealVideo
『A SALUTE TO "DEEP IMPACT" BY THE COMETS』だそうな、わはは。っていうかBill Haley & The Cometsってまだ現役なのか!すげー。
NASA TVでは、衝突に向けての中継が既に始まっているようです。
[http://spaceflightnow.com/deepimpact/status.html:title=SpaceFlightNow]でも恒例のリアルタイムアップデートがかなり前から始まっているようです。
現在のところ、インパクター(突入体)は異常なし、インスペクター(探査機本体)はハイゲインアンテナに若干乱れがあるが、大きな問題ではないとのこと。コントロールルームでは、げん担ぎのピーナッツが回されたりしているようです。(13:00)
さて、一時間をきりました。今のところ軌道修正は非常にうまくいっているようです。もう一回の修正が予定されていますが、「このまま、何にもしなくても当たると思う」とのこと。
[http://www.nasa.gov/mission_pages/deepimpact/images/index.html:title=インパクターから送られてきている画像]では、徐々に彗星の核の形が見え始めてきています。(14:00)
最初のクローズアップ画像 (SpacefligntNow)
衝突を確認(15:00)
[http://www.spaceflightnow.com/deepimpact/050704firstcloseups.html:title=衝突の瞬間]。すごい。
地上からも[http://spaceflightnow.com/deepimpact/050704faulkes.html:title=増光が確認]されたようです。
どーん、どーん。わーい!
えー、最初に計画が発表されたときは、そのネーミングセンスに腰が砕けそうになりましたが、とうとうその日がやってきました。本日7月4日、日本時間の午後2時52分前後に突入体が目標の9P/Tempel 彗星に衝突します。詳細情報は、あちこちで紹介されていますから、わざわざここでやることもないでしょう。とりあえず関連情報をリンクしておきます。
NASA - Deep Impact (NASA)
Deep Impact: Your First Look Inside a Comet! (NASA:JPL)
ディープインパクト公式ページ
NASA - Deep Impact Viewer (NASA)
ここからほぼリアルタイムの、ディープインパクト探査機からの画像が閲覧できます。結構ノイズがのってますねえ。
日本語での基本的な情報はここが充実しています。
惑星探査機関連の情報鮮度に定評のある月探査情報ステーションのトピックページ
ディープ・インパクトの衝突現象に向けたすばる望遠鏡の取り組み (すばる望遠鏡)
今回は世界中の望遠鏡がテンペル彗星を見守っています。もちろんすばる望遠鏡でも。
Deep Impact at ESO (ESO)
こちらは欧州南天文台のディープインパクト特集ページ
バラバラになったらどうするんだという声がありますが、杞憂です。ディープインパクトの突入体は3.2m X 2.6m。対するテンペル彗星の核のサイズは14km X 4kmと推測されています。例えていえば、シロナガスクジラに蚊が止まるようなものです(35m:8mm)。割れたり、軌道が変わったりしたらそれこそびっくりです。
. Date: 20050705 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary ASTRO-EII/M-V-6昨日の今日ですが、今度は日本でロケットの打上げです。7月6日(水)12:30?13:00に内之浦の射場からM-Vロケットを使って、X線天文衛星ASTRO-E2が打ち上げられます。13日がシャトル復帰第一回目の打上げですから、次から次へとイベント目白押しですねえ。
今回の打上げは、ひとことで言えば、2000年のM-V-4によるASTRO-Eの軌道投入失敗を受けてのリベンジです(だからASTRO-E "2" なんですね)。
打ち上げに使われるM-Vロケットは、世界でも珍しい全段個体燃料の打上げ機、個体燃料打ち上げ機としては最大のものです。JAXA統合前は宇宙研(ISAS)に属し、ペンシルロケットから面々と続く日本の個体燃料打上げ機の最新鋭機ですね。射場は種子島ではなく内之浦です。前回は今小惑星ITOKAWAに向かっている「はやぶさ」ことMUSES-Cを打ち上げました(その前が失敗したASTRO-Eです)。
今回M-Vに乗せられているのはX線天文衛星です。平たく言えば、ハッブル宇宙望遠鏡のX線版といったところでしょうか。日本はこれまで5機のX線天文衛星を打上げ、X線天文学では世界のトップレベルにあります。
せっかく作ったので、使いましょう。下記ページのチャートを見てください。すでにASTRO-E2も加えてあります。<%= fn 'なんて便利なんだ!' %>
天空を見つめる数多の瞳 (Junkyard Review)
X線の波長領域で見えるのは、ブラックホールや星の爆発といった宇宙でもかなり激しい現象。また、太陽系内の惑星でもかなり活発なX線の放射が観測されたりしています(土星の輪にも!)。X線による観測は、大気にさえぎられて地上からは観測できないため(チャートの赤いラインに注目)、この分野の観測には宇宙望遠鏡が必要不可欠なんです。うまく軌道に乗れば、面白い知見をもたらしてくれること必須です。
では、関連情報を上げておきましょう。
ASTRO-EII/M-V-6 カウントダウンページ (JAXA)
JAXAのカウントダウンページ。当日はストリーミング中継も行われるようです。
M-V (JAXA)
打上げ機M-Vシリーズについてはこのページを参照のこと。
ISASニュース 1997.5 No.194 (JAXA)
上のページからもリンクされていますが、ISAS NewsのM-V特集号は、開発に携わった方々の声がたくさん詰まっていて特におすすめです。
ASTRO-EII (JAXA)
JAXAのASTRO-EII紹介ページ。
Astro-E2衛星プロジェクト ホームページ (JAXA)
こちらは宇宙研 X線天文グループのASTRO-E2公式ページ。
日本の宇宙開発の現場リアルタイム更新ならここしかありませんね。今回も複数のメンバーが乗り込んでいるようです。既にレポートが上がり始めています。
ちょっとお楽しみをひとつ。
科学衛星の打上げに際しては、打上げから探査機の軌道計画までをまとめた「性能計算書」というものが出されますが、旧宇宙研の頃からこの表紙に毎回打ち上げる衛星に引っ掛けたお酒のパロディラベルが印刷されるのが慣習になっています(前回「はやぶさ」のもの「銘酒『虎の児』」)<%= fn 'タバコのラベルだった時期もあるようです' %>。凝りに凝って作ってありますがちゃんと蔵元に許可を取っているそうです。こういうの、いいですねぇ。
今回はどんなラベルになるんでしょうか?
天候不順のため、8日以降に延期とのこと。うんうん、無理はいかん無理は。
打ち上げの判断は、7日午後2時に行われるとのこと。
参考)
M-V-6号機の打上げ実験延期について (JAXA プレスリリース)
. Date: 20050707 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新サーバのログに、ある特定のIPから、ある特定の検索エンジンを使って、ある特定のキーワードで、ある特定の時間帯に、ある記事へのアクセスが集中する、というちょっと変わった足跡が数週間に渡って残っていた。
どこかの学校で「検索エンジンの使い方」の授業でもやっているのかと思って、なんとなく、ほっこりしながらそのログを見ているうちに、彼らに手紙を書きたくなった。
中身は、例のごとく「落書き宣言」と「落書き宣言再び」に書いてあることと、まったく同じ。これっぽっちも進歩してない。お前にはそれしかないのか!と言われそうだけど...うん、まあ、それしかないな。
どうやら打上げは、10日以降に延期になったみたいですね。
観測結果が続々と出始めましたね。あー、分光結果が待ちどおしいなあ。
ディープ・インパクトの衝突現象観測 (SubaruTelescope,NAOJ)
すばる望遠鏡からは、中間赤外線観測装置COMICSの生データが公開されています。
Deep Impact Captured by Gemini (Gemini)
Geminiからの中間赤外線(11.6μm)での画像。
Mahalo! Mr.dtomono
Observing Deep Impact with Keck (KECK)
ケックからも衝突前後の巨大な生データが。さすがに、1.36GBもあるデータは素人には扱えませんね
Deep Impact at ESO - Observations (ESO)
ESOからは中間赤外カメラTIMMI2の画像、多天体分光器FORS2からの画像、近赤外線分光カメラSOFIのJ-BAND(1.1-1.3μm)の画像がそれぞれ公開
HubbleSite - Hubble Captures Deep Impact's Collision with Comet - 7/4/2005
こちらはハッブル宇宙望遠鏡。
Deep Impact: Collaborators' Public Images
大型天文台による観測結果を集めたページ。DeepImpactの公式プロジェクト。
Deep Impact: Small Telescope Science Program (STSP)
小型望遠鏡を使った観測結果を集めたページ。こちらも公式プロジェクト。
Deep Impact: Amateur Observers Homepage
こちらはアマチュアによる観測を集めたページ。こちらも、もちろん公式プロジェクト。
NASA - Deep Impact (NASA)
もちろんNASAからも山のように画像や映像が上がっています。
中にはこんなのも...
Comets a Smash at JPL(JPL/NASA)※RealVideo
『A SALUTE TO "DEEP IMPACT" BY THE COMETS』だそうな、わはは。「ロックグループ"ザ・コメッツ"が、ディープインパクトの成功を祝して新しいミュージックビデオを作ってくれました」とのこと。っていうかBill Haley & The Cometsってまだ現役なのか!すげー。
. Date: 20050708 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Dump the truth....でも、人は悲しかったり、怒っていたり、いらいらしていたりすると、このことをすぐに忘れてしまう。たとえば、ケンカや、人殺しや、戦争や、テロはたいていそうやって起きる。. Date: 20050711 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary ASTRO-E2/M-V-6
世界にあるのは「嘘と本当」の2種類じゃない。世界には沢山の「本当」があるだけなんだ。君がどの「本当」を選ぶのかは、君が自分で決めなくちゃいけない。誰かに選んでもらうことはできない。だから、よーく調べて、よーく考えて選ばなくちゃいけない。そして、一番忘れちゃいけないのは、君の目の前にいるあの人は、君とは違う「本当」を選んでいるかもしれない、ということだ。
君の「本当」を誰かに押し付けるのはやめた方がいい。だからと言って誰かの「本当」を何も考えずに採用するのもあまりおすすめしない。君が努力すべきなのは、2つの「本当」をひとつにすることじゃなくて、それぞれの「本当」のどこが同じで、どこが違っているかをちゃんと理解することだ。
検索サイトから来た君へ (junkyard review)
ASTRO-EII/M-V-6 打ち上げ成功 (JAXA)
2005.07.10 12:30JST、無事打上げに成功。ASTRO-E2は所定の軌道に乗った模様。わーい!とりあえず、打上げ成功おめでとうございます。名前は、すざくとつけられたようですね。「すざく」はこれから、数日間の軌道制御を経て、ソーラーパネルの展開、X線望遠鏡の展伸が行われて定常状態に移行します。もうひとがんばり!
さて、今度はスペースシャトルです。日本時間7月13日午前4時51分の打上げ予定。今回は国際宇宙ステーションの補給/組み立てミッションということになりますが、一方で事故後最初の打上げということで、退役予定の2010年まで飛行を継続する上での安全性を確保するための各種のテストが行われます。また、日本人宇宙飛行士 野口聡一さんが搭乗していますね。
ずっとこの間の流れを追いかけていたので、なんとも感慨深い限りです。無事、ミッションが成功することを心からお祈りします。...がんばれ、スペースシャトル!
では、関連URLをまとめておきましょう。
NASA - Return to Flight (NASA)
NASAの「Return to Flight」。今回の打上げに関する公式情報はここからたどるのが一番いいと思います。
Launch Complex 39, Pad B(Google Maps)
通常スペースシャトルの打上げにはケネディ宇宙センターの39番射場が使われます<%= fn 'ここはかつてアポロ計画で使用され、サターンロケットの組立、打ち上げが行われた場所でもあります。' %>。今回打上げが行われるのは、39番射場に2箇所ある発射台のうち、北側のB発射台です。画面下へと続いているのが組立塔(VAB:Vehicle Assembly Building)から続く誘導路。右下に見えているのがA発射台。誘導路をたどって画像をドラックしていくと左下にVABが見えてきます。さらに左へ行くと、帰還予定の滑走路が見えますね。
STS-114 国際宇宙ステーション組み立て再開 - JAXA (JAXA)
JAXAのSTS-114特集ページ。このミッションに関する非常に詳しい情報が日本語で提供されています。
スペースシャトル飛行再開に向けて (JAXA)
コロンビア事故とその後の対策についてはこのページがよくまとまっています。
途中で止まっているのがなんとも心苦しいんですが、いちおうご紹介。拙作、公式事故調査報告書の日本語訳です。
. Date: 20050714 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]STS-114どうやら、センサーのトラブルで打ち上げが延びているようです(4:45)
外部燃料タンクの底に設置された液体水素燃料の残量を計測するセンサー(ECOセンサー)4つのうち1つが適切な値を示していなかったとのこと。このセンサーは、液体水素の残量が異常に低下した時にエンジンをカットオフするためのもの(ECOはエンジンカットオフの略です)。
ちなみに、4月の燃料充填テストでも同じセンサーの故障が発覚して、燃料タンク丸ごと交換しています。
打ち上げは少なくとも17日以降とのこと。
. Date: 20050715 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [prog]Google Maps API で遊ぶ。GoogleSat - satellite tracker on google maps
えーと、要するに緯度と経度を指定してマーカーが置けるんだから...おぉ、あれが作れるじゃないか。
というわけで作ってみました。ページが読み込まれた瞬間の国際宇宙ステーションの現在位置を表示するスクリプト。誤差は緯度と経度で3度弱、距離にすると300kmぐらい。実用にはならないけど、雰囲気だけならこれぐらいでも十分かな。
元になったのは、ちくちくと作っているOpen Planisphereの次期バーション用コード。軌道計算の結果を元にISSのアイコンを配置しています。Google Maps APIの使い方としてはさほど変わったことはやっていません。
地図をズームさせながら、今ここに宇宙ステーションがいて、宇宙飛行士たちはこういう風景を見下ろしているんだなあ、と思うとなかなか趣き深いものがありますね<%= fn 'ISSのアイコンをクリックすると...' %>。
倍率とISSアイコンのON/OFFを指定できるようにしました。「googlesat.php?zoom=12&marker=off」の書式でスクリプトを呼び出せば指定できます。アイコンをOFFにして倍率6?8にすると「宇宙飛行士たちが今見ている風景」になると思います(ただし、この倍率だと海の上では画像が表示されません。)。
ディープインパクト続報・衝突で明らになった彗星の表面と、火星の水が失われたプロセス (Astroarts)
ディープインパクトの衝突の観測結果が分かりやすくまとめられています。(dtomonoさん、ありがとうございます)吹飛ばされたチリのサイズは化粧パウダーほどにも細かく、その下は雪ではなく氷でできていたそうな。また、X線のデータからは、彗星の表面から水が失われる様子が分かったらしい。おぉ!
ディープ・インパクトの衝突現象観測 速報 (Subaru Telescope, NAOJ)
すばるのサイトには、ハイビジョンの動画とキャプチャ画像があがってますね。
. Date: 20050718 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『3.7 Debris Analysis』をアップしました。また、約半年ぶりの更新ですね。わはは。
捜索によって回収された破片の分析に関するお話です。
. Date: 20050719 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記昨日に引き続き、『STS-107 CREW SURVIVABILITY』をアップしました。
空中分解の際に乗務員室がいつまで残っていたのか、に関する3-7章の囲み記事に当たる文章です。
短く簡潔に書かれていますが、その意味するところはかなりショッキングな内容です。
. Date: 20050721 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [prog]GoogleSatTrack (旧GoogleSat)アップデートGoogle Maps APIを使って、国際宇宙ステーションの現在位置をプロットするスクリプト
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/googlesat/googlesat.php
軌道要素の自動取り込みに対応。ローカルに保存したデータが古くなると新しいのを取りに行く。
実は、今までは毎日手作業で値をコピーペーストしていたのだ。わはは。
ついでにソースコードを公開。ほんとはまだ見せられたものじゃないんだけど、参考までに。
どうやらシャトルの打上げが、7/26の10:39 a.m. EDT(日本時間同日23:39)に決まったようです。
でも、燃料の枯渇センサーの誤作動の原因は特定できていないようですね。要するに、常温でテストしても原因が分からないから、もう一回タンキングテスト(抜いた燃料を最充填してのテスト)をやってみて、問題がなければそのまま打ち上げてしまおうということみたい。まさか「原因が分からないけど、うまく行っているからいいか」で打ち上げないとは思うけど...
GoogleLocalとの連携は2069年を予定しているらしい。サービス開始時で当方97歳、ふむ、ぎりぎりなんとか間に合うかな?「サービスの連携を前倒しにせざるを得ない状況」が来ることを切に望む。
ちなみにGoogleMoonは、Google Copernicus Center計画の一環として位置づけられている<%= fn 'Google Copernicus Center計画が発表されたのは2004.04.01' %>。本気?
Discovery Channelが資金を出して、ローウェル天文台に新しい望遠鏡を建設するというお話。これは机上のお話しじゃなくて、予備調査が終わり、設計が終わり、「建設が始まった」というニュース。やるなぁ、Discovery。
Discovery Channelが資金提供しているといっても、放送目的じゃなくて、ちゃんとした研究用のもの。望遠鏡のサイズは4.2m。このクラスとしては桁外れに広い視野と観測波長領域を持つ予定。しかも、この広角モードから非常に狭い領域を観測する長焦点モードへすばやく切り替えることができるそうな。プレゼン資料(PDF)には「大きい!早い!視野が広い!はっきり見える!」と、深夜放送の通販番組みたいなキャッチが...もし、スペックどおりの性能が出るなら、とても小回りが効いて汎用性の高いファミリーカーみたいな望遠鏡ができるかもしれない。ファーストライトは2009年の予定。楽しみ。
Discovery Channel Telescope (公式サイト)
GOSE9との中継器としての役割もこれで終了、本当の退役です。ご苦労様でした。
参考)The Last Sunflower (Junkyard Review)
演芸場の舞台の上に、タキシードに蝶ネクタイというべたな格好の男が二人。
どうやら漫談か漫才をやっているらしい。らしいというか、そのうちの一人は僕だ。
相方は大学時代の友人M君。なんだか客の入りも良く、大入り状態。
でも、漫談にしては内容がちょっとおかしい。
僕はホワイトボードに絵を描きながら、
ひたすらドップラー効果で星の動きを測る方法を説明している。
K「...こういう風に、星が近づいていると青く、遠ざかっていると赤く見えるわけやね」
――いつの間にかMがKに異常に接近している
M「...青い?」
K「ちがー!」
M 「え、じゃ」
――M、今度はずいーっと離れる
K「ちがー!そんなに離れてどうすんの!」
M「変だな」
K「変じゃないよ!動きだっていってるでしょ!」
M「おー」
K「おーって ... とにかく、この星の動きで波長が変わることをドップラーシフトと...」
――気づくと、Mがうねうねと変な動きをしている
K「... なにやってんの」
M「いや、ちょっと。どっぷらーしふと?」
K「ちがー!」
M「え、じゃあ、こ、こうかな?」
――M、さらにゆっくりうねうねと動く
K「いや、それはただのスローモ?ションだから」
場内大爆笑
M「さいえんすー!」(両手を上げるポーズ)
K「さいえんすー!」(あわてて、両手を上げるポーズ)
M「そうそう、ドップラーシフトといえば、この間...」
あー、文字に起こすと、さらにくだらないな。
ただ、「サイエンスを伝えよう」という気がこれっぽっちもないあたりが、
個人的に理想とする「サイエンスのお話」にかなり近い気がするなあ。
. Date: 20050725 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]STS-114 主要イベントカウントダウンSTS-114の主要イベントの時間、現在時刻からのカウントダウンを表示するスクリプトを作りました。
打上げ前イベント
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/space_exploration/sts114pre.php
上昇中/軌道上イベント
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/space_exploration/sts114.php
26日午前10時39分(日本時間26日午後23時39分)の打上げ<%= fn '奇しくも、コロンビアとまったく同じ打ち上げ時間ですね' %>に向け、すでにカウントダウンが始まっています。
問題になっている燃料枯渇センサーですが、現状では不具合の原因は分かっていません。ただ、「もし仮に前回とまったく同じ状態でセンサーの不具合が確認された場合限り」、今回は特別に、4つあるセンサーのうち3つが正常に稼動していれば打ち上げにゴーサインを出すとのこと。超低温の燃料を何度も入れたり抜いたりしていると、タンクの各パーツが膨張収縮を繰り返すために負荷がかかり強度が低下する危険性がありますから、タンキングテスト(燃料を充填してのテスト)をあまりやりたくないのはわかりますが...
むしろ、打上げの可否を決めるのは、フロリダ沖合いの台風の影響による天候の悪化ということになりそうです。最新の天気予報では打上げ可能な天気の可能性は60%とのこと。
リアルタイムの情報は、CBSとSpaceFlightNowを押さえていればほとんどフォローできるはずです。
CBS News Coverage of Shuttle Mission STS-114 (CBS)
Spaceflight Now | STS-114 Shuttle Report | Mission Status Center (SpacefligntNow)
CBS Newsの記者William Harwood氏がレポーターズハンドブックと、各種のパラメーターをリアルタイムで参照できるエクセルファイルを公開しています。すげーよ!ハーウッドさん。
CBS News Space Reporter's Handbook / SpaceCalc (CBS)
ハンドブックは、STS-114およびこれまでのシャトルとISS関連の情報が非常にコンパクトにまとめられています。
Excelファイルのほうは、STS-114の各種パラメーターを元に、打上げやドッキングなどの各イベントの時間を計算します。
ただ、このエクセルファイルはシステムの時計がEDTで動いていることが前提になっているので、日本で開くと時間が狂います。以下のように修正が必要です。
Mission ControlタブのA1のセル(一番左上)を以下のように修正。
「=NOW()」 → 「=NOW()-(13/24)」
Mission Controlタブの一部のセルが#VALUEとなっている場合は、セル内の日付の指定を以下のように修正。
「月/日/年 時:分:秒」→「年/月/日 時:分:秒」
Entry TimelineタブのH列(一番右端)が「=NOW()-C数字」という形式になっているので
全て、「=NOW()-(13/24)-C数字」に修正。
ISS Docking TimelineタブのI列(一番右端)が「=NOW()-B数字」という形式になっているので
全て、「=NOW()-(13/24)-B数字」に修正。
まだ他にもあるかもしれませんが...要するにNOW()が指定してあるところに、日本との時差を入れるだけです。
これで、打ち上げ時間が変更された場合に以下のセルを修正すれば他の値は再計算されます。
Mission Contorol : H21
Master Flight Plan : C4
STS Countdown : F118
. Date: 20050726 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [prog]GoogleSatTrack STS-114http://www.lizard-tail.com/isana/lab/googlesat/googlesat_sts.php
GoogleMapsAPIを使ってスペースシャトルの現在位置を表示。プレビューバージョン。
まだ精度のチェックができていませんが...まあ、気分は味わえるかと。
正確な位置は以下のサイトで確認をしてください。
こちらはほぼ正確な位置を表示します。
[sts]STS-114打上げ打上げ予定時刻は米国東部夏時間26日10時38分59秒、日本時間同日23時38分59秒の予定です。
燃料充填にGOサインが出ました。現在のところスケジュールは予定通り進行中です。(13:00JST)
燃料充填が終了し、前回エラーを検知したテストを行ったところ、全てのセンサーが正常に動作していることを確認したとのこと。軌道制御システムにトラブルがあったようですが、現在は解消しています。また、天候不良の可能性は以前の40%から20%に下がりました。カウントダウンは順調に進行中です。(17:45JST)
国際宇宙ステーションの最新の追跡データに従い、打ち上げ時間が1秒早められているようです。カウントダウンスクリプトのターゲットタイムを修正しました。カウントダウンは順調に進行中です。(19:30JST)
シャトルは既にハッチが閉じられ、現在各種の最終チェックが続いています。緊急着陸時に使用する各地の滑走路を含め、天候不良の可能性は10%まで下がりました。(22:15 JST)
発射台に最後に残っていたクルーが退去しました。燃料枯渇センサーの最後のテストは良好とのこと(23:20 JST)
"Go for launch !" 最終的な打ち上げにGOサインが出ました。いよいよです。(23:28 JST)
5分前。ラウンチウィンドウ(打ち上げ可能時間)が開きます。
打ち上げ !
SRB切り離しに成功!
メインエンジンカットオフ/外部燃料タンク切り離し
あとは軌道投入噴射を残すのみです。
軌道投入に成功しました。打ち上げ成功です。
おめでとうございます。そして、クルーの皆さん、いってらっしゃい!!
NASA - Return to Flight (NASA)
STS-114 - JAXA (JAXA)
今回のミッションに関する基本的な情報、公式発表などは上記公式サイトから。
ニュース速報
CBS News Coverage of Shuttle Mission STS-114 (CBS)
Spaceflight Now | STS-114 Shuttle Report | Mission Status Center (SpacefligntNow)
LIVE Mission Journal: Counting down to liftoff (FloridaToday)
上記サイトから、ほぼリアルタイムの情報が得られます。
各イベントの時間対照表
Countdown for STS-114 pre launch
Countdown for STS-114 post launch
秒読み開始から着陸までの各イベントの米国東海岸夏時間、日本時間、残り時間の対照表です。
略語対照表
NASA/JAXAのミッションで使用される略語の対照表です。上記イベントリストを読み解くためには必須です。
ライブストリーミング
NASA - NASA TV Landing Page (NASA)
NASA TVライブ中継 - JAXA (JAXA)
NASA TV番組表 (JAXA)
NASA-TVの中継は 7/26 00:00EDT(13:00JST)に始まります。打上げまで10時間近く中継が続くことになります。
NASA TV:スペースシャトル”ディスカバリー号”生配信、宇宙映像や実況解説 -casTY宇宙コンテンツ- (casTY)
casTYでは、NASA-TVのミラーリングに加えて、実況解説などが行われます。TEPCO光ユーザーはこちらから。
日本語関連サイト
5thstarは野口宇宙飛行士が選抜された第5次第3次宇宙飛行士選抜受験の2次試験受験者によるグループ。
black_knight氏によるBlog/宇宙開発関連ニュースクリッピング。そりゃ気合も入りますよ、ね?
現地で取材をしている毎日新聞の元村記者のBlog。
その他
ケネディ宇宙センター 39B発射台 (Google Maps)
今回打上げが行われるのは、シャトル用の39番射場に2箇所ある発射台のうち、北側のB発射台です
国際宇宙ステーションの現在位置(GoogleSatTrack)
GoogleMapsAPIを利用した衛星追跡プログラムです。軌道要素が確定すれば、シャトルも追加できるかな?
Dear Rocketeer. (Junkyard Review)
. Date: 20050727 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events2日目。今日はロボットアームを使った機体のチェック、ISSとのランデブーに向けた軌道制御などが行われます。
昨日の打上げ時に、外部燃料タンクからの断熱材の脱落や、オービターからの耐熱タイルの小片と思われる小さな物体が脱落するのがカメラで確認されています。
Launch debris images (SpacefligntNow)
ただ、かなり小さい破片(2?3cm)なので、今日のチェックで該当箇所が分かるかどうかは微妙ですね。
GoogleMapsを利用したISS/STSの現在位置表示スクリプト。
国際宇宙ステーションとディスカバリーの両方を表示するように変更。誤差が出るのは相変わらず...どうせ、今日明日はかなり頻繁に軌道変更があるし、明日以降はISSと同じ軌道だし、とりあえずこれでいいことにするか。
. Date: 20050728 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events3日目。今日のハイライトは、なんといってもISSとのドッキングですね。
ファイナルアプローチの開始が、日本時間の18時53分、ドッキングが20時17分、各種チェックを終えた後、ハンドシェイクイベント(ISSとSTSのクルーが軌道上で始めて顔を合わせる)が22時18分の予定です。
お、もう同じ画面に入ってきましたね。(12:30)
スクリプトの精度を信じるなら、両者の距離は200kmぐらいですが ... (17:00)
軌道要素が古くなってしまったので、スクリプト上ではずれが発生しています。もうシャトルはISSの真下に居ます。 (19:30)
ドッキングも無事終わり、気密も確認されたようですね。 (21:30)
歓迎の鐘が鳴りました。STS-114のクルーがISSに到着しました。おめでとうございます ! (21:50)
Foam loss grounds shuttle fleet again (SpacefligntNow)
打上げ時の外部燃料タンクからの断熱材の剥離についてですが、「原因が特定できるまでシャトルの打上げを行わない」との判断が出ました。これは、コロンビア事故調査委員会の「外部燃料タンクから断熱材や氷の剥離が無いこと」という勧告に従ったものです。軌道上のシャトルには今のところ目立った外傷は発見されていません。
. Date: 20050729 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch eventsISSとのドッキングも終わり一安心というところです。さて、4日目のハイライトは、シャトルが運んできた多目的補給モジュール (JAXA)をISSに結合する作業ですね。食料、水、衣料、実験装置などが沢山詰まった「おみやげ」です。
あとは、明日の船外活動に備えてプレブリーズという作業が行われます。これはちょっと説明が必要かもしれません。
宇宙服の中で船外作業員が呼吸するのは0.3気圧の純酸素です。これは、宇宙服内の気圧が高いと外気圧(ほぼゼロ)との差が大きすぎて宇宙服がパンパンに膨らんでしまい、身動きが取れなくなってしまうからです。ソ連のレオーノフが人類初の船外活動を行ったときにも、宇宙船から出たはいいけれど、宇宙服が膨らんでしまってハッチに入れなくなってしまい宇宙服から一部空気を抜いて事なきを得た、なんて事がありました。
ただ、スペースシャトルの船内は1気圧(酸素21%、窒素79%)なので、いきなり0.3気圧の酸素を吸うと、体内の窒素が気泡になって減圧症にかかってしまいます。そのため段階的に気圧を下げ、体を慣らしていくんです。EVAを行うクルーはまず、60分間純酸素を吸い、その後シャトルの船内を0.7気圧まで下げて12時間保持(この工程には他のクルーもお付き合いします)、EVA直前に40?75分間再び純酸素を吸います。もちろん、シャトルの船室が0.7気圧に下げられている間はISSとのハッチはいったん閉じられることになります。まあ、ほとんど寝ている間におこなわれるので作業に支障はありませんけどね。EVAが始まるとハッチは再び開放されます。
. Date: 20050730 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [prog]GoogleSatTrack 2 - satellite tracker on google mapsGoogleMapsを利用したISS/STSの現在位置表示スクリプト「GoogleSatTrack 」をバージョンアップしました。
今度はISSの位置を自動追尾します。ようやく最初に思い描いたものに近づきました。
Satelliteモードにして、ズームアップしてみてください。
本物には遠く及ばないかもしれませんが、
今、たぶん彼らはこういう風景を見下ろしています。
これまで通り、各データを詳しく表示するバージョンはこちらから。
5日目。今日はなんといっても、第1回目の船外活動 (EVA) が行われます。日本時間の30日17時30分ごろ23時頃まで、6時間以上にわたって行われます。今回は、ISSの組み立て以外にも、耐熱タイルの修理技術の実証試験が行われます。野口宇宙飛行士大活躍ですね。
少し遅れていたみたいですが、始まりましたね。膝と生命維持装置に赤いラインが入っているのが野口さんとのこと。がんばれー!(19:15)
打ち上げのときにも紹介した、black_knight氏が、打ち上げ以来精力的にニュースクリッピングをされています。すばらしい。各報道機関の記事へは、ここから行くのが一番早道じゃないでしょうか。
. Date: 20050731 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events6日目。今日は運んできた物資を、ISSに搬入するのが主な仕事。7時間近くEVAしたあとですから、ちょっとお休みです。明日またEVAが行われますから、今夜もプレブリーズが行われます。そうそう、今日は広報イベントがありますね。日本時間20時08分と21時43分からの2回、2回目にはEVAを行ったロビンソン・野口宇宙飛行士も登場します。昨日の話が聞けそうですね。
Shuttle mission extended to give bonus day at station(SpaceFlightNow)
NASAはSTS-114の軌道滞在を一日延ばすことを決定しました。これは、先日発表された次のシャトルミッションの延期を受けて、宇宙ステーションへの機材の積み込みなどの追加作業を行うためと、耐熱タイルの調査と分析をより完全なものにするためです。これによりシャトルの帰還は8月8日になります。
. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20050801 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events7日目。今日は第2回目の船外活動EVAが行われます。開始予定時刻は日本時間17時13分の予定。終了は22時53分です。5時間30分以上の長丁場。がんばってください。
今日行われるのは、故障しているISSのコントロール・モーメント・ジャイロの交換です。えー、解説しましょうか。
このコントロール・モーメント・ジャイロ(Control Moment Gyros: CMG)というのは、国際宇宙ステーションが姿勢制御を行う上で非常に重要な機能を果たすパーツです。小さな衛星なんかだとリアクション・ホイールと言ったりします。「ジャイロ効果」というのはご存知でしょうか。「回転する物体は常にその向きと回転数を保とうとする」という効果のこと<%= fn '少し不思議な感じですが、ただの慣性の法則です' %>です。こまがなかなか倒れないのと同じ理由ですね。このCMGというのは、この「こまがなかなか倒れない」という効果を使って衛星の向きを変えるシステムなんです。
ちょっと、ジャイロの軸を両手で持っているところを想像してみてください。そうそう、軌道上は無重量なのを忘れずに。回転しているジャイロは、その傾きを一定に保とうとしますから、無理矢理傾けようとすれば持っている自分のほうが反対方向に回ってしまいます。また、同じようにジャイロは回転数を一定に保とうとしますから、ブレーキをかけたり回転数を上げたりすると、向こうか手前に体が回ってしまうでしょう。
「軌道制御」なんていうと、小さなロケットを「ぶしゅっ」と吹かす所を想像するかもしれませんが、向きを変えるためだけにそんなことを毎回やっていたんじゃ燃料がいくらあっても足りません。そこで、大きなジャイロを回しておいて、それを傾けたり、ブレーキをかけたりして、その反動を使って宇宙ステーションの姿勢を変えるんです。CMGがものすごく重要なパーツだと言うのがお分かりいただけたでしょうか? 何しろ全部壊れると宇宙ステーションの向きが変えられませんからね。
ISSのジャイロは4つありますが、2002年6月からそのうちのひとつCMG1がずーっと壊れたままです。CMG2は回路遮断機の故障で今年の頭に止められ、先日の第1回EVAで補修されています。CMG3はずっとベアリングの調子が悪く、先日のSTS-114とのドッキング以来異音が発生しているなんていう話もあります。まともに動いているのは一つだけ。ISSの軌道を安定させるには最低でも2つ必要なので、かなりの綱渡り状態ですね。第2回EVAでは2002年に壊れたCMG1の交換が行われます。
CSGに関するより詳しい情報は、プレスキット (JAXA)のP84を、第2回EVAについては同P42を参照してください(via Space Fighter Now)
冥王星よりも大きな天体が発見され、すわ「第10番惑星か」という話になっているみたい。上は発見者のブラウン博士のサイト。この人は、前回惑星か?と騒がれたセドナの発見者でもある。
んー、冥王星でさえ、「本当のこというと惑星にしときたくないんだけど、まあこれまでのこともあるし、とりあえず惑星にしときますか」と言う感じで、仕方なく惑星認定されているぐらいなので、この天体は「大きな小惑星」ということになるんじゃないかな? たぶん見つかっていないだけで、カイパーベルト内には冥王星より大きな天体はごろごろしているはずだから、いちいち惑星認定しているときりがないよ。
と、ありきたりなコメントで済ませたいところだけれど...実は、本人も「セドナが10番目の惑星か」と騒がれたときに、「ちがうよー、それいい始めれば、冥王星だって惑星じゃないよ」とコメントしていたりするのだ。今回は逆に「冥王星が惑星だって言うなら、僕が見つけた天体だって惑星じゃないの?」といっている。このおっさん、絶対確信犯だよ。新惑星に娘と同じ名前つけたりしてるし。
ほら、本人だってそういってるじゃないか。
Thus, we declare that the new object, with a size larger than Pluto is indeed a planet. A cultural planet, a historical planet. I will not argue that it is a scientific planet, because there is no good scientific definition which fits our solar system and our culture, and I have decided to let culture win this one. We scientists can continue our debates, but I hope we are generally ignored.
というわけで、僕たちはこの冥王星よりも大きな天体を惑星だと宣言することにしたんだ。文化的、歴史的な意味で惑星だってね。でも、科学的な意味で惑星だとは僕らも思わない。だって、僕たちの文化と太陽系の両方にぴったり来る「科学的な惑星の定義」なんてどこにもないんだからね。で、今回は「文化」の方を優先させてみたってわけ。またぞろ僕たち科学者は議論をすると思うけど、できればみんなにはあまり相手にしないで欲しいな。
前回セドナのときにみんなが大騒ぎしたもんだから、からかってるだけだって。このニュースはニヤニヤ笑いながら見るのが正解だと思う。
彼がセドナの発見者であることに触れた新聞記事は殆どなかった。記事を書く前に、ほんの少し検索するだけで、彼がこれまでにどんな発見をしていて、そもそも発見者自身がこの天体を本気で惑星だと思っているかどうか調べられるのに、何でその手間を惜しむかなぁ。
. Date: 20050802 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events8日目。今日は休養日。クルーにはそれぞれ4時間のお休みが与えられます。大きなイベントとしては、クルー全員での写真撮影と記者会見ですね。日本時間19:03からの開始です。そして夜には、明日の第3回目のEVAに備えてプレブリーズが行われます。
NASA gives go-ahead to spacewalk repair work (SpacefligntNow)
明日のEVA3でシャトルの補修作業が行われることが決まりました。フライト中の補修作業はこれが初めてです。
ISS接近時に撮影された、シャトルの外観のチェックによって判明した、耐熱システムの不具合のうち、耐熱タイルの隙間を埋める「ギャップフィラー」が飛び出している2箇所について、この不具合を修正する作業をEVA3の中で行うとのこと。これを放置すると、大気圏突入時に空気の流れが乱され、局所的に通常より温度の高い部分ができて耐熱タイルを破損してしまうかもしれません。
EVA3では、宇宙飛行士がシャトルの下面に接近し、まずギャップフィラーを手で引き抜くことを試みます。それが不可能ならば、のこぎりを使って切り落とすことになります。実は今回の作業で一番難しいのは、不具合の箇所に到達することです。これは今まで一度も試みられたことがありません。おそらく、ISSのロボットアームに乗って接近することになるはずです。
実は、ギャップフィラーが飛び出していたのは今回が初めてではありません。ただ、以前は着陸した後の調査でしか分からなかったんです。その際には、今回の予測と同じように、乱れた空気の流れによって発生した局所的な高温が耐熱タイルにダメージを与えていました。一部に「ギャップフィラーが飛び出していた→やっぱりシャトルはダメ」という意見が見られますが、これはちょっと短絡的じゃないでしょうか。むしろ、事故に繋がる危険を軌道上でチェックし補修することができるようになった、というとても大きなアドバンスだと思います。
. Date: 20050803 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events9日目。今日は3回目、最後の船外活動が行われます。今日行われるのは、追加された「ギャップフィラー」の補修作業以外にも、船外保管プラットフォーム2(ESP-2)の取り付け、新しいMISSE-5実験装置の設置などが行われます。開始予定は日本時間17時頃から、ギャップフィラー関連の作業は日本時間20時15分頃からの予定です。なお、「ギャップフィラー」の修復作業が追加されたため、当初5時間10分の予定だった船外活動は7時間に延長されています。
ちなみに、ESP-2(External Stowage Platform 2)はISSの外部に取り付けられている機器の交換パーツを補完しておくためのパレットです。また、MISSE-5(Materials ISS Experiment)というのは材料曝露実験装置と呼ばれ、宇宙船などに使われる様々な素材を宇宙空間に直接晒し、熱や光、放射線、ダストなどによる劣化や変質を観測するためのものです。
ギャップフィラーは、ロビンソン宇宙飛行士によって、二つとも手で引き抜かれました。すばらしい。 (21:55 JST)
スケジュールの変更にあわせて上記スクリプトのデータを変更しました。細かいスケジュールの発表がされていないため、EVA3関連部分以外は、NASA-TVのスケジュールから再構成してあります。
明日の日本向け広報イベントの時間も変更になっていますので、注意してください。
. Date: 20050804 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events10日目。予定されていた3回のEVAも終わり、今回のミッションも一番大きな峠を越えました。そろそろ帰り支度です。
今日の目玉はなんといっても日本向け広報イベントでしょう。あとは、ISSで使わなくなった機器などを収納した多目的補給モジュール(MPLM)の回収などが行われます。(変更になりました)
広報イベントは午後6:19分からの予定です。当初のフライトスケジュールからは変更になっていますので注意してください。また、21時からはコロンビアのクルーを偲ぶ記念セレモニーが行われます。
うー、せめて、もうちょっと勉強してくれ > 小泉さん (19:00)
STS-114 Master Flight Plan (SpacefligntNow)
新しいフライトプランが発表されたので、データを詳細なものと差し替えました。
ご好評いただいているGoogleSat2ですが、Plusの方に新しい機能をつけてみました。
軌道要素を指定することで任意の衛星の位置を表示できます。
この間打ち上げられたX線天文衛星「すざく」だとこんな感じ→ASTRO-E2
GoogleSatTrack 2の予測精度についてですが、おそらく最新の軌道要素を使っても、100km強の誤差が出ると思います。たとえば、高度350km付近では衛星は秒速7.5kmで移動します。つまりPCの時計が15秒ずれているだけで約100kmの誤差が出るんです。ただ、このスクリプトが使い物になるのは、せいぜい左下のゲージが20kmぐらいの所までですから、これぐらいの精度でも十分なはずです。
ちなみに高度350kmでは地平線までの距離は2000km以上ありますから、100kmぐらいの誤差なら「宇宙飛行士たちが今見ている場所」と言っても、さほど大げさじゃないと思いますが...だめかな?
残念ながら、GoogleSatTrack2の上で人工衛星が自分の住んでいる街の上を通り過ぎたからといって、その瞬間に窓の外を見てもたぶん衛星を見ることはできません。衛星を見るためには「観測地の上を衛星がいつ通り過ぎるか」という、まったく別の位置予測をする必要があるんです。
参考)ISS・スペースシャトルを見よう (JAXA)
. Date: 20050805 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events11日目。今日は地球に持ち帰る多目的モジュールの停止、カーゴベイへの収納などが行われます(昨日やってると思ってたよ^_^;)。また、ロボットアームを延長して各種の検査を行うOBSSをISSとシャトルの間で受け渡すテストが行われます。
現時点での予定では、明日ISSとシャトルの切り離しが行われ、STS-144のクルーは帰途に着くことになります。が、現在コックピット付近の耐熱タイルの浮き上がりを補修するため、第4回目のEVAが検討されており、実行が決定されるとさらに滞在期間が延長されることになります。
Fourth spacewalk ruled out (SpacefligntNow)
どうやら、4回目のEVAはいらないという判断が出たようですね。
昨日、軌道上で行われたコロンビア事故の追悼イベントのページ。ビデオとトランスクリプトがあります。ただひたすら、ISSの窓の外を流れる風景を映し出す映像にかぶせられたメッセージはとても美しく、胸を打ちます。
あまりに感動したので、トランスクリプトの日本語訳を作りました。
Exploration - The Fire of the Human Spirit 日本語訳
. Date: 20050806 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events12日目。今日はとうとう国際宇宙ステーションに別れを告げ、シャトルが帰途に着きます。
お別れイベントが日本時間13時24分から行われ、その後ハッチが閉じられます。各種のチェックの後、切り離しが16時22分、しばらくISSの周りにとどまった後、離脱の噴射が行われるのが17時39分の予定です。
ISSからの離脱噴射が滞り無く行われ、STS-114は帰途につきました(18:30)
GoogleSatTrack2シリーズは8/8の軌道離脱まで、STS-114を追跡します。<%= fn '現段階では若干離れすぎてますね 08/06 18:30' %>
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/googlesat/googlesat2.php
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/googlesat/googlesat2_plus.php
着陸の予定は明後日、日本時間8日17時46分の予定。既に飛行ルートが発表されています。
NASA - STS-114 Landing Ground Tracks
. Date: 20050807 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events13日目。軌道上で過ごす最後の一日です。今日行われるのは、再突入に備えての各種のテストやシミュレーション、キャビンの後片付け、そして全員そろっての最後の記者会見などです。記者会見は日本時間18:14からの予定。
また、Ku-バンドアンテナと呼ばれる、大容量通信を行うためのアンテナが収納されるため、動画の配信は今日が最後です。今後は、コマ送りの静止画と音声が主になります。
明日はいよいよ軌道離脱です!
. Date: 20050808 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [sts]Countdown for STS-114 post-launch events14日目。いよいよ着陸です。日本時間16時41分に軌道離脱噴射開始、高度400,000ft(約122km)に到達する再突入開始時間(Entry interface)は17時15分、そして17時46分にケネディ宇宙センターの滑走路(GoogleMaps)に着陸予定です。
どうか、無事に帰ってきてください。
第1回目のGo/NoGO判断で、NoGOがでました。ディスカバリーはもう一周地球を周回します。(16:20)
第2回目のGo/NoGO判断でも、NoGOがでました。本日の着陸はありません。(18:10)
夏休み!親子でISSを見よう! (JAXA)
ISS・スペースシャトルを見よう(JAXA)
9日午前4時20分前後、シャトルとISSが日本上空を通過します。地上ではまだ夜明け前ですが、高度360kmでは既に夜が明けて太陽が当たっており、目視観測する絶好のチャンスです。予報では、1等星を超える明るさで見えるはず。ちょっと時間が時間ですが、またとないチャンスです。ぜひ、外に出て空を見上げてみましょう。天気がいいといいんですが...
見える方角や角度は上記サイトを参考にしてください。予報はISSのものですが、見える角度や方角は全く同じです。タイミングは、この時間ならばシャトルはISSの1分前に通過すると考えればさほど時間はずれないはずです。
追記)残念ながら、自宅からは曇っていて見えませんでした。
再突入のタイムラインが発表されたので、再突入用のカウントダウンスクリプトをアップしました。
最新データに更新しました。(16:45)
最新データに更新しました。明日以降の着陸予定候補時間を入れてあります。(18:10)
. Date: 20050809 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Countdown for STS-114 re-entry eventsおまけの一日。着陸が一日伸びたせいで、クルーは少しのんびりしたみたいです。昨日は音楽をバンバンかけてずいぶん楽しそうにしている様子が通信の端々から聞こえてきました。
今日の着陸のチャンスは6回(内訳は上記ページを参照してください)。NASAとしては、なるべくケネディ宇宙センターに下ろしたいという希望があるので(他の所だと機体を運ぶのにお金と時間がかかってしまうため)。2回目のホワイトサンズはパスすると思います。また、明日10日にはケネディ宇宙センターから火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターの打ち上げがあるため、できれば今日中に着陸させたいところ。1回目、3回目でケネディ宇宙センターにトライして、ダメならエドワーズに降ろすという感じになるんじゃないでしょうか。
第1回目の着陸にNoGOが出ました。やはり、ホワイトサンズはパスしてケネディ宇宙センターに再トライします。次の判断は18時20分頃の予定。上記ページのデータを2回目のものにアップデートしました。
第2回目の着陸にもNoGoがでました。次のチャンスは、エドワーズ空軍基地への着陸になります。次のGO/NoGO判断は19時45分頃の予定。上記ページのデータを3回目のものにアップデートしました。
エドワーズの天気は良さそうですから、次でGOが出るかもしれませんね。
ただし、エドワーズに着陸が決まると、シャトルを移送するのに最低でも1週間かかってしまうため、ディスカバリーがバックアップ機としてアサインされている、9月中のアトランティスの飛行が難しくなります。
エドワーズ空軍基地(GoogleMaps)
エドワーズ空軍基地は、もともとシャトルの開発時に使用され、着陸のテストなどが行われていた場所であり、コロンビアの第一回目の飛行の際にも着陸地になっていました。ライトスタッフを見た人なら覚えているかもしれません、あの映画の舞台になったのはこの基地です。イエーガーがX-1で音速を破ったのはこの場所です<%= fn 'もちろん、パンチョバーンズのHappy Bottom Riding Clubもここにありました。' %>。
” 'Go' for Deorbit burn ! ” 軌道離脱にゴーサインが出ました。
エドワーズ空軍基地への着陸が決定しました。(19:45 JST)
軌道離脱噴射が日本時間で20時06分27秒、シャトルが大気の影響を受け始める「大気圏突入開始時間(エントリーインターフェイス)」が20時40分11秒、着陸が21時11分48秒の予定です。
軌道離脱噴射を開始しました。(20:10 JST)
この噴射は2分42秒間続き、ディスカバリーは軌道を離脱します。この後、機体は徐々に高度を落とし30分強で大気の影響を受け始めます。
軌道離脱噴射終了。(20:14 JST)
どうか無事に戻ってきてください。
これをもって、GoogleSatTrack2のSTS-114の追跡を終了します。(20:30 JST)
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/googlesat/googlesat2.php
http://www.lizard-tail.com/isana/lab/googlesat/googlesat2_plus.php
大気圏突入開始(20:41 JST)
ロールリバーサル開始(20:47 JST)
速度を落とすための、1度目のS字飛行を行います。順調に飛行中。
コロンビアからの通信が途絶した地点を通過。順調に飛行中。(20:56 JST)
最も高温になる区間を無事に通過。順調に飛行中(21:00 JST)
追跡機のカメラが、ディスカバリーの姿を捉えました。(21:03 JST)
マッハ2.5まで速度を落としました。(21:06 JST)
パイロットのマニュアルコントロールに切り替えられました。(21:08 JST)
滑走路を視認、ファイナルアプローチを開始(21:10 JST)
タッチダウン!!!!(21:12 JST)
お帰りなさい ! あー、涙出てきた。
Welcome home ! Dear Rocketeers.
クルーの皆さん、フライトを支えた関係者の皆さん、おめでとうございます。
心から感謝します。本当にありがとう。
私たちがそこへ行くのは、ただあなた方に負うものがあるからではなく、私たちがあなた方と同じように、よりすばらしい世界への夢を見ているからです。
Exploration - The Fire of the Human Spirit 日本語訳(原文)
そして、どうか、このフライトが未来につながる飛行でありますように。
. Date: 20050810 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingこちらこそ、今後ともよろしくお願いします >Space Fighter Now
本日、日本時間10日の夕方に打ち上げが予定されていた、マーズ・リコネッサンス・オービターですが、一日延期になったようです。東部夏時間11日の7時50分から9時35分の間になりました。日本時間では同日20時50分?23時35分ですね。
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)は、直訳すると「火星偵察衛星」。火星の軌道を周回しながら約2年間に渡って火星の地形をくまなく探査します。地表の1mの物体を識別できる超高解像度のカメラ<%= fn 'おぉ、これまで送ったバイキングや火星ローバーが写りますね。' %>や、大気や地中内部の状態を探査するレーダーなどを搭載しています。
しかし、昨日シャトルが帰ってきたばっかりだっていうのに、昨日の今日で火星探査機か...いくら緊縮財政だっていっても、これだけのの余力があるんだから、やっぱり、すごいねぇ。
先日打ち上げられたX線天文衛星「すざく」にトラブルが発生した、というニュース。どうやら、冷却用の液体ヘリウムが漏れ、XRS(X-Ray Spectrometer:X線分光検出器)が使えなくなってしまったらしい。がーん。
すざくのXRSはこれまでX線天文衛星に搭載された検出器より性能が一桁高いという、超高感度のX線検出器。「すざく」に搭載された観測機器の中でも目玉のひとつだったんだけど...なんとも残念。まあ、他の機器は生きているから観測ができなくなったわけじゃないけどね。
参考)すざくの現在位置(GoogleSatTrack2_plus)
航空機の黎明期、まだ飛行機が木と布でできていた時代。主翼の面積と重量と剛性という相反する要素を両立させるために、複葉という形式が多く用いられました。羽を上下に2枚並べ、支柱でつなぎ、鋼線で張力をかけることで、面積を稼ぎながら軽量で剛性の高い主翼を作り出したんです。
さて、飛行機の翼は同じ面積なら、前後の幅を狭くし左右の長さを長くした方が揚力が増します。じゃあ...細い翼を沢山重ねれば性能のいい飛行機ができるに違いない。当時は重く非力なエンジンしかありませんでしたから、誰もが必死で軽くて揚力が大きい翼を作ろうとしていた時代です。この理屈に飛びついたエンジニアが沢山いたのも致し方ないでしょう。
確かに、三葉機ぐらいまではうまくいきました。でも、4葉、5葉、とうとう10葉機なんていう代物が作られるにいたっては、もう本末転倒です。構造的にも複雑で、機体重量は増加するわ、剛性はまるでないわで、とても飛べた代物ではありませんでした。
まあ、要するに、なにごとも中庸が肝心、というお話です。
ところで、先日街を歩いていたらとつぜんテストパイロットにスカウトされました。普段三葉機を飛ばしている人間に、あの機体を任せるとはなかなかの目の付け所。で、早速、勇んで飛ばしてみましたが...
羽を増やせばいいってもんじゃないぞ!!!がぁ!!
. Date: 20050811 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping1人1億ドルで月まで連れて行くぜ!と、かのスペースアドベンチャーがぶち上げた、というお話。5日半で月を回って帰ってくる、というコース。最短で2008年には飛ばすそうな。
これがどこかのベンチャーの大言壮語ならあんまり気にしないんだけど、なにしろ言い出したのは「世界で唯一実績のある宇宙観光旅行会社」スペースアドベンチャー<%= fn 'デニス・チトーとマイク・シャトルワースをISSに連れて行ったのはこの会社' %>。この会社は、ロシア宇宙局とエネルギアとの協力関係があり、今回のプロジェクトもこの両者が実際の訓練や打上げなどを担当し、打上げ機/宇宙船にはソユーズ-TMAを使う。そう、この会社は既に具体的な「手段」を持っているのだ。
ただし、ソユーズは月への飛行を想定して作られていない。ソユーズの軌道上の滞在可能時間は月を回ってくるのに十分だけど、月に送り込むための追加のブースターは新規開発になる。それに、ソユーズにブースターをつなぐにはソユーズを改造しなくちゃいけないし、ブースターをつないだソユーズを打ち上げるためには打上げ機にも改造が必要。そう簡単にはいかないかもしれない。
昨日打ち上げられる予定だったMROですが、若干打ち上げ時間が後ろにずれたようです。
打ち上げ予定は東部標準時9:00、日本時間の22:00の予定です。
うゎお、打ち上げ10分前に24時間の延期が決定しました。また、明日です。(22:00 JST)
ブログ作者に投げ銭を (jkondoの日記)
なぜ「受け取らない」という選択ができないのかな?
. Date: 20050812 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary ペルセウス座流星群が極大12日夜から13日の夜明けにかけてペルセウス座流星群が活発になります。極大は13日午前2時から4時。今年は22時ぐらいには月が沈んでしまうのでかなりの好条件。1時間に数10個は見られるとのこと。ペルセウス座流星群は、テンペルタットル彗星を母彗星とする流星群で、ダストと地球の衝突速度が速いため、明るい流星が多いのが特徴です。
ペルセウス座流星群という名前は、放射点の名前から来ていますが、どの方向が見えやすいということはありません、なるべく空が広く見渡せるような場所にねっころがるのが一番です。また、目が暗いところに完全に慣れるには思っているより時間がかかります、すぐに見えないからと言ってあきらめない方がいいかもしれません。
最近はずいぶん流星群の出現予測も正確になってきましたが、比較的正確な天文現象の予測の中でも最もあてにならないもののひとつです。ご存知のように、流星群は彗星の残していったダストに地球が突っ込むことによって起きます。このダストの分布予測がかなり正確になり、以前に比べればかなり信頼できるものになりました。
でも、突発的な大出現は予測できません、一時間に数百個という「流星雨」、数千個という「流星嵐」の出現の可能性がないわけじゃないんです。もしかしたら、「予想外の大出現」は今夜かもしれないんです。
さあ、今夜は外に出ましょう。
ぼんやり空を眺めながら、「もしかしたら」を待つのもなかなかいいもんです。
関東は大雨だよ...しくしく(23:00)
再三にわたり、打ち上げが延期されていたMROですが、無事に打ち上げのプロセスが終了、衛星は火星へと向かう軌道に乗ったとのこと。わーい。おめでとうございます。
MROが火星に到着するのは来年の3月。その後、5ヶ月かけて火星の上層大気を使って徐々に速度を落とし、目標の火星周回軌道に乗るのは、ちょうど来年の今頃です。
いってらっしゃーい。
. Date: 20050816 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping「はやぶさ」、小惑星イトカワの撮影に成功! (JAXA)
いよいよ近づいてきましたね、どうやら小惑星イトカワまでの距離も3万キロを切っているようです。とはいうものの、「はやぶさ」はイトカワの後ろから追いかけるような形で接近しているのでもう少し時間がかかります。
この記事で紹介されているスタートラッカーというのは、探査機が自分の位置を確かめるための装置のひとつ。スタートラッカーを備えた探査機は、メモリの中に星図を持っていて、この星図と実際の星空を比べて自分の姿勢と位置を確認するんです。「えーと、あの星がここに来ていて、この星があそこにあるってことは...このあたり?」とかやってるわけですね。かわいいなあ。
. ---キリトリ---